女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
官能小説 朝靄の契り〜前編〜
初めての恋
梅がほころびかけていた。
時は如月、申の刻(午後4時頃)。
西の空に広がった夕焼けが美しい、ここは江戸・曳舟。
とん、とん。
家の戸を遠慮がちに叩く音がした。小さな窓から梅ごしに夕焼けを眺めていたさとは、少しいぶかしく思いながら立ち上がった。父なら家に入るときにわざわざ戸を叩いたりしない。
「どなたさま?」
そっと戸を開けると、そこには見知らぬ青年が思いつめたような顔で立っていた。
「田川広芳さまのお宅はこちらでござろうか?」
「は、はい……」
さとは澄んだまっすぐな瞳に戸惑いながらも頷いた。
「父に……ご用でございますか?」
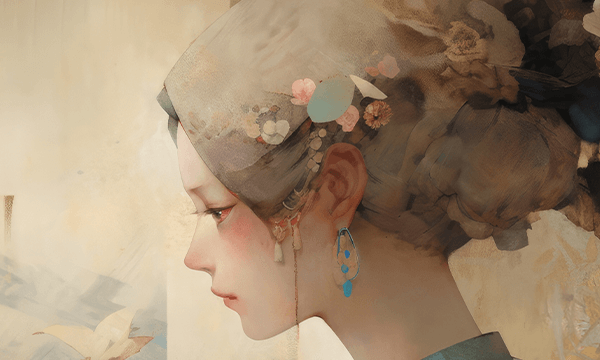
「深川から参りました本山半次郎と申します。
お父上の画(え)について、ぜひお話しさせていただきたいことが……」
さとの父は近年人気が出始めた春画絵師、名を田川広芳という。
幼い頃に母を亡くしたさとを男手ひとつで育ててくれた。
絵師としての経歴は長かったもののなかなか日の目を見ることができず、
春画に転向したところ、向いていたのか少しずつ注文が増えてきた。
その父は、所用があって両国の知り合いのところに行っている。
そろそろ帰ってくるはずだが、さてどうしたものか。
迷っていると、折よく父が歩いてくるのが見えた。
「弟子入り!?」
父がひっくり返った声を出した。
深川の海苔屋の次男坊である半次郎は、
店を継いだ兄の手伝いをしながら日々を送っていたが、幼い頃から絵を描くことが好きで、
いつか生業にしたいとぼんやり考えていた。
それが広芳の春画を目にして衝撃を受け、迷った末、
弟子入りを志願するべくやって来たのだという。
いかにも生真面目そうな仕草や口ぶりながらも、絵の話になると急に熱心になるところに、
広芳もさとも好感を抱いた。
「なら、明日から通ってきてみなさい」
それから半次郎は、ほぼ毎日家を出入りするようになった。
半次郎の手が伸びてくると…
半次郎が弟子入りしてから一月ほど経った。
広芳は半次郎を伴い、画材を求めに日本橋へ出かけていた。
留守番のさとは食事を用意していたが、
鍋を※囲炉裏(いろり)の火にかけたところへ半次郎が一人で帰ってきた。
「師匠は途中で馴染の弥吉さんとばったり会って、今日は飲みがてらあちらに泊まるそうです」
なぜか半次郎がばつが悪そうに言う。
「それで俺のぶんの夕飯はお前が食べて帰れと」
父は半次郎をすっかり気に入っている。もう家族のような気分でいるのかもしれない。
半次郎が若い男であるという意識が薄れているのではないかと、さとはわずかに気を揉んだ。
二人だけでの食事となると、さとは何を話していいのかわからなかった。
その場の空気を持て余して、囲炉裏でつけている※燗(かん)を何度も気にしていると、
「お嬢さん、今日くらいはゆっくり食事をしてください」
と半次郎が困ったように笑った。
さとははっと息をのんだ。
暗くなり始めた屋内で、囲炉裏の火がぼうっと半次郎の輪郭を描き出し、
端正な顔が妖しく映えていた。
「いえ、そんな大した…」
うろたえながら徳利(とっくり)を出そうとすると、焦っていたせいか取り落としてしまった。
熱くなった酒が頬にはねる。
「あっ……!」と顔を背けたのと、
半次郎に腕を掴まれ引っぱられたのは同時だった。
こぼれた酒が囲炉裏の炭火を消した。しゅう……という音とともに、あたりが薄闇に包まれた。
一段黒い影となった半次郎の手が伸びてくる。さとは思わず身をすくめた。
半次郎の手が頬に触れる。
「大丈夫ですか?」
優しい声だった。さとはおそるおそる半次郎を仰いだ。
急激に頬が熱くなった。火傷はしていない。あまりにも近くから半次郎に見つめられていたからだ。
「だ……大丈夫です。ありがとうございます」
かろうじて声を出したときだった。
頬に添えられていた半次郎の手が、ゆっくりと首すじへ下りていった。
「……いけません」と言いかけた唇に、半次郎の唇が重なった。
半次郎の舌が唇を割って入ってくる。
その感触に、今まで感じたことのない熱いものが体の奥から湧き上がってくるのを感じた。
初めての接吻だった。自然に反応することができたかどうか、自分ではよくわからない。
ただひたすら、幼子が親にすがりつくように半次郎の舌に舌を絡めた。
うっすら目をあけると、眉間に少し皺を寄せている半次郎の切ない表情が見えた。
身じろぎするたびの衣擦れの音。荒くなり始めた息遣い。
どのくらいそんな時間を過ごしていただろうか。やっと半次郎が唇を離した。
半次郎はさとの腰をぐっと引き寄せると、耳元でほとんど呻くように囁いた。
「ずっと……お慕い申しておりました」
喉の奥が詰まったようになって、返事ができなかった。
そのかわり、半次郎の背に手を回して、自分もまた彼を強く抱きしめた。
初めて会った日の澄んだ目を思い出す。
あの時からすでに、半次郎に惹かれていたのかもしれない。
「私も……初めてお会いしたときから……」
みなまで言う前に、二人はまた唇を重ねた。
体がふわりと浮いたように思われた。
気がつくと仰向けになっていたさとは、闇の中で半次郎の重みを感じた。
あらすじ
さとの父は人気の春画絵師。
父に弟子入りを志願してきた半次郎と年ごろのさとは自然と惹かれ合っていく…

















