女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
官能小説 甘い指先に囚われて
触れる指先、届かぬ想い
麻衣が足繁く通う表参道のヘアサロン「Ciel」。
そこは、麻衣にとって、ただ髪を切る場所ではなかった。
担当スタイリストである、孝宏。彼の指先が髪に触れるたび、麻衣の心はさざ波のように揺れる。
孝宏は、このサロンのチーフスタイリスト。36歳。
その確かな腕と、どんな客をも魅了する話術、そして、常に柔らかな笑顔は、まさにサロンの「顔」だった。
男女問わず指名客が絶えず、彼の予約はいつも数ヶ月先まで埋まっている。麻衣もその常連客の一人として、もう3年も通い続けていた。
孝宏の優しい指先が髪を梳き、頭皮を滑るたび、麻衣は日々の仕事の疲れも忘れ、まるで夢の中にいるような心地になる。
けれど、これはあくまで「お客様とスタイリスト」の関係。彼が麻衣のような一常連客に特別な感情を抱くことなど、決してないだろう。
彼が誰にでも見せる優しい笑顔の奥に、どれほどの女性が心を奪われてきたか、麻衣はよく知っている。
この想いは、決して口にしてはいけない秘密。そう、ずっと、自分に言い聞かせてきた。
シャンプー台の秘密、雨の誘い
いつものように予約の時間にサロンを訪れると、孝宏は他の客を接客中だった。
麻衣は待合室で雑誌を広げながら、ガラス越しに彼の姿を追う。
陽光を浴びて輝く、彼のしなやかな指先。その指が、今、他の女性の髪に触れている。胸の奥に、ちくりと小さな痛みが走る。
「麻衣さん、お待たせしました」
孝宏の声に、ハッと顔を上げた。彼はいつもの優しい笑顔で、麻衣をシャンプー台へと案内する。
「今日は、どんな感じにしましょうか?夏の疲れ、髪にも出てますね」
「そうですね……。孝宏さんにお任せします。いつも素敵にしてくださるから」
麻衣がそう答えると、孝宏はふわりと微笑んだ。
彼の指が、麻衣の頭皮に触れる。その指の腹が、髪の生え際から頭頂部へとゆっくりと滑っていく。
心地よいマッサージに、全身の力が抜けていく。目を閉じると、シャンプーの爽やかな香りと、彼の残り香が混じり合い、麻衣を包み込む。
この時間が、たまらなく好きだった。
「孝宏さん、いつもお仕事お忙しいのに、どうしてそんなに穏やかでいられるんですか?私なんて、仕事に疲れると、つい眉間にシワが寄っちゃって……」
麻衣が問いかけると、彼の指の動きが少しだけ緩んだ。
まるで、麻衣の言葉に耳を傾けるように、ゆっくりと頭皮を優しく押さえつける。
「そう見えるかな?麻衣さんも、いつも頑張ってますよね。でも、そういう頑張り屋さんほど、無理しちゃうんですよ。だから、たまにはちゃんと自分のために休んで、心も体もリラックスさせてあげてくださいね」
彼の言葉に、シャンプーの泡のせいか、頬が熱くなるのを感じた。この優しさは、きっと「お客様」へのプロの気遣い。
そう分かっていても、どうしても期待してしまう自分がいた。
「麻衣さん、髪、本当に綺麗になりましたね。いつもケアをしっかりしてるのが分かります」
シャンプーが終わり、鏡の前に座ると、孝宏は麻衣の髪をタオルで優しく包みながら言った。
そのタオル越しの指が、麻衣の首筋をかすめる。
「孝宏さんが、いつも綺麗にしてくださるからですよ」
麻衣がそう言うと、孝宏はふっと笑った。
その笑顔は、相変わらず穏やかで、麻衣の胸をきゅんとさせた。
「麻衣ちゃんも、変わらないですよ。相変わらず、綺麗だ」
不意打ちの言葉に、麻衣の頬がカッと熱くなる。彼の視線が、まっすぐに麻衣を見つめている。
その瞳には、プロとしての優しさだけではない、何か熱いものが宿っているように見えた。
夏の終わりの日が差し込む窓辺で、二人の間に、密やかな空気が流れる。
カットとカラーが終わり、麻衣は会計を済ませた。
外に出ようとすると、突然、土砂降りの雨が降り出した。予報にはなかった雨に、麻衣は思わずため息をつく。
傘は持っていない。
「麻衣さん、傘、お持ちですか?」
振り返ると、孝宏が心配そうな顔で立っていた。
「いえ……降るなんて聞いてなかったから」
「じゃあ、僕の使ってください。僕はもう少し残業があるので」
孝宏が差し出したのは、シンプルな黒い傘だった。
「でも、孝宏さんが困っちゃいますよ」
「大丈夫です。少しの雨なら濡れて帰っても平気ですし。麻衣さんが風邪を引いたら大変ですから」
彼の優しい言葉に、麻衣の心臓がトクンと鳴った。こんなにも自然に、自分を気遣ってくれる。
「ありがとうございます。助かります。また、近いうちにお返ししますね」
「ええ、いつでも。……あ、もしよかったら、今度カフェにでも寄って、返してもらってもいいですか?お礼なんていらないですから、ただ、少し話したいなって」
孝宏が、少し照れたように耳の縁を赤くしながら言った。
その一言が、麻衣の胸に直接響く。この誘いは、ただの「傘のお礼」以上の意味を持つのではないか。
彼のまっすぐな瞳に見つめられ、麻衣は小さく頷いた。
「はい、ぜひ!」
傘を受け取り、サロンを出る。
孝宏の残り香がする傘に、麻衣はそっと顔を埋めた。
雨の中を歩く足取りは、いつになく軽やかで、麻衣の心には、秘めていた恋がゆっくりと動き出すような、確かな予感が満ちていた。
カフェの誘い、触れる確かな距離
孝宏から借りた傘を手に、麻衣は週末のカフェへと向かった。約束の時間は午後2時。
少し早めに着いてしまった麻衣は、窓際の席に座り、胸の高鳴りを抑えようと深呼吸を繰り返した。
しばらくして、カフェのドアが開く。孝宏が、いつものサロンとは違うカジュアルな服装で現れた。
白のTシャツにデニムというシンプルな装いも、彼が着るとどこか洗練されて見える。
「麻衣さん、お待たせしました」
はにかんだような笑顔で席に着く孝宏。いつものサロンでの「チーフスタイリスト」としての顔とは違い、目の前にいるのは、一人の男性としての孝宏だった。
そのギャップに、麻衣の心臓はさらに大きく脈打つ。
「いえ、私も今来たばかりです」
他愛ない会話から始まったものの、二人の間には、サロンでは感じられなかった親密な空気が流れ始めていた。
仕事の話、休日の過ごし方、好きな映画や音楽。今まで知らなかった孝宏の顔が、少しずつ見えてくる。
「麻衣さんは、いつもどんな時にリラックスしますか?」
孝宏の問いに、麻衣は少し迷ってから答えた。
「そうですね……。孝宏さんに髪を切ってもらっている時が、一番リラックスできるかもしれません」
麻衣が正直な気持ちを伝えると、孝宏は少し驚いたように目を見開いた後、優しい笑顔を浮かべた。
「嬉しいな。僕も、麻衣さんの髪に触れていると、心が落ち着くんです」
その言葉に、麻衣の頬が再び熱くなる。コーヒーカップを握る手に、じんわりと汗が滲んだ。
カフェでの時間が終わり、外に出ると、空はすっかり晴れ渡っていた。
帰り道、孝宏は自然な動作で麻衣の隣を歩く。ふとした拍子に、二人の指先が触れ合った。
麻衣が思わず手を引こうとすると、孝宏の指がそっと麻衣の指を絡めとった。彼の人差し指が、麻衣の手のひらを優しくなぞる。
「あの……」
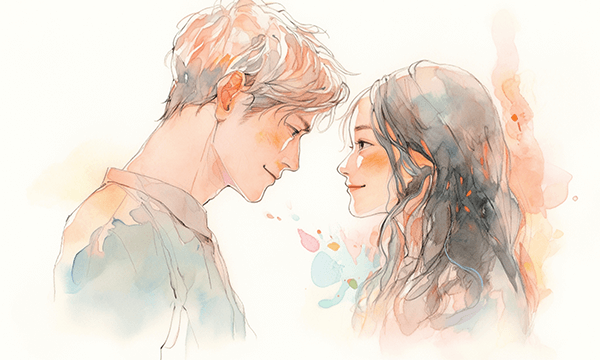
麻衣が顔を上げると、孝宏は真っ直ぐに麻衣を見つめていた。
その瞳には、今までサロンで見せていたどの表情よりも、真剣な光が宿っていた。
「麻衣さん。もしよかったら、僕と、もう少しだけ、一緒にいてくれませんか?」
彼の言葉は、麻衣の心に直接響いた。
迷いはなかった。
「はい」
麻衣が小さく頷くと、孝宏は嬉しそうに微笑み、握られた手に力がこもった。
繋がれた指先から、彼の温もりと、確かにそこにある「想い」が伝わってくるようだった。
秘めた想いの開花
それから、二人は頻繁に会うようになった。
カフェでの他愛ない会話から始まり、美術館に行ったり、夜景を見に行ったり、二人の時間はゆっくりと、しかし確実に育まれていった。
サロンで会う時も、二人の間には以前とは違う、特別な視線が交わされるようになっていた。
ある日、麻衣は仕事で遅くなり、孝宏のサロンにぎりぎりで予約を入れた。
閉店間際だったため、他の客はすでに帰り、スタッフも麻衣のシャンプーが終わると次々に退勤していく。
やがて、サロンには麻衣と孝宏だけになった。静まり返った店内に、シャワーの優しい音だけが響く。
シャンプー台でのいつもの会話。
彼の指が麻衣の頭皮に触れるたび、二人の距離は物理的にも、そして心理的にも縮まっていく。
「麻衣さん、知ってますか?僕、麻衣さんが初めてお店に来た時から、ずっと気になってたんです」
突然の孝宏の言葉に、麻衣は心臓が止まるかと思った。
シャンプーの泡で濡れた髪が、熱くなった頬に張り付く。
「え……でも、私はただのお客さんで……」
「最初はそうでした。でも、麻衣さんと話すうちに、どんどん惹かれていったんです。麻衣さんの真面目なところも、少し不器用なところも、全部。シャンプー中に、麻衣さんの髪に触れるたびに、この気持ちが溢れそうになってた」
孝宏の声は、いつになく真剣だった。
彼の指が、優しく麻衣の髪を撫でる。毛先を一本一本確かめるように、丁寧に、慈しむように。
「僕、麻衣さんが好きです。お客様としてじゃなくて、一人の女性として、麻衣さんが、好きです」
麻衣の目から、止めどなく涙が溢れ出した。ずっと心に秘めていた想い。
お客様とスタイリストという壁を乗り越えて、孝宏も同じ気持ちでいてくれたこと。
その喜びが、麻衣の全身を満たした。
「私も……私も、孝宏さんが、好きです」
震える声でそう答えると、孝宏はゆっくりと麻衣を抱きしめた。
シャンプーの香りと、孝宏の温かい香りに包まれて、麻衣は至福の時を過ごした。
深まる絆、未来への一歩
二人が恋人になってから、麻衣と孝宏の関係は急速に深まっていった。
サロンでの「お客様とスタイリスト」という立場は変わらないが、二人の間には、より深い信頼と愛情が育まれていった。
休日は二人で過ごすことが増え、時には孝宏のマンションで手料理を振る舞い合うこともあった。
孝宏の淹れるコーヒーは、どんな高級カフェのコーヒーよりも麻衣を癒し、麻衣の作る簡単な家庭料理も、孝宏はいつも美味しそうに食べてくれた。
ある夜、孝宏の部屋で過ごしている時、彼は麻衣の髪を優しく撫でながら言った。
その指先が、麻衣の髪の束を丁寧にすくい上げ、毛先をくるりと丸める。
「麻衣さん、僕、麻衣さんと出会えて本当に良かった。今まで、仕事一筋で生きてきたけど、麻衣さんのおかげで、僕の世界がすごく広がったよ」
麻衣は孝宏の胸に顔を埋めた。
彼の温かい体温と、心地よい心臓の音に、心が満たされる。
「私も、孝宏さんと出会えて、本当に幸せです。孝宏さんがいなかったら、今の私はなかった」
二人の会話は、仕事のこと、将来のこと、そして時には、ささやかな夢へと広がっていった。
お互いの価値観を共有し、理解を深めていく中で、二人の絆はより一層強固なものになっていく。
「麻衣さん、僕と、これからもずっと一緒にいてくれませんか?」
孝宏の言葉に、麻衣は顔を上げた。
彼の瞳には、真剣な、そして優しい光が宿っている。
深まる夜、秘密の熱
「はい……。喜んで」
麻衣の言葉に、孝宏は優しく微笑んだ。その瞳の奥には、確かな熱が宿っている。
孝宏は麻衣の顔を両手で包み込み、ゆっくりと唇を重ねた。
それは、カフェで交わした初めてのキスよりも深く、互いの秘めた想いを確かめ合うようなキスだった。
その夜、二人は自然な流れで孝宏さんのマンションへと向かった。
部屋に入ると、孝宏は麻衣のコートを優しく受け取り、ソファへと促した。
間接照明が落とされた部屋は、昼間の喧騒を忘れさせる、穏やかな空気に満ちていた。
「麻衣さん、少し、ワインでも飲みますか?」
孝宏の問いに、麻衣は小さく頷いた。二杯目のワインを口にした頃、麻衣の頬はほんのりと赤く染まっていた。
孝宏は麻衣の隣に座り、そっと彼女の手を取った。彼の親指が、麻衣の手の甲をゆっくりと撫で、指と指の間にそっと絡みつく。
指先が触れ合うたびに、電流のような感覚が麻衣の全身を駆け巡る。麻衣は思わず、微かな息を漏らした。
「麻衣さん、いつも、サロンで麻衣さんに触れるたびに、もっと、こうして触れていたいって思ってた」
孝宏の声は、いつになく甘く、麻衣の耳元で囁かれる言葉は、麻衣の理性を溶かしていく。
彼はゆっくりと、麻衣の髪を撫で、頬をなぞった。
彼の指先が触れる場所すべてに、熱が灯るような感覚に、麻衣は身を委ねた。
まるで、麻衣の存在を確かめるように、頬から顎のライン、そして首筋へと、彼の指先が優しく、しかし確かな熱を伴って滑る。
その辿る軌跡に、麻衣の肌は粟立ち、抗えない陶酔が全身を支配していく。
麻衣の喉からは、甘く、誘うような「ん…」という声が、意識せずとも漏れた。
麻衣は、彼に吸い寄せられるように、そっと孝宏の胸に顔を埋めた。
彼の温かい体温、そして彼の匂いが、麻衣を安心させる。孝宏の腕が麻衣の背中に回され、抱きしめられる力が強まる。
「麻衣さん……」
孝宏が麻衣の名前を呼ぶ声は、もう、サロンでの穏やかな声とは違う、熱を帯びた声だった。
麻衣は顔を上げ、彼の瞳を見つめた。
その瞳には、麻衣への抑えきれない情熱が燃えているように見えた。
二人の呼吸が重なり、唇が再び触れ合う。今度は、もっと深く、もっと激しく。
服の隙間から滑り込む孝宏さんの指が、麻衣の肌に触れるたび、麻衣の体は熱を帯びていく。
麻衣もまた、彼に応えるように、彼の背中に手を回し、その肌の感触を確かめた。
彼の繊細な指の動きが、麻衣のブラウスの裾から滑り込み、背中を、腰を、そしてその柔らかな肌を、ゆっくりと、しかし執拗になぞる。
孝宏は麻衣の耳元で甘く囁いた。
「かわいい、麻衣さん……もっと、僕を感じてほしい」
彼の指先が触れるたびに、麻衣の思考は甘く痺れ、内側から蕩けていくような快感が全身に広がり、抗う術を失っていく。
麻衣の唇から、抑えきれない「ぁ…」という甘い吐息が零れ落ちる。
「ん…、あっ、孝宏さん…そこ…」彼の指が腰のくびれを辿り、その熱が肌に直接伝わると、麻衣は小さく身を震わせ、「んっ…」と、喘ぐような声を漏らした。
時間も、理性も、すべてが曖昧な空間に溶けていく。
その夜、二人は、互いの肌を通して、言葉以上の深い絆を確かめ合った。
それは、今まで秘めていた想いが、今、確かに愛へと昇華した瞬間だった。
朝の光、二人の時間
翌朝、麻衣は孝宏の腕の中で目を覚ました。
カーテンの隙間から差し込む柔らかな朝の光が、二人の体を優しく照らしている。
麻衣は彼の胸に顔を埋め、彼の穏やかな寝息を聞きながら、昨夜の出来事を思い出した。
「起きた?」
孝宏の優しい声に、麻衣はゆっくりと顔を上げた。彼の瞳は、朝の光を映してきらめいている。
「おはようございます……」
少し照れながらも、麻衣は彼の腕の中で身動きした。
孝宏は、麻衣の髪を優しく撫で、額にキスをした。その指先が、麻衣の髪を絡めるように梳き、額に触れる感触は、昨夜の熱を思い出させた。
「よく眠れた?」
「はい……。孝宏さんの隣だと、すごく安心して眠れます」
麻衣が素直に答えると、孝宏は嬉しそうに微笑んだ。
「僕もだよ。麻衣さんが隣にいると、心が落ち着く。ずっとこうしていたいな」
二人はしばらくの間、言葉もなく抱きしめ合った。
この穏やかな時間が、何よりも尊いものだと麻衣は感じていた。
ベッドから出て、孝宏は麻衣のためにコーヒーを淹れてくれた。挽きたての豆の香りが、部屋いっぱいに広がる。
麻衣は孝宏のシャツを借りて身につけ、ソファに座って彼が淹れてくれるコーヒーを待った。
「はい、どうぞ。麻衣さんの好きな淹れ方にしたよ」
孝宏の手から差し出されたマグカップは、温かい。
一口飲むと、芳醇な香りが口の中に広がり、昨夜の余韻とともに、麻衣の心を満たしていく。
「美味しい……」
「それはよかった。麻衣さん、今日、もしよかったら、僕の部屋でのんびりしない?ランチも僕が作るよ」
孝宏の誘いに、麻衣は嬉しそうに頷いた。
普段は忙しい孝宏と、こうしてゆっくりと過ごせる時間は、麻衣にとってかけがえのないものだった。
二人は、ブランチを作り、音楽を聴き、他愛ない会話をしながら、穏やかな休日を過ごした。
孝宏がふと麻衣の頭を優しく撫でた。
「麻衣さんの髪、今日もすごくいい感じだね。僕の指が、いつも麻衣さんの髪を求めてるみたいだ。」
その指先が髪に触れるたび、いつも電流が走るようにビリビリと甘い痺れが全身を駆け巡る。
麻衣は確信した。これからも、きっと彼の甘い指先に、ずっと囚われていくのだろうと。
この日、二人の関係は、体だけではなく、心でも深く結びついたのだった。
END
あらすじ
麻衣はお気に入りのヘアサロンの担当スタイリスト、孝宏のことが気になっている。
一人の客として相手にされるわけがないとわかっている彼女はその想いをひた隠しにし、今日もサロンを訪れる…
















