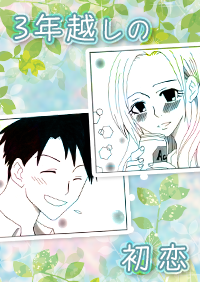女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
官能小説 ウーマン・オブ・プラネット 5話 〜仕事と恋愛の狭間で〜
雨の香りと、薔薇の香りと
花屋の路地を曲がると、一軒家の小さな店が佇んでいる。
白亜色のモダンなドアを開けると、そこは私の城。
正確に言えば、マスターが午前0時に戻るまで、私が任されているバーだ。
カウンター10席とテーブル3つ、合計20席の空間は、
ベネチアングラスのような光沢のある壁が、
スワロフスキーの飾りのシャンデリアできらきらと光っている。
棚には200種類以上の酒類がずらりと並び、
カウンター席では、水晶の花瓶に生けている深紅の薔薇が、甘い香りを放っていた。
バーテンダーを志望したのは偶然だった。
派遣社員で働くことに不安を感じ始め、
そこで求人サイトの「仕事をしながら手に職がつく」というカテゴリーから、
バーテンダーがヒットした。
最初は半信半疑だったが、
お酒も接客も好きだった私は面接ですんなりと採用され、
2年後に今の店にスカウトされた。
仕事が楽しくあっという間に半年が過ぎた。
お酒の在庫をチェックしてからカウンターキッチンで洗い物をしていると、 ピンクの薔薇の花束を抱えた商社マンのタカさんが勢いよくドアを開けた。
「商談成立!嬉しくて絵里ちゃんに花をプレゼントしたくなったんだ」
カウンターで華やぐ深紅の薔薇と、 タカさんからもらったピンクの薔薇との組み合わせで 店はたちまちゴージャスな雰囲気になった。
「ありがとう。嬉しいわ」
「絵里ちゃんには毎日プレゼントを贈りたい。今度一緒に食事しよう」
強引な商社マンのタカさん。会うたびにいつもアグレッシブに口説く。
「すぐにOKを言わない絵里ちゃんが好きだよ。仕事が終わったら、また来る!」
タカさんがドアを閉めると、裏口のほうから氷の業者の気配がする。 届いた氷を取りに行こうとするとドアが開き、 ぱっと雨の香りが舞い込んだ。
「急に降ってきたよ」
雨に全身が濡れたマサヤさんが駆け込んできた。 タオルを差し出すと「ありがとう」と雨の滴をふき取る。 ヘアクリームがとれてくせ毛が現れたマサヤさんは、 少年のようなあどけない顔になった。
髪がくしゃくしゃのマサヤさんのスマホが鳴った。 会社からのようだ。 受けたマサヤさんが「わかりました」と静かに返事をする。
「雨宿りだけして、ごめん。仕事が終わったら、必ず寄るから」
店に置いてあるビニール傘を渡すと、マサヤさんがにこっと笑った。 無口な人の笑顔が心に残り、雨の香りと、薔薇の香りがまじりあう。
ふと一週間前に見た夢を思い出した―――
窓の外は冷たい雨。 ぬくぬくと暖かな羽毛ベッドで、彼に抱かれた余韻が残っている。
「ねえ、どうしたら感じるの?」
「男が女に尋ねるみたいだね」
目を閉じて嬉しそうに笑う彼。
横になりながら彼の一番感じやすいところを指で撫でてあげる。
「くすぐったい」と体をよじるので、片方の手を彼の背中に廻す。
耳元で「指より舌がいいの?」と囁くと、
「エッチ」とさらに体をよじって、今度は私の敏感な部分に指を入れる。
「濡れているよ。本当にエッチだなぁ」
鋼鉄のように鍛えあげた体と真夏の陽光で焼けた艶肌で、 まるで黒い豹のようにしなやかに動きながら、 私の耳朶、首筋、乳首にキスをしてから、 肩のホクロを歯で軽く噛み、長い脚を私の脚に絡めながら、 唇を強く吸い上げる。
「そんなにエッチなら、また食べちゃうよ」
と、じっと私を見つめる。彼の目の奥に強い欲望の光が宿っている。 その瞬間、再び彼の熱い息づかいに身を任せていく。
下半身が熱くなった瞬間に、目が覚めた―――
黒い豹のようにしなやかに動く男。 夢の中で私を愛撫するしぐさの一つ一つを思い起こすたびに、 体が火照ってしまう。 いけない、開店の時間が過ぎている。 そのときドアが開いて、数人の男性客が騒々しい声をあげて入ってきた。
「いらっしゃいませ」
最初のお客さん達を笑顔で出迎える。一日がスタートするのだ。
午後11時少し前に、タカさんがやってきた。 この時間帯から、マスターとチェンジする午前0時までの間は、 ほぼ常連さんだけになる。
「僕は絵里ちゃんが好きだから」とタカさんが堂々と宣言してから、 「夜景が綺麗で料理もワインも最高のレストランに行こう。今度の休みはいつ?」 と他のお客さんの前で、口説く。
やんわりとかわすと、マサヤさんが入ってきた。 「ありがとう」とビニール傘を返すマサヤさん。
「マサヤくんに親切だね」と他の客がタカさんを肘でつつくと、タカさんが
「絵里ちゃんは誰にでも優しい。だから競争率が高いんだよ」
と負けずに言い返す。
マサヤさんがシングルモルトのダブルを無言で飲んでいると、 ふいにドアが開いた。
照明に照らされた黒のレインコートの男と目が合った。 5年前の記憶が一度に蘇る。 私から別れを切り出したリュウヤだ。 黒のレインコートを脱ぐと、 シャツの間から鍛え上げられた筋肉が見え隠れする。 夢の中の黒豹のような男と、リュウヤがクロスした。
一番感じるところに唇を…
仕事が終わり、バーの裏口から出ようとすると、男が待っていた。 一杯だけ飲んで帰った元カレのリュウヤに似た黒いコートの男だった。
バーで逢った瞬間は、リュウヤだと思い込んだ。 動悸を抑えながら、注文のカルバドスのロックを差し出すと、 「どうも」と頭を下げた。 声はリュウヤと違っていた。
リュウヤに似た男は裏口で、リュウヤの弟だと名乗った。 驚いて少し後ずさりをすると、突然の訪問を謝罪してから、 リュウヤから預かってきたという文集を返しに来たと言った。
リュウヤから、小学生のときに親が離婚してから 5人兄弟が離れたことを聞いていた。 複雑な家庭環境のせいか、リュウヤは情緒不安定なところがあり、 ときどき拳を挙げて周囲と大喧嘩することもあった。 リュウヤを支えきれなくて、5年前に私から別れを切り出したのだ。
付き合って間もない頃に、転校を繰り返していたリュウヤから、 楽しい学校の思い出がないからと頼まれて、 田舎の学校の文集を貸していたことを思い出した。 代理で文集を返してくれた弟が、 リュウヤはライフプランナーとして トップセールスマンになった年に結婚したと教えてくれた。 来年親になるのだという。
リュウヤの弟と別れてから、駅まで急ぐ足が重い。 リュウヤが真面目に働くようになったのは、 きっと奥さんの影響が大きかったのだろう。
ふいに寂しさがこみあげてくる。 自分から振った男なのに。 リュウヤの力になれなかった自分が不甲斐なかった。
翌日のカクテル勉強会に参加しながら、バーテンダー2年目の焦りを感じた。 昼食タイムになったので会場を出ると、スマートフォンが鳴った。
求人サイトの子会社のヘッドハンティング会社からだった。 今よりも収入や条件が充実している企業経営へのバーの転職を勧めるメールが、一週間前に届いた。 バーテンダーの世界は狭くしがらみもあるので、 同業者から引き抜かれるより、企業から引き抜かれる方が、気が楽だ。 だが、自分の方向性がまだわからない。答えが見つからない。
「まだ考え中です」
言葉を濁しながら、スマートフォンを切った。
いつものように店に入ると、電話が鳴る。 マスターからだった。
「ごめん!インフルエンザになってしまった。休むから0時で閉店してくれ」
一人で店を閉めるのは初めてのことだった。 その日は夜が更けるにつれて、人が増えて賑やかになった。 ふと気が付くと、午後11時を過ぎている。 カウンターには、タカさん他数人の客が残っていた。 マスター目当ての客さんがやってきたので、事情を伝えると、 「また来る」と帰っていく。 残ったお客さんも次々と帰り、タカさん一人だけになった。
「手伝うよ」
黙々とグラスをカウンターの一か所にまとめてくれたり、 乱雑になっている椅子を整えたりと、 甲斐甲斐しく手伝ってくれるタカさん。意外だった。
午前0時が過ぎたころに、やっと後片付けが終わった。
「送るよ。その前にお腹も空いたから、どこかで軽く食べようよ」
タカさんが私の手を握った。
「疲れているんだね。僕が慰めてあげる」
いつもアクレッシブに口説いていたタカさんが、 優しい手つきで私の下着を脱がせてくれる。 するするっとブラジャーが外れると、 恥ずかしくて、思わず両手で乳房を隠した。 乳房を覆う手を握ったタカさんが、私の指をゆっくりと舐めた。 指の間から舌を出して、乳房を舐める。
「あ、いや」
手が緩むと、すかさずタカコウタさんは私の手を払いのけて、 露わになった乳房にかぶりついた。
「マシュマロみたいだ。いい香りがする」
乳首を吸い上げながら、パンティーを脱がせる。 素早い動きで私の上に乗り、茂みの奥の敏感な部分に指を入れる。 私はもう、濡れていた。
「ずっと欲しかったんだ…」
腰に手を当ててから、私の体を持ち上げる様に抱きかかえてから、 一番感じるところに唇をつけて、強く吸い上げていく。
「あ、もうだめ。いきそう」
「まだダメだよ」
いやいやと首を横に振って、「早く入れて」とお願いすると 「そんなに欲しいの」と、今度は私をうつ伏せにして、後ろから指で乳首を愛撫する。 さらに一番感じる部分に後ろからキスをしようとする。 アクロバティックなタカさんの動きについていうとすると、頭が真っ白になった。
「お願いだから…」
うつ伏せになった私が体をよじると、 「入れてくださいとお願いしてみて」と命じられる。 押し寄せる快感の波にのまれないように、 私は「お願い」と言い続けた。
黄色い薔薇の花言葉
インフルエンザを完治したマスターが復帰してから、二週間経った。 いつものように開店の準備をしていると、 花屋が黄色い薔薇の花束を抱えて入ってきた。
「マスターからです。絵里さんに渡すように、メッセージカードも一緒に」
「素敵な薔薇でね、イエローの薔薇。あまり見たことがないわ」
「特注なんですよ、マスターの」
「今日は特別なお客様でもいらっしゃるのかしら?」
呟きながら、水晶の花瓶に生けてカウンターに飾ると、 いつもより華やいだ雰囲気が広がった。 メッセージカードを開いた途端に、私は言葉を失ってしまった。
『Dear 絵里ちゃん
お仕事いつもお疲れさま。一生懸命に働いてくれてありがとう。 マスターは感謝でいっぱいです。 黄色い薔薇をカウンターに飾ってくれたかな。 綺麗でしょ。僕は黄色い薔薇が大好きです。
ところで、絵里ちゃんは、黄色い薔薇の花言葉を知っていますか。 僕はいつも黄色い薔薇を綺麗と称賛していたんだけど、 ある日、その花言葉を知って、驚いたんだよ。
黄色い薔薇の花言葉、それは「ジェラシー」。
綺麗な薔薇には棘があるというけど、花言葉にも棘があるんだね。 最近、絵里ちゃんが少し落ち着かないようだけど、大丈夫かな?
お客様っていうのは、自分がいつも一番だと思っているわけよ。 特に女性のバーテンダーに対して、一番の客だと思いたいわけ。 だから彼氏ができると、敏感なんだよなぁ。 お客様の嫉妬や思惑をうまくかわしながら、 楽しませるのも、仕事のうちだよ。 彼氏ともお客様とも、うまくやってね』
マスターのアドバイスに、思わず胸が苦しくなった。 タカさんと一夜を共にしてから、 店で露骨に愛情表現をしてくるようになった。
他の客から冷やかされたときに、すぐにかわせないと 「未熟だな」とつい自分を責めてしまう。 常連の女性客から「気にしない、気にしない」と慰められるものの、 はずみでタカさんと付き合ってしまったようなものだから、 タカさんとの関係を守ろうとする気持ちも弱いのだ。
その夜は、マスターのバーテンダー友達の予約が入っていたため、 午後9時からカウンターに入ったマスターと一緒に仕事をすることになった。
営業中に氷がなくなったため、 近くのコンビニに買い出しに出かけようとすると 「僕も手伝うよ」と、マサヤさんが同行してくれた。 氷の袋を二人で抱えながら歩いているときに、 ふいにマサヤさんが、ぼつりと言った。
「恋愛に生きるか、それとも仕事を選ぶか、 どちらかに決めたほうがいいと思うよ」
驚いてマサヤさんの顔を覗き込む。 真面目な表情だが、いつもとは違って饒舌だった。
「僕は会社で、人材をデザインする仕事もしているんだ。 人材育成、いわゆるブランディングだよ。 そこで感じるのは、恋も仕事も手に入れたい女性が多いけど、 プロフェッショナルを目指すなら、 ある時期は仕事に専念するほうがいい。 プロフェッショナルな目標が達せられたときに、 恋愛にも余裕が出てくる。 これは男も女も同じ。 たくさんの人間をデザインしてきたから、 言えることかもしれないけどね」
マサヤさんの言葉に心を打たれた私は、 マサヤさんにヘッドハンティングのことを打ち明けた。
「新しい場所で、チャレンジしてみたいんです。自分をもっと成長させたいから」
「絵里ちゃん、自分で答えを出したね」
にっこり笑ったマサヤさんの笑顔が眩しかった。
夜景が美しい高層階のホテルバーで、 私はカクテルを次々と作っている。 アレキサンダー、フローズンストロベリーダイキリ、楊貴妃… 女性客が多いから、一晩で50以上のカクテルのオーダーが入る。 もうじき閉店の時間だ。
バーの裏口からロッカーに向かう。 従業員出入り口を出てから、正面玄関に回り、 ホテルの客室に向かった。 地方のリゾートホテルから帰ってきた彼が、 スイートルームで待っているはずだ。
婚約したのは、つい1ヵ月前。 4年間務めた今のホテルバーを続けるという条件で承諾すると、 彼は出張で地方に飛び、さっき帰ってきた。 わざわざ私のためにスイートルームを用意してくれるなんて、嬉しい。
ドアをノックすると、バスタオルをまとった彼が出迎えて、キスをした。 私もシャワーを浴びてから、シャンパンで乾杯をした。 彼はシャンパンを飲み干すと、 私を抱きしめて、何度もキスをする。 バスローブの紐が緩んで、乳房がぽろりとこぼれだした。 あわてて手で隠そうとすると、 「絵里は可愛い」と手を掴んで、私をソファーに押し倒した。
「ベッドに行きましょう」
ベッドで彼は、足の指先から、丁寧に舐めていく。 私は彼の頭を撫でながら、「優しいのね」とうっとりとすると、 彼がさらに念入りに、足首、太もも、下腹、そして繁みへと ゆっくりと舌でベトベトに舐めながら、 「絵里の全てが好きだよ」と呟きながら、 私の手を取って、自分の股間に触らせる。
既に大きくなった彼の股の下にあるものに、 「いやぁ」と声をあげてから、 思わず「マサヤ」と言いそうになって、 あわてて口をつぐんだ。
婚約者の名前は「ユウヤ」。 仕事とは何かを教えてくれたマサヤさんと似たような名前だが、 マサヤさんとは正反対な性格。 ユウヤは見事に鍛えた筋肉で私を抱きしめる。 夢の中に出てきた黒豹のような堂々とした体躯だ。 今頃、物静かでクレバーなマサヤさんは、あのバーで飲んでいるのだろうか。
ふっとマサヤさんの顔を思い浮かんだ瞬間、 ユウヤが私の体に入ってきて、激しく動いた。 二人の男たちの顔が交錯していく中で、私もやがて果てていった。
END
この小説に関連するおすすめコンテンツ
今、人気・注目のタグ<よく検索されるワード集>(別サイト)
あらすじ
絵里は路地裏の小さなバーで働くバーテンダー。
手に職をつけるために半信半疑でバーテンダーになったが、お酒も接客も好きだった絵里には天職だった。
仕事に没頭し恋愛からは遠ざかっていた絵里の前に突然現れたのは…?