女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
官能小説 恋欠女子とバーチャル男子 StoryA 伊川咲の場合 シーズン2
代わりにお前が
『体調は大丈夫か。ひょっとして、大変なことになっているんじゃないか。
もし迷惑じゃなかったら、今から家に行って看病しようか』
そんなメールを送ってきたのは、上司の荒木さんだった。
(ひ、ひえええっ)
声にならない悲鳴をあげてしまう。
荒木さんは確かに頼れる上司ではあるけれど、それはあくまでも上司としてであって、これはさすがに遠慮してしまう。
めまいがしてきた。
それを我慢しながら、返信メールを打つ。
『大丈夫です。もう快方に向かっています。何日もお休みしてしまい、申し訳ありません。すぐに復帰できると思います』
***
「だってよ。まあ、俺に人望がないのはわかってたけどよ」
荒木さんは会社のカフェテリアで、一緒にお茶を飲んでいる俺、和田恵一に、伊川さんからの返信を表示させたタブレットを見せた。
伊川さんに休まれると、アイのプロジェクトは進まない。
俺たちはスケジュールの仕切り直しまで視野に入れて、今後どうするかを話し合っていた。
幸い、このプロジェクトは完全に自社だけで完結しているので、スケジュールは比較的柔軟に変更できる。
「あいつは仕事以外は不器用そうだからな。ロクなものを食べていないんじゃないか」
「心配する気持ちはわかりますけど、いきなり上司からこんなことを言われたら、そりゃあびっくりしますよ」
俺は苦笑いでタブレットを返す。
この人は開発や研究に関しては天才的なところがあるが、人との距離の取り方が……よくいえば個性的だ。
「それにしてもなあ、今、ダウンされても困るんだよな。本当は今日、様子を見に行って、継続が難しそうだったらいったんプロジェクトマネージャーから外そうとも思っていたんだよ。いくら自社開発といっても、あまり大幅に延期するわけにはいかない。無理をしすぎるのは、あいつ自身にも会社にもよくないだろう。抜擢は、やはりまだ早かったな」
「そんなこと、ないと思いますよ」
俺個人としては、彼女にはその実力はあったと思っている。
ただ、少し前から妙なイメージチェンジを図るなど、おかしかったことは間違いない。
今回の一連の遅れはそれが悪く影響してしまった結果ではないのか。
であれば、まずはいったい何があったのか質すのが先決ではないだろうか。
結果メインで人を評価するこの業界で、こういう考え方をするのはごく少数派だとわかっている。
でも、べつに伊川さんに対してだけではなく、俺は誰に対しても結果だけで切り捨てたり掬い上げたりするようなデジタルな人間にはなれない。
単にサポートが細かいだけでなく、こんな性格も、「世話女房タイプ」なんて呼ばれることになった理由の一端を担っているのかもしれない。
「あ、そうだ。じゃあ代わりにお前が行ってくれないか」
「え」
「サブマネージャーだったら遠慮することもないだろうしな」
「そういうことじゃない……」
言い終わるよりも早く、荒木さんはメールを送ってしまう。
数分後、『和田さんだったら、まあ……』という、承諾はしているものの、あまり気乗りしていなさそうな返事が来た。
「様子を見てくるだけでいいんだ。頼んだぞ」
「えー……」
眉をひそめてみせる。
上司よりマシとは言っても、同僚としての接点しかない男にいきなり家に押しかけられるのはイヤだろう。
二度連続で持ち掛けられて、断りづらかっただけじゃないのか。
だが、荒木さんはこうしたほうがいいと考えたら退かないタイプだ。
そのとき、気づいたことがあった。
気のせいかもしれないけれど、荒木さん、ちょっと寂しそうな顔をしていないか。
ひょっとして伊川さんに特別な思い入れがあったとか……?
(いやいや、まさかこの人に限って……)
俺は心の中で首を横に振ってから、「わかりました、行ってきます」とため息交じりに答えた。
あったかくて、甘い
私、伊川咲は後悔していた。
和田くんが来ることについて、「荒木さんが来るよりは……」とついOKしてしまったのだ。
(こういうの、心理学で何か専門用語があったな。受け入れがたいものの後に、それよりハードルの低いものを提示されると、受け入れてしまうという……)
が、何を思ってももう遅い。
今さら「やっぱり来ないでください」とも言いづらい。
幸い、家はいつでも人を呼べるぐらいにはきれいに保っている。
結も私も、きれい好きなのだ。
(仕方がない。あきらめよう。あきらめて、やりすごそう)
和田くんが来るまで、もうひと眠りすることにした。
***
「本当は荒木さんが行こうとしたんだけど、あまりにも伊川さんが遠慮しているからって、代わりに俺が……いきなりすいません」
到着早々、俺はいきなり言い訳した。
自分の意志で押しかけたのだと思われたくない。
「ごめんなさい。いつもだったら妹がいて、頼れるんだけど。フリーライターで、ちょっと前から取材旅行に出ているの」
なぜか伊川さんも謝る。
妙な空気感だった。
伊川さんはさっきまで寝ていたらしい。
パジャマにパーカーを羽織っただけの格好だった。
手ぶらで行くのもなんだからと、俺はリンゴを買ってきていた。
「キッチン、使ってもいい?」
「自由に使って。妹はグルメライターだから、変わった調味料とかたくさんあるけど」
俺はキッチンに立って、さっそくリンゴ粥をつくり始めた。
すりおろしたリンゴを砂糖で煮て、温めた牛乳をかける料理だ。
するすると口に入るわりには栄養価が高く、子供時代、風邪を引いたときには必ず母親がつくってくれた。
調味料棚にはバニラビーンズもあったので、軽く振りかける。甘い香りがほわりと立ち上った。
「お待たせー」
できあがったりんご粥をお盆に乗せ、伊川さんのいる寝室に持っていく。
「うちは、体調不良といったら昔からこれなんだ。よく母親がつくってくれた。俺も下の兄弟につくったよ」
「そうなんだ、ありがとう」
伊川さんは微笑んで、スプーンを手にとった。
湯気の立つすりおろしリンゴを掬い、口に運ぶ。
「あったかい。あったかくて、甘い……」
その目がみるみるうちに潤んで、ぽろりと涙がこぼれた。
驚いたが、胸のどこかでなんとなく「ありえること」だと予測していたような気もした。
俺は黙ってティッシュを一枚取って渡した。
「あ……ごめん。私……泣いたりとか、そんなつもりなかったんだけど。あったかくて、おいしくて……ちょっとだけ、悲しくなって……」
伊川さんは鼻をすすりながら、ティッシュで涙を拭く。
「伊川さん、何があったの?」
俺は傷ついた蝶にそっと触れるように、言葉に力を入れないようにして尋ねた。
「もちろん、言いたくなければ言わなくてもいいけど」
いい仕事をしてほしい
「これは別に、教えてほしいと催促する意味で言うんじゃないけど」
俺は続けた。
「伊川さんが急にイメージチェンジをしたこと、何となく心配になっていたんだ。仕事もうわの空だし、しっかりしてほしくてつい強い口調になってしまった。もし君に何か起こっていたのだとして、あれで傷つけていたのだったらごめん」
伊川さんはぽかんとした表情でこちらを見つめた。
そんなことを言われるなんて思ってもいなかった、とおでこに書いてありそうな顔だ。
「ううん、悪いのは私だよ。同僚がちゃんと仕事をしないことを注意するのは、悪くも何ともない。和田くんは当たり前のことをしてくれただけ」
そう言われると少しほっとしたが、根本的には何も解決していない。
伊川さんに何があったのかはわかっていないままだ。
とはいえ、ひたすら押して喋ってもらうのは本意ではない。
俺はもう、引くことにした。
「サブマネージャーは、マネージャー一人では抱えきれないことに対応する役目だ。もし何かあったら、いつでも遠慮なく声をかけてほしい。べつに仕事じゃなくてプライベートのことでも、できるだけ相談に乗るようにする」
我ながらカッコいいことを言うものだと思った。
でも、べつにポイントを稼ごうとしたわけではない。
俺は本当に伊川さんを評価している。
人間的には少し幼いところもあるけれど、頑張り屋だし、それに結果が伴う様子を見るのもすがすがしい。
だから伊川さんには、いい仕事をしてほしいのだ。
「うん、ありがとう」
伊川さんはそれっきり黙った。俺も何も言わなかった。
りんご粥をすする音だけが、再び部屋に響く。
「ごちそうさま」
時間はかかったが、皿は空になった。
「よかった。食欲はあるみたいだね」
「ここ数日なかったんだけど、すごくおいしかったから」
皿を下げて横のサイドテーブルに置く俺に、伊川さんは笑いかけた。
そのとき、あ、なんかちょっとかわいいなと、思ってしまった。
「和田くん、あのね」
思っていたことが思っていたことだったから、伊川さんがまっすぐに見つめてきたとき、ドキっとした。
「全部、話すよ。迷惑かけちゃったし、これからの仕事のことも考えると、和田くんには知っておいてもらったほうがいい気がする」
「……いいよ、無理しないで」
聞きたくはあるが、傷つけてまでではない。
「ううん、話す。りんご粥があんまりおいしくて、なんだか、いろんなことに対して元気が出てきたというか……とにかく前に進めた感じがするんだ。おいしいものって、すごい力があるんだね。妹がグルメライターをしている気持ちがわかった気がする」
伊川さんは、教えてくれた。
アイの完成度を上げるため、女心を知る目的で、妹さんの協力を得て女性らしくなろうとしたこと。
そうしたら、男性から声をかけられるようになったこと。
その中の一人の男性を悪しからず思ったので何度か食事に行ったが、相手は本気ではなく、遊びのつもりだったらしいこと。
その男性とやらが誰なのかは、さすがに話さなかった。もちろん俺も尋ねない。
でも、話しぶりから社内の誰かなのだろうというのは推測できた。
押し倒すような格好
すべて話してもらった後、何と声をかけようか迷ったが、仕事の話に落としこむような形にした。
単なる同僚に、あまり深入りするようなことを言われてもいやだろう。
「精神的な落ち込みは、人間である以上仕方のない問題だからね。アイは幸い自社だけで回している実験的な開発だし、リリース時期を遅らせよう。体や心を壊してしまっては元も子もない」
「でも、私はプロジェクトマネージャーだし……」
伊川さんは頷く。
責任感ももちろんあるだろうし、せっかく手にしたポジションを失うのも怖いのだろう。
荒木さんの、結果を出すことへのシビアさを、俺たちはみんな知っている。
「大丈夫。荒木さんには俺から説明しておくよ。今、スケジュールを切っているのは俺だからね。どうとでもなる……とはいえないけど、多少の融通は効かせられると思う」
「……ありがとう。ほんと、助かる」
伊川さんは、ほっとしたような表情になった。
「食器、洗ってくる」
俺は空になった皿を持って立ち上がろうとした。
「洗い物ぐらい、私がやるよ」
「でも、まだ本調子じゃないだろう」
「もうだいぶよくなったよ。それにりんご粥のおかげで体も温まったし」
伊川さんは俺に行動させまいと、横から皿を取ろうとする。
「だめだってば」
伊川さんの肩を軽く掴んで、ベッドに戻そうとした。
「いいよ、これぐらいやらせて」
知ってはいたが、伊川さんはなかなか頑固だ。
つい、肩を押す力に手を込めてしまった。
その拍子に、伊川さんはベッドに仰向けに倒れた。
「え……」
そんなに力を入れたつもりはない。
思ったよりも伊川さんがか弱かったのだ。
急に力の向きが変わったので、俺も前のめりになった。
「……!」
俺は、伊川さんをベッドに押し倒すような格好になってしまった。
「あ……」
突然のことに、体がすぐに反応してくれない。
見つめ合ったまま、顔に血が上っていく。
どく、どく、と早鐘を打ち始めた心臓の鼓動が、自分のものなのか、伊川さんのものなのかわからない。
「あ、わ……っ、ごめん」
我に返って、慌てて体を離した。
「わ、私のほうこそごめん」
伊川さんも俯いて謝った。
伊川さんはべつに悪くないのだが、こういうときに何と言っていいのかわからなかったんだろう。
結局、食器は俺が洗った。
「じゃあ、帰るね。荒木さんには話しておくから、安心して休んで。こういうのは治りかけが肝心だっていうからね」
「ありがとう」
玄関まで見送りにきてくれた伊川さんに手を振って、家を後にした。
まだ顔が少し熱い気がした。
こ、告白とか……?
念のため翌日もう一日休んで、出社したのは翌々日だった。
正直なところ、ほかのメンバーたちの目が怖かった。
プロジェクトマネージャーなのに何を呑気に何日も休んでいるんだ、マネージャーの自覚がないんじゃないのか……直接言われることはなくても、そう思われるのは当然だ。
私がメンバーの立場だったら、遠慮なくそう思うし。
だが、メンバーたちは暖かく迎えてくれた。
「入院直前までいったそうですね。無理しすぎないで下さいよ」
「あまり着ないタイプの服を着て、お腹とか冷えたんじゃないですか、なんて」
入院? と首を捻りかけたが、向こうにいた和田くんがウィンクしてくる。
どうやら和田くんが、私の立場が悪くならないようにうまく説明してくれたらしい。
「あんまり根詰めすぎるなよ。体調管理も仕事のうちだが、だからこそ具合が悪いと感じたら早めに休んでおけ」
荒木さんも、それほどきつい叱り方はしないでくれた。
ランチの時間、私は和田くんを誘った。
「お礼だから」と、近所の少し高級なお蕎麦屋さんに行って、食べたいものを食べてほしいと促す。
和田くんはざるそばを頼んだ。
「余計なお世話かなとも思ったんだけど。あ、余計なお世話ついでに、もうひとつ提案がある」
ざるそばを空にした後、和田くんは指を一本立ててみせた。
「アイの最終調整のこと。伊川さんだけが一人で何とかしようとする必要はないんじゃないかな。例えば男女一緒に会話をすることで、さらに複雑な神経系統を構築するというような方法でも、完成度は上げられると思うんだ」
「なるほど……」
私は深くうなずいた。
アイは一対一での使用を想定しているが、テストと割り切るのなら、複数を相手にするのでも、考えていたのとは違う方向からより柔軟な「性格」を獲得できるかもしれない。
「正論ばかり言う」のではない、人間らしい揺れ幅がある性格を。
私は今度は、男女のペアでアイのテストに協力してくれる人を募った。
私自身は和田くんと組んだ。
和田くんのことは、この間のお見舞いのこともあったし、もともと優しくて誠実な人だとは思っていた。
このテストの中で、それは確信になった。
私が「仕事で疲れた〜」と呟くと、アイは「まだまだ頑張って」と答える。
私のことを「仕事に対して向上心の強い人物」として処理しているから、気持ちをさらに盛り上げるようなことを言ってくれるのだ。
正しい反応だと私は思う。
だが和田くんは苦笑した。
「違うよ、アイ。そういうときは『お疲れ様。でも、あんまり頑張りすぎないでね』って言ってあげるんだ。頑張り屋がどこまでも頑張ったら倒れちゃうから、誰かがほどほどのところで止めてあげないと」
「そういうものなんだ。覚えた」
アイは再度私に向き直り、にっこりと笑う。
「咲さん。仕事を頑張るのはいいことだけど、たまにはおいしいものを食べてゆっくり休んで。あまり頑張りすぎないでね」
***
製品テストは順調に進み、リリース日が近づいてきた。
ある日の仕事帰り、和田くんに「二人で前祝いでもしない?」と食事に誘われた。
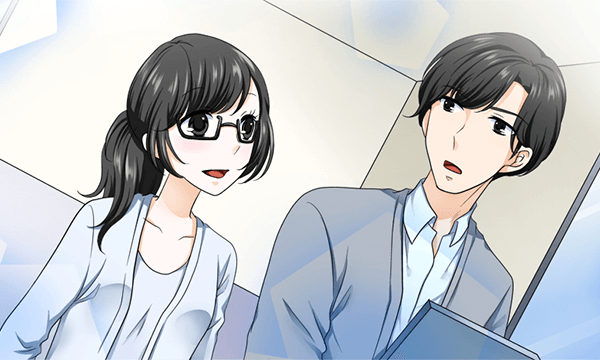
ずっと一緒に仕事をしてきたけれど、改めてこんなふうに誘われると、なんだかドキドキしてしまう。
「あ、う、うん。いいね」
そのドキドキには気づかれないように答えた。
私たちはアイに協力してもらって、美味しそうな和食の店を選び、週末に予約を入れた。
約束の日、和田くんは私の家の最寄りの駅まで車で迎えに来てくれた。
「久しぶりに実家に置いてある車を出してきちゃった」と、なぜか照れくさそうだ。
おいしい食事に舌鼓を打った後、軽くドライブをすることにした。
「どこか行きたいところがある?」
「そうねえ……」
私は平静を装って考えるふりをする。
内心では、食事を誘われたとき以上にドキドキしていた。
食事中からずっと、予感があったから。
ドライブに行った先で、何かが起こりそうな気がする。
(こ、告白とか……? いや、まさか……っ)
⇒【NEXT】「もう、遠回しに言うのはやめにするよ」(恋欠女子とバーチャル男子 StoryA 伊川咲の物語 シーズン3)
あらすじ
なんでも相談に乗ってくれるアプリの開発中、行き詰まり体調を崩してしまった咲。
そこへお見舞いとして同僚の和田がやってきて…?


















