女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
官能小説 秘密の氷が溶ける音 最終話
コンプレックスの核
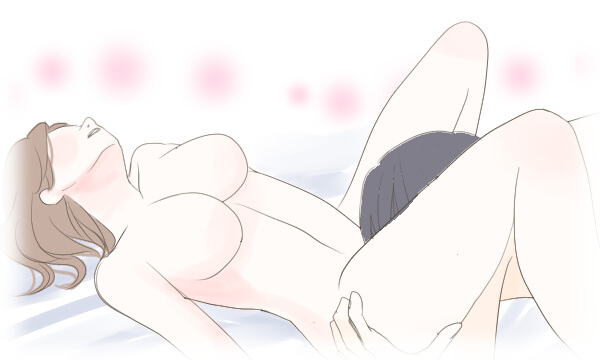
「こっちも、舐めていい?」
意志のこもった声と、太ももの間に忍ばせる手に、私は自然と、ほんの少し頷いていた。
マシュマロをつぶさないような柔らかさで、洋平は私の脚の間に入り、私の手を握ると、花びらに口づけた。
「あぁ」
まるで全身が彼の舌に包み込まれているような錯覚に、全身がじんわりと熱を帯びる。
そっと優しく花びらを包み込んでいた唇が、チュルチュルと音を立てる。
グッと、彼の手を握る手に力が入った。
「平気?」
即座に口を離して目を合わせる彼に、「して」と返している自分に驚いた。
「よかった」
そう静かに言って、もう一度私のめしべに顔を埋める洋平。
「はぁぁ…」
自分の指で触れるのとは、まるで違う温かみときもちよさに、思わず声が漏れる。
「すごく美味しいよ、夕子さん」
彼の声も、吐息混じりになり、口から漏れる音も、ジュルジュルと、より湿り気を増していた。
彼の舌は、花びらの内側をなぞり、クリトリスから、私のコンプレックスの核の核にも及んでいく。私の心に氷を張り、その氷を厚くし続けてきた核に、私は、やはりまだ緊張していた。 けれど、洋平の舌は、まるで帰って来たかのように、そこに馴染んだ。
「んん…ぁぁ」
ひとつ声がもれると、熱い息が、次々と口をついて出る。 同時に、私のコンプレックスの核で溶けていく氷は、蜜に姿を変えていった。
「はぁ…洋平…くん…ぁぁ」
吐息の隙間から出てくるのは、彼の名前ばかりで、そのたびに、彼は私の名前を呼び返し、手をギュッと握ってくれた。
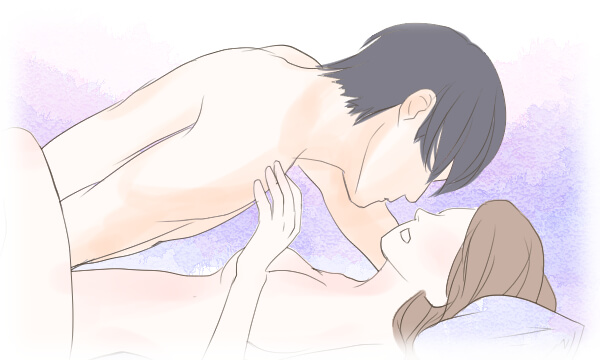
「つらくなったら、言ってね」
仰向けの私の上に四つん這いになって、洋平は、彼自身の先端で蜜の泉の入り口を撫でた。
「うん…」
やはり、緊張が舞い戻ってきた。
初めて男性を受け入れることが、不安なのか。 学生時代の恋人の舌打ちが脳裏にこびりついているのか。 洋平を失望させてしまうことを心配しているのか。 …私の中で、緊張の理由が、入れ代わり立ち代わり顔を出している。
洋平は、少しずつ、泉の入り口に体重をかける。
彼の目をまっすぐに見ながら、意識的に体の力を抜こうとするけれど、呼吸さえもおぼつかない。
「イタッ…」
ミシリと引き裂かれるような感覚に、思わず言葉が出た。
「ご…ごめん」
そう言っていたのは、私だった。
/p>「謝らないで」洋平は、彼自身の代わりに指で泉の入り口を愛撫しながら、たっぷりとキスをしてくれた。
彼の指が、少し、泉の中に忍んでくる。
「大丈夫?」
舌を絡ませながら訊く洋平に「うん…きもちい」と答えた言葉は、本音だった。

ゆっくりと指で私の泉をほぐし、洋平は改めて私の上に四つん這いになる。 そして、本当に少しずつ、私の中に入ってきた。
視線をしっかりと結びながら、彼の肩にしがみつくようにつかまる。 彼自身の圧迫が、体のすべてを支配するような、とても不思議な感覚は、半分は痛みだったと思う。けれど、もう半分は、喜びだった。
「ぁはぁぁ…」
彼が、一瞬目を閉じて、息を漏らす。
「全部、入った、夕子さん」
目を開けた彼は、すごく大人っぽいようでもあり、時折見せる年下の無邪気さもある。
「あぁぁ…」
安心のような、嬉しさのような、何かが終わったような、そして何かが始まったような そのないまぜが、熱い息になって、私の口からも流れた。
「幸せ」
洋平は、そう言うと、慎重に胸を合わせて、再び口づけた。 荒くとも言えるかもしれない彼の舌の動きに、私の舌も同じ激しさで絡まっていく。
「すごくあったかい、夕子さんの中。きもちい…」
唾液を吸いながらそう言うと、彼は徐々に腰を動かし始めた。
「はぁぁ…あぁぁ…」
熱を増す私の息に、彼はもう、大丈夫かと言葉で確かめることはなかった。
「嬉しい…夕子さんと、ひとつ…に…なれて」
「私も…」
彼に合わせて、私も、腰が少し揺れる。 ふたりの波が重なっていくようで、ただ、嬉しかった。
「ありがとう」
快感の息の間から出た言葉に、彼は「俺も、ありがとう」と汗を落としながら答える。
すべてが終わると、私は、頭がうまく働かず、ベッドの上でぼんやりと横たわっていた。その私を、洋平はさらに優しく私を抱き寄せて、また、一晩中腕枕で寝てくれた。
彼色に染まるカラダ
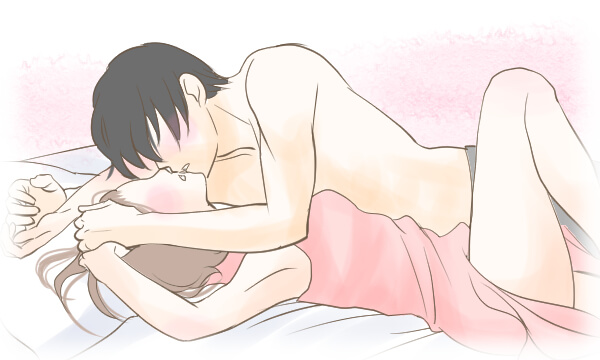
「夕子、この鍋、欲しいんじゃない?」
「ありがとう。でも、洋くんの家にあるお鍋、使いやすいんだよね…」
洋平とつき合い始めて、4カ月。 お互いの呼び方も変わって、結婚の準備のために買い物をしていた。 ひとまずは彼のアパートで結婚生活をスタートさせる予定なので、ほとんど買う物はない。 それでも、ついあちこちに目が向くのは、やはり少し浮かれている証拠かもしれない。
彼のアパートに戻って、新しいリネンをクローゼットに片付ける。 ベッドは「毎晩一緒に寝るからクイーンサイズにしよう」という彼の提案で新調することになったのだ。
「あと何回、このベッドで寝るのかな」
クローゼットを閉める私に、洋平は後ろから抱きつき、抱き上げるとベッドに寝かせる。
「このベッドで夕子を抱けるのも、あと少しだね…」
私の耳に吸い付く彼は、いつも以上に興奮している。
「…うん」
彼の興奮に引き上げられるように、私の熱も一気に上がる。
付き合い始めてから、何度体を重ねただろう。 処女というコンプレックスの氷を彼の腕の中で溶かし、 30歳の誕生日を彼の腕の中で迎え、 彼にも喜んでほしいという愛を彼の腕の中で抱き、 ひとりではなくふたりで味わうオーガズムを彼の腕の中で知り…。 彼の腕の中で刻んだ全ての瞬間が、私を深く癒やしている。
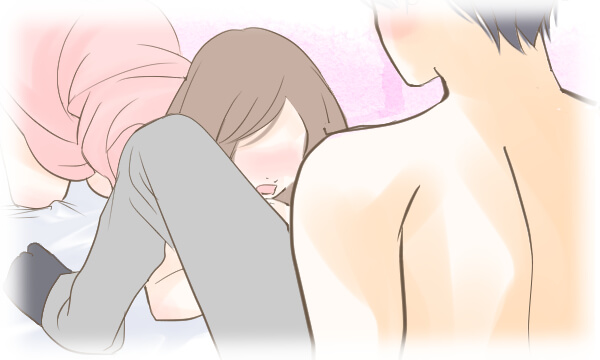
「洋くん、いいにおい」
彼の首筋に顔を埋めると、私の右手は、自然と彼のベルトのバックルに伸びる。
「ベルト外すの、上手になったね」
耳元で聞こえる彼の言葉に、半分は照れながら、もう半分はさらに興奮させられた。
「だめ?上手になったら」
「ううん。いいよ。嬉しい」
彼が私のワンピースをスルスルと脱がせ、私は彼の下着まで一気にはぎ取る。その勢いに、さらに全身が高揚する。
「ねぇ…、舐めたい」
私からそう言ったのは、初めてだった。
「嬉しいな…。夕子がそんなこと言ってくれて」
洋平は、本当に嬉しそうに、半分飛び跳ねるようにベッドの上に座ると、「舐めて」と私の顔を彼自身に誘導した。 彼自身の根元に手を添えてその先端に軽く口づける。ビクッと、彼自身がさらに硬く大きくなるのが分かった。 舌先で彼の先端を濡らすと、ゆっくりと全体に舌を伸ばす。 時々彼自身を口の中に深く含んで、また口から出すと舌を這わせる。
「美味しい…」
彼が私を舐めるときにいつもそう言ってくれるように、私も、同じ言葉が出るようになっていた。
「ぅぅ…いい…夕子、すごく…上手になってる」
私の髪を撫でながら彼の熱い息を聞くと、しゃぶりつくように口に含んでしまう。
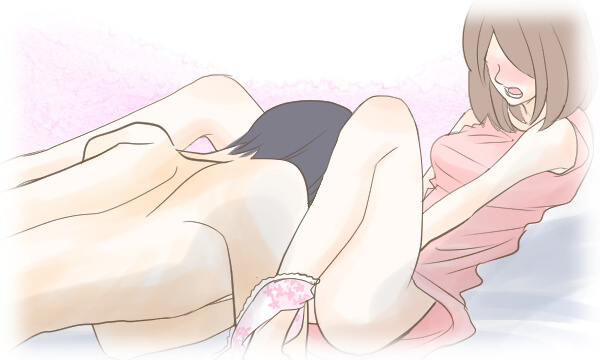
「ねぇ、夕子。我慢できない。…ぁぁ、俺も、舐めていい?」
私の返事を聞く前に、彼は姿勢を変える。 彼の顔は私の脚の間に、私の目の前には、彼自身があった。 私たちは、同時にお互いのカラダに口づけて、ジュルジュルと音を立てて舐め合った。
彼の熱い舌が、私の蜜の泉の中に差し込まれる。
「はぁぁ…洋くん…いい…」
彼自身をほおばりながら、泉の中に彼の舌のざらつきを、もっともっとと求めていた。
「こっちも、好きでしょ、夕子」
蜜をジュッと音を立てて吸い上げると、洋平は、今度はクリトリスを舌でつつく。 すでにすっかり充血して敏感になっていためしべは、一瞬彼の舌が触れただけで、快感の電流が走る。
「あぁぁ…」
彼を口に含む動きが止まってしまうほどの気持よさに、唾液の音がさらに湿り気を増した。
「すごい…たまんないよ…」
洋平は、口の中でクリトリスを転がしながら、泉に指を沈める。
「あぁぁぁ…そこ…いい…」
泉の中の壁の、一番敏感な部分をこすられながら、はじけそうなめしべを舌でねっとりと包まれて、体の芯に熱が凝縮するような熱さを感じる。
「だめ…洋くん…そんなにしたら…」
私の声が聞こえていながら、彼はさらに執拗に泉の壁とめしべとを愛撫する。
「ねぇ…い…いっちゃ…う」
必死で彼自身を舐め回しながら訴える私に、彼は、何も言わずに舌と指の動きを速めた。
ドクドクと脈打つクリトリスも、彼の指に翻弄される泉の壁も、もう、歯止めがきかない。
「あぁぁ…だめ…もぅ…」
口で彼自身にしがみつきながら、私は、遠くへ遠くへと果てた。
私のカラダは、この4カ月で、すっかり洋平の色に染まっていた。
彼がくれた、溶けた氷が育てた、自信
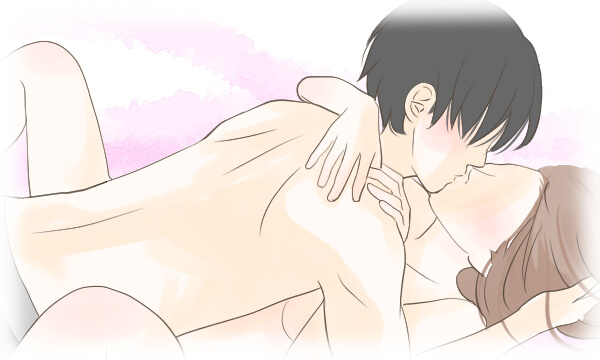
「…いれて」
シックスナインでオーガズムに導かれ、ぐったりとしたカラダから、荒くなった息と共に出てきたのは、彼自身を求める言葉だった。
「上から?後ろから?」
私の好きな体位を把握している洋平は、少し意地悪な声を出した。 その声に、さらに興奮が高まって「上から」と素直に答える。
洋平は、私を仰向けにすると、一気に奥まで貫いた。
「あぁぁ…」
オーガズムの後で、まだ少しぼんやりとしていた全身に、一気に、鋭く快感を掴もうとする感覚が舞い戻ってくる。
「覚えてる?」
腰をゆっくりと前後させながら言う彼に、同じ波長で腰を揺らしながら「何を?」を返す。
「夕子が泣いててさ。処女なんだって教えてくれて。俺、時々、あの夜のこと、思い出すんだ」
「恥ずかしい」
彼の口を慌てて右手で押さえると、彼はその指先を口に含んで、軽く噛む。 そして、チュッと音を立てて吸うと「言わせてよ」と腰をズンと強く奥に突いた。
「はぁぁ」
「何度もあの夜のこと、思い出して。それで、こうやって変わっていく夕子を見て。俺、あの夜の夕子も、どんどん大胆になる夕子も、どっちもどんどん愛おしくなる。そのギャップが激しくなるほど、両方、すごく愛おしくなる」
時々、眉間のシワを深くしながら、彼は、まっすぐに視線を結んだまま言った。
「あぁぁ…。そこ…あぁ…こすって…」
片脚を彼の肩に担がれ、激しく蜜の泉の壁をこすられると、一瞬ごとに敏感になる。
「これ、好きだね、夕子。ほら、ここでしょ。ここ…」
「んん…はぁぁ…そこ…」
「こっちもね…」
そう言いながら乳首に伸びてくる彼の指に、体中の関節が緩んでいくような快感を覚える。 あまりの気持ちよさに体をくねらせてしまう私を、四つん這いにさせ、お尻を高く持ち上げると、彼は、バックから、また一気に私の奥を突き上げた。
「あぁぁ…突く…」
洋平は1本の指でスーッと私の首から腰までなぞると、両手で大きくお尻の肉を撫で上げる。
「夕子、顔、見たい」
しばらく後ろから泉の奥を突くと、洋平は、再び私を仰向けにした。
「可愛いな、ほんと」
激しく腰を動かしながらも、私の顔にかかる髪をそっと優しく指で流しながら、頬を撫でてくれる。
「あぁぁ…洋くん…すごい…」
息がいっそう荒くなる彼に、「私、絶対、洋くんでよかった」と、続けた。
「ほかの人、知らないけど。…あぁ…でも、…私には…洋くんしかいないって…ぅぅ…分かる」
快感に息を詰まらせながら、私は、本音を言葉にする。
「どうして、俺しかいないって分かるのか、分かる?」
まさか質問が出てくるとは思わず、私は、不思議そうな顔をしてしまったかもしれない。
「それはね、俺にも、夕子しかいないからなんだよ」
私が答える前に答えを口にすると、洋平の腰の動きは、一気に速まった。
「あぁぁ…洋くん…ダメ…そんなにしたら…ガマン、できない…」
ダメと言いながら、彼に合わせて、私の腰の動きも激しくなる。
「俺も…。ぅぁあぁ…」
さらに熱の高まった息と腰をぶつけ合い、ふたりともに快楽と苦しさをごちゃ混ぜにした表情になる。
「夕子…っいく」
「私…も」
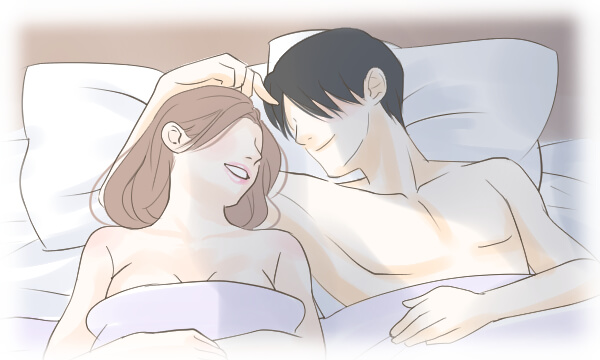
彼の腕枕で抱き合いながら、一緒に少しずつ息を整えて、「愛してる」とキスをする。 やがて洋平は、「夕子…」と半分は寝言で言いながら、眠りについた。
洋平は、私の心にこびりつき、年々大きく厚くなっていった氷を、愛という熱で溶かしてくれた。 その溶けた氷は、“私たちふたり”という土壌に深く染み込んでいるのかもしれない。 処女だったから、心が重かったことは、確か。でも、おしゃれをして、女らしくして…鎧をつけなくてよかった、きっと。愛したい、愛されたいという気持ちに素直になれば、重荷は自然に消えていく。
今の私は、どんな彼でも愛おしいと思う。どんな彼を知ってももっと愛する自信がある。その自信は、どんな私でも好きになる自信があると断言してくれた洋平がくれた、かけがえのない贈り物。洋平が溶かしてくれた氷の、その水が育ててくれた自信。
彼の香りを胸の奥に吸い込みながら、髪を少しだけ揺らす彼の寝息を感じながら、私も、まどろみに沈み込んだ。
END
今、人気・注目のタグ<よく検索されるワード集>
あらすじ
壊れ物を扱うように優しく触れる洋平に対し、夕子は徐々に乱れ、心を開いていく。
少しずつ夕子の中に入る洋平。
彼に体のすべてを支配されるような不思議な感覚は、夕子にとって痛みを伴う喜びだった。





















