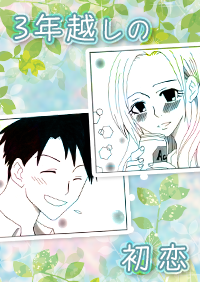女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
官能小説 同居美人 プロジェクトB 〜想子編〜 シーズン12
「俺と結婚してください」
わたしたちはウェディング・プランナーの小島泰明さんのプランニングで、都心からそう遠くない海辺の静かな教会で結婚式を挙げることにした。
小島さんの手際はとても鮮やかで、あやふやな断片でしかない私たちの願望を会話から汲み取って、「ずっと昔からこんな結婚式にしたかったのに、どうして気づかずにいたのだろう」と思うような式を完璧に計画してくれた。ただただ、感嘆するばかりだ。
何度か通って大体の形を決めた後、小島さんは同じテーブルを囲んだよしみということで大幅なディスカウント価格を提示してくれたが、わたしたちは既定の料金を払った。あんなプロの仕事を見せつけられては、いくらよしみだといわれても失礼な気がする。わたしも悠さんも、まがりなりにもそれぞれの道のプロだからこそ、プロの仕事はきちんと評価したかった。
式の場所と日取りを決めて家に帰ってきた日、いつもの夕食を終えた後、悠さんから改まって「話したいことがある」と持ちかけられた。
「遅くなったけど……」
悠さんは、小さな箱を取り出した。
どきん、と胸が鳴った。その中に入っているものが何なのか、さすがのわたしでもわかったからだ。
「俺の仕事は女性と関わることがほとんどだから、不安になることも少なくないと思う。それに不規則だから、なかなか会えなくて寂しい思いをさせてしまうことも。でも、俺が好きな女性は想子一人だけだ。だから幸せにしたい。いや絶対に幸せにする。俺のそばにずっといてほしい。改めて、俺と結婚してください」
悠さんは箱の蓋を開けた。中には予想した通り、かわいらしくカットされた小さなダイヤが輝く指輪が入っていた。
「…………」
はい、と返事したいのに、喉が涙で詰まってしまってうまく声が出ない。
悠さんは微笑んでわたしの左手をとると、指輪を薬指にそっとはめてくれた。
「想子は俺のいちばんの理解者だ。何かあっても絶対に裏切らないし、大切にする。守る……愛していく」
「……はい。こちらこそ……よろしくお願いします」
悠さんに抱きついてやっとそう言えたのは、ひとしきり泣いてからだった。
「ケンカも必要なこと」
わたしたちは小島さんの計画をもとに、結婚式の準備を始めた。
式場に行ってドレスや食事を選んだり、知り合いに招待状を出したり……。
「結婚式の準備って、こんなに大変なものだったんだ」
結婚式が単なる夢でしかなかった頃にはとても想像できなかった多忙さだった。
ありがたいことに二人ともそこそこ忙しかったし、お姉ちゃんの会社の仕事も軌道に乗ってきたので、思うように準備が進まないこともあった。時期によってはどちらかだけに負担がかかったり、どうしても予定を変えなくてはいけなくなってしまったりもした。
そんなときは、ケンカした。
「二人の結婚式なのに、もう少しぐらい手伝ってよ!」
忙しかったときは悠さんに任せる量が多くなってしまったことも忘れて、怒ったこともある。
悠さんがあるドラマの打ち上げで、帰宅が遅くなってしまった夜だった。式場の各テーブルに置くウェルカムカードが、想像していたのとだいぶ違う形で印刷されてしまって、落ち込んでも焦ってもいた。
「結婚式のことも放っておいて、夜中まで飲んでいるなんて。わたしには悠さんだけなのに!」
感情を高ぶらせて涙を流すと、悠さんは驚いたようにわたしを見つめて、それから抱きしめた。
慰めるように、頭を撫でてくれる。「ごめん」と何度も耳元で謝ってくれた。
悠さんはわたしよりもずっと大人だった。売り言葉に買い言葉にならなかったおかげで、抱きしめられているうちにだんだん気持ちが落ち着いてきた。
しばらく抱きしめた後、悠さんはわたしの顔を覗き込んだ。
「悠さんだけなのに、ってもう一度言って」
申し訳なさそうにしながらも嬉しそうな表情に、つい噴き出してしまう。何だか怒りも忘れてしまった。
でも、ケンカも必要なことだったと思う。
わたしたちはケンカを通して相手の事情や周囲との関係をより正確に知っていったし、それをどんなふうに受け止めるのが相手を尊重することなのかというのも知った。
少しずつ、相手をいちばんに愛しながらもそこに溺れきってしまわないバランス感覚を身に着けていった。
大事なのは、どんなときでもきちんと意見を言うこと、それに相手の意見をきちんと聞くことだった。違う人間なのだから、勝手に期待だけしていたってその通りにならないことのほうが多い。ちゃんと言葉にしないと伝わらないのだ。その上で自分にできることとできないことを考える。
そうやって、ゆっくりと家族に近づいていった。家族というのは、ある日突然なれるものではないのだとわかった。
それから数ヶ月後、いよいよ結婚式の朝がやってきた――。
「誰よりも幸せにする」

結婚式の会場は海辺のチャペルと、そこから歩いていけるレストランだった。
式には道場で一緒に暮らした人たちや、家族、仕事でとくにお世話になっている人を呼んだ。
もちろん、お姉ちゃんも。
お姉ちゃんには、誰よりも来てほしい。自分が素直にそう思えているのが嬉しかった。
小島さんの部下だという女性の指揮で、当日の準備はすべて順調に進んだ。小島さん本人は、今日はいち招待客として心から楽しみたいと言ってくれている。
メイクのサービスはプランニングの中に含まれていたけれど、あえてそれははずしてもらって、悠さんにしてもらった。
二人で選んだドレスを着たわたしを、悠さんは控室にメイク道具を一式持ち込んでこれまで以上に丁寧にメイクした。
「うん、今まででいちばんきれいだ」
たっぷり時間をかけてメイクを終わらせると、一度は下げたベールをもう一度上げてキスをしてくれる。せっかく塗った口紅が落ちないように注意しながら、ごく軽く。
「これからも想子のことを誰よりもきれいで、幸せな女性にするよ。愛してる」
いつもみたいなディープなキスができないのを残念がるように、軽いキスを何度も求めてくる。くすぐったいような感触のせいもあって、思わずくすくすと笑ってしまった。
「わたしだって、悠さんを誰よりも幸せにする。これからもよろしくね」
「うん、よろしく」
わたしたちは小島さんの部下が呼びに来るまで何度も何度もバードキスを交わして、結局、控室を出る直前に口紅をもう一度塗りなおした。
***
チャペルでの式は終始おごそかに進んだ。予想はしていたけれど、いざ自分が主役になってみると緊張してしまって、神父さんに
「お互い、一生愛していくことを誓いますか」
と尋ねられたとき、「誓います」と答えた声がすっかり震えてしまった。
悠さんも緊張していたみたいで、同じように「誓います」の声が震えていた。意外だった。テレビの生放送なんかにもよく出演しているから、こういう場面で動揺したりはしない人だと思っていたのに。
後でそのことを話してみたら、
「好きな人との結婚式で、緊張しないわけないでしょ」
と苦笑されて、頭をぽんぽんと撫でられた。
指輪を交換すると、いよいよキスだった。
「では、最後にキスを」
悠さんがわたしをそっと抱き寄せる。
不思議なことに、ここまで来てしまうと緊張がすっと抜けていった。
みんなに見られているのに、悠さんと今、この場所で二人きりでいるような気がする。そして、この時間が永遠に続いていくような。
わたしたちは静かにキスをした。耳の奥に、すぐそこにある海の、穏やかな波の音が届いた。
式が終わると、みんなで披露宴――というほどの規模のものでもないけれど、の会場のレストランに歩いて移動した。そのままでは引きずってしまうドレスの裾は、千織ちゃんとなぎささんが持ってくれた。
「世界でいちばんきれい」
「今日の想子ちゃん、世界でいちばんきれいだね」
少し後ろを歩いていた千織ちゃんが、しきりに感心してくれる。
「悠さんのメイクのおかげだよ。わたしは、そんな……」
「こんなときに謙遜しちゃだめだよ」
すかさずなぎささんが口を挟んだ。
「本当にきれいなんだから。今日は胸を張ってなきゃダメな日だよ」
ストーカー事件のこともあって、なぎささんは今に至るまでわたしたちとは距離を置いている。わたしたちのほうはもう終わったことだと思っているけれど、なぎささんのほうはまだわたしたちと向かい合う心の整理ができていないようだった。
だから、こんなふうに真正面から素直な言葉で褒めてくれたのは嬉しかった。
***
レストランでの食事が終わると、手渡されたマイクで、来てくれた人たちに改めてお礼を述べた。
みんなの前でマイクで話すなんて経験はしたことがなくて、最初は少し不安だった。でも決まっていたことだったから言うべきことは事前にちゃんと決めていたし、いざそのときになってみると、とにかくみんなに感謝の気持ちを伝えたいという思いのほうが大きくて、それほど緊張しなかった。
家族や友人たちへのお礼を伝えると、最後に道場のカリスマさんや千織ちゃんたちの席のほうを向いた。
「皆さんとビューティ道場で出会えたことで、今のわたしになれました。地味で内気だったわたしを変えてくれたのは、道場の皆さんのおかげです。本当にありがとう。これからもよろしくお願いします」
そこまで言うと、深く、頭をさげた。
でも、これで終わりじゃない。最後に、ここにいる人たちに聞いてほしいことたある。
涙で喉が詰まって、言葉をうまく発せなくなっている。でも絶対に言いたかった。
「本当に、本当に感謝しています……。ここにいるすべての人が、幸せになれますように!」
わたしは、心からそれを祈っていた。
自分が幸せだと、人の幸せも素直に願えるものだと、悠さんと暮らす日々から教えてもらった。
卑屈にならずに済むように、大事な人の幸せをちゃんと望めるように、わたしはこれからもまず自分が幸せでいられるように努力しよう。正しく自分本位にならないと、まわりに優しくなんてなれない。
空が優しいオレンジ色に翳(かげ)ってきた頃、パーティは終わった。
みんなを送り出した後、わたしと悠さんは今夜泊まる予定になっている、近くの小さなホテルに移動した。
「新しい世界」
海の見える小さなホテルは、ヨーロッパの古いアパートの一室のような内装だった。
レトロな家具に、光量を落とし気味にした照明。今日泊まるわたしたちが結婚式を終えたばかりの新婚だと知っているのか、木製のテーブルの上には見事なバラが活けられた花瓶と、季節のフルーツがたくさん載ったバスケットが置かれていた。
フルーツをかじってひと休みしてから、一緒にお風呂に入った。猫足の白いバスタブにお湯をためて一緒に浸かっていると、悠さんはいつもよりも激しく、後ろからわたしを抱きしめた。
「今日の想子、すごくきれいだった……ごめん、今日は優しくできないかも」
耳たぶを甘噛みしながら囁く。それだけでもぞくぞくして、息が荒くなってしまう。
指が普段よりもわずかに強い力で、胸や腰を這った。優しく撫でられるのも好きだけれど、こんなふうなのも余裕なく求められている感じがして、いやじゃない。
少し強引に悠さんのほうを向かされて、唇を重ねられた。舌が入り込んでくる。
「ん……っ」
わたしの全部を奪おうとするような、激しいキスだった。
「だめだ、これ以上我慢できない」
その気持ちはわたしも同じだった。
急かされたようにお風呂を出ると、二人でもつれあうようにしてベッドに倒れ込んだ。
さっきよりも激しいキスを交わした後、悠さんがこちらをじっと覗き込む。
「今日からは……使わなくていいよね?」
何を、とはすぐにわかった。
結婚したら子供がほしいという話を、ずっとしていたから。
わたしは黙ってうなずいた。たった一枚隔てるものがなくなるだけなのに、何だか妙に新鮮な気がして、顔が熱くなってしまう。
胸もお尻もたっぷり愛撫されて、だんだん高ぶっていく。とくにお尻は、悠さんにいっぱい触られたり揉まれたりしているうちに、すっかり性感帯になってしまった。自分で意識してプルプルにしているせいもあるかもしれない。
悠さんは立ったまま、後ろから入れる体位が好きだ。お尻をちょっと突き出すと、腰からのラインがきれいに見えるのと、胸も一緒にいっぱい触れるのと、何よりもわたしが振り向けば顔が見えるからだという。その状態で舌を伸ばしてキスをするのもいいそうだ。
悠さんに好きだといわれれば、わたしもだんだんそれで感じるようになってきて、今では二人のお気に入りになっている。
「あ……んっ」
立ったまま入れられて当たるところが、すっかり敏感になった。こすられていると、そこからじんわりととろけそうになってくる。
もっとほしくて、自分からも腰を動かす。今までからは信じられないぐらい、わたしは積極的になっていた。騎乗位や体面座位で、恥ずかしがりながらも自分から挿入して、乱れて喘ぐこともある。悠さんがそんなわたしをきれいだと言ってくれる。
(このまま……ずっととろけていたい)
熱いキスを受け止め、悠さんを包み込みながら、幸せと快感を同時に噛みしめる。やがて、奥に熱いものがいっぱい注がれた。
***
結婚してからも、道場の人たちとは頻繁に連絡をとっている。
とくに千織ちゃんと大樹さんの夫婦とは、一緒に遊びに行ったり、ホームパーティに呼び合ったりすることが多い。
悠さんとは相変らずケンカもするけれど、ちゃんと仲良くやれている。
最近、妊娠が発覚した。
ずっと子供はほしいと思っていたけれど、いざそうなってみると不安でもある。
でも……今のわたしなら、やっていける。新しい命を、悠さんと二人で育んでいける。
二人だけじゃない。きっと、もっと多くの人の力を借りることになるだろう。人間をひとり、育てるのだから。
わたしにとっても、悠さんにとっても初めての体験だ。
わたしたちの前に、また新しい世界が広がった。
END
あらすじ
悠と想子の結婚式は海辺の静かな教会で挙げることになった。
準備中にはケンカもしたけれど…とうとう結婚式の朝がやってきた――。