女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
官能小説 同居美人 プロジェクトB 〜想子編〜 シーズン2
激しい言葉で気持ちを主張した

篠村さんは少し考えて、お姉ちゃんに会うのはメイクアップ・アーティストの有本悠さんがいいのではと提案してくれた。
彼ならきっと、お姉ちゃんが日々どんなスキンケアをしているのか、どんなメイクテクニックを持っているのか見抜いてくれるだろうから、と。
そしてそれが、努力と呼ぶに値するものなのかどうかも。
「有本さん……ですか」
正直なところ、わたしは有本さんがまだ少しだけ苦手だった。
もちろんきれいにしてくれたことに感謝はしているけれど、あの「チャラい」ノリに慣れるのにはもう少し時間がかかりそうだ。
こればかりはもともとの性格なので、感謝しているからといってすぐに変わることはできない。
「悠が苦手なら、俺が行こうか?」
まだ部屋にいた福生さんがからかうような声をかけてくる。わたしが有本さんが苦手なことを、この人はとっくに見抜いているのだ。
かちんときて、いらっとした。
わたし、この人がきらいだ。
「お断りします」
自分でもびっくりするぐらい強い口調で、わたしは福生さんに言葉をぶつけていた。
「どうしてそんなに無遠慮に人の心の中に入ってくるんですか。いえ、心の中だけじゃないです。聞き耳まで立てた上、ノックもしないで部屋に入ってくるなんて信じられません。常識を疑います」
言い終わった後、わたしは自分でも呆然としていた。
今までこんなにはっきりと、激しい言葉で気持ちを主張したことがあっただろうか。
さっき「お姉ちゃんの正体を暴く」と聞いてぞくぞくしてしまったことといい、この人――福生さんと話していると、今まで知らなかった自分がどんどん外にひきずり出されてくるような気がする。
怖いような、なんとなく心地いいような……何と表現していいのかわからない、不思議な気分だ。
「それは申し訳なかったな。俺としてはアドバイスをしたかっただけなんだが。これから気をつけるよ」
福生さんは苦笑して、やっと部屋を出ていった。
翌日、わたしはお姉ちゃんにメールを送った。
何かあったときのために、ルームシェアの代表者を一応紹介しておきたいという内容だ。
メールを打っていると、緊張で手が震えだした。
どうして実の姉にメールをするのに震えるのだろう。悲しくも情けなくもなる。もしかしたら自分は大それたことをしているのではないかという、どこか怖ろしい気にも。
『お父さんやお母さんより、年の近いお姉ちゃんのほうが紹介しやすいなと思って』
何だか言い訳をしているようだ。
次の日、お姉ちゃんから返事があった。
『しばらく忙しいから、再来週ぐらいでもいいかな』
わたしたちは、翌々週の週末に会うことになった。
幸せになるひとつの秘訣
こういうことは、決まったらすぐ実行するほうがいい。
時間が空くと、かえって不安が膨らんでいってしまう。
二週間以上空いてしまった時間を過ごす間に、わたしはどんどん落ち着かなくなっていった。
今回のことは、カリスマのみんなにも伝わっていた。篠村さんに話していいか確認されてわたしが許可したのだ。
わたしがここに住み始めた理由は、地味で自信のない自分を変えるため。
そのいちばん根深い原因のひとつがお姉ちゃんの存在だというのなら、このことはわたしを助けてくれるみんなに知っておいてもらったほうがいいと思った。
いろんなことが連続して起こって、少しヤケになっていたというのもある。
「お姉さんに会うの、不安?」
ある夜、リビングに一緒にいたウェディング・プランナーの小島泰明さんが話しかけてきた。
ほかには篠村さんと有本さん、それにエクササイズ・インストラクターの平野井さんと千織さんもいて、みんなで何を話すでもなく、テレビをつけたままにしてお茶を飲んでいた。
「えぇ……まぁ」
わたしは言葉を濁す。
「じっと待っているから不安が膨らむんだよ。その間にできることをしていれば、多少なりとも不安を忘れられる」
「できること、ですか……」
といっても、何も思いつかない。
「表情筋のトレーニングとかどうかな?」
「表情筋?」
「うん。今回のことに直接役に立つかどうかはわからないけれど、今まで僕が見てきた花嫁さんたちは、みんな表情が豊かでね。それって幸せになるひとつの秘訣なんじゃないかなと思っているんだ」
「でも、鍛えたからって表情は豊かになるものなんですか?」
「なるよ」
篠村さんが横から答えた。
「表情が豊かなのは慣れみたいなところがあるからさ。先に表情筋のほうを鍛えてしまうっていうのはいいアイディアだと思う。実際、感情はそのとき浮かべている表情によって大きく変わるという研究結果もあるんだ」
狐につままれたような思いではあったけれど、確かに何もやらないでいるよりはずっと気が晴れそうだ。
「いいんじゃない。コスメの良さも、明るい表情あって引き出されるものだしね」
有本さんも納得している。
「じゃあ大樹、何かいいトレーニングはないかな」
「結局俺に振るのか」
小島さんに聞かれた平野井さんが噴き出す。
「もちろんあるよ。じゃあせっかくだから千織さんもやろうよ。表情筋のトレーニングは顔痩せにもなるからね。顔が痩せれば、全体も引き締まって見える」
「えっ、本当に!?じゃあやります!」
千織さんが食いついたので、みんな笑った。
「よーし、じゃあ手鏡を持ってきて」
こうして平野井さんの指導のもと、表情筋のトレーニング大会が始まったが……
「ちょ、ちょっと待って。こんな顔しないといけないんですかっ!」
わたしと千織さんは焦った。さすがに表情筋だけあって、かなりの変顔になる。
「仕方ないよ。でもその分、効き目はある」
「わたしたちだけがこんな顔するの、恥ずかしいですよ!みんなでやりましょう!」
千織さんは横にいた有本さんのほうにも鏡を向けた。
「えっ、俺も!?」
「いいね。じゃあみんなで表情を豊かにして幸せになろう」
小島さんが謎の大人の余裕で率先する。
「じゃあ、まずは下唇を思いっきり突き出して……」
平野井さんの号令のもと、みんなが変顔になる
賑やかであたたかな時間が過ぎていった。
やがて、運命の日がやってきた。
「あんまり考えすぎることないよ。とりあえず元気にいこう」
同行する有本さんが笑いかけてくれたけれど、そう簡単に気分は晴れなかった。
何をしてもきらきらする人
俺、有本悠と想子ちゃんは、想子ちゃんのお姉さんに会うべく、都心のカフェに向かった。
週末の午後。都内でも有数のオシャレ地域にあるカフェを指定してきたお姉さんは、俺たちよりも早く着いていて、オープンカフェで雑誌を読んでいた。
なんて華やかなんだろう、というのが第一印象だ。
服装もメイクも髪型も、そしてもともとの顔かたちも、まったくスキがない。だけどそれが絶妙なバランスで嫌味にならず、華にだけなっている。
道を行く人たちも、吸い込まれるようにお姉さんを見つめていた。
「お姉ちゃん……」
近づいた想子ちゃんが、おどおどと声をかける。
「あらっ」
お姉さんは顔をあげて、キラキラーっ!と音がしそうな笑顔になった。うっ、眩しい。
「想子、久しぶり。どう、ルームシェア生活は?」
「うん、まぁまぁ……お姉ちゃんも元気そうで、何より」
想子ちゃんのほうはどんどん暗く、どんよりとしていく。この対比は見ていてなかなかつらい。
「こちらが、その、住人代表の……有本さん」
想子ちゃんが紹介してくれたので、俺はサングラスをちょっとずらしてから頭を下げた。サングラスをかけているのは、テレビに出るようになってから街で声をかけられることが増えて、それと同時に面倒も増えるようになったからだ。
「あらっ……あ、あれっ?ひょっとして……有本悠!?」
お姉さんはこちらがびっくりするぐらい驚いた。すごい美人なのに、さっきから表情が壊れる一歩手前まで極端に、めまぐるしく変わっている。だから「すごい美人」というのさえ、何だかかわいらしく見えてしまう。
表情が豊かなのは幸せになるひとつの秘訣、と泰明さんが言っていたことを思い出した。
「あ、はい、そうなんです。どうも」
「えーっ、なんでなんで!?なんで想子が有本悠……さんとルームシェアしてるの?
超羨ましい!……あ、ごめんなさい、私ったらはしゃぎすぎね」
何をしてもきらきらする人だ。はしゃいだらはしゃいだで、今度はまた人の目が集まる。
「有名人なんだし、目立っちゃいけないわよね。中に入りましょうか」
屋内で落ち着いて話してみると、お姉さん――瞳子(とうこ)さんは最初に感じた通り、さばさばしていて話しやすい人だった。
あまりにも完璧すぎる、と想子ちゃんから聞いていたから、もっとキツい人なのかと思っていた。
けれど、これはこれで完璧なのかもしれない。想子ちゃんが「お姉ちゃんは努力なんてしていない」と言っていたのも、今なら理解できる。努力とは無縁に見える自然体ぶりだ。
仕事は外資系化粧品会社の広報をしているという。聞くと俺もよく使うメーカーだった。
「うれしい!言ってもらえれば割引できますよ。想子に伝えてもらえれば用意しておきます」
俺に会えたとはしゃいでいるが、それで想子ちゃんに嫉妬する様子もない。もっとも、はしゃいでいるのなんてただの社交辞令かもしれないけれど。
「おでん屋さんで知り合ったの?そういう偶然ってあるのよねぇ。でもよかった、想子は小さい頃から引っ込み思案だったから少し心配だったのよ。でもこんなイケメンとルームシェアなんて、立派に成長したってことよね」
真っ白な肌にほどよい桜色の頬。
老若男女、誰が見ても「品がいい」と褒めるであろうネイル。
シンプルなバレッタで束ねた長い髪は、十分に水分を含んで艶めいている。
それでも俺の目はごまかせない。
(「頑張りすぎて」いる……)
俺はすぐにそれを察した。スキンケアもヘアケアもネイルケアも、自然体なようでいて何もかも力を入れ過ぎている。
スキンケアなんて、力を入れ過ぎて傷み始める寸前だ。
もはや不安になるほどだ。いったい何が彼女をここまで「頑張らせて」いるのだろう。
もしかしたら彼女は、想子ちゃんや、いや、彼女自身が考えているほど幸せではないのかもしれない。
「ねぇ、有本さん。想子は家ではどんな感じなんですか?」
明るい声をかけられて、はっと我に返った。
「あ、あぁ……確かにおとなしいけど、最近はちょっと元気ですよ」
「本当に?私、想子は絵の才能があるんだから、もっとどんどん自分を売り込んでいけばいいのにってずっと思っているんです。そうできるぐらい元気になってくれたらいいな」
心からそう思っているのだろうと感じさせる、強さとぬくもりのある声。
「お姉ちゃんのほうがかっこいい仕事をしているよ。わたしなんて……」
想子ちゃんはうつむいて、泣きそうな顔で笑っていた。
俺が保証するよ
お姉ちゃんと別れた後、わたしたちは大通りを少し歩いた。
地下鉄の駅はすぐそばにあったけれど、何となく、歩こうということになった。
「お姉さんはさ……」
有本さんが話し始めたので、わたしは体を硬くした。
彼がお姉ちゃんのことをどんなふうに評価したのか、さっきからずっと気になっていた。
二人はとても楽しそうに見えた。もしかしたら有本さんも、内田さんみたいにお姉ちゃんの虜になってしまったのではと不安だった。
「お姉さんは、俺には十分努力しているように見えたけどな」
「そう……ですか?」
「うん。でも想子ちゃんが『努力なんてしていない』と言いたくなる気持ちもわかった。お姉さんは努力を見せないのが上手なんだと思う」
意外なコメントだった。考えてもいなかったことだったので、何と返していいかわからずに黙ってしまう。
「確かにお姉さんはキレイだ。でも同時に自分をより良く見せる方法をわかっているというのも大きい」
言っていることの意味自体はもちろんわかるが、そのことをどうしてもお姉ちゃんにあてはめられない。
あんなにのびのびしている人が、人によく見られよう、必要以上にきれいだと思われようと努力しているというのがどうにもピンと来ないのだ。
「方法ですか……」
「うん、技術といってもいい。それを掴めば想子ちゃんも十分にきれいになれる。俺が保証するよ」
微笑んでくれたが、わたしはまだ腑に落ちないのもあって複雑だった。
「まぁ、あまり難しく考えすぎないでもそのうちわかるよ。女の子はみんなそれを理解する才能があるって俺は思ってる」
有本さんはわたしの頭をぽんと撫でて、話題を変えた。
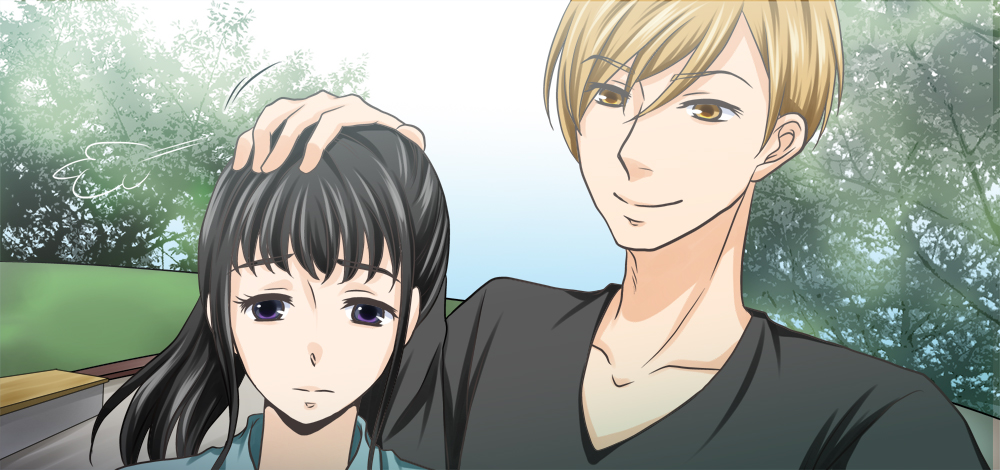
「それに想子ちゃんのことをちゃんと褒めていて、いいお姉さんだよね」
「えぇっ」
わたしは大きな声をあげてしまった。
「ちゃんと褒めてる?本当にそう思いました?」
思わず有本さんに詰め寄ってしまう。
「……思ったけど?」
有本さんは怪訝そうな顔をした。
「まさか!お姉ちゃんはできる自分とくらべてわたしがあんまり哀れだからああいうことを言うんですよ。あんなこと、本当に思っているわけないじゃないですか」
わたしは必死で訴えて、有本さんの誤解を解こうとした。だが、
「……あのさぁ〜」
大きなため息とともに今度はぽんぽんと二回、さっきより強くわたしの頭を撫でる。
「想子ちゃん、いくら何でもひねくれすぎ。そりゃああんなに美人で、自分の見せ方もよく知ってるお姉さんとくらべたらひねくれたくなる気持ちもわかるけど、でもお姉さんは本当に想子ちゃんのことをすごいと思っているよ」
「嘘……」
それ以上、言葉が出てこない。息が荒くなるばかりだ。
そんな、信じられない。お姉ちゃんがわたしのことを……本当に……?
あんなに完璧な人が、わたしのことを才能があるなんて思ってくれているの?
「嘘、でしょ……?」
「嘘じゃないよ。少なくとも俺はそう感じた」
有本さんは立ち止まって、わたしの顔を覗き込んだ。
「わかったよ、今の想子ちゃんに必要なこと。肌や髪をきれいにするのももちろん大事だけど、まずはお姉ちゃんに対してまっすぐな気持ちを取り戻そう。それだけでいろんなことが変わる気がする」
わたしはその場に立ち止まったまま、しばらく動けなかった。
卑屈になりたくない
お姉ちゃんも努力している。お姉ちゃんがわたしのことを本当に認めている。
それがお姉ちゃんの正体だった。少なくとも有本さんの見立てでは。
「正体を暴く」と聞いて感じたぞくぞくした気持ちは何だったのか、自分でもよくわからなくなってしまった。
わたしはお姉ちゃんを何者にしたかったのだろう。
自分が意地悪で嫌味で情けなくて卑屈で心の汚い人に思えてくる。いや、たぶん本当にそうなんだろう。
地味な上に心の中までどす黒いなんて最悪だ。だけど私は意外に落ち込まなかった。
有本さんがかけてくれた言葉があったから。
――お姉ちゃんに対してまっすぐな気持ちを取り戻そう。
まっすぐな気持ちを取り戻すにはどうすればいいのか、それを考えることがわたしを救ってくれた。
わたしはスキンケアを引き続き頑張りながら、スタイリストの松垣洸太さんに頼んで、今までより少しだけ明るい印象になれる服を買いに行った。
これ以上卑屈になりたくない。まずは見た目だけでももう少し明るくなりたい。
「いいんじゃないかな。表情もそうだけど、見た目を変えると中身もだんだんそれにつられてくるんだ。中身が最終的には見た目に出るのと同様に、見た目も中身に影響を及ぼすんだよ」
篠村敦さんがそう言ってくれたのも励みになった。
ある夜、廊下で福生さんと会った。周囲に誰もいなかったのもあって、つい体を硬くしてしまう。
やはりというか、福生さんは厳しい言葉をかけてきた。
「やればできるなら始めから頑張れよ」
あれ?これって……口調自体は厳しいけど、ひょっとして、褒めてる?
「以前よりはきれいになっているんだからさ。あんたも努力すれば変われるんだよ」
逸らしていた目を福生さんに向けると、照れたような、怒ったような表情をしていた。
ひょっとしてこの人も、まっすぐになりたいのかもしれない。思わず微笑んでしまう。
福生さんもつられたように微笑んだ。
「ありがとうございます」
少しだけ頭を下げて、福生さんの横を通った。以前ほどいやな人だとは感じなかった。
その数日後、お姉ちゃんからメールが届いた。文面を見て、背筋がすぅっと冷たくなった。
『よかったら有本さんを紹介してほしいの。もちろん彼がいいと言ってくれたらだけど。スキンケアとかについて相談したいことがあるんだよね』
有本さんをお姉ちゃんに紹介する……?
真っ先に湧き上がったのは、「いやだ」という気持ちだった。紹介して、二人がわたし抜きで仲良くなってしまうのが怖い。
あれ以来、わたしの有本さんを見る目は「チャラいのは見た目だけな、いい人」に変わりつつあった。尊敬の念も感謝の気持ちも持っている。
お姉ちゃんにも怖じずに、もう少しだけでいいから近づきたい。わたしは二人を、以前よりずっと「好き」になろうとしていた。
なのに、その矢先にわたしだけ置いていかれてしまうようなことになったら……。
二人のことは「好き」なのだから、幸せになってほしい。でもその結果として自分が疎外感を覚えるのはつらい。幸せになってほしいのは、こういう形でではないのだ。
これはわたしのわがままなのだろう。わたしはやっぱり卑屈で勝手な人間なのだろうか。わたしは、試されているのだろうか。
真夜中、一人で部屋にいたら気持ちがどんどん沈んでしまいそうで、わたしはひとり、リビングでハーブティを飲んでいた。
「何かあった?」
後ろから声をかけてくる人がいた。
彼も今回のことはひととおり知っている。
「悩みがあるなら聞くけど」
(……この人には隠しごとはできないだろうな)
そう感じたわたしは、打ち明けることにした。
あらすじ
篠村と福生と有本の3人は相談し、チャラ男有本が想子の姉に挨拶に行き、姉のスキンケアの秘訣を探ることに…。
有本のアドバイスのおかげで想子は綺麗な肌を手に入れることができたが、有本のチャラいところは依然として苦手で…。


















