女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
官能小説 同居美人 プロジェクトB 〜想子編〜 シーズン3
隠しごとはできない

(この人に隠しごとはできない)
そう感じた相手は、コミュニケーション・アドバイザーの篠村敦さんだった。
「どうしたの?何か考えごと?」
篠村さんが相手なら、変に守りに入りながら話すよりも、全部打ち明けてしまったほうがいいのかもしれない。
そもそも、一歩前に進めたのは篠村さんのおかげなのだ。篠村さんに隠すのは、フェアではないような気もする。
「何でも相談してくれたらいいよ。心のモヤモヤって、正直に吐きだすと案外それだけ解決しちゃったりするからね。全部聞くから、俺を頼って」
話すだけで解決することはないだろうけれど、それはそれとして、好意に甘えて篠村さんを頼ることにした。
わたしはお姉ちゃんからもらったメールの内容と、もしお姉ちゃんの希望を叶えて有本さんと会わせたら、これまでと同じ結果――有本さんとお姉ちゃんが仲良くなって、地味で自己主張の苦手なわたしはかやの外に置かれることになってしまうのではないかという不安を話した。
「なるほどね……」
篠村さんはキッチンで自分用にカフェインレスコーヒーを淹れてテーブルについた。じっくり向き合ってくれるのだということが、その行動からわかる。
「二人にもっと近づきたいと思っているのは本当なんです。でも二人『だけ』が近づいてしまうのは……いやなんです」
冷めかけたハーブティを少し多めに口に含んで、一気に飲み干す。放っておいたら口からもっと出てきてしまいそうな弱音や愚痴を、体の中に押し戻すように。
「わたし、全然成長できない。性格が悪くていやになります」
それを認めれば許されるわけでもないのに、言い訳のように口にしてしまう。それがまた一層強く自己嫌悪させる。
篠村さんはわたしの話が終わると、ぽつりと言った。
「そんな気持ちを持つのは人として当たり前のことだよ。成長できていないわけでも、性格が悪いわけでもない」
優しい声だった。
「好きな人たちの中で自分だけがのけものになってしまうのは、誰だって苦しい」
「じゃあ、わたし……どうしたらいいんでしょうか」
わたしはきっと、縋るような目をしていたと思う。
嫌われたりしないでしょうか

「悠にちゃんと気持ちを伝えたらいいんじゃないかな」
篠村さんの穏やかな口調に、わたしはどきりとする。
気持ちを伝える――そう聞いて胸に浮かんだのは、有本さんに恋心を伝える自分自身の姿だった。
慌てて、違う、そうじゃなくて……と言いかけたが、言葉が口から飛び出す寸前に気づく。篠村さんは「そういうこと」を言っているのではない、と。
わたしの葛藤を察したかどうかはわからないけれど、篠村さんはそのまま続けた。
「お姉ちゃんと悠が二人だけで仲良くなってしまったら寂しいから、何か進展があったら自分にも教えてほしい、そう伝えればいいんじゃないかな。それが想子ちゃんの偽らざる気持ちだろ」
「はい」
深くうなずく。その通りだ。
その通りなのだけれど、少し、迷う。
そんなことを頼むなんて、出しゃばりすぎだし、何だかみじめな感じもする。
篠村さんは今度こそ、わたしの気持ちを察したようだった。
「まぁ、あまり格好いいことじゃないよね。けど、自分の本当の気持ちを隠さずに伝えることなんて、よほど状況が整っているのではない限り格好いいことじゃない。『自己満足に過ぎないのでは』とか、『自分勝手だと思われそう』とか、心配になるものだと思う。でも伝えずに黙って、願っているだけでは、何も始まらないんだよ」
言葉を受け止めながら、今までの自分のことを考える。
これまでそんなふうに、自分の気持ちを誰かに伝えたことはあっただろうか。
伝えたいと思ったことはもちろん、あった。けれどやはり、篠村さんが今言ったような不安に押し潰されてしまって、実現することはなかった。
「嫌われたり……しないでしょうか」
不安はいつだって、この恐怖に行き着いた。
嫌われて、取り返しがつかなくなったら……
そうなるぐらいだったら、自分の気持ちなんて押し殺したほうがいい。
篠村さんはふわりと、氷がゆっくりと溶けていくような笑みを浮かべた。
「気持ちをただ主張して、相手に『押しつけて』いたら嫌われるかもしれない。だからあくまでも希望として『そうだったらうれしい』こととして伝えるんだ。最終的な決定権はもちろんあなたにありますというのを話しながらきちんと示すんだよ。相手にきちんと逃げ場をつくるのがコツかな」
「逃げ場、ですか」
「そう。例えば『もしよかったら』とか、『負担にならない程度に』とか、『時間があるときでいいから』とか……まぁそんな一言を、話の端々に入れるんだ」
そうか。
ふっと肩から力が抜ける。
単なる自己主張というよりは、提案なんだ。「あなたとこれからも心地良く関係を築いていくために、こうしてくれたらうれしい」という。
わたしは結局、自分のことばかり考えていた。
「自分が」自己主張をしていないか。「自分が」嫌われないか。
でも、少しの間自分のことを忘れて相手の立場に立てば、解決することはきっとたくさんあるのだ。
「わかりました。ありがとうございます」
ぺこりと頭を下げる。
本当にありがたかった。篠村さんはわたしの意見を尊重しながらも、正しい道を指し示してくれる。
「ま、悠はああ見えて派手な感じの人はタイプじゃないんだ。だからどっちにしても心配しなくて大丈夫だよ」
いたずらっ子みたいな顔で、篠村さんはコーヒーの最後の一口を飲んだ。
もう遅いのでそろそろ寝ようということになる。わたしは篠村さんのカップを受け取って、流しで洗い始めた。この程度のことがお礼になるとは思えないけれど、今、できることとしてやっておきたい。
「そうだ、想子ちゃん。もうひとつ聞きたいことがあるんだ」
背中に、篠村さんの声が掛かった。
きれいになっていい

「ここでの生活はどう? みんなとの生活は楽しめている?」
これまでの流れからは思いも寄らない質問だったから、一瞬黙り込んでしまった。
けれど、答えはすでにわたしの中にあったので、沈黙は長くは続かなかった。
「楽しいです」と言ってから、しかし、それだけでは足りないと思った。
「楽しいし……それに充実しています。わたしたちを支えてくれるカリスマさんに、少しずつだけど、逃げずにまっすぐ向き合っていこうと思えるようになって……今までとは違う、そんなふうに前向きになれている自分にちょっと戸惑っているけれど……」
説明がどうしてもたどたどしくなってしまう。自分も知らかった新しい自分のことを説明する言葉を、わたしはまだあまり持っていない。
それは、これからひとつずつ手に入れて、大事に磨いていくのだろう。
「よかった」
篠村さんが近づいてきて、横から頭をポンと撫でてくれた。
「想子ちゃんが俺たちにちゃんと向き合ってくれるなら、俺たちも想子ちゃんを助けられる。戸惑うのは成長しているからだよ。それは新たな出発でもあるんだ。これからも安心して戸惑っていい」
「安心して、って……」
安心して戸惑うなんて何だかおかしくて、思わず噴き出してしまった。
洗い物が終わる。タオルで手を拭くと、挨拶を交わして、それぞれの部屋に戻った。
不安は全部消えたわけではない。それでも篠村さんとの会話で生まれたほっこりしたぬくもりがその不安を包んで、わたしの心を守ってくれていた。
それでも、理性で考えるほど、感情は簡単に動いてくれなかった。
翌日の夜、わたしはお姉ちゃんにメールを返そうとした。
もちろん、有本さんに紹介すると伝えようとして。
けれど、指はなかなか動かなかった。
ともすれば、「会わせたくない」と打って、すべてを壊したくなるような衝動にも駆られる。これを破滅願望というのだろうか。
わたしは部屋でひとりで、しばらくの間、スマートフォンとにらめっこをしていた。もしかしたら脂汗も滲んでいたかもしれない。
ふいにドアがノックされた。はっとして顔を上げる。
「どうぞ」
答えると、有本さんが顔を出した。
「想子ちゃん、ちょっといいかな」
助かった、ととっさに思う。
自分の部屋に来てほしいというのでついていくと、メイク用の大きな鏡の前に座るようにいわれた。
「ひとつだけ、ちゃんと伝えておきたいことがあってさ」
なぜメイクをしてくれるのだろうと疑問に思う間もなく、有本さんは手早くメイクを進めていく。
「想子ちゃんだって、十分きれいになれる素質があるんだってことを。活かし方の問題なんだ」
できあがったメイクはお姉ちゃんと何だか似ていたけれど、いい意味でふわっと力が抜けている印象だった。
お姉ちゃんほど完璧な美人ではない。でも、お姉ちゃんにはない柔らかさがある。
(きれい、だな……)
素直にそう感じた。
(これが「わたし」……「わたしのきれい」なんだ)
体から強張りが抜けていく。
わたしも、きれいになっていい。きれいを目指していいんだ。
今までそれを望みつつも、心のどこかで怖れていた。
やっぱりお姉ちゃんにはかなわないと突きつけられるのが怖くて。
でも、わたしとお姉ちゃんは違う人間だ。かなう、かなわないじゃなくて、違うのだ。
だからもう、むやみに背中を追いかけて絶望するのはやめよう。追いかけるのではなく、向き合いたい。カリスマさんたちにそうできたように。
「有本さん、じつは……」
メイクが終わると、わたしはお姉ちゃんのメールのことと自分の気持ちを有本さんに打ち明けた。
想子も来てほしい

数日後――。
わたしは有本さんと一緒に、お姉ちゃんの会社の応接室にいた。
「で、有本さんには、弊社の国内向けの主力商品となる見込みのある、このラインの……」
向かいに座る私たちにノートPCの画面を見せながら、お姉ちゃんが説明する。
お姉ちゃんが有本さんに相談したいといっていたのは、今度開発するという自社の国内向けスキンケアラインの監修と、イメージキャラクターへの就任だった。
大きな窓から都心の風景が一望できる高層複合ビルにオフィスを構えるお姉ちゃんの会社は、女性なら誰でも一度は聞いたことがある外資系化粧品メーカーだ。
大学院を卒業後すぐに就職して以来、お姉ちゃんはここでずっと広報として働いている。最近は広報で培ったマーケティングの知識を活かして、国内向け製品を開発する開発部とも連携をとるようになったらしい。
「開発自体まだ先の話だし、もし受けてもらえたとしたら有本さんの今後の活動にもきっと影響が出ると思うから、ゆっくり考えていただきたいんです」
お姉ちゃんの声を聞きながら、ちらちらと窓の外の光景を眺める。
わたしが今ここにいるのは、お姉ちゃんが「想子も来てほしい」と言ってくれたから。てっきり有本さんがお姉ちゃんに取り計らってくれたのかと思ったけれど、そういうわけでもないらしい。
でも、話を聞いている限りでは、どうしてわたしが呼ばれたのかよくわからない。
わたしに用があるというわけではなさそうだ。
紹介してもらった手前、わたし抜きで話を進めるのを悪いと思ってくれたのだろうか。
そうであればわたしの懸念は杞憂に終わったことになるけれど、何となく腑に落ちない。
わたしの知っているお姉ちゃんは、人懐こい反面、感情に流されすぎないシビアなところのある人だから。
「そうですね。うれしい申し出なのは間違いないんだけど、ほかのメーカーの製品を今まで通りに使えなくなるかもしれないし……うん、やっぱりよく考え させて下さい」
有本さんの声も横顔も、今までにない緊張を湛えている。
当たり前だろう。お姉ちゃんの会社はこの先の自分のブランドイメージ、ひいては人生を変えるかもしれない規模なのだ。
「えぇ。でも、もし有本さんがよかったらだけど、製品開発の現場はどちらにしても一度見ていただきたいんです。イメージキャラクターになっていただくにしても、いちユーザーのままだとしても、どんなふうにつくっているのか知っていただくのは無駄じゃないと思うから。もちろん、機密保持契約は結んでいただきますけど」
キッチリとしたスーツ姿のお姉ちゃんは背筋を伸ばし、凛としている。家でもきれいな人だけれど、ここではさらに磨きがかかって、もはや光り出すのではないかというばかりだ。
「で、次は想子へのオファーなんだけど……」
傍観者として二人のやりとりをぼんやり受け流していたわたしは、名前を呼ばれてはっとした。
って、……え?オファー?
こんな形で近づくなんて
「このラインのイメージイラストを、想子にお願いしたいの。パンフレットやウェブサイト、雑誌やテレビ媒体に共通して使用する、一目でこのラインだとわかるようなイラストを……」
「え、わたし……?」
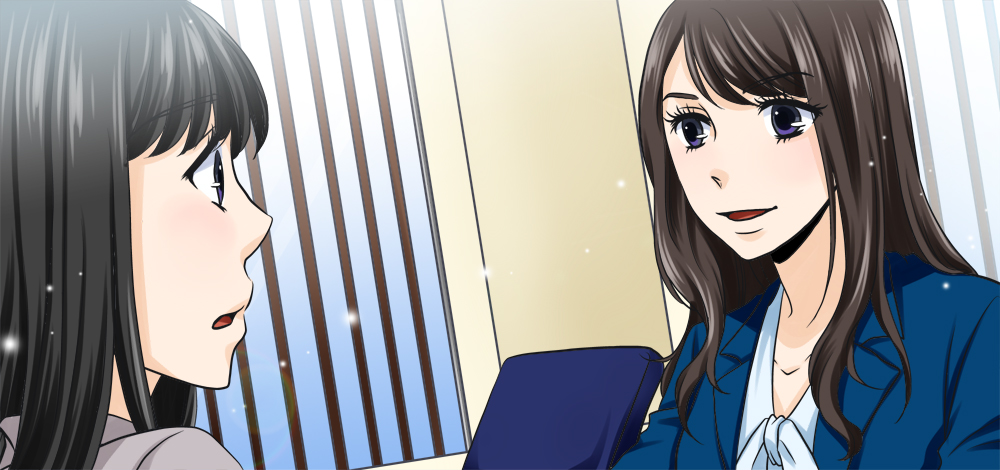
じっとこちらを見つめる熱っぽいまなざしに耐えられなくて、目を逸らした。
「そう。このラインのテーマは、『洗練されているけれど、どこか少女のような甘さと切なさを残す女性たちへ』。聞いたときにすぐに想子のイラストが思い浮かんで、上司や同僚にも見せてみたんだけど、みんなも乗り気になってくれたわ。あとは想子次第」
「…………」
驚きに声が出てこない。
わたしは一介のイラストレーター。お姉ちゃんは誰もが羨む外資系化粧品メーカーの花形社員。
決して埋められないと思っていた距離が、こんな形で近づくなんて……。
「もう少し具体的にプロジェクトが進んだら、改めて正式にお願いする予定よ。考えておいてくれる?」
「……わかった」
うなずくのが精一杯だった。
「お姉ちゃんは想子ちゃんの実力を認めているって、これでわかっただろ?」
帰り道に有本さんからいわれて、わたしは認めざるを得なかった。
もう、卑屈になってはいられない。
また少し心が軽くなった。
有本さんはお姉ちゃんから呼ばれて、打ち合わせのときに話が出たように開発現場を見に行ったりと、お姉ちゃんと一緒にいる時間が長くなった。
「大丈夫。想子ちゃんが仲間はずれになるような結果にはしないよ」
有本さんは帰宅するとその日何があったのかを必ず教えてくれる。
お姉ちゃんも毎回お礼と簡単な報告のメールをくれた。
大丈夫。これだったら二人を信じて、わたしも自分のするべきことに力を注げる。
絵の技術をもっと磨くのはもちろん、この時間をさらに自分を高めるために使おう。
(二人と同じ目線で笑い合えるようになりたい……!)
わたしは、カリスマさんの一人にあるお願いをした。
あらすじ
チャラ男、有本悠のおかげで姉と向き合う決心がついた想子だったが、直後に瞳子から悠の紹介を頼まれてしまう。
二人が近付くことにモヤモヤと悩む想子に声をかけたのは…。


















