女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
官能小説 同居美人〜番外編〜 ワケありイケメン 池部宗一郎〜ワケありの理由〜
「料理を挟んで笑い合う時間」
僕の両親は、僕が小学校3年生のときに離婚している。
理由は、ひとことでいうなら性格の不一致だったらしい。おおらかでさばさばした母と、細かいところまで気にする性格の父は、衝突とまではいかなかったが、何かとうまくいかないことが多かったようだ。
一度、そんな二人がなぜ結婚したのか尋ねてみたことがある。母は少し考えて「恋している間は、自分には合わないと思うところも妙に魅力的に見えちゃうのよね」と苦笑した。
僕は母に引き取られた。母は建築士として一般的な男性以上の収入を得ていたので、生活は苦しくはなかったが、祖父母やほかの家族と同居しているわけではなかったので、家事はどうしても手の行き届かないときもあった。お手伝いさんに頼った時期もある。僕が成長してからは、家事の半分以上は僕の仕事になった。
それでも母は、料理にだけは力を注いだ。栄養バランスがどうこうというよりは、手作りの料理を一緒に囲むことを親子のコミュニケーションの一環として捉えていた。
僕はそんな母の考え方に共感していたし、そう考えてくれたことをありがたくも感じた。
だからこそ、母だけに負担をかけたくなかった。僕はわりと幼いころから、率先して料理の知識を身につけようとした。大人向けの図書館に行って、料理や食材の本を借りてきては読み漁り、実践した。
その成果もあって、小学校高学年になる頃には、母に代わってキッチンに立つことが多くなった。ある程度思い通りに料理がつくれるようになると、大好きな人、つまり母と自分のつくった料理を挟んで笑い合える時間は、何よりも大事なものになった。
料理が趣味なことと関係があるのかどうかわからないが、僕は昔から穏やかな性格をしていた。泣いたことはあっても、怒ったり興奮したりした覚えはあまりない。
そんな性格を買われたのか、小学校6年になってしばらくしてから、担任の先生からあることを頼まれた。
「木田恵さんに、このプリントを届けてほしいの」
木田さんというのは、6年になってから一度も学校に来ていない、不登校の女の子だった。
先生はもちろん学級委員、それまで仲のよかった友人たちも家に行ったことはあるものの、母親には会えても本人には会えなかったらしい。
「木田さん」という名前に違和感を覚えつつ、話を聞いていた。
去年まで、彼女は違う苗字だった。彼女の母は離婚したのだ。不登校はもしかしたらその影響もあるのかもしれなかった。
「……わかりました」
僕たちは似た境遇だけど、僕は十分すぎるほど幸せに暮らしている。不登校が離婚のせいだとしたら、彼女には何か足りないものがあるのだろうか。
翌週、僕は緊張しながら彼女に家に向かった。
「悪い子じゃないの」
木田さんの家は、街の中心部にあるマンションの5階にあった。学校から歩いて15分ぐらいの場所だ。
インターホンを押して待つ。その日、木田さんのお母さんは仕事が休みで家にいるはずだとは、先生を通して確認済みだ。
しばらくすると、お母さんが玄関のドアを開けてくれた。木田さんと目元が似ていて、親子なんだとすぐにわかる顔だちだった。
家に上がらせてもらう。お母さんはすぐにお茶とお菓子を出してくれた。僕らの街ではそこそこ有名なケーキ屋さんのパッションフルーツショートケーキで、僕と母の好物でもあった。
プリントを渡すと、お母さんは木田さんを呼んでくるといって席を立った。ケーキをひとりでもそもそ食べながら待つ。ふと、母にも半分分けてあげたいと思った。そうしたらきっともっとおいしく感じられただろう。
やがて、見るからにがっかりした様子でお母さんが戻ってきた。木田さんは部屋から出たくないと言っているそうだ。
「恵を悪く思わないでね。私のせいなの」
お母さんはまるで言い訳をするようだった。
「知っているかもしれないけど、おばさんは去年離婚したの。離婚前とはどうしても生活が変わってしまってね。恵はそれになかなか慣れられないみたい」
「僕、恵さんの気持ち、ちょっとだけわかりますよ」
他の人の家のことにあまり深入りしないほうがいいと思いつつ、つい答えてしまった。
「僕の母も3年前に離婚して、僕は今、母と二人で暮らしているんですけど、やっぱり最初はちょっと戸惑いました。僕はわりとすぐに慣れましたけど、人それぞれのペースってあると思います」
きっとお母さんは疲れていたのだろう。まるで抱えていたものを、僕の話を聞いてうっかり気を抜いてこぼしてしまったように、こんなことを話した。
「結婚していた頃と同じほどには料理に手をかけられなくなったことを、怒っているみたいなの。昔からおばさんのつくる料理を大好きでいてくれたから」
僕の母と同じシングルマザーである木田さんのお母さんは、同じように忙しく、何とか時間を捻出しようと努力はしているものの、どうしても料理にまで手が回せないこともあるとのことだった。
部屋をちらりと見回す。何だかわかる気がした。どこもかしこもちゃんと整理整頓されている。母のように手を抜けない性格なのだろう。母は料理以外のことは結構ズボラだったから、料理する時間があったのだ。
「どうしても出来合いのものになってしまうこともあって、そんなときは部屋に閉じこもってしまって食べてくれないのよ。自分のお小遣いからお菓子を買ってきて、部屋でひとりで食べているの」
単に閉じこもっていることだけではなく、育ちざかりの時期に健康も心配だとお母さんは言った。
「本当にね、悪い子じゃないの。ただ生活が変わって、混乱しているだけなのよ。でも私も働かないといけないから、どうしようもできないときがあって……」
そうなんですか、とうなずいたときには、僕の頭の中には「あるアイディア」が閃いていた。
「今度、宗一郎くんのお母さんに会わせてね」と懇願するように言うお母さんに、僕はそれとは別にひとつの提案をした。
「よかったら、一緒に食べない?」
僕はときどき食材を持って木田さんの家に行き、料理をつくることにした。
料理を通して木田さんに「いいたいこと」があったのだ。
母にそのことを話すと、宗一郎なら絶対にできるから、何かあれば協力すると言ってくれた。僕を通して母と木田さんのお母さんも仲良くなった。
慣れてくると、木田さんのお母さんがいない日でも、借りた鍵でどんどん入っていってキッチンを使わせてもらった。
一方で木田さん自身にはなかなか会えなかった。
予想していたことだったから、がっかりはしなかった。
食事はいつも部屋の前に置いてきたが、お盆にいつもカードを載せていた。表面に料理の説明や、木田さんへのメッセージを書き、裏にはその日の料理の感想や食べたときの気持ち、体調、次はどんなものを食べたいかなどを書いてもらう欄をつくった。
裏面は最初は白紙だったが、少しずつメッセージが増えていった。内容も、「ありがとう」とか「おいしかった」とかいうひとことだったのが、だんだん僕に対する質問や、学校のことを尋ねる内容、料理についての思い出語りといったものに変わっていく。
今や料理は単なる食べ物ではなく、心を伝え合うためのコミュニケーションの手段になっていた。
ある日、いつものようにつくった料理を部屋の前まで運び、ドアをノックした。
「木田さん、食事、ここに置いておくね」
そう伝えるとドアの向こうから少しくぐもった声で「ありがとう」とだけ聞こえる、はずだった。それがいつものことだった。
だが、その日は違った。
返事の声がなかなか聞こえない。おかしいなと思っていると、突然ドアが開いた。
木田さんが立っていた。
「あの……いつも、ありがとう」
初めて、木田さんの声をドア越しではなく直接聞いた。
「よかったら、一緒に食べない?」
目を逸らしてもじもじしながら、木田さんが言う。
「……いいの?」
僕のほうも驚いた。声が少し震えてしまったぐらいには。
木田さんは黙ってうなずいた。
「行動を起こせば、何か見えてくる」
吐き出したくても、吐き出せる場所がなかったのだと思う。
部屋で一緒に食事をしながら、木田さんはぽつりぽつりと雫を垂らすように気持ちを打ち明けてくれた。
お母さんの料理が大好きだったこと。
頻繁に凝った料理をつくれなくなったのは仕方がないとわかってはいるけれど、これまでとは変わった環境で大好きなものがすべてとはいわないまでもなくなってしまったのに、いいようのない不安を感じてしまったこと。
彼女は何度か、寂しいとか不安だとかいう言葉を口にした。
ショートカットのボーイッシュな外見と、芯のあるはっきりした声質からは、意外なようにも、よくわかるようにも思えた。どちらかといえば活発な子のほうが、寂しさに弱いし、敏感だ。
「私、どうしたらいいのかわからないんだ。お母さんを困らせたいわけじゃないし、離婚だって、それでお母さんが不幸にならずに済んだのなら、してくれてよかったと思ってる。でも、顔を合わせたら料理のことでいっぱい責めてしまいそうな気がして怖い。本当に、どうしたらいいかわからない……」
「自分から行動を起こせば、きっと何か見えてくるはずだよ」
僕は料理を通して「いいたかったこと」をやっと口にした。
「何かしてもらうことを待っているだけだと、人は不安になるんだと思う。お母さんの料理を食べると安心できるというなら、例えば、今度は木田さんがつくることで、お母さんを安心させてあげることもできるんじゃないかな。大好きな人が安心してくれれば、自分も安心するだろ? どんなにあがいたって過去には戻れないけれど、自分の行動や心の持ち方で今を変えることはできる。新しい『安心』を、今度は自分でつくるんだ」
「それって、自分で料理をつくるってこと? 無理よ、私はまだ子供だし……」
言いかけて、木田さんは口をつぐむ。今まさに食べているものは、同い年の僕がつくったということに気づいたからだろう。
「それに料理って、気持ちが晴れるんだよ。いろんなことをきちんと順序立てて同時進行しないといけないし、そのひとつひとつに集中しないといけないから、余計なことを考えずに済む。そうやってできたものを食べるときは、なかなかの達成感を味わえるし」
最初は疑わしげだった木田さんの表情が、徐々に好奇心に満ちたものになっていく。僕が楽しそうに喋ったせいかもしれない。子供はいつだって、人が楽しそうにしていることに興味を持つものだ。
僕はそれから木田さんに料理を教えることになった。
木田さんはセンスがよくて、僕が半年かけて身につけたことをほんの数週間で理解したり、絶妙な味付けをきちんと測るのではなくほとんど感覚だけでつくってしまったりした。
数か月後には、彼女は手料理をお母さんに振る舞えるようになっていた。
僕たちは家族ぐるみでお互いの家を行き来するようになり、みんなでつくった料理を囲んで親交を深めた。そのときには木田さんの不登校はすっかりなくなって、もとの明るい女の子に戻っていた。
やがて僕と木田さんは同じ中学に進学した。
僕と木田さんに驚くべき事件が起こったのは、それから少し経った後だった。
「背中を押された気がした」
僕の母と、木田さんのお母さんは同時期に再婚することになった。
その夫たち、つまり僕たちのお父さんというのが、兄弟だったのだ。
僕たちははからずも、同じ「池部」という姓を持ついとこ同士になった。
「なんかさぁ、落ち着くところに落ち着いたって感じだよねぇ」
恵ちゃん――僕たちはその頃には、お互いを「恵ちゃん」「宗一郎」と呼び合っていた――は、たまたま下校のタイミングが重なって並んで歩いたとき、しみじみと言った。
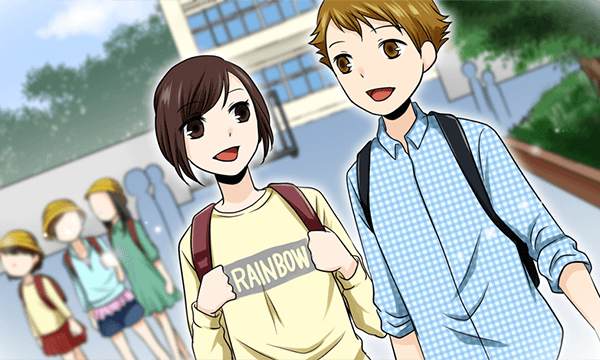
「落ち着く?」
「うん、私、前々から宗一郎は他人って気がしなかったんだよね。確かに料理の先生ではあるけれど、それよりもさらに近い存在というか……家族とか兄弟みたいだなって思ってた。そしたら本当にいとこになっちゃうなんて」
「兄弟、かぁ」
その言葉を呟くと、口の中がほろ苦くなったような気がした。
きっと恵ちゃんはこれからも僕のことをそういう目で見続けるのだろう。ダメ押しになるような出来事も起こってしまった。
僕の初恋は、きっと実ることはない。
予想した通り、僕たちが恋人同士になることはなかったけれど、その代わり、いいライバルになった。
僕たちは同じように料理の道を志し、それぞれプロになった。
だが、分野はかなり違う。
僕は都会に住む人々の生活スタイルや好み、価値観に合わせた料理をつくることが多いけれど、恵ちゃんは全国津々浦々をみずからの足で逞しく回って、土地土地の食材を使った料理をつくり、地域おこしなどに貢献している。肩書きは「創作郷土料理研究家」。地方創生が叫ばれる昨今、その土地の特長や個性を料理を通して伝えるメッセンジャーとして話題だ。
プロになってからも僕たちは何かあるたびに連絡を取り合い、悩みがあれば相談し合っている。
有本悠さんとテレビ出演を通じて知り合い、ビューティ道場に入らないかと誘われたとき、僕は「自分が女性の人生を変えてしまうような場所に行っていいのだろうか」と悩んで、恵ちゃんに電話した。
恵ちゃんはちょうどそのとき、佐渡島でアジを釣っていたらしい。電話の向こうからは威勢のいい潮鳴りが聞こえた。
「受けたほうがいいよ」
彼女の答えは明快だった。
「私は宗一郎に人生を変えてもらって、幸せになれたよ。宗一郎の料理は人を幸せにできる力があるんだから、受けたほうがいい」
今の恵ちゃんだけでなく、小学生のときの小さな僕と恵ちゃんにも、ぽん、と背中を押された気がした。
⇒【NEXT】「我慢できない、早くほしい」耳を軽く噛みながら、熱っぽく囁いてくる(同居美人〜番外編〜ワケありイケメン 池部宗一郎〜ラブストーリー〜)
あらすじ
同居美人の番外編として、7人の男性キャラクターのうちひとりを主人公にした短編ストーリーが登場♪
▼キャラ紹介
池部宗一郎 25歳 料理研究家
女性だけでなく、男性からも人気があり、料理を通じて相手とのコミュニケーションを図るのが得意。
引っ込み思案なところもあるが優しく、相手を思いやることができる人。
そんな彼のワケありの理由がわかるストーリーが楽しめます!


















