女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
官能小説 同居美人〜番外編〜 ワケありイケメン 小島泰明〜ワケありの理由〜
「注目されるカップルに」
物心づいたときにはモテていた。
4月生まれだったおかげで、同じ学年の子どもたちよりも勉強も運動もでき、背も高かった。
容姿も悪くなかった。母親の美貌と父親の精悍さが、いやみにならない程度のちょうどいいバランスで混ざり合っていた。
増長しないよう、自分が人よりいろんなことができるのは実力ではなく単に運なのだと両親に言い聞かされて育ったので、それを鼻にかけるようなこともしなかった。
全部、単に運がよかっただけ――。
そう考えながら幼い日々を過ごすうちに、僕は妙に厭世的で、どこか虚無的な少年になっていった。
中学になって、初めて女の子と付き合った。僕に告白してくれた、同学年で違うクラスの生徒だった。
付き合った理由は、告白されたから。とくに彼女のことが好きだったわけではない。モテるのが運のおかげだというのなら、選り好みなんてしてはいけないだろう。
小学校の頃にも告白されたことはあったが、いくら何でも小学校では早いだろうと丁重にお断りをした。中学で付き合った子は、入学していちばん最初に告白してきた子だった。
それから高校を卒業するまで、僕は「告白されれば付き合う」ことを繰り返した。
フラれるのは、大抵僕のほうだった。
僕があまりにも恋愛に対して不熱心なものだから――たとえば休日に会おうとしなかったり、電話に出なかったり、夏の海水浴やクリスマスといったイベントごとに無関心であったり、連絡の返事が遅かったり――みんな、だんだん我慢できなくなって離れていった。
たまに僕がふることもあったが、相手が僕の行動を強制しようとしたり、プライベートにまで無理に立ち入ろうとした結果、致し方なくだった。
そんな僕が、初めて自分から恋をした。大学に入学してすぐのことだ。
勧誘されて何となく入った映画サークル(つくるのではなく、観るほうだ)に、彼女はいた。
同じ1年で、僕は経済学部だったのに対し、彼女は文学部。好きになった理由は……自分でもよくわからないが、恋愛なんてそんなものだろう。
しいていえば自分が何をしたいか、何がほしいかといった好みがあらゆる面ではっきりしていたところだろうか。
今まで付き合った子がだいたいみんな何でも僕の好みに合わせようとしてくれたせいだろうか、やけに新鮮に映った。
夏になる前には、自分から気持ちを伝えた。
彼女、服部瑞穂は最初は断ったものの、その理由は「ほかに好きな人がいる」のではなく、「恋愛に興味がない」だったので、結局合計3回告白した。
告白は3回までが1セットだと、なぜかわかっていた。ほかに好きな人がいるか、自分のことが嫌いか、状況的に無理なのでなければ、3回もすれば大体は心が動く。逆に3回しても断られるのなら、潔く退かねばならないが。
こうして僕たちは付き合い始めた。
瑞穂はなかなかの美人で、僕も決して悪くはない容姿だったので、僕たちはサークル内だけでなく学校内でも注目されるカップルになった。
だが、僕たちの歯車はすぐに噛み合わなくなった。
「大事なものがあった」
映画サークルの活動は、「週に一度学内の一教室にみんなで集まって、何か一本部員のおすすめ映画を観る」というユルいものだった。
しかし、それほどユルい活動にも関わらず、瑞穂はサークルにあまり顔を出さなかった。
サークルに参加しないだけではない。学内の行事も何かと理由をつけてよく欠席したし、僕との外出もあまり乗り気ではないようだった。
当然といっていいのか、体の関係にもなかなかなれなかった。それがすべてだとは思わないが、あるのとないのとではやはり距離感が変わる。
(せっかく付き合ったのに、これじゃ意味がない)
少しずつ不満が募っていった。
注目されてしまっただけに、友人を始めとする校内の人々にはこの状況がどんなふうに見えるのかも気になる。
不仲そうなところを見せればすぐにせせら笑い、あることないこと得意げに周囲に吹き込む奴が出てくるだろう。
僕は昔から人よりいろんなことができたせいで、十分謙遜していても妬まれることが多かった。妬まれるのは構わないが、そんな奴らに付け入る隙を与えるのは嫌だ。他人のアラを探し、拡大して見ることで優越感を覚える連中には生理的な嫌悪感を覚える。
僕は瑞穂に不満を伝えたが、しかし、彼女にはそれよりも大事なものがあったのだった。
「私、漫画家になりたいの」
その夢のことは、付き合う前から何度か聞いていた。
大学までは親のいうとおりに真面目に勉強したものの、第一志望に入学できたらあとは自由に夢を目指すという約束を、瑞穂は親と交わしていた。
映画サークルに入ったのも夢のためだった。大学のサークルというものを経験しておけばのちに漫画に活かせるかもしれないし、映画を観れば創作の引き出しも増えるだろうという狙いだ。
そう聞くと、僕と付き合ったのもひょっとして経験値のためかと疑ったが、それは否定してくれた。
すでにある賞で佳作を受賞し、今は担当もついて二作目に取りかかっているという瑞穂にとっていちばん大事なのは、漫画を描くこと。それを優先できるのなら、恋人との時間を十分に取れないのも、まわりの羨望のまなざしを失うのも仕方がない。
その理屈はわかりやすく、そして僕にとっては残酷だった。
「チャンスだった」
今、振り返ってみれば、僕は本気で「そんなこと」を考えてはいなかったと思う。
ただ、不満に耳障りのいい理由をつけたかっただけだ。
それでもあのときは、自分は彼女を本気で心配していると思っていた。
「漫画家なんて職業で一生やっていけるのは、才能も運もあるほんの一握りの人間だけだ。そんなことに若い時分の貴重な時間を費やす暇があったら、文学部なんてただでさえ潰しがきかないのだし、将来役に立つ資格でも取っておいたほうがいいよ」
――そうやって人生のプランを若いうちに前もって設計しておけば、就職先も選べるだろうし、ゆくゆく結婚、妊娠したとして、職場復帰も余裕になるだろう。家に入るにしても余裕を持って子供を教育できるようになる。
結婚も出産もしないのならなおさら、計画は綿密に立てるべきだ。今の日本のシステムは、未婚の女性が一人で生きていくには何かと不都合なことばかりなのだから。
年を取ったとき、「やっぱり漫画家になれませんでした。あるいはデビューしたけど、鳴かず飛ばずでした」なんてことになったら、君はその先どうやって生きていくつもり?
……手を替え品を替え、そんな内容のことを並べ立てては、彼女を夢から引き離そうとした。
夢ではなく、僕のほうを見るように。
そして、周囲の誰もから「幸せそうなカップル」だと感嘆されるように。
だが、思うようにはならなかった。
「泰明が言っていることは、私がいちばんよくわかってる。それに、そういうことは私、さんざん両親と話し合ったの。その上で覚悟を決めたし、夢が叶わなかったときにどうするかも、今は言葉にしたくはないけど、私なりに考えてる。ねぇ、漫画のことは私にとってとても大事な話なの。あまり深入りをしてほしくないんだ」
最後の言葉に、ひそかに怒りを覚えた。
深入りをしてほしくない? 恋人同士なのに?
君のことを誰よりも大事に思っているから、わざわざ忠告してやったのに?
このときに僕は彼女の薄情さを詰って、別れるべきだったのだ。そのほうが瑞穂にとってもよかっただろう。
それでも僕は彼女が好きだった。いや、執着というべきだったかもしれない。
「何人もの女性が僕を望んでも手に入らなかった」、そんな自負を粉々に蹴散らした瑞穂を、何とかして振り向かせたい。僕なしではいられなくしたい。
ちょうどその頃から、瑞穂は落ち込むことが多くなった。二作目のネームがなかなか通らなかったのだ。
チャンスだった。
「瑞穂の絵って特徴に欠けるというか、あまり心の残るものがないよね」
「この展開、ダメ出しされた理由がわかるな。次のページで何が起こるかすぐにわかる」
「これ、言い回しがわかりづらいよ」
僕は瑞穂の作品に対して、辛辣な言葉を浴びせ続けた。
だが、もとはと言えば、彼女が感想を述べてほしいと頼んできたのだ。僕は思ったことを正直に話しただけだ。
だから言葉が少々きつくなっても、瑞穂はいやな顔をせずに素直に受け止め続けた。彼女も何とか突破口を見出したくて、もがいていたのだろう。
……違う、全然正直なんかじゃない。
本当は感じていないことまで、しゃあしゃあとそれらしく言った。彼女の作品がいかに凡庸か、伸びしろがないか、面白みに欠けるか。
罪悪感はなかった。
僕のアドバイス通りに生き、僕と今以上に相思相愛になるのが、瑞穂にとって幸せなことなのだから。
その信念は日々、強くなっていった。自分もいつの間にか自分に洗脳されていたのかもしれない。執着に心を狂わされて。
正常な精神状態の瑞穂であれば、あくまでも「いち素人の意見」というぐらいにしか受け止めなかったであろう的外れな評価は、僕自身驚いたぐらい次々と深く彼女に刺さっていった。
「私、やっぱり漫画家になれないのかな。泰明の言うようにしたほうが、幸せになれるのかな」
瑞穂の口からそんな弱音がぽつりと吐き出されたとき、内心でガッツポーズを取った。
「これ以上ない充実感」
夢という支えを失いかけた瑞穂を、僕は完全に「矯正」しようとした。
もう、僕そっちのけで漫画を描きたいなんて言い出さないように。
どこに行っても、誰と会っても羨まれるカップルになるために。
最初に好きだった彼女の「好みがはっきりしているところ」は、いつしかひとつひとつ叩き潰すべきところに変わっていた。
僕は自分の考える「こうすれば女性は幸せになれる」という像を次々提案した。というより、命令した。今までが自由すぎた瑞穂に対しては、仕方のないことだった。
服装、喋り方、趣味、取っておくべき資格……。
愛する女性を自分が正しいと思う方向、こうすれば絶対に彼女は幸せになれると確信できる方向にプロデュースすることは、「マイ・フェア・レディ」のようで、これ以上ない充実感があった。
瑞穂は徐々に漫画を描かなくなっていき、代わりに僕と一緒にいる時間が増えていった。
しかし、破滅はある日突然訪れた。
大学の構内を一緒に歩いていたときだ。
瑞穂は、買ってあげた靴の高いヒールでバランスを崩し、転んでしまった。
それまでヒールのある靴なんてほとんど履いたことがない女の子だった。なかなか慣れられないのも仕方のないことだ。
とはいえ、少しずつでも努力はしてもらわなければ。
「女性なんだから、このぐらいのヒールは履けるようになっておかないと、この先大変だよ」
優しい中にも厳しさをにじませるよう意識した声で注意しつつ、瑞穂を助け起こそうとする。
当然焦って立ち上がり、謝ってくるものだと思ったが、違った。
瑞穂は座り込んだままだった。
「……ないの」
「え?」
「見えないのよ」
瑞穂の表情は、顔のまわりに垂れた髪でよく見えない。ショートカットだったのを伸ばすようにいった髪は、中途半端な長さでまだ結わえることもできなかった。
「見えないって、何が?」
転んでしまったのが恥ずかしくて、動転しているのだろう。今度は優しさだけの声で尋ねる。
「『この先大変』のこの先って何? どこにあるの? 私、自分がどこに向かっているのか、そこで何をすればいいのか、全然わからない」
「……とにかく立とう、瑞穂」
この期に及んで何を言っているのだと苦々しい思いが広がる。そんなことは何度だって語って聞かせたはずだ。
だが、今そんな問答をするわけにはいかない。人の目がだんだん多くなっている。まずは彼女を立たせて、どこか人目のないところへ行かなくては。
次の瞬間、彼女は予想の斜め上どころか、上空三千メートルぐらいの行動に出た。
転んだ靴を脱いで高々と掲げると、一気に地面に振り下ろしたのだ。
ガツン! と大きな音を立ててヒールが外れる。
大きな音だったので、転んだだけではさして気にせずにいた周囲の人たちも一斉に振り返った。
「ごめん、泰明の考える『幸せ』っての、私にはやっぱり合ってないみたい」
呆然とする僕に、折れたヒールの靴を押し付ける。
もう片方もその場に脱ぎ捨てると、瑞穂は裸足のまま僕を置いて歩いていった。
「かっこよくなくてもいい」
事件は、ちょっとした噂になった。
その後、瑞穂は僕と距離を置くようになった。
サークルには完全に出てこなくなったし、校内で顔を合わせてもまるで逃げるようにそそくさと立ち去ってしまう。
家に行っても入れてもらえなくなった。
電話も、出てはもらえてもすぐに切られた。この頃はメールはまだそう普及していなかったが、もし出したとしても無視されたか、何通かに一通返事をもらえたかどうかというところだっただろう。
当然、僕たちのカップルとしての評判も地に落ちた。
学校に行くと誰かが自分をせせら笑っているような気がして、僕は家に閉じこもった。
何事につけ人よりも勝っていた自分は、あの一瞬で壊れてしまったのだった。
壊したのは直接的には瑞穂だが、しかし恨みは湧かなかった。これほど大ごとになるとはさすがに予想しなかったが、こうなることはどこかでわかっていた気がする。落ち着いた状態で一歩引いて自分を見直してみれば、むしろ「調子に乗りすぎた」と反省した。
約半月も閉じこもっていただろうか。
いつまでもこんなことをしていたら余計に印象が悪くなると、僕は意を決して大学に行くことにした。
僕が自己嫌悪に完全に陥って周囲を拒絶しなかったのも、瑞穂に恨みを向けずきちんと反省できたのも、突き詰めればこの「外面の良さを気にする」性格のおかげだ。僕を壊したのも、救ったのもこの性格だったわけである。
大学に行くと、ほとんどの人はあえてその話題を避けようとしたが、例外が一人だけいた。
同じ映画サークルの福生正光先輩だ。
福生先輩は、去年、ある小説の新人賞を受賞したという。そのことを明かしてはいなかったが、瑞穂はどこからかその話を聞きつけ、創作の先輩として、ときどきだが相談を持ちかけていたそうだった。瑞穂と同じく、創作のネタを増やすために映画サークルに入っていたという点も親近感になったようだ。
だがあるとき――僕が彼女の夢を壊しにかかっていた時期だ――からその相談がぴたりとなくなったので、どうしたものかと心配していた。瑞穂の相談はあくまでも物語づくりに限ったことだったが、日に日に覇気がなくなっていくのも気になっていたらしい。
後でつるむようになってわかったことだが、福生先輩はいつもはぶっきらぼうで人付き合いも悪いものの、自分を心から頼ってきた相手や、何かを目指して一心に努力する相手は決して邪険にしない。
だが、普段の態度のせいで人と仲良くなることがあまりなく、ゆえにその良さが伝わることが極めて少ない。
瑞穂は「アドバイスがほしい」という一念から食いついたので、誰も知らなかった恩恵に預かったのだった。
事件の後、瑞穂は事をすべて明らかにはしなかったものの、「やっぱり漫画家を目指します」という、先輩にしてみれば前後関係のよくわからない決意表明をよこしてきたという。
「いったい何があったんだ? あの事件に関係があるのか」
先輩にしてみれば、僕への遠慮よりも「弟子」を心配する気持ちほうが勝ったのだろう。
そのストレートな尋ね方に、かえって肩の力が抜けていった。
(かっこ悪いなぁ、僕)
内心で自嘲した。悪い気分ではなかった。かっこよくなくてもいいというのは、案外楽なものだ。
僕は福生先輩に思いきって全部話した。
「それはお前、愛情じゃなくてエゴだな」
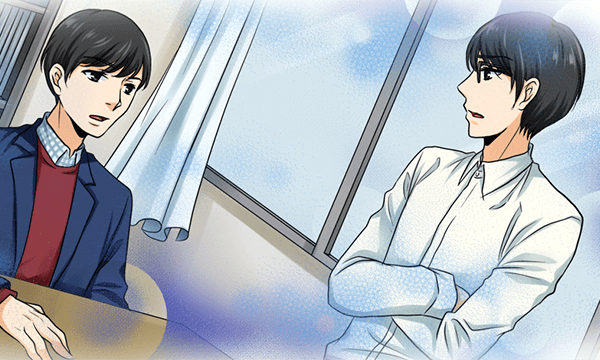
先輩はぴしゃりと言った。
はっきりした物言いに、小気味よさを感じる。
「確かに漫画家が生き残るのは大変だろうが、好きで続けていれば、思った通りではなくても何らかの形で結果は出るものだよ。その過程を見守って、必要があれば手助けをすることが、私は愛情だと思うけどな」
先輩はなぜか少し寂しそうだった。
しばらくして、瑞穂は学外の同じ漫画家志望の男性と付き合い始めたと聞いた。
福生先輩とはそれから何かとつるむようになった。人付き合いの苦手な福生先輩と、外面が良くて人付き合いにそつのない僕は、心底までわかり合ってしまえばなんだかんだで相性バッチリで、僕はよく「福生先輩と外界とをつなぐメッセンジャー」だと周囲にからかわれた。
福生先輩が誰にも話したことがないという過去を打ち明けてくれたときは、心から同情したとともに、自分にだけ教えてくれたことが嬉しくも誇らしくもあった。
その後、僕はまた自分から人を好きになり、付き合ったが、就職のときに結婚相談所を選んだのは、瑞穂にしてしまったことへの後悔と反省があったからだ。
自分のエゴや思い込みだけでなく、本当にその人のことを見て、その人のことを考えて、望む道に進めるようアドバイスしたい。
その結婚相談所はほどなくして売り上げを急増させ、結婚式のコンサルティング事業も行うようになった。
後輩たちに「相談を受ける際の姿勢や心構え」についてすべて教えた僕は、二十代の後半からはプランナー部門に異動したが、やること自体は違っても、持つべき心がけは同じだった。
やがて「行列のできるウェディング・プランナー」としてメディアで取り上げられるようになると、篠村さんからビューティ道場に入らないかと誘いを受けた。
「いいですよ。僕の力で女性を幸せにできるのであれば」
そのときの胸の中には、やはり瑞穂の姿があった。
⇒【NEXT】「俺の前ではエッチになっていいんだよ。きれいだよ」(同居美人〜番外編〜ワケありイケメン 小島泰明〜ラブストーリー〜)
あらすじ
同居美人の番外編として、7人の男性キャラクターのうちひとりを主人公にした短編ストーリーが登場♪
▼キャラ紹介
小島泰明 35歳 ウェディング・プランナー
「行列のできるウェディング・プランナー」として雑誌やTVでも紹介されている。
紳士で大人な彼だが、言うべきことははっきりと言う。
このような職についているが、本人は忙しくて婚期を逃した。
そんな彼のワケありの理由がわかるストーリーが楽しめます!


















