女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
官能小説 同居美人〜番外編〜 ワケありイケメン 松垣洸太〜ラブストーリー〜
「きれいになった」
仕事の都合で、ビューティ道場から離れてから半年ほど経った頃のことだった。
「鈴村りょうがフランスから帰国した」
その噂は、あっという間にファッション業界の関係者の間を駆け巡った。
やっぱりなんだかんだ言っても華があるんだよ。みんな忘れられなかったんだ」
ほぼ一年ぶりに俺と会ったモンさんは、そんなことを言って一人でうなずいていた。
俺たちはその噂が噂になる前から知っていた。りょうさんが帰国前に直接知らせてくれたのだ。彼女はフランスでの成果を伝えたいから、日本に着いたら俺たちと三人で食事をしたいとも言ってくれた。
俺とモンさんは今、その待ち合わせ場所――最近オープンしたばかりのカジュアルフレンチレストランに向かうべくタクシーに乗っている。平日の夜なのに、雨のせいで道はけっこう混んでいた。
「何かとお騒がせな子でしたからね。忘れたくても忘れられないって人も多かったんじゃないですか」
俺が苦笑すると、モンさんは
「そういうのも、まぁ、才能のうちだよ」
となぜか自分が胸を張った。彼女だってりょうさんには何かと振り回されていたはずなのだが、気にしている様子はまったくない。もしかしたら忘れているんじゃないかと思うほどだ。
「お久しぶりです!」
すでに席についていたりょうさんは、俺たちを見るとぱっと燃え上がるような笑顔になった。
ふと、成田空港で別れたときの姿が脳裏によみがえる。
あのときと比べると、少しだけふっくらした。髪がだいぶ短くなった。ちょっと日焼けした。表情や身振りが大きくなった。
そして、きれいになった。
「乾杯!」
俺たちは挨拶もそこそこにテーブルにつき、まずは再会を祝ってワインを開けた。
今日はりょうさんがすべておごりたいとのことだった。俺とモンさんは相談の結果、遠慮なく甘えることにした。知り合いの店らしいので、オーダーも基本的には彼女にまかせた。
「それで、通訳にはなれたの?」
モンさんがいきなり切り込む。この人は良くも悪くも聞きたいことを遠回しにしない。
「ええ」
りょうさんはうなずいた。
「でも、今やっていることは通訳だけじゃないんです」
「というと?」
現地で努力したりょうさんは通訳として独り立ちしたものの、ただの通訳はほかにもたくさんいた。りょうさんは差別化を図るべく、現地で培った人脈や元モデルとしての完成を駆使し、ファッションに特化したポジションを目指していた。
さらにその延長で、優れた若手デザイナーを関係者に紹介したり、彼らの商品を扱うセレクトショップをフランスで経営したりしているという。日本でもいい物件が見つかり次第、店舗をオープンさせる予定だそうだ。
「はぁ、多才だねぇ……」
日本にいた頃のりょうさんからは考えられない精力的な活動ぶりに、俺とモンさんは舌を巻いた。
「同じ目線で」
俺たちはそれぞれ連絡先を交換した。これからしばらくは日本にいるから、また近いうちに顔を合わせようと約束して、別れた。
それから数週間後。俺はハーフの男性モデルのスタイリングを頼まれた。海外なら珍しくないのだろうが、日本で暮らしているにしてはちょっと変わった子で、アジア人、白人、黒人全部の人種の血が入っている。俺に用意できる服の中には似合いそうなものがなかった。
(困ったな……)
そのとき、りょうさんのことを思い出した。
優れた若手デザイナーを関係者に紹介したり、彼らの商品を扱うセレクトショップをフランスで経営したり……そんなことを言っていた。今までにない新しい感性の服なら、彼に似合うものが見つかるかもしれない。
俺はすぐにりょうさんに連絡をとった。
りょうさんは倉庫がわりにしている自宅に屈託なく俺を招待してくれた。
「すみません、すごーく散らかっているんですけど」
本当に散らかっていた。
家自体はなかなか広いのだが、さすがに倉庫と兼用となるとしっちゃかめっちゃかになっていた。店舗物件が見つかるまでの辛抱だと割り切っているのだという。だがそのなりふりかまわないともいえる状態に、りょうさんの夢にかけるパワーを感じた。
数十分もせず、「これ!」というものが見つかった。
それ以外の服に関しても、俺はりょうさんの独特のセンスに内心舌を巻いた。母親に言われるままではあったが、子供時代からのモデル経験で磨かれた感性は伊達ではなかったのだ。
使い終わったらすぐに返すことを約束して、その服を借りた。
***
そのことをきっかけに、俺たちは情報交換がてら食事をするようになった。前の食事のときにまた会おうとは言ったものの、ああいうのは社交辞令のことが多い。きっと次に会うのは来年か、もっと先か……なんて思っていたのに、ぜんぜんそんなことはなくなった。
モンさんも何度か誘ったが、彼女はそのたびに断った。……彼女なりに俺の背中を押してくれているのかもしれないと感じた。意外と、といっては失礼だが、人の気持ちに敏感な人なのだ。昔、りょうさんに恋心を抱いていたこともバレていたかもしれない。
俺は自分にないものを持っているりょうさんに、改めて惹かれていった。新しいものを取り入れていくパワー、センス、単純な行動量、その結果としての人脈――。
焦りもした。いつか手の届かないところに行ってしまうのではないかと。前のように、「違う世界での手の届かないところ」ではない。今度は同じ世界の手の届かないところだ。
りょうさんと俺は、今や同じ業界をサバイブしようとするライバル同士になっていた。
だが、惹かれるのはそういうのも全部ひっくるめて、だ。
俺はりょうさんに素直に、君をすごいと思っていると伝えた。本当にすごいと思ったから、いわずにはいられなかった。
りょうさんは俺の努力家なところと、その努力に見合っただけの結果を出すところ、そして変なプライドにこだわらずいいものはいいと認められるところが素敵だと言ってくれた。
俺たちはいつしか、完全に同じ目線で話すようになっていた。
「嵐に背中を押された」
ある夜のことだった。
俺とりょうさんは仕事終わりに落ち合って、俺の家のそばにあるバーで飲んでいた。
家のそばの店を選んだのは、下心からではない。その店はマスター自身がマニアな日本酒バーで、普通の店では扱っていないような銘柄の酒がたくさん置いてあった。りょうさんにそれを話すと、ぜひ行ってみたいとのことだったので連れていったのだ。
「最近は海外の人でも日本酒に詳しい人は多いから、私も覚えたいんです。私、海外に出て初めて自分があまりにも日本のことを知らなかったのに気付いて愕然としたんですよ。これからはファッションだけでなく、日本の歴史や文化のことも勉強していきたい」
りょうさんは最近、茶道と着付けも習い始めたという。仕事で忙しいだろうに、やはりパワフルな人だ。
わからないことは素直に尋ね、人の話をよく聞くりょうさんのことをマスターも気に入って、とっておきのお酒をどんどん出してくれた。
「今度は洸太抜きでもいつでも来てよ。まだまだ飲んでもらいたいお酒がたくさんあるんだ」
「はい、必ず来ます!」
和やかな時間を過ごして店を出ると、外はどしゃ降りになっていた。
「ええっ」
思わず声を出してしまう。風も強くて、これはもう嵐といってもいい。
「そういえば台風が来てるって言っていましたけど……」
「速度が思ったより速かったとか?」
「そんなこと、あるんですかねぇ」
「少なくとも天気予報では言っていなかったけどね」
俺たちは口をつぐんだ。真相を明らかにしたところで目の前の嵐が止むわけでもない。
「私、折り畳み傘を持ってます。これで松垣さんの家まで送っていきますよ」
「悪いね」
断らなかったのは、家は本当に目と鼻の先だったからだ。
だが……
「きゃあっ!?」
ほんのすぐそこまで行く途中に、強風を受けて傘が壊れてしまった。
「危ないよ」
俺はとっさにりょうさんを抱きしめた。壊れた傘で彼女がけがをしないように。
「え……」
「あ、ご、ごめん!」
すぐに体を離す。考えるより先に体が動いてやったことだった。
「とにかく家に来ないか。傘を貸すよ。……よかったらだけど」
そう言うと、りょうさんはおずおずとうなずいた。
歩きながらいろいろ考える。家に着いたらまずタオルを出して、髪や体を拭いてもらう間に温かい飲み物を用意しよう。それから女性でも着られそうな替えの服を探す。着替えてもらったらなるべく丈夫そうな傘を見繕う。タクシー代は俺が出そう。俺を送らなければ傘は壊れなかったのだし、そのぐらいのお詫びはしたい。
濡れているからシャワーを浴びてもらったほうがいいのだろうけど、さすがにそこまでは言いづらい。抱きしめてしまったことで、りょうさんも警戒しているだろうし……
だが、そんな心配は結局杞憂に終わった。
玄関を入ると、俺たちはびしょ濡れのままごく自然に、お互いに引かれ合うように、キスをした。
なぜそんなことができたのか、よくわからない。
ただ、嵐の日は気圧が変わるせいで、人の気持ちや行動にいつもとは違う変化が表れることもあるという。
きっと俺たちは、嵐に背中を押されたのだろう。
「理性が飛ぶほど好き」
俺たちは一人ずつシャワーを浴びると、ソファーに並んで腰かけてお互いへの気持ちを語り合った。
外は嵐でも、家の中は静かで暖かだった。
「モデル時代は、手の届かないところにいる人だと思っていたんだ。だから少しでも近づこうとがんばって……りょうさんがいてくれたから、今の俺があるようなものだよ。押しつけがましくする気はぜんぜんないけどね」
そこでいったん息を小さく吐いて、さらに続けた。
「でも今は、同じ場所に立っているライバルだという気がする。もちろん、いい意味でだよ。肩肘を張らずに向き合えて、でも負けないようにしようと思える。そういう気持ちも、今までのことも全部ひっくるめて……好きだ」
家の中まで嵐の魔法が効いているのかどうかわからなけれど、不思議に照れることはなかった。伝えるべきことをきちんと伝えたいと、ただそれだけを思っていた。
「私も……ずっと松垣さんのことを忘れられなかったんです。フランスであちらの男性と付き合ったこともありましたけど、いけないと思いながらも松垣さんがずっと心のどこかにいて。日本にいたときから、私のことを遠くから見守ってくれているように感じていたんです。きっと勝手な思い込みだろうなと思っていたんですけど、でも、あの、いつの間にか……好きに……」
りょうさんは言った。
なんてこった、と肩をすくめて笑い出したくなった。本来だったらうれしくて飛び上がりたくなるところなのだろうが、それよりも先に自分にあきれてしまった。俺たちはもう何年も前から、惹かれ合っていたのだ。勇気を出して告白してくれば、もっと早く手に入っていた恋だった。
でもきっと、今だからよかったのだ。今だから、単なる憧れではなくちゃんと向き合えるようになった。
俺たちはもう一度キスをした。
そのままりょうさんをソファーに押し倒す。
抵抗はしなかった。
俺はりょうさんの服――というか俺の服だが、を脱がせていった。
ふいにりょうさんがくすっと笑う。
「どうしたの?」
「松垣さん、やっぱりスタイリストなんだなぁと思って。皺がつかないように脱がせてる」
「あー……」
言われてみて気がついた。こんなときにまで出てくるなんて職業病といわずして何といおう。
その指摘で緊張が少しだけ解けた。
彼女の裸は、きれいだった。
スタイルや肌の美しさだけでいったらモデル時代のほうがきれいなのだろうが、あの頃は「誰かに求められているから、自分でもよくよく考えずにそうしている」という感じだった。
今は全身から自信が溢れていて、間違いなくりょうさんの体なのだという気がする。
「服を着ている姿も素敵だけど、何も身に着けていないほうがもっときれいで素敵だ」
本気でそう思った。
「そんなことを言われたら、これ以上好きになってしまうわ」
「俺はもう、理性が飛ぶほど好きになってる」
たまらずにりょうさんの頬を両手で包み、少し強引に舌を入れる。強引にしたというよりは、なってしまった。求める気持ちが強すぎて。
舌を追い、捕らえ、絡め、唾液を味わい、啜る。そうしながらも指は首筋を辿り、鎖骨に撫で、乳房の弾力を味わう。
「……は、あ」
彼女の吐息が、俺をさらに駆り立てた。もう止められない。
「つながっている」
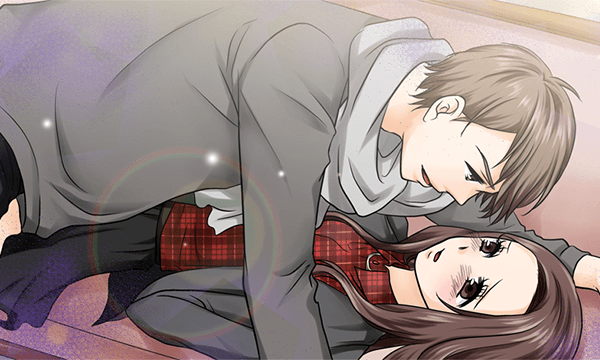
俺は彼女の全身に少しずつキスをしていった。唇が触れるたびに、彼女は小さく吐息を漏らす。
「お願い……」
か細い声で彼女が訴える。
「電気を……もうちょっと暗くして。太ってしまったから、恥ずかしいの」
一瞬、言われたとおりに体が動きそうになった。彼女が望むことなら叶えてあげなければと思った。
でも、途中で止まった。
太ってしまったから恥ずかしい?
「そんなことないよ」
俺は言った。
実際、りょうさんは太ってなんていなかった。モデル時代に比べればふっくらしたけれど、太いというには程遠い。
「今のほうがずっときれいだ」
りょうさんは内心ではまだ怖れていたのかもしれない。自分は本当にこれでいいのかを。モデル時代はたとえ自分の好みではなくても、まわりのいうとおりに振る舞い、いうとおりに服を着て、いうとおりの体型を維持していれば誰かから好きだと言ってもらえた。
でも今は違う。
「俺は今の君が好きだよ。だからもっとよく見たいんだ」
もう一度キスをすると、りょうさんは少し照れたように微笑んだ。
電気は、消さなかった。
***
りょうさんはどこも敏感だった。キスをして、指先で撫でて、舐めて吸って……何をしても切なそうなかわいい声をあげてしがみついてきた。
とくに感じやすかったのは、脚の付け根の可愛らしい木の芽だ。春先にぴょこんと飛び出したかのようなそれは、息を吹きかけるだけでも感じてしまうらしい。
僕はそれを指でほんの軽く摘まみ上げて、口に含んだ。そのまま吸う。
「あぁぁっ、だめ、そこは……弱いのっ!」
身もだえするが、許したくない。もっともっと気持ちよくなってほしい。
「あああ……私、もう……イッちゃう……」
りょうさんは全身を硬直させ、二、三度痙攣した。イったというのはすぐにわかった。
ぐったりしたりょうさんから、しかし俺は離れない。
また同じように、そこを舐める。
「だめ、松垣さん、イった後はすごく敏感になってて……」
「だからいいんじゃないか」
さっきよりは多少優しくしながら、ごく小さな飴玉を転がすように舌先で包む。
「さっきよりずっと深くイケるよ。深く、激しく……」
「や、あぁ……んんっ! あぁぁっ!」
予想した通り、二回目はあっさりといってもいいぐらい、さっきよりもずっと早く達した。
ぐったりしたりょうさんのあそこはぱっくり開いて、白く濁った蜜を垂れ流している。
ほしがっているのだと、すぐにわかった。
「入れて、いい?」
りょうさんを抱きかかえて、その部分に硬くなったものをあてがう。
「え……もう少し休んでから……」
「今のほうがいいんだ。今のほうが体が開いているから……もっと気持ちよくなれる。自由に感じてごらん」
「そういうものなのかな」
りょうさんも多少は好奇心が湧いたようだ。
少しずつ、りょうさんの中に入り込んでいく。
二回もイった中は、トロトロになっているくせに襞という襞が絡んで締めつけてきた。
「う、そ……なんだよ、これは……」
すぐには腰を動かせなかった。こんな気持ちがいいなんて、俺のほうがイってしまいそうだ。
「あぁ、松垣さん……気持ちいいっ、いいの……こんなの……初めて……おかしくなっちゃう……」
りょうさんのほうは、もう極限まで敏感になっていた。挿れただけでイってしまいそうになったようだ。ほとんどうわごとのように言って俺にしがみつく。
ゆっくり腰を動かす。……すぐにゆっくりしていられなくなりそうだけど。
「いいよ、一緒におかしくなろう。一緒に……イこう」
俺たちは、同時に上りつめた。
***
りょうの仕事の関係で長期間会えなくなることが多くなってきたから、俺たちは一緒に住める家を借りた。
長期といってもまあ1、2ヶ月程度だから我慢はできないことはないし、どちらかが生活や仕事を変えなければという危機的状況にもならない。
りょうがフランスに行く前の夜は、とくに激しいエッチをした。
「いつでも俺はりょうのことを思っているよ。りょう以外は愛せない」
今、俺たちの中では、お互いの体の服で隠れる部分にキスマークをつけるのが流行っている。キスをして、甘噛みをして、相手が自分のものだというしるしを残す。軽く噛むこと自体も気持ちいい。
離れているときは、バスルームでそっとキスマークを眺める。りょうもきっと同じ見ているのだろうと確信できる。俺たちは、離れていてもつながっている。
⇒【NEXT】家はいつしか俺にとって、「地獄」と感じるところになっていた。(同居美人〜番外編〜ワケありイケメン 篠村敦〜ワケありの理由〜)
あらすじ
同居美人の番外編として、7人の男性キャラクターのうちひとりを主人公にした短編ストーリーが登場♪
▼キャラ紹介
松垣洸太 33歳 スタイリスト
カリスマスタイリストのアシスタントから独立。
生まれながらのセンスに努力を重ね、引っ張りだこ。
変わった人が周りに多く、疲れ気味な常識人。
そんな彼のラブストーリーが楽しめます!


















