女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
官能小説 同居美人〜番外編〜 ワケありイケメン 篠村敦〜ワケありの理由〜
「俺の家族は、まともじゃない」
俺の家族は、まともじゃない。
うすうす感じていたが、はっきりわかったのは高校受験に失敗したときだった。
俺の父は高学歴・一流企業勤務のいわゆるエリート、母はいわゆる教育ママだった。そんな二人の間に一人っ子として生まれたからには、幼稚園に入る前からその後延々と続く受験に向けての英才教育を施された。俺は物心づくどころか、立って歩けるようになる前から塾のようなところに通わされ、まずは見事幼稚園の受験に合格した。
そのままトントン拍子に進んでいれば、俺は家族の異常性に気付くこともなく、自分自身も歪んで成長しただろうと思う。
高校受験に落ちたのは、中学二年ぐらいときから、母に勉強しか許されていない自分のあり方に疑問を覚えたからだ。確かに進学校ではあったけれど、まわりの友人たちは部活もしていたし、勉強以外の時間もきちんと楽しんでいた。
俺が勉強以外のことをしようとすると、母はいつも血相を変えた。今考えれば、万が一にも自分の理想とするレールから外れたりしてはたまらないと思ったのだろう。皮肉なことに、彼女が俺の行動を締めつけるあまり、それは現実のことになってしまったのだが。
三年にもなるとすっかり勉強をしなくなり、成績もだいぶ落ちた。俺はことあるごとに母と衝突し、母はついに心療内科に通うようになった。
母は父にも相談したが、父は「敦のことはお前の責任だろう」と取り合わなかった。母は悔しそうだったが、昔から絶対に父に対しては強く出られない人だった。
俺は母が父に逆らっているところを見たことがない。猫撫で声で甘えるか、ご機嫌をとるかしかしない人で、自分が中学生にもなると、それはグロテスクにさえ見えた。母に背いたのは、そんな理由もあったかもしれない。
そして、俺は第一志望の高校に落ちた。まぁ、当たり前の結果だった。
母は半狂乱になって、自殺未遂をした。心療内科でもらっていた睡眠薬の過剰摂取だ。しかし、そもそもがそれほど強い薬ではなかったので、命に別状はなく、「自殺をしようとした」という事実だけが残った。
俺は安心し、多少なりとも反省したが、父は母を労わらなかった。それどころかさらに責めた。
「敦はもともと俺に似て頭がいいんだ。なのにこの程度の高校にも合格させられないなんて、母親として失格なんだよ。俺が仕事で頑張っている間、お前は家で一体何をしていたんだ。お前と結婚したのは間違いだった。子供の教育も満足にできないなんてな」
父は俺も責めたが、俺のほうはあくまでも勉強ができないことだけだったのに対し、母に向かっては人格そのものを攻撃した。母は口答えもせず、ただ震えて「ごめんなさい、ごめんなさい」と繰り返していた。
「敦ちゃんが頑張らなかったから、ママはパパに捨てられちゃうかもしれない。敦ちゃんさえ頑張ってくれれば、ママは一生愛してもらえたのに」
俺と二人になると、彼女はうわごとのようにこんなことを恨みがましく呟き続けた。
実際、その頃から父が家にいる時間は減っていった。
俺は再び勉強に力を入れるようになったが、母のためでも、ましてや父のためでもなかった。
冷静になって考えてみれば、ほかに目指すものがあるわけでもないのに、本来得られるはずだった学歴をこんなふうにフイにしたっていいことなんてない。
それでも、家からはなるべく離れるようにした。勉強は学校か、図書館か、友達の家でやった。
父にも母にも会いたくない。家はいつしか俺にとって、「地獄」と感じるところになっていた。
「どうしてこんなことに」
そのうちに母の行動がおかしくなった。
厚化粧と若作りはいつものことだが、友人に紹介されたという占い師のところに毎週通うようになった。
彼女は家庭円満に効果があるのだといって、家じゅうの家具を取り換えようとしたり、数十万円もするブレスレットを買ったりした。
それは、母にとっては努力だったのかもしれない。だがその努力は、父にとっても俺にとっても悲しくなるぐらい見当はずれのものだった。
俺は母に会うといつもセンスのないブレスレットをはめられそうになるので、今までよりも顔を合わせなくなったし、父はさらに母を罵るようになった。それまでも常に母を見下していたが、今ではちょっとしたイライラや怒りをぶつける対象にさえしているようだった。いや、逆に母を見るとイライラしたのかもしれない。
母はそれでも、父に媚び続けた。哀れというよりは、滑稽だった。
俺は両親を冷静に観察し始めた。
自分の学歴や勤務先に絶対の自信を持ち、同じレールの上を行く以外の生き方を認めず、そうでない人間は総じて見下す父。彼は自分が努力して今の地位を得たから、そうでない人間は努力していないクズとして、見下してもいいと思っている。
母は、昔は美人だったらしい。今でも確かに造形自体は整っていると思う。だが、それ以外の長所は、息子の俺がいうのも悲しいが何もない。特技があるわけでも、性格がいいわけでもない。実家が裕福なわけでも、特別な学歴や職歴があるわけでもない。
彼女は今でも自分はまだ二十代のまま美しいと思っている、あるいは思いたくて、もう四十を超えているのに、言動も服装も二十代のようにしている。本当に好きでそれをやっているのならむしろすがすがしいが、彼女はただ周囲に、特に父にちやほやしてほしいだけだ。
女性の美しさは、年齢ごとに種類が変わるものだ。たとえば二十代、三十代、四十代の美しさはそれぞれ違う。少しずつ、内面が滲み出るようになるからだ。母はいつまでも二十代の美しさにこだわり続けた。
二人は知り合いの紹介で結婚したが、そこに愛があったのかどうかはわからない。結婚当初は「一生愛していく」ぐらいのことは、勢いで言ったかもしれないが(俺は母からよく「パパはママを一生愛してくれるって言ったのよ」と聞かされて育ったから、多分言ったのだと思う)。父はおそらく母の美貌と従順さを選んだのだろうし、母は安泰と父のステータスを選んだのだろう。
外見を磨くことにしか力を注いだ経験のない母は、自分一人で生きていける力もなく、結婚してからも何かを学んだり、自分を高めたりすることとは無縁の生活を過ごした。外見を磨くのはもちろん大事だ。しかし、当たり前だが人間の魅力はそれだけではない。もっと総合的なものだ。
母は日々目減りしていく若さに怯え続け、代わりに父の歓心を得られるものとして、俺を彼の理想通りに育てることにした。
結果、父にとって俺は見栄で、母にとっては父の愛情をつなぎとめるための手段になった。
(俺の家は、打算だけで結びついている)
「玉の輿」の無残な結果が、ここにはあった。
俺は勉強を進めるうちに、心理学を学ぼうと決意した。
父も母も、どうしてこんな人間になってしまったのか、「救う」ことはできないのか。それを知りたかった。
「結婚を意識するように」
両親に心理学を学びたいと打ち明けると、最初は反対された。
父いわく、もっと実利に直結するような、例えば政治や経済のことを学べ。母は父がイエスといえばイエスだし、ノーといえばノーだった。白いものを見せられても、父が黒いといえば白というだろう。
だが、そのために目指したい大学名を伝えると、手のひらを返したように賛成してもらえた。子供でも名前を知っていそうな一流大学だったからだ。
大学受験にはストレートで合格した。
受験を通ってから、家族は今まで通りの姿に戻ったように見えた。だが、俺にはもうその正体がすっかりわかってしまった。俺が上位の成績を収めていることを、「自分の息子なのだから当たり前」のこととして受け止め、母の日々のフォローなどには目も向けない父と、そんな父に捨てられないため、俺にさえ奴隷のように仕える母。「いつもの暮らし」がまた始まった。
だが三年のとき、家庭教師のバイトして溜めたお金で俺は半ば強引に家を出て一人暮らしを始めた。父は大きな反応を示さず、ただ成績は絶対に落とすなと言っただけだったが、母は泣き叫んで止めた。自分の目の届かないところに俺が行くのが不安だったのだろう。
最初は内緒でバイトをしていたことに対して怒っていた。だが、次第にどうして自分から離れるのか、この家にどこか悪いところがあるのならなおすからという哀願に変わっていった。
この人はそのあたりをいちいち説明しても理解しないだろう。
実家から電車で三つ目の駅に安いワンルームのアパートを借りたが、両親には鍵を渡さなかった。それでも母は週に何度もやって来ては、家の前に時間をかけて作ったらしい惣菜や、自分がどれだけ家で苦しい思いをしているかを綴った長い手紙などを置いていった。洗い物や洗濯などは全部自分がやると言ってくれたが、受け入れる気はなかった。
大学卒業後は院に進むことにした。心理学の知識を活かした職業に就きたかったからだ。そうなると学士資格だけでは足りない。
そこまで勉強してわかったことは、俺の家族はおそらくもう救えないだろうということだった。病的なまでの自己愛と自己承認欲求がそれぞれ別の形で噴出し、それが彼らの姿を形成して何年も、何十年も経ってしまった。母のほうは特にタチが悪かった。自分のそれらの欲望を、丸っきり他人で満たそうとしている。
もしそれらを変えるのなら、今持っているすべてを捨てるぐらいの覚悟が必要だ。この人たちはそんなことは絶対に納得もしないし、そもそも変わる必要も感じないだろう。
このまま少しずつ、家族との距離を開けていくこと。家族との関係で傷つかないよう自衛するには、それしか方法はなかった。
大学院に入った年、俺は違う大学院に通う女性と共通の友人の紹介で付き合い始めた。何だかんだで今まで女性と付き合ったことはなかったから、そういう方面に関してはかなり遅い「スタート」だったといえる。
彼女は賢くて美しくて、さらに上を目指すために自分を高めていくことを厭わない女性だった。誰に対しても自分の意見を冷静に主張できて、その結果疎まれたり、手を差し伸べられなくなったりしても、痛くもかゆくも感じない。弱さや無垢さを武器にしなくても、ちゃんと男性に大事にされる――。
そう生きていけるのは、経験に基づいた知性と自信という武器を持っているからだった。母とは何もかもが正反対だった。
博士号を取得して大学院を修了すると、俺は大手企業に臨床心理士として就職した。彼女は院に残り、自分の研究を続けた。
俺の就職から数年後、俺たちは結婚を意識するようになっていった。
「自己愛ばかり強くて」
両親とはあまり連絡を取らないようにしていたものの、さすがに結婚のことともなると一人でどんどん進めてしまうのは気が引けた。
彼女の両親には挨拶に行ったのだからと、俺は自分の両親にも彼女をきちんと紹介することにした。
礼儀正しく知性に溢れた彼女であれば、両親のお眼鏡にもかなうはずだ。
彼女にはあらかじめ、両親はちょっと変わった人で、それゆえに距離を置いていると伝えておいた。その距離は、結婚しても縮めるつもりはないとも。
果たして、俺の予測は半分は当たり、半分ははずれた。
父は、彼女を気に入った。しかし母には受け入れられなかった。
母も、父の前では曖昧な笑顔を浮かべて「パパがいいのなら」と一度はうなずいたのだ。だが数日後、三人だけで会いたいといわれ、妙にオシャレで紅茶が一杯二千円するカフェを指定されて行くと、猛反対された。
「パパの手前ではああ言ったけど、正直、ママは敦ちゃんにこの子は合わないんじゃないかなって思ってるの」
彼女を目の前にして、母は言い放った。
母は驚いて黙ってしまった彼女に向き直り、さらに続けた。
「大学院に入るぐらいなんだから、勉強ばかりしてきたんでしょう。家事はどのぐらいできるの? 敦ちゃんにいい加減なものを食べさせたりしたら困るわ。結婚したらもちろん仕事なんてしないわよね。全力で敦ちゃんを支えてもらわないと……」
俺もあっけにとられた。
俺は自分の決断を後悔した。この母の言動は、もっとちゃんと考えれば予測できたはずだった。俺にとっていちばん大事だと母が思うものは優秀な伴侶ではなく、優秀な俺を支える伴侶だった。……自分が父や俺に対してそうであろうとするように。
母は話しているうちに、だんだん興奮してきたようだった。日頃、父に対して抑えていたものが、だんだん噴出してきたようでもあった。
「ママはかわいいお嫁さんがほしいのに、どう見てもかわいいって感じじゃないわよねぇ。女の子のくせに髪の毛が短すぎるし、マニキュアも塗っていないってどうなの? あぁ、一緒にいて恥ずかしくなってきちゃった。ねぇ、料理は何が得意なの? まさかカレーなんて言わないでね。女の子は愛する人をちゃんと支えてあげられるのがいちばん大事なのよ。お勉強ばかりしてきても、そういうことがきっとわからないのよねぇ。もっと素直でかわいい子だったら、ママもいろいろ教えてあげられるんだけど」
要するに彼女が「嫁」として自分の手にはとても負えそうにないことが気に入らないのだ。さんざん虐げられてきた母は、自分が見下せる存在を求めていた。
もともと理論立てて何かを説明するなどしたことのない人である。それからも思いついたことをそのままの順番で一方的にぶつけると、最後はこともあろうに、
「あーあ、ブスっていやねぇ!」
と叫ぶような声で締めた。
店内の人たちが、何があったのかとこちらを窺う。
俺と彼女は真っ赤になって俯いていたが、母だけは自信満々といった様子で胸を張っていた。してやったり、と顔に書いてある。
言っておくが、彼女はブスとは程遠い。だが母にとって「ブス」は最大級の悪口で、ほかに的確な言葉を探せるだけのボキャブラリーがなかったのだ。
数ヶ月後、俺と彼女は別れることになった。
恋人として付き合い続けるのならいいが、結婚して、母と親族になると考えたらつらい。よくよく考えたが、どうしてもあの母を受け入れられそうにない。そう打ち明けられた。引き止められなかった。
その頃から、母は俺に見合い話を持ってくるようになった。相手は若い頃の母に似た、ふわふわした社会経験のないお嬢さんたちだ。これなら「勝てる」と思う人間を選んだのだろう。
(このままでは、人生を壊される)
俺は就職した大企業を辞める決心をした。
両親にとって、母にとって、理想の息子であることを止める。そうすればもう、一方的な「夢」を押し付けられることもなくなるだろう。
その暁には、両親も、その仲もきっと壊れるだろうが……。
そうなったら父は一人でも生きていけるだろうが、母はきっと難しい。自己愛ばかり強くて、何もできない人なのだ。
それでも俺は何だかんだ言って、母を愛していたのだろう。
もし両親が離婚でもすることになったら、距離を測りながら俺が面倒を見ていこうと心のどこかで決めていた。
「女性を幸せにできる場所」
だが、結果として俺の行動は吉と出た。
両親は俺の行動がもとで離婚した。父が母を捨てた形だった。父はその後、ひとまわり以上年下の女性と結婚したと聞いたが、離婚してから一度も会っていないので、よくわからない。
離婚後、母は錯乱といってもいい精神状態になり、しばらくは毎日のように病院に通わなければいけなくなった。
それでも徐々に、心も体も落ち着いていた。数年かかったが、確実に。
俺は最初は慎重に距離を測りつつも、ずっと、「母は悪くない、若いときからたまたま悪い選択を繰り返してしまっただけだから、それをひとつひとつ反省して行動を変えていけば今からだって幸せになれる」と言い続けた。
母の美点を、俺はやっとひとつ見つけることができた。素直だったのだ。
母は俺のいうことを素直に聞いて、今まで自分が何を求めていたのか、それを手に入れるためにはどうすればよかったのかと向き合い始めた。
「ママは結婚がゴールだと思っていたのよ。結婚したからには、あとはパパがママを幸せにしてくれるのが当たり前なんだと思ってた。ママには何もないけど、必死で尽くせばパパは誰にもバカにされないものを何でも与えてくれるんだって……。だからパパに捨てられるのが、怖かった……」
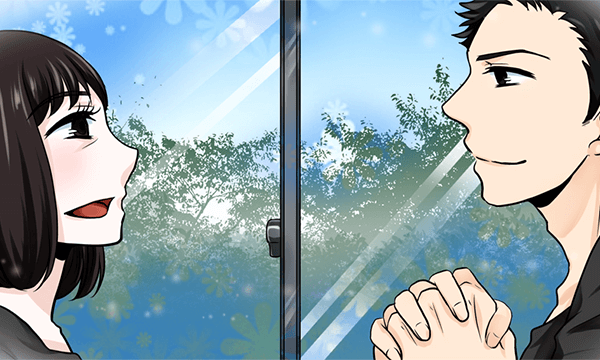
幸い、慰謝料はうなるほどあった。これから少しでも自分を磨き、自分のために人生を楽しみたいという母に、俺はコミュニケーションのコツから教えた。
それからまた数年後、母は見違えるようにイキイキし始めた。生まれて初めてまともに就いた事務の仕事のかたわら、様々な年代の男女が集まるカルチャースクールで俳句を始めたりもした。最近は同年代の女性に離婚について相談され、「経験者」としてアドバイスしたらしい。今は地区主催のコンテストの入賞を狙い、一日3句作るのを目標にしている。ライバルは78歳のおじいさんだそうだ。
彼女はその頃はもう一度一緒に暮らしていた俺に、自分はもう大丈夫だから、いい人を探すために一人暮らしをするように持ちかけてきた。
「いつまでもママが一緒だと、彼女が遠慮しそうだしね」
母なりに、あのとき元彼女にとても失礼なことを言ったのを気にしているようだった。
俺は母の家に歩いていける場所に家を借りて、新しい生活を始めた。
少し落ち着いて改めてまわりを見渡すと、母ほど極端ではないにしても、女性として自立できていない女性たちはまだまだたくさんいることに気がついた。
本当のことをいえば、数年続けていたおでん屋台の仕事を辞めて、また会社勤めでも始めようかと考えていたのだが、思い直した。
(女性を幸せにできる場所を作りたい)
そのときから俺は、ビューティ道場の構想を練り始めた。
⇒【NEXT】「声だけじゃなくて、感じてる顔も体も……全部かわいい」(同居美人〜番外編〜ワケありイケメン 篠村敦〜ラブストーリー〜)
あらすじ
同居美人の番外編として、7人の男性キャラクターのうちひとりを主人公にした短編ストーリーが登場♪
▼キャラ紹介
篠村敦 30歳 コミュニケーション・アドバイザー
おでん屋台のお兄さん。
実は心理学の博士号を持っている。
あることをきっかけにビューティー道場のアイデアを生み出した。
そんな彼のワケありの理由がわかるストーリーが楽しめます!


















