女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
官能小説 同居美人〜番外編〜 ワケありイケメン 福生正光〜ワケありの理由〜
「いちばん美しい言葉」
今でこそイケメン作家などといわれている私は、高校の頃まではデブで垢抜けない少年だった。
学校の勉強だけはできたが、得意なことといえばそのぐらいで、それ以外のことはからっきしだ。とくに運動神経は鈍くて、普段の動きからしてドンくさかった。だから太ってきたのか、それとも太っているからドンくさくなったのかはわからない。
当然女の子にはモテなかった。すると、「あのブドウは酸っぱいんだ」理論で、恋愛なんてくだらないものだと思い始める。デブでブサイクで、恋愛をバカにする男。私は本や漫画を読んだり、アニメを見たりすることだけが楽しかった。それでよかった。
そんな人生が変わったのは、高校1年のときだ。
入学してすぐ、同じクラスの女の子に一目惚れした。
雷が落ちるどころか、落ちた雷でさらに燃え上がったような、圧倒的な恋だった。ごく普通程度の一目惚れであれば「恋愛なんてくだらない」という、自分を守るために時間をかけて作り上げたフィルターに掛かって、その思いを封じ込めようとしただろう。だが、そんなこともできないぐらいの熱量を、その恋は持っていた。
名前は姫野あすか。それは、私が知る中でいちばん美しい言葉になった。
彼女はやがてギターを背負って登校するようになった。話にそれとなく耳を傾けていると、入学早々軽音楽部に入ったらしい。中学の頃からバンドをやっていたようだ。
ある放課後、私は、ついふらふらと彼女の後をつけてしまった。そうしようと思ってやっていたわけではない。気がつくとそうしていた。
いや、怪しまれないような距離はきちんと取り、窓の外なんぞをちらちら気にしながら歩いていたのだから、「ついふらふらと」ではないかもしれない。
彼女は校舎の4階にある技術作業室に入っていった。どうやらそこが軽音楽部の部室がわりになっているらしかった。教室に入っていく背中を見届けて引き返そうと思ったものの、すぐにいいことを思いついた。
来週、私は技術実習の準備担当になっている。先生に頼まれたとか何とか言って中に入り、適当に教室や準備室を探っていれば、彼女と話す機会ができるかもしれない。
自分は気持ち悪いデブなんだから、二言三言話したところできっと嫌われて終わりだろうと思ったが、反面、せっかくのチャンスをふいにするのももったいなく感じた。準備担当にもう一度なれるとしたら、かなり先のことになるだろう。私は昔から妙に貧乏性で、それが発揮されたわけである。
中に入ると、彼女と、もう一人別のクラスの女の子がいた。彼女はギターを、もう一人はベースを抱えていた。小さなアンプも置いてある。
彼女は首を傾げて私に尋ねた。妖精のように可憐な仕草だった。
「福生くんじゃん、どうしたの?」
奇跡は起こるのだと、神の存在を信じた。まさか私の名前を覚えていてくれたなんて。いや、キモいデブだから覚えていたのだろうか。
「あぁ、うん……ちょっと来週の実習、俺、担当だから、その準備で……」
素っ気なく答えながらも、せっかくのチャンスなんだからと意味もなく棚を見て回ったり、つづきになっている準備室に出入りしたりする。
二人はしばらく、そんな私を見守っていた。楽器を弾かないのは聞かれたら恥ずかしいからだろうか。であれば、早く出たほうがいいのだろう。
唐突に姫野さんが話しかけてきた。
「福生くんさぁ、部活まだ入ってないんだよね?」
心臓が大気圏まで届きそうな勢いで口から飛び出しそうになる。
「そ、そうだけど……」
どきどきしながらも、彼女がどうしてそんなことを知っているのかはすぐに思い当った。教室の後ろに、まだ部活に入っていない生徒の名前が貼りだされているのだ。私の学校は部活動にとくに力を入れていて、どこかに入部するのがほとんど強制されていた。とくに興味を惹かれる部もなかったので、しばらく様子を見るつもりでいたのだ。
姫野さんはもう一人に何かひそひそ声で話す。しばらくすると二人は顔を合わせてうなずいた。
「あのさぁ、軽音楽部に入ってよ」
「倒れてしまった」
いったい何が起こったのかしばらくわからなくて、状況を理解するまで30秒はかかった。普段はどんなに動顛したとしても5秒で冷静な思考を取り戻せる私だから、どれぐらい混乱したかわかってもらえるだろう。
話を聞けば、我が校の部活は部員の数が部費の額に大きく影響するらしい。姫野さんは何やら大きくて高額な機材が欲しいらしく、一人でも多く部員を入れたいとのことだった。
なんだ、誰でもよかったのか失望はしなかった。彼女の特別な存在になれるなんて図々しいことは露ほども考えていない。自分に自信はあったが、それが恋愛面で発揮されるわけがないのは重々自覚していた。
「……いいけど」
少し迷ったが、そんなことをしたってどうせ彼女に近づけるわけはないんだし、だったらやってもいいかと決めた。近づけないにしても、見ていられるだけでもきっと幸せになれる。我ながら卑屈なのか前向きなのかよくわからない。
「よかったぁ。じゃあ今、明日、教室で名簿に名前を書いてくれる?」
「わかった」
こうして私は軽音楽部部員になった。
といっても、私は何の楽器も弾けなければ、人前で歌を歌うような度胸もない。しかし部員になってしまった以上は何かしないといけないらしく、話し合った末、姫野さんのバンドの作詞を担当することになった。姫野さんは友人のベース女子と二人でユニットを組んでいた(ドラムはドラムマシーンを使っていた)が、二人とも壊滅的に歌詞づくりが苦手らしい。
「福生くんって、国語の成績学年トップだよね。じゃあ詞とかも書けるんじゃない?」
「……書けなくも、ないと思う」
これが、私が物語をつくることになった初めの一歩だった。
歌詞と物語は、起承転結をつけてストーリーを紡いでいく点では同じだ。私は次第に世界観をつくりあげる楽しさにはまっていき、同時に理数系は得意だが国語は苦手だという彼女に国語を教え始めた。
私たちは頻繁に一緒に行動するようになった。姫野はバンドで何かあるたびに、「福生は頭いいから、何かいい案を出してくれると思って」と私に相談してくるようになった。いつの間にか私たちはお互いを福生、姫野と呼び合っていた。
そうしているうちに私は、あまりにもキラキラ輝く彼女の隣にいることが恥ずかしくなった。彼女は実際、かなりモテる。こんなキモいデブが隣にいていいわけがないのだ。
だが、賽はすでに投げられている。今さら姫野を裏切るわけにはいかない。
であれば、解決策はひとつしかなかった。私が変わることだ。
私は一念発起してダイエットをすることにした。「キモいデブ」が、「キモい」になるだけでも、かなりマシになるのではないだろうか。ひどさとしては二分の一になるのだから。
ほとんど絶食のようなダイエットをして、最初の1ヶ月に10キロ痩せた。次の月は6キロ。だが、そこから先は進まなかった。
倒れてしまったからだ。
ある日の掃除の時間、目まいがしたと思ったら、もう、意識がなくなっていた。
「私たちの恋が始まった」
気がつくと、保健室のベッドの上にいた。
ベッドの横には姫野がいて、こちらを心配そうに覗き込んでいた。
時計を見ると、掃除を始めた時間から1時間ほど経過していた。
「……大丈夫?」
姫野はおそるおそるといった様子で尋ねる。私が倒れたことをクラスメイトに聞いて駆けつけてくれたそうだ。
「……大丈夫だよ」
かすれた声で答えた。
姫野は怒り出した。
「嘘。福生、最近おかしいよ。お弁当だって、やっぱりほとんど食べてないでしょ。何度も注意したのに、食べてるなんて嘘ついてさ。何なの? どうしたの?」
「…………」
脳に栄養が行き渡っていなくて、私はおかしくなっていたのだろう。
言ってしまったのだ。隣にいることが、恥ずかしくなったと。
とたんに、姫野の瞳から涙がぽろぽろ溢れ出した。涙は保健室のレースのカーテンに滲む夕日を反射してきらきらと光った。きれいだった。自分には手の届かない高価すぎる宝石を眺めるように、私はそれをぼーと眺めていた。
「そりゃあ……デブの福生よりかっこいい福生のほうがいいけどさ……でも、デブの福生だって私、好きだよ」
「それ、フォローになってない」
「いいから黙って聞いて。頑張るのに水を差す気はないし、嬉しいけど、体を壊しちゃ何もならないじゃん。そういうのはちょっとずつやればいいんだよ。頭いいくせにバカなんだから」
さすがにバカ呼ばわりは聞き捨てならないから言い返そうとしたが、その言葉は永遠に形になることはなかった。
彼女の唇に、私の唇がふさがれてしまったから。
こうして、私ではなく、私たちの恋が始まった。
私と姫野、いや、あすかは、お互いの家を行き来するようになった。
彼女の家はシングルマザー家庭で、かなり貧しいようだった。はっきりいわれたわけではないが、どうやら母と離婚した父が養育費をきちんと払わないらしい。だから彼女は週に数回バイトをして家計を助けていた。付き合うようになって初めて知った。
「俺もバイトするよ。そうすればあすかはもっとバンドの練習ができるだろ」
だがあすかはそのたびに、「絶対にそんなことしちゃだめ。これは私とお母さんの問題だから」と、怖いような冷たいような目をした。
あすかの家にはうさぎがいた。お母さんが職場で押しつけられるようにしてもらってきたらしい。しかし経緯はどうであれ母子に十分愛されて、母子もまたうさぎを心の安らぎにしているようだった。
あすかはよくうさぎを撫でながら夢を語った。
「うちは貧乏だけど、今の成績を維持すれば奨学金ももらえるし、頑張って大学に行くよ。大学に行ったら、もちろん勉強もちゃんとするけど、バンドにも力を入れてメジャーデビューしたいな」
メジャーデビューがそんなに簡単にできるものなのかわからなかったが、もちろんわざわざそんなことはいわない。あすかがやりたいことがあるのなら、確率なんて関係なく応援するつもりだった。
「私さ、正光の歌詞大好きなんだ。正光って女の子の気持ち、よくわかってるよね」
「そうかな。自分には関係ないひとつのストーリーとして書いてるだけだけど」
「じゃあ天才なんだよ、きっと」
今日のお弁当のおかずのことを話すみたいに天才なんて気軽に口にするあすかの若さが、同い年のくせにまぶしかった。
「これからもずっと、一緒に音楽をつくろうよ」
「あぁ、必要としてくれる限り、俺はあすかの曲に歌詞を書くよ」
私は二人の未来に思いを馳せた。
「見せてもらえなかった」
その未来が訪れることは、なかった。
あのときの自分を思い出すと、今でも未来から乗り込んでいって殴り倒したくなる。
あんなに近くにいながら、どうしてお前は気がつけなかったのか、と。
バンドは本気でやろうと思えばなかなかに金のかかる趣味だった。あすかはかなり無理をして、バイトのシフト時間を増やしていた。
それでいながら大学進学を目指して勉強も手を抜かなかったし、もちろん部活にもちゃんと顔を出した。私と会う時間も捻出してくれた。
人を好きになることと、その人を束縛することがイコールでつながらない性格の私は、「忙しいから」となかなかデートの回数が増えないことも、電話に出ないことも(当時はメールは一般的ではなかった)とくに不満だとも思わなかった。学校で四六時中顔を合わせていたせいもある。
会うたびに彼女は元気に笑っていた。だから、何もおかしいと感じなかったのだ。いや、もはや何を言っても言い訳にしかならないだろう。
あすかは交通事故に遭って死んだ。
コンビニのバイトが終わって家に帰ろうとしていたとき、うっかり赤信号を渡ってしまい、向かってきた大型車にはねられたという。
ヘッドホンで音楽を聴いていた上、もうすぐテストだったからあまり寝ていなかったらしく、ぼーっとして渡ってしまったのだろうと、あすかのお母さんは泣きながら言った。
あすかには、会わせてもらえなかった。
あすかのお母さんと私の両親が話し合った結果、まだ高校生の私にはその死体は見せないほうがいいと判断した。
「なんでだよ! 俺は……俺はあすかの彼氏だぞ! なんでっ……なんで!!」
私は生まれて初めてブチ切れ、生まれて初めて怒鳴り、生まれて初めて両親に殴りかかり、生まれて初めて父親に殴られて、人生で何十度目かの鼻血を出した。
結局、会えたのは骨壺に収められたあすかだった。
――体を壊しちゃ何もならないじゃん。
骨壺のはるか高いところから、あすかの声が降ってきた気がした。
「……その言葉、そのままお前に返すよ」
私はあすかの家に簡易的につくられた仏壇の前で、しばらく骨壺から離れなかった。
しばらく何もする気が起きず、家で寝てばかりいた。
当然学校には行かなかったが、テストだけは顔を出した。それで成績が落ちていなかったせいか、親も先生も何もいわなかった。それとも、気を使ってくれていたのだろうか。
とにかく眠ってばかりいる日々が半年ほど続いた。そのわりに体重が戻らなかったのは、食事の量が極端に減ったからだ。
私はある日、むくりと起き上がった。
パジャマのまま机に向かい、ノートを開く。
自分の意志でそうしようとしたのではなく、体が勝手に動いた。体はなおも動き続け、ノートには次々と言葉が綴られていった。
「生き残る存在」
私は小説を書いた。
生きて、大学に進学したあすかをモデルにした小説を。
その主人公には彼氏もいる。モデルはもちろん私だ。
二人は別々の大学に通うものの、一緒に音楽をつくり続けて、やがて彼女はメジャーデビューを果たす、そんな内容だった。
もう私には、歌詞をつける曲はない。でも物語や世界観をつくる力自体は、私の体の中に残ってくすぶっている。
(そうだ、小説を書こう)
そう思ったのは、無我夢中になって長編小説を一本書き上げた「後」だった。
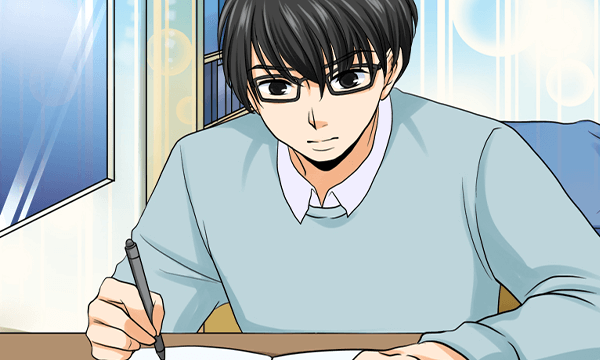
私が書いた小説には、どれもあすかをモデルにした登場人物がいた。今だってそうだ。
ときには主役だし、ときには脇役だ。あすかが生きることのできなかった時間と可能性を、私は小説の中でつくり上げる。
しばらくは誰にも見せずに一人でこっそり書いていたが、初めての執筆から数年後、私はまさに当時のあすかと自分の恋愛を描いた小説を公募に応募して最優秀賞を受賞、作家としてデビューした。
あすかを描いた小説を世に出すのにはためらいもあった。だが、高校の同窓会で久しぶりに会った元・同級生たちからあすかの話がほとんど出なかったことで心が決まった。
このままだと、あすかは忘れられていく。
自分のPCの中でだけ生き残る存在であるよりは、はっきり彼女だと認識されるのではなくても、私以外の誰かの心にも残り続けてほしい。
私は今日も、彼女が生きたかもしれない時間を書く。彼女が見たかもしれない風景を書き、成長した彼女に会った人が彼女について抱いたかもしれない印象を書く。
この経験を通して私は、「頑張る」ことに対してすっかり厳しくなってしまった。
誰かが生半可に「頑張っている」なんて主張していても、ストイックだったあすかと、どうしても比べてしまう。しかし、だからといってもっと頑張ってくれればいいというものでもない。それはそれで、あすかのようになるのではないかと心配になる。
ビューティ道場には、大学の後輩だった小島から「夢を持って前向きに頑張る女性を応援しませんか」と誘われて入った。小島はただ一人、あすかのことを打ち明けた相手だ。
過去にとらわれたまま抜け出せる様子もない私に、たぶん気を使ってくれたのだろう。
だから、道場に入ったのは、大仰な理想に乗ったからというよりも、小島への礼のつもりだった。
あすかのことを忘れたいとは思わない。いつか、語ってもいいと思える人が現われれば御の字だ。「ビューティ道場」で奇妙な日々を送りながら、私はそんなふうに考えている。
あらすじ
同居美人の番外編として、7人の男性キャラクターのうちひとりを主人公にした短編ストーリーが登場♪
▼キャラ紹介
福生正光 37歳 恋愛小説家
昔は暗くてさえない少年だったが、初恋をきっかけに自分を磨きイケメンに。
暗くて皮肉屋、毒舌だが後でこっそり後悔することも。頭の回転がとても速い。
そんな彼のワケありの理由がわかるストーリーが楽しめます!


















