女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
官能小説 同居美人〜番外編〜 ワケありイケメン 篠村敦〜ラブストーリー〜
「会ってもらって、謝罪して」
その日は、同窓会だった。
ビューティ道場では、ときどき卒業生を集めて同窓会のようなことをする。
俺たちにとっては、卒業後の女性たちがどんなふうに活躍しているのかいい機会になるし、女性たちにとっては、ここで自分を磨いたほかの卒業生を知ることがいい刺激になるようだ。同窓会で知り合った女性たちが意気投合して、会社を立ち上げたなんて話もある。
同窓会のペースはだいたい1年に一度ほど。新しく卒業生ができたタイミングで行うようにしている。
千織ちゃん、想子ちゃんが卒業してから数ヶ月後、俺たちはさっそく同窓会を企画した。まだ新しく入居する女の子は決まっていないから、女性たちの参加者は卒業生だけだ。
大樹と悠はそれぞれ千織ちゃん、想子ちゃんと結婚を前提に住むために道場を出る準備を本格的に進めていた。だから今回は、二人の送別会のような形にもなった。昔、ここにいた女性たちは二人の結婚を祝って、改めてこれまでの感謝を示した。
だいぶ前に出ていった女性たちが落ち着いて堂々としているのは当たり前といえば当たり前だったが、千織ちゃん、想子ちゃんも負けていなかった。
とくに想子ちゃんのほうは、悠が彼女のために開発したというルージュがよく似合っていた。派手ではないピンクベージュで、肌の色に溶け込みすぎることなく、口もとを艶やかに引き立てている。必要以上に自己主張はしないけれど、自分の意見はちゃんと持っている。想子ちゃんの性格のようだった。
次第に時間が経って、初対面の女性たちも打ち解けだし、お酒がほどよく回ってくると、俺たちがなぜ今の職業に就いたのかを話すことになった。そういえば、隠しているわけでもないがあえて話したことはなかった気がする。
ジャンケンで順番を決めると悠がいちばん最初に、俺がいちばん最後になった。
「俺は……まぁ、そもそも家族がちょっと変な人たちだったんだ」
俺は家族のことから始め、そこから過去に失った恋愛のことまで話した。心理学を学んだこと自体は家族との話だけで十分説明できるが、臨床心理士として勤めていた会社を辞めて屋台のおでん屋になり、ビューティ道場を立ち上げようと決めたのは、昔の彼女のことに触れないと説明できなかったからだ。
話題はいつしか、俺の過去の恋のことが中心になっていた。
「まぁ、後悔していないといったら嘘になるし……まだ彼女のことが多少は気になっているし。あのとき、もっとちゃんと引きとめられたんじゃないかとも思ってる」
お酒が入っていることも、目の前にいるのが信頼できる人たちばかりだからというのもあり、俺は正直な心情を吐露した。
「篠村さんは別に悪くなかったと思う。でもねぇ……」
「うん、もうちょっと何かできたんじゃないかなぁ」
今年司法試験に合格した卒業生と、去年、地元の下町に和菓子教室を開いた卒業生がうなずきあう。
「篠村さんは、コミュニケーションを得意としているのに行動力のほうが足りないんですよ。後悔するぐらいならもう一度会ってもらって、誠心誠意謝罪して、これまでのことを知ってもらうのが大事なんじゃないですか。私はそういうことを、ビューティ道場で教わったと思っています」
いちばんイタいところを的確に突いてきたのは千織ちゃんだった。
「どうして今さら」
千織ちゃんに発破をかけられたような形で、俺は元彼女――大場理香子に連絡をとった。
会いたいというと彼女は一度は渋ったが、その理由を「改めてきちんと謝りたいから」と伝えると、OKしてくれた。
俺たちは母のあの事件という濁流に否応なく流されるような形で、きちんと腹を割った話し合いをしたわけでもなく別れていた。俺は一方的に彼女に別れを告げられたと思っていたが、彼女からしてみれば、これ以上当時の母のような人間やその周囲と関わり合いになりたくなかったのだろう。悪いというのなら、それをフォローもしなかった俺のほうだ。
「どうして今さら?」
「やっと自分のするべきことに気付けたんだ。もうとっくに手遅れかもしれないけど、理香子にちゃんと謝るべきだったって。何年も経った今さらもう一度つきあってもらえるとは思っていないから、そこは安心してくれ」
最後の一言は、嘘が混じっていた。本当のことをいえば「あわよくば」という気持もあった。だが、叶うとは思っていなかったのだから、結果的に嘘にはならないだろう。まあ、屁理屈ではあるが。
俺たちは彼女が通う大学と、俺の住む町との中間地点ぐらいにあるカフェで数年ぶりに顔を合わせた。理香子はその後も大学院に残っていて研究を続けているそうだった。
「久しぶり」
「……久しぶり」
理香子はだいぶ痩せていた。表情も精彩に欠けている。
「何か」があったのだとすぐにわかったが、それが何か俺のほうから尋ねるようなことはしないでおこうと決めた。心配ではあったが、こういう場合は相手が話すのを待つほうがいい。
俺はまず、理香子と別れた後のことや、母が今ではすっかり「まとも」な人間になったことを伝え、その上で頭を下げた。母が今ではむしろ自慢の存在になっていることや、機会があったら会ってほしいことなども伝えたかったが、今のタイミングでは話しても逆にいやな気分にさせそうだ。これから先、また話す機会があれば……でいい。
理香子は俺と話していて、少しずつリラックスしてきたようだった。別に心理術を駆使したわけではない。彼女は昔から俺といると安心できると言ってくれていた。だから今も、俺を前にして少しずつ心のこわばりが解けてきたのだろう。
彼女はやがて、ついこの間失ったという恋のことをぽつり、ぽつりと口にした。元々彼の前で元彼のことを話す、しかも久しぶりに会った場で……というのは、理香子の性格的には普段であれば避けそうなことではあった。もともと自分の恋愛のことを軽々と話題にしたがらない人なのだ。
だから今は、彼女にとって「普段」ではない心境なのだとわかった。
その相手は、年の離れた大学教授だった。最初は理香子の憧れから始まった。研究はできるがわがままな男で、さんざん振り回された末に別れを告げられたという。
話しぶりからして、まだ未練はあるようだった。
「もし気分転換になるようだったら連絡してよ。いつでも話を聞く」
そう言って、その日は別れた。
「時間が動き出した」
理香子から電話が来たのは、1ヶ月経つか経たないかという頃だった。
「会ってみたいの」
「誰と?」
「……敦のお母さん」
意外すぎる展開ではあったが、その意図はすぐに読めた。単純に母と会いたいというよりは、過去から抜け出すきっかけがほしいのだ。そのための起爆剤にできるような経験を求めている。
心の底がどうであれ、俺にとってはうれしいことだった。さっそく母に話すと、少しうろたえたが覚悟を決めてくれた。
そう、覚悟。理香子と会うことは、過去の自分の愚かさと向き合うことに他ならない。父のことを忘れ、一人でたくましく日々を生き抜く母にとっては、どんなにきれいな言葉で飾ってもやはりつらいことだろう。
だが俺は、母は彼女に会うべきだと思っていた。その経験を経て初めて、母は本当に自立できるだろう。自立というのは、自分の強さだけでなく弱さや傷も受け入れてするのでないと、いつか、揺らぐ。強さだけでは、弱いのだ。
「怖い気もするけれど、ちゃんと謝らないといけないことだったものね。その機会が来たことに感謝するぐらいじゃないとね」
母は気丈に言ってくれた。
「これで彼女が許してくれたら、敦と彼女はまた仲良くなれるの?」
仲良くというのは、恋人に戻るという意味だろう。母は自分がきっかけで俺たちが別れたことをちゃんと理解していたし、罪悪感も抱いていた。
「さあ、それはないと思うけど……でも気にしないでよ。何もしないでいた俺だって悪いんだ」
母の負担になりすぎないよう、俺は微笑んだ。
***
俺たちは3人で母の家で会った。
会ってすぐに、母は以前のことを深く頭を下げて詫びた。
「本当にごめんなさい。あのときは私がばかだったんです。あなたを深く傷つけてしまったこと、心から反省しています」
それは申し訳ないという気持ちが切々と伝わってくると同時に、どこか凛としたものも感じさせる姿だった。ただまっすぐに相手に向かい合って、素直に気持ちを表明し、媚びていない。
美しいと思った。家族の贔屓目ではないはずだ。
理香子は黙って母の手を取って、その体を抱き起した。
「いいんです」
彼女は母の顔を優しく覗きこんだ。
「ここに来るまではいろんなことを考えていました。でもたった今、全部どうでもよくなりました。ご丁寧にありがとうございます」
その後は、母がこのときのために腕を振るった料理をみんなで味わった。母は2日前から下ごしらえをしていた。
ワインが入ると、二人とも少しずつ緊張が解けていった。現代ヨーロッパにおける移民の学習支援問題を研究する理香子の話を、母は興味深そうに聞いていた。以前なら3分で飽きて爪の手入れを始めていただろう。
母は最近ようやく念願の賞を取ったという俳句の話をした。理香子も、今まではまったく縁のなかった世界で面白く感じるのか、身を乗り出していた。
穏やかで暖かな時間が流れていく。
そのぬくもりは、凍りつき、固まっていた過去を溶かしていくようだった。
ああ、時間が止まっていた時間が動き出した――俺はそう思った。
帰り際、母は「よかったらまた来てね」と理香子を送った。
理香子はその言葉に甘えてくれて、それからも家を訪れるようになった。
あの日のカフェでの出来事が、嘘みたいだった。
これは後から聞いた話だが……今まで大学教授との恋で背伸びばかりしていた理香子は、家に来るたび、等身大で語り合える母と、おいしい手作りの料理と、ゆったりと時間が流れる雰囲気に、泣きたいほどの安らぎを感じていたそうだった。
「情熱的に、強引なぐらいに」
やがて俺と理香子は再び付き合うようになった。
千織ちゃんには本当に感謝しなければいけない。もちろん、ヨリが戻ったことは彼女に真っ先に伝えた。
俺はビューティ道場に住み込んでいるので、会うのはほとんど彼女の家だった。奮発してホテルなどに行くこともあるけれど、そうしょっちゅうではない。
普段は自立して強く見える理香子だったが、俺の前ではよく弱音を吐いた。
懐かしかった。
昔からそういう女性だった。甘えられる人の前では、きちんと甘えて自分にストレスをかけない。おそらく以前付き合っていた大学教授には、甘えることができなかったのだろう。
俺のほうも、会うときには情熱的に、強引なぐらいに理香子を求めた。
ベッドだけでなく、リビングやキッチンなどでも急に抱き寄せてキスして、その場で押し倒してしまったり、立ったままコトに及んでしまうことも多い。俺、意外と性欲強かったんだな、なんて今さら思い出した。
その日も、俺はリビングのソファーで理香子に迫っていた。
痛くならないよう注意しつつ壁に押しつけてキスをする。ディープな、まとわりつくようなキス。舌で理香子の舌を追い、絡みつけ、ときどき上唇を甘噛みする。
最初はちょっとしたイタズラのつもりだったのだが、理香子がキスで感じて声を漏らし始めるとたまらなくなってきた。
「理香子の声、かわいい」
「やだ……」
かわいいと言うと、理香子は頬を赤らめて照れる。小さい頃から勉強のできるクールな子として通っていた理香子は、かわいいと言われた経験があまりないらしい。
そこも、好きだった。いろんな「好き」を、少しずつ思い出す。
「声だけじゃなくて、感じてる顔も体も……全部かわいい」
耳元で囁くと、理香子はそれだけで感じてしまうようだった。
俺も決して経験豊富なわけではないが、理香子も相当ウブだった。ただでさえ感じやすいのに加え、言葉で気分が高まるタイプだ。
服を脱がせて、俺も脱ぐ。灯りはつけたままにしておいた。
「肌、きれいだよね。腰のくびれがすげーいやらしいし、乳首も小さいのにピンと勃ってて、なんかいじらしくてかわいい」
「そんなに……いっぱい見ないで」
「いや、もっと見るよ。隅々までね。理香子の恥ずかしがる顔を見ると興奮するんだ。もっと感じさせて、やらしく反応させたい」
俺は理香子の体のさまざまなところに、点々とキスを降らせていった。
もちろん、ただキスするだけじゃない。指でも愛撫しながら、そこがどうなっているのかちゃんと言って聞かせた。
「全部俺のものにしたい」
俺は脚の間にあるきれいな花に近づいた。
「理香子のここ、びしょ濡れになってる。俺のこと欲しがってて、指で開かなくても自然に開いちゃう……中がよく見えちゃうよ」
「そんなに近くで見ちゃ……」
「いやなの? のわりには、さっきよりも濡れてきたけど。あ、中もひくひくしてきた」
花びらにキスをすると、理香子は小さく声をあげて背中を反らせた。
嘘は何ひとつ言っていない。全部、事実だ。それぐらい理香子は感じやすかった。いや、実際には触れていないのだから、感じやすいというのもおかしいかもしれない。これはもう、感性の問題なのだろう。
「見られて感じたんだろ。中の襞がうごめいて……震えてる」
「敦……もう、もう私……っ」
聞こえるか聞こえないかぐらいのごく小さな声。次の瞬間、そこがきゅっと締まったのが外からでもわかった。
「イッた……んだ?」
理香子は恥ずかしそうにこくんとうなずいた。
「俺はまだ触れてもいないのに、淫乱な悪い子だなあ。俺も気持ちよくなりたいよ」
俺が苦笑すると、理香子はごく自然に、大きくなったペニスに口をつけた。
完全にスイッチが入ってしまったことが、とろんとした目つきと上気した頬でわかる。
奥まで咥え込んで、舌をまったりと中で動かした。
「なあ、こっち向いて……口いっぱいに頬張って……やらしくて、かわいい顔」
その言葉でまた興奮したのか、舌の動きが激しくなった。
「んく……はぁっ、気持ち、いいよ……」
「本当? うれしい……」
「でも、まだまだこんなモンじゃ済まさないよ」
俺はペニスを理香子の口から抜き、体勢を変えて理香子を押し倒した。
「挿れるよ」
うなずいたのを確認して、先を押し当てる。力をかけて、中へ、中へと侵入させていたた。
「あああぁんっ!」
理香子が俺にしがみつく。
中はもうトロトロで、なのにきゅんきゅん締めつけてきた。
「理香子の中……気持ちいい。いっぱい感じたから、トロトロになってるね。でももっと……びしょびしょにするから」
「そんな、そんなこと言われたら……私、私っ……あああぁっ」
きゅうっと中が締まる。また、イったのだ。すっかりイキぐせがついている。
俺のほうはまだ硬いままだから、中に入れたままにしておいた。といっても締めつけてくるので、それなりに我慢が必要だったが。
「はぁ、はぁ……」
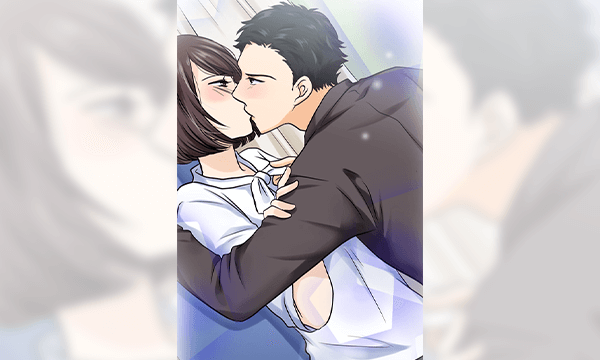
少し落ち着いてくると、ゆっくりと腰を動かし始めた。だんだん高まってきて、理香子以外見えなく、感じられなくなる。理香子の反応も息づかいも、何ひとつ逃したくない。全部俺のものにしたい。
「理香子、愛してる。お前が欲しいんだ。ずっと一緒にいよう。絶対に幸せにする。もう悲しませない……」
いつしか俺も、言葉攻めという意識を忘れて本音をひたすら口にしながら理香子を突いていた。
奥がくぱくぱと吸いついてくる。
理香子のほうも多少落ち着いてきたのだろうか。潤んだ目で俺をじっと見つめて、「うん」とゆっくりうなずいた。
俺たちは、もう一度キスをした。
END
あらすじ
同居美人の番外編として、7人の男性キャラクターのうちひとりを主人公にした短編ストーリーが登場♪
▼キャラ紹介
篠村敦 30歳 コミュニケーション・アドバイザー
おでん屋台のお兄さん。
実は心理学の博士号を持っている。
あることをきっかけにビューティー道場のアイデアを生み出した。
そんな彼のラブストーリーが楽しめます!


















