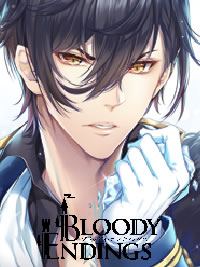女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
官能小説 同居美人〜番外編〜 ワケありイケメン 平野井大樹
「俺でよかったら協力する」
平野井大樹の足取りは、その夜も弾んでいた。
とくに何か嬉しいことがあったわけではない。半年前に今の仕事を始めてから、帰宅のときはいつもこんなふうになる。
体を鍛えることが好きだった大樹が昔から憧れていた、エクササイズ・インストラクターの仕事。大学卒業後、安定と収入を求めて一般企業に就職したものの、やはり夢は捨てきれずに2年で辞めて資格を取り、あるスポーツジムに就職しなおした。
夢だったぐらいだから知識も経験も最初からそれなりにあった。会社に勤めていたときもジム通いは欠かしていなかった。大樹は即戦力として重視され、向上心に溢れる多くの会員たちに紹介してもらうことができた。
彼らは皆、大樹の指導に満足してくれた。言葉でもそう伝えてくれるし、実際に結果も出た。エクササイズは頑張ればそれだけ確実に結果が出て、さらに上に目指そうと意欲が湧く。それが好きな理由だったし、同じ気持ちを会員たちも抱いてくれたようだった。
そんな日々の充実感は、半年経っても衰えることはなかった。今も毎日帰宅するときには、内側から染み出してくるような幸福感を持ち帰る。
その足が止まったのは、彼にとっては懐かしいある女性とばったり会ったからだった。
生駒茜という、大学の同級生だった。経済学部の同じゼミ出身ということもあり、何かとつるんでいた相手だ。恋愛がらみのあれこれはついぞなかったが、さっぱりした性格もあり付き合いやすい相手だった。男女の友情は成り立つのだということは、彼女教えてもらった気がする。卒業後に会ったのは初めてだった。
大樹にとって、茜はいつも明るく笑っていて、冗談などにもすぐ反応する「活きのいい」女性という印象があった。頭はいいがひけらかすことはなく、元気はあるものの、それが押しつけがましくもうざったくもならない人あたりのよさがあった。
その茜が、ぎょっとするぐらい痩せていた。いや、やつれたというべきか。顔が青白く、髪もぱさぱさになっている。
相手も大樹にすぐに気づいて、二人は道端で立ち話をした。
大樹は茜の変貌が気にはなったが、もちろんすぐには聞かない。茜は新卒で就職した商社に今も勤めていて、今年からアジア方面の食品原材料買い付け業務を担当しているという。今は新規取引先への挨拶の帰りだそうだった。
「平野井くんは今は何をしているの?」
大樹は新卒で入った会社は辞めて、ずっと夢だったエクササイズ・インストラクターをしていると答えた。
途端に茜の目がぎらりと、やけに粘っこく光った。大樹は思わずぎょっとした。
「ねぇ、私、もっと痩せたいの。どうしたらいいかな」
「痩せたいって……もう十分すぎるほどだよ。それ以上はかえって危険だと思う」
少し迷ったが、大樹は飾りのない言葉で伝えた。大学時代の関係を考えれば、そうすることが普通だと思えた。
「そう……」
茜はあからさまにがっかりしていた。肩を落とす姿は大学時代とは比べ物にならないほどはかなく、今にも崩れ落ちてしまいそうだった。スーツごしに肩の骨が浮き出ている。
いたましかった。
「あのさ、よかったら今度、そのあたりのことの相談に乗るよ。これ、俺の名刺」
大樹は所属するスポーツジムの住所が書かれた名刺を出した。
「ダイエットだったら素人考えでやるよりも、一度プロに指導を受けたほうがいい。俺でよかったら協力する」
とりあえず今の時点で自分にできることはこれぐらいしかないだろう。数年ぶりの再会で不用意に相手の事情に踏み込むわけにはいかない。
ありがとう、と力のない声で礼を言って、茜は名刺を受け取る。
「だいたい毎日いるよ。直接来てくれてもいいし、事前に電話してくれてもいいし……」
二人は軽く挨拶を交わし、別れた。
「もはや強迫観念だな」
茜は来てくれるだろうか――正直なところ不安だったが、十日ほど後、事前の連絡なしでジムを訪ねてきた。
受付で大樹の紹介だと告げてくれたので、すぐに彼女と話すことができた。
茜は正式な会員登録はせず、まずは3回までのトライアルエクササイズを受けることになった。いわゆるお試し期間だ。会員になれば会費が月額払いになるが、この場合はそれよりも多少お得な金額で、回数ごとの支払いとなる。
「来てくれてありがとう。じゃあさっそくだけど……」
大樹は受付横のごく小さなミーティングルームで茜と向かい合った。
このジムではたとえトライアルエクササイズであっても、事前に丁寧なカウンセリングを行う。エクササイズの目的、なりたい体型、普段の生活など、インストラクターがカウンセラーのように細かく尋ね、その人に合ったプログラムを決める。
「痩せたい……体重をもっと落としたいんだけど……」
茜の要望は、それだけだった。
大樹は気づかれないように小さく溜息をつく。
茜のような「とにかく痩せたい」という願望を持つ女性は決して少なくはない。その大半は確かにダイエットが必要な体型だった。
しかし、中には茜のように十分痩せているのにまだ足りないと思っている女性もいる。
それはある種の病気のようなものだと大樹は思っている。ダイエットを続けるうちに、基準がどんどん極端になり、思い込みが激しくなっていくのだ。その思い込みの中で結ぶ像も、骨ばっているほどの姿になっていく。
病気のようなものだとしたら、根本的に原因を解決しなければまた再発する。大樹はいつも、過剰な痩せたい願望を持つ女性たちには、どうしてそう思うのかという点から質問していた。今回ももちろんそうした。
「会社の同僚にアドバイスしてもらったの」
茜の指先にわずかに力が入ったのを、大樹は見逃さなかった。
何でも同じ課に配属になった同期入社の男性が、茜が仕事で結果を出すたびに冗談めかして、
「生駒はそれでもっとスリムになったら、仕事もできてスタイルもよくて、最強の女子になるのにね」
だとか、
「せっかく仕事ができるんだから、太めなことでマイナス評価をされたら損だ。あと20キロぐらいは痩せないと!」
などと、二人でいるときに言ってくれるのだという。数ヶ月前からだった。
「つかぬことを聞きたいんだけど……」
大樹はこの件で、もっとも重要だと考えたことを確認した。
予想通りだった。彼は茜よりも仕事の成績が下だった。
大樹からすれば、それは明らかに男の嫉妬だった。持ち上げるふりをして、自分はみじめなのだと思わせようとしている。だが、当の茜は気づいていない。
茜は賢い女性だ。「普通の状態」であれば気づいただろう。彼は男女の壁を超えた友情ゆえだと言っているそうだが、女性の体重にずけずけ口を出してくるのもおかしい。
しかし、その「アドバイス」が始まったときは、多忙による生活の不規則が原因で、実際に大学時代に比べて10キロ近く太っており、本人もそれをかなり気にしていた。一時的にだが、軽い不眠で心療内科にも通っていた。精神的に参っているところに付け込まれたのだ。
しかも悪いことには、同僚は彼女がひそかに思いを寄せていた先輩まで巻き込んだ。
「この間、泉先輩とサシで飲んでさ。お互いの好きなタイプとか、話したんだ。やっぱり痩せていてスタイルのいい子が好きなんだってさ。生駒さん、頑張りなよ。目標体重まであと何キロ?」
どうやら同僚は人の心の機微に敏感なようだった。茜は同僚が自分の思いを察していたことに驚き、加えて、太っている自分をさらに嫌悪した。
同僚のいうことには説得力があった。そのときすでに厳しいダイエットを始めていた茜は、少なくともそう感じた。先輩は以前確かに、スタイルの良さで有名な、モデル出身のある芸能人が好きだと言っていたことがある。
(もっと、痩せなきゃ……)
短期間の無茶なダイエットでやがて体力がなくなり、仕事の効率が落ちた。精神力でミスは出さなかったが、成績は今も下降し、ほかの社員にも心身の心配をされている。
それでも痩せたいのだと、茜は言う。
「だって私、まだ44キロもあって……何とかして30キロ代になりたい」
茜の身長は165センチだ。すでに明らかにやりすぎである。
(もはや強迫観念だな)
大樹は頭を抱えたくなった。真面目なだけに、一度思い込むと突き進んでしまうのだ。それが裏目に出ている。
「わかった、何とかできると思うよ」
大樹がうなずくと、茜は少しだけ表情を緩めた。
「『自分』を取り戻そう」
トレーニングで、茜の体重は一時的に増えた。
体重計の数字が人生のすべてだったそれまでの茜にとって、このことは最初こそ恐怖だったが、大樹に根気よく説明されるうちに痩せるというのは数字だけの問題ではないことがわかってきた。
「体重がいくら軽くてもぶよぶよの体の人はいる。脂肪は軽くて、筋肉は重いからね。逆にびっくりするぐらいスリムな人が意外と体重があるケースもある。生駒さんはただ体重を落としたいだけじゃなくて、スリムになりたいんだよね。だったらある程度の筋肉は必要だ。そうなると、今よりも体重が増える場合もある。でもそこは重要じゃない」
それまでも知識としては理解していたことだが、写真などを見せてもらいながら説明されると、徐々に実感として体に染み込んだ。体重が増えてもジム通いをやめなかったのは、ぶよぶよの体の写真や、骸骨に皮膚が張りついているように痩せさらばえた写真を見て「こうはなりたくない」と思ったからだ。
それが自分の目指していた先にあるものだったと改めてわかったとき、目の前がさぁっと明るく開けた気がした。
どうしてこんなことがわからずにいたのだろう。
いや、理由ははっきりしている。
今までは会社と家の往復ばかりで、新しい視点や価値観を発見する機会がなかった。だから同僚から示されたただひとつの価値観だけが絶対のものになり、実行しているうちに大きく膨らんで、胸を侵食していた。繰り返し言われ続けていたというのも大きかった。
要するに、刷り込まれていたのだ。
それがわかると、茜はやっと同僚の「アドバイス」はアドバイスでも何でもなかったことに気づいた。悪意があったか否かは彼女にはわからなかったが、仮に善意だったとしても鵜呑みにするべきではなかった。
大樹はエクササイズの理由を理屈で説明するのが上手だったが、エクササイズ本番になるとそれが信じられなくなるほど、底抜けに明るくなった。
ちょっとしたダンベルトレーニングでさえ、全力で応援してくれる。
「いいね、頑張ってるね。……うん、その調子。あと3回、2回、1回……よくやった!! これでまたきれいになったよ。すごいね!」
声が大きく、何をやってもやたらに褒めてくれる。こういう場所でなければ噴き出してしまいそうだったが、最中はなぜか縋りたいほどありがたく感じられる。勢いに呑まれて、もっとできる、頑張りたいと思えてしまう。
これはもはや才能や特技といっていいだろう。理屈と勢いの両輪が、大樹というインストラクターの魅力だった。
体を適度に動かしていると、暗いことや後ろ向きなことを考えなくなる。太ってもいいとは思わないが、数字は目安程度にして、あくまでも自分の美意識で自分の体をチェックしようと、茜は思えるようになった。食べ過ぎても運動でカロリーを消費できるから、一回一回の食事にも神経質にならずに済んだ。
大樹はエクササイズが終わると、毎回、全身写真を撮ってくれた。
「すぐに変わるものではないけれど、こうやって細かく変化を追っていけば、自分はどんな体型を目指したらいいのか具体的にイメージしやすくなる。結果が目に見えることでやる気にもつながるし」
そこから自分にはこんな体型が似合うのではないかとイメージした体型は、太っているとまではいかないが、今よりも少しふっくらしていた。だが、今までがおかしかったのだと、もう自覚はできている。
先輩は痩せている女性が好きだと言っていたが、それだってどの程度の痩せ具合を指すのかもわからないし、だいたい直接聞いたわけでもない。芸能人の好みとは関係なく、話の流れでそう答えたということだってあり得る。それでも、もしガリガリな子が好きなのだとしたら……そのときはそのとき。今はとにかく、「自分」を取り戻そう。
よく運動し、それなりに食べるようになった茜は、頭がきちんと回るようになり、仕事も挽回した。
「私の気持ちを無視しないで」
清水英吾はいらついていた。
すっかり痩せて生気がなくなり、仕事の成績もすっかり落ちていた同僚の生駒茜が、最近、また元気を取り戻している。
当初、自分の「アドバイス」がこんな素晴らしい結果をもたらすとは思っていなかった。同期入社なことを利用し、友達のふりをして、「仕事が少しできるからって調子に乗るなよ。お前にはこんな短所があるんだ」と、耳当たりのいい言葉で遠回しにわからせてやるだけのつもりだった。
だが、茜は持ち前の真面目でそれを真正面から受け取り、無茶なダイエットに励み始めた。
そうなると、俄然面白くなった。
英吾は茜に、「最近少し太ったんじゃないか」とか、「ダイエットを止めたらもったいないよ。せっかくだからもう少し頑張ったら?」だとか、声を掛け続けた。もちろん、二人だけのときを狙って。そんなことを誰かに聞かれたら、セクハラだとかモラハラだとされかねない。
彼女がひそかに思いを寄せる先輩の泉の名も出し、さらに追い詰めた。
泉が「痩せている子が好きだ」と言っていたのは嘘ではない。一緒にランチに行ったとき、「ぽちゃめの子と痩せている子だったらどっちが好きですか」と尋ねたら、「痩せている子」と答えた。
茜には、これは「友情」だと言っている。頭の悪くない女だったから素直にそう受け取ってくれるか最初は不安だったが、ちょうど精神的に参っていた時期だったせいもあるのか、心配には及ばなかった。
友達だから、多少は失礼なことを言ってもいいのだ。
「お前、最近また太ってきたぞ。もっと痩せないとヤバいって。何キロ太った?」
このところあまり言っていなかったことを、英吾は久しぶりに口にした。
茜は答えた。
「私、体型に対して神経質になりすぎないことにしたの。太らないようにするのは当然として、痩せすぎることにばかりこだわりすぎたらいけないんだなってわかったから」
思わず内心で歯噛みした。お前は無力さに打ちひしがれなければいけない存在なのに、どうして。俺の下で、情けない思いをしていなければいけない存在なのに。
数日後の部署の飲み会で、英吾は茜の隣に座った。
おいしそうに焼き鳥を食べ、ビールを注ぎ込む茜に、英吾は何度も耳打ちした。
「生駒、いいのかよ。お前、最近おかしいぞ」
「いいの、いいの」
茜はにこにこしながら、今度はポテトサラダに手を伸ばした。
「泉先輩だっているのに、そんなにパクパク食べてたら印象が悪く……」
ドン、とテーブルが響く。
茜が音を立ててビールジョッキを置いたのだった。
「あのさぁ」
眉をしかめて、茜は英吾を見据えた。
「どうしてそんなに私の体型のことに口を出すの? アドバイスしてくれるのはありがたいけど、私は自分で納得してこうしているの。私の気持ちを無視しないでくれる?」
「む、無視なんて……っ!」
英吾は焦った。茜が反抗すれば、自分がしていたことが明るみに出るかもしれない。ここは何とかなだめないと。
「俺はただ、生駒のことを思って……」
「じゃあ、私も清水くんのことを思って、アドバイスするけど……」
茜は英吾に向き直った。
自信が全身から立ち上っている。英吾はわずかにたじろいだ。
「清水くんこそ痩せすぎだよね。もっと体を鍛えればいいのに。うぅん、鍛えるべきだよ。かっこいし、仕事もできるんだから損だよ。ねぇ、私のアドバイスも聞いてくれるよね」
「瞬間、頭に血が上った。何もかもを忘れそうになった。
「お、俺のどこが……っ!」
舌がもつれてしまう。痩せすぎていることに対してひそかに抱いていたコンプレックスが、急に意識の上に現れた。
気がつけば、尋常ではない空気に場が静まりかえっていた。皆、二人をじっと注視している。
「はい、ストーップ!」
二人の間に割って入ったのは、先輩の泉だった。
すでに酒がだいぶ入っているようで、顔が赤い。
「はいはい、ケンカしない」
「してませんっ!」
英吾がムキになる。
何があったのか聞かれたので、英吾は先んじて返答した。「生駒に体型のことをとやかくいわれたからですよ。体を鍛えろなんて余計なお世話を……」。
「お前ら、子供か」
泉は噴き出して、「じゃあ、こういう方法で決着をつけるのはどうだ」と、あることを提案した。
「元気になってよかったよ」
数日後、エクササイズが終わってから一杯飲もうと茜と入ったバーでそのときのことを聞いた大樹は、大笑いした。
酒の入った泉が持ちかけたのは、「腕相撲」だった。
「体を鍛えろと言われて不満なら、すでにもう十分鍛えてるってところを見せてみろ」
酔っぱらいのそれではあるが、一応、理屈としては通っている。
結果は、茜の圧勝だった。
「本当は負けるつもりだったのにな〜」
茜はハイボールをぐいと傾けた。
「『これ以上体型のことをごちゃごちゃ言うな』って気持ちは伝わったと思ったから、余計に引っ張りたくなかったんだよ」
英吾はびっくりするぐらい弱かった。レディ・ゴーの掛け声とともに勝ったほどだった。それほど力を入れたつもりもない。
「まさかあんなところでもエクササイズの成果を確認できるとはね」
茜は苦笑しながら腕をぽんぽんと叩く。決して筋肉がつきすぎているとは思わない。やはり英吾が弱すぎたのだ。
飲み会の翌日、茜は泉に呼び出された。昨日は冗談めいて話を片づけたものの、実際に何があったのか知りたいとのことだった。
茜はこれまでのことを、平野井のもとでエクササイズを始めて心身の健康を取り戻せたところまで含め、全部話した。
「あいつにも困ったものだな……」
泉は大きな溜息を吐いた。聞けば英吾は、茜相手以外にもパラハラ、モラハラめいたことをしていると報告があったそうだ。
結局、彼は別の部署へ時期外れの異動となった。今は社内でもとくに厳しいと噂の上司のもとで鍛えられている。
「どうやらあいつは、仕事ができる人間を妬む癖があったようだからな。なおすには、自分が実力をつけるしかないだろう」
と、泉は話してくれたそうだ。
「まぁ、俺は何よりも、生駒さんが元気になってよかったよ」
大樹もハイボールをぐいと飲んだ。いつもより美味い気がした。
しばらくして、大樹の担当会員がもう一人増えた。茜と同じ時間枠内。泉だった。
茜から大樹のことを聞いて、興味を持ってくれたという。
そのときには、二人はもう付き合っていた。茜が英吾の件と話すときに、どうしても泉に好意があることを伝えなくてはいけなくて、それをきっかけに交際が始まったそうだ。
問題の、好みの体型については、
「ぽっちゃりか痩せているかでいったら痩せているほうが好きだけど、でも、その人らしくいきいきしていれば体型なんてそんなに気にしないよ」
とのことだった。
大樹流のエクササイズを、泉も気に入ったようだった。
「いいですね、うん、すごく頑張ってる! 絶対明日は今日よりかっこよくなれます! よーし、この調子でもう1セットいっちゃいましょう。大丈夫、大丈夫です! やれます!」
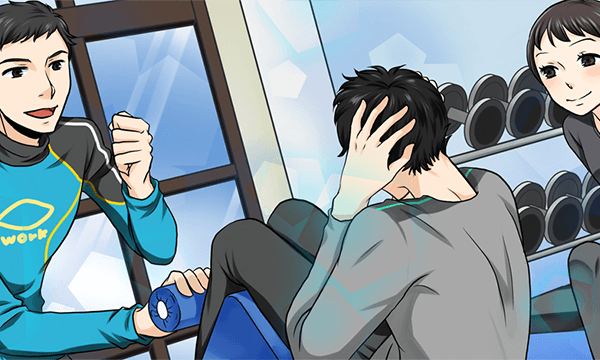
二人のことを大樹は心から祝福し、自分も早く彼女を見つけようと決心した。
大樹は、やがてカリスマと呼ばれるようになった。
その噂を聞いた篠村敦が会いに来て、「ビューティ道場」のことを伝え、入ってくれないか交渉した。
時期もよかったのだと思う。数週間後に茜と泉の結婚式が控えていた。
自分のエクササイズで、ああいう幸せな女性を増やせるのなら満更ではない。
「よろしくお願いします」
大樹は、敦が差し出した手を硬く握り返した。
⇒【NEXT】「あの……いつも、ありがとう」初めて、木田さんの声をドア越しではなく直接聞いた(同居美人〜番外編〜ワケありイケメン 池部宗一郎〜ワケありの理由〜)
あらすじ
同居美人の番外編として、7人の男性キャラクターのうちひとりを主人公にした短編ストーリーが登場♪
▼キャラ紹介
平野井大樹 28歳 エクササイズ・インストラクター
明るい体育会系お兄さん。
見た目に違わず、大抵のことは勢いで何とかしてしまう。
彼のエクササイズは「楽しい」「続けられる」と人気!
そんな彼の知られざるストーリーが楽しめます!