女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
官能小説 パラレル・ラブ ストーリーB 〜洋輔編〜 シーズン9
「素直に甘えたい」●西原ななみ
私と洋輔さんは相談して、お父さんに納得してもらうために3人でお話をすることにした。
私から電話をして、「どうしても聞いてほしいの」とお願いすると、お父さんは迷うこともなく応じてくれた。どうやら私たちがそんなふうにいいだすだろうと予測していたようだ。
静かなところでゆっくり話したかったので、個室のある懐石料理の店を選ぶ。店で直接待ち合わせをすることにした。私たちは15分ほど前に店に到着し、お父さんは時間ぴったりに着いた。
お父さんを見るなり、洋輔さんは「今日はどうもありがとうございます」と深々と頭を下げた。お父さんもそれに合わせて丁寧にお辞儀をした。
二人はともに緊張している様子だったから、私が率先して話した。少し前だったら、自分にこんなことができるようになるなんて考えられなかった。いつも誰かの後ろに隠れて、誰かが何かいいだすのを待っていただけの私が。
食事が少しずつ運ばれてくる。まず話したのは、出会った場所について。もちろん洋輔さんの了承済だ。少し恥ずかしい気もしたけれど、どこでどう知り合ったのかわからないのは不安だろう。
パーティ会場で洋輔さんに助けてもらい、その後、再会して病院に連れていってもらったことも伝えた。さらに洋輔さんに惹かれていく中でいろんな経験を経て変化して、今までよりずっと強くなれたこと、たしかにこれまで寂しいと思うこともあったけれど、それを乗り越えて結婚したいと思うようになったことを話した。
「お付き合いしている今でも会えない日が続く。でも私たちはきちんと話し合って、それを受け入れることができたの。私たち、これから何かあっても、こうやって自分たちなりの愛情の示し方について話し合って、2人で協力して未来をつくっていきたいのよ」
「たとえばこのあいだ2人で決めたことですが……僕が日本にいないときは、毎日連絡すると約束したんです」
洋輔さんが補足してくれる。
私は胸を張って、まっすぐにお父さんを見た。もう昔の、ただ寂しがりなだけの私ではないことを態度で表わすように。
「洋輔さんが留守がちなのはたしかに寂しい。でも一緒にいたいと思う人なの。だから洋輔さんがいないときでも、私なりに上手に待つ方法を考えている。もちろん、それでも一人では大変なときもあるかもしれない。お父さんが心配してくれた出産だって、洋輔さんは仕事を休んでくれるつもりだと言っているけれど、予定通りにはいかないかもしれない。でも、そんなときは素直にいうから、信じてほしい」
言いながら、私はこのあいだの帰り際お母さんが言ってくれた言葉を思い出していた。
「お父さん、お産になったら別にウチに里帰りしたっていいじゃない。お嫁に行ったってウチの娘なんですから」
お嫁に行ってもウチの娘。その言葉がうれしくて、ありがたくて、涙が出そうになった。だから、素直に甘えたいと思った。
「自分が自分で いてもいい」●高木洋輔
「どんなに離れていても、洋輔さんとなら何でも乗り越えていけると思う」
ななみはそこまで言うと、小さく息を吐いた。
よく見ると、肩が少し震えている。じつの父親が相手でも、こんなふうに自分の考えを強く口にしたことはなかったのかもしれない。言えなかったのではなく、言う必要がなかったのだろう。
何ごとも起こらなかった、僕が石を投げいれて波紋を生じさせた。僕という存在そのものが。
その責任は負ってみせる。
だが、意気込みとはうらはらに、その後の会話はあたりさわりのないもので終わってしまった。お義父さん(と呼んでいいのか迷うが)のほうが肝心なことを話すのを避けているのだ。
ななみも僕も内心であせったが、どうしようもできない。
最後の小鉢が出てきたときだった。
「ななみの考えはよくわかったよ。……高木くん、このあと二人で少し飲みにいかないか」
お父さんは僕のほうを向いた。
「じつは僕もお誘いしようと思っていました」
僕はうなずいた。
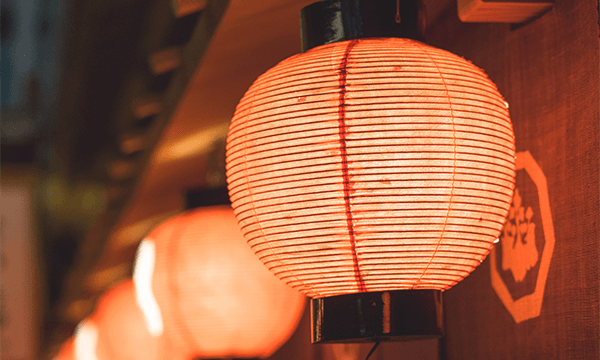
ななみを先に帰らせて、僕たちはお義父さんの行きつけだという居酒屋に行った。
しばらくは2人で日本酒をちびちびと飲んだ。
僕は自分からは喋らないことにした。
どんな考えがあって黙っているのかわからないのだから、一方的に喋るのは得策ではないだろう。
やがて、お義父さんがぽつりと言った。泣きだしそうな笑顔を浮かべている。
「すまないね、いろいろ話したいんだけど、何から話していいのか整理できなくてね……。だから君のことを聞かせてくれるかい? まず、ななみのどこが好きになったのかな?」
とたんに親近感が湧いた。自分の弱さをさらけだしてくれるこの人に。
お義父さんのお猪口が空だったので、銚子から注ぎながら、僕は考える。
ななみのどこが好きか。今となってはあえてどこと答えるのも難しい気がする。でも、最初は……
「僕は昔から、人の気持ちを考えるのがどうも苦手なようで、悪気はなくても言い方がきつくなってしまうときがあるんです。でも、自覚ができないのでなおしようがなくて。ななみさんはそれを注意してくれたんです。それも深刻になりすぎず、笑い飛ばしてくれながら……僕はそれだけで、どれだけ楽になれたかわかりません。自分が自分でいてもいいのだと思えたんです」
お父さんはお酒をくいくい傾けながら話を聞いている。またお猪口に注いだ。
「それが好きになったきっかけです。でも今はもう、どこが好きなのかわからなくなりました。一緒に時間を過ごすうちに、好きなところが増えていって……かけがえのない人になりました」
お義父さんはまた黙ってしまった。黙って、お酒を飲み続ける。止めたほうがいいのだろうか。それともこういうペースなのだろうか。
しばらくして、酔いの回った目がこちらに向けられた。
「高木さんは、ななみを幸せにしてくれるのかな?」
「お義父さんの 涙なのだろう」●高木洋輔
僕はお義父さんを真正面から見つめた。
その瞳は、赤い顔には似合わず鋭い眼光をたたえている。酔ってはいても、心の底からではないのだとわかる。
「確かにななみさんには寂しい思いをさせるかもしれません。でもななみさんを不幸には絶対にさせません」
居酒屋の喧騒が妙に耳につく。でも、耳にはつくのに気にはならなかった。
その喧騒を貫いてお義父さんにまっすぐ届かせるように、言葉を続ける。
「離れている時間はあっても、誰よりも幸せにしたいと思っています。悲しませたりしません。何かあったときは、多少無理をしてでもそばにいたい。だから……」
僕は昔から、真面目にはなっても真剣になったことはあまりない。真面目に取り組んでさえいれば、真剣になんてならなくても大抵のことはできてしまったからだ。真剣になったのは、パイロット養成試験を受けたときぐらいだろう。
その僕が、今ばかりは真剣になっていた。
「だから、ななみさんをお嫁にください」
時間が止まった、ように感じた。
お義父さんが何もいいださなかったからだ。
やがてお義父さんの喉がくっくっ、と鳴った。どうやら笑っているらしい。
「高木くんは……本当に人の気持ちを考えるのが苦手なようだね」
はっとする。僕、また何か言ってはいけないことを言っただろうか。体内に少しだけ入っていた酒が、すっと引いていく。
「少しは俺の気持ちを察してくれよ。そんなにはっきり言われたら……ダメだとはいえなくなるじゃないか」
お義父さんの目の、涙の膜が厚くなる。酔ったからではないのだとすぐにわかった。
そんな姿をごまかすように銚子を持ったので、慌ててお猪口を手にする。
酔っ払いのお義父さんが継ぐ日本酒は少しこぼれて、僕の指を濡らした。いやな気分はしなかった。これはお義父さんの涙なのだろう。
お義父さんのお猪口にはまだお酒が入っている。僕たちはちびり、ちびりと口をつけた。
「自分はやっぱり賛成はできない。でも……反対もできない。だからさ、結婚して、幸せな生活を見せてくれ。賛成しなかった俺は馬鹿だったんだなと思わせてくれ」
お義父さんは僕を見なかった。見ずに、微笑んでいた。
店を出ると、お義父さんの足はすっかりふらついていた。タクシーを止める。お義父さんは断ったけど、ななみの家まで送っていくことにした。
道が空いていたこともあって、十五分もかからずに到着する。先に降りて、出てくるお義父さんを支える。
「期待、しているよ」
ぽつりと言い残して、お義父さんは門の中に消えていった。
「もう 近づかないで」●高見遥
「もう僕の出番はなさそうだね。西原さんをこんなキレイにさせる彼がいるんだから……。正直、くやしいよ。でも本当におめでとう」
西原さんから結婚の報告を受けた僕は、にこやかな笑みを浮かべながらそう返した。
今後のポスターの展開について意見があれば聞いてみたくて、オフィスに呼んだタイミングだった。
彼女は最初はいいにくそうにしていたものの、本当に幸せそうだった。何だかこのタイミングでまともに話をするのもバカバカしくなってしまって、結局、この日は早々に話を打ち切ってしまった。
会社が終わって帰宅すると、ウィスキーをストレートのまま呷(あお)った。
たしかに西原さんはきれいになっていた。あんなにきれいになるのは……セックスでも満たされているからだろう。
男女の関係はセックスがすべてだとは思わないが、見せつけるように輝かれると、やりきれない気持ちになる。
(こんな気持ちになるなら、もっと強引に迫っておけばよかったかな)
チャンスは何度もあった。小さかったものの、手ごたえを感じた瞬間もあった。
あまり鼻にかけないようにしてきたが、僕は小さな頃から何でもできた。女の子の気持ちを掴むことだって、もちろん。そんな自分なら、きっとできたはず……。
そこまで考えたところで、ふぅっと大きく息を吐き、頭を横に振る。
そんなこと、全然なかっただろう? 掴もうとして、掴めなかっただろう? 何でもできるなんて、お前の勘違いなんだよ。
頭の隅から自分自身の声が響く。
昔、じつは自信過剰なのを見抜かれたことがある。当時好きだった女の子に、だ。
僕はその子に、強引に迫っていた。今、胸をよぎったように。それまでほかの女の子にしていたようにすれば、彼女も簡単に落ちると思っていた。
そんな僕に、彼女は「気持ち悪いから、もう近づかないで」と嫌悪感をつきつけた。
それからというもの、僕は必要以上の自信は捨てることにして、謙虚で理性的な人間になった。
……なったはずだったのに。
(いけないな、変なことを考えてしまいそうだ。少し夜風にあたろう)
テーブルにグラスを置く。棚から煙草を取り出して、ベランダに出ようとした。煙草は人前では絶対に吸わない。
広々としたベランダに一歩踏み出したとき、声をあげそうになった。
きらびやかな夜景を背にして、小学生ほどの男の子が立っていたからだ。
「き、み……は?」
どこから入ったんだ? どこの子供だ? 聞きたいが、うまく声が出ない。
「高見遥さんだね」
子供の声音なのに、大人以上に大人びた言い方だった。
「まずは自己紹介をするよ。僕は……カミサマと呼ばれている」
えぇと……僕、そんなに酔っていないはずだよな?
「デート……? をしてほしいんだ」●西原ななみ
「えぇぇぇぇっ!? たっ、高見さんとっ!?」
久しぶりに姿を現わしてくれたカミサマを前にして、私は叫んでしまった。
前回現われようとしたときは、もうひとつの世界での私のライバル――ユリさんという女性の「念」に時空を超えて引きずられてしまい、結局肝心なことを伝えられなかったらしい。
肝心なことというのは……2つに分かれてしまった世界を、どちらかの私が消えることなくひとつにするためには、高見さんの力を借りなければいけないということだ。ちなみにあちらの世界では、そのユリさんの力が必要らしい。
「そう。デート……というのか? それをしてほしいんだ」
カミサマは平然と答える。
彼の言うことは、こうだった。高見さんの内面の「葛藤」は、もうひとつの世界にいるユリさんの「念」とやらに勝るとも劣らない強烈な力を持っている。
その葛藤を一時的にでももっと引き出すことができれば、その力を利用して世界をひとつにできるかもしれない。
「で、でも、高見さんはカミサマのことを信じたんですか?」
「信じた」
カミサマはあっさりうなずいた。パラレルワールドのことや、私がもうひとりいることも話したという。
「突然高層マンションのベランダに現われたり、そこから消えたりしたら、信じないわけにはいかないのだろう。それに……君ともう一度やりなおせる口実を得られるのなら、僕が何者でもよかったんじゃないか」
カミサマは高見さんがひそかに持っていた葛藤について教えてくれた。心の中を覗いてしまったようで悪い気がしたが、世界と私自身の存在がかかっていることなので、聞かないわけにはいかなかった。
「彼からはすぐに連絡が来るだろう。会ったら思いっきり翻弄してやってくれ。君自身の存在のためにもね」
私の反応も待たず、カミサマは消えた。
なんてことだろう。お父さんの反対も乗り越えて、これから結婚へ進んでいくばかりだと思っていたのに。同棲を始めるために、洋輔さんは私の実家のそばに引っ越す予定も立ててくれていたのに。
私はすぐに洋輔さんに相談した。その時点ではロンドンにいたから、メールを送った。
迷いはしたものの、二人で出した結論は、「どんなに迷おうが、最初からこうするしかないとわかっていた」ものだった。
私は高見さんと、デートすることにした。
ただ、その日は自分の休みに合わせてほしい……洋輔さんはそう希望した。
⇒【NEXT】「…戻ってきてくれてありがとう。もう絶対離さない」(パラレル・ラブ スストーリーB 〜洋輔編〜 シーズン10)
あらすじ
洋輔との結婚に難色を示すななみの父。
納得してもらうために3人で話し合いの場を設けてもらい…


















