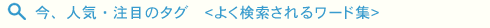女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
官能小説 パラレル・ラブ ストーリーB 〜洋輔編〜 シーズン6
「僕のことを 忘れないで」●西原ななみ

考えた結果、私は少しのあいだ距離を置くことを決めた。
次に会えるのは2週間後……そのことだけでもすでに心が折れそうだった。自分はそんなに弱い人間ではないと思っていたけれど、それは今まで大きな事件が何も起こらずにいたからにすぎないのかもしれない。私は自分でも情けなくなるぐらい、本当は脆かったのだ。
「わかった……ななみさんの意見を尊重する」
別れ際に、洋輔さんは私を強く抱きしめた。その腕の感触から、洋輔さんが私と短いあいだでも別れたくないと思ってくれていることが伝わってくる。その力強さに負けて、撤回してしまいたかった。……でも、ダメ。そんなことをしたら、もっと寂しくなってしまう。
「気持ちが落ち着いたら連絡がほしい。……僕のこと、忘れないで」
「忘れるわけ、ありません」
腕の中から洋輔さんを見上げる。
「違うんだ。記憶から消えるという意味だけじゃなくて……つまり……」
洋輔さんのまなざしには、不安の色が広がっていた。微笑んで塗りつぶそうとしているけれど、あまりにも濃い色だからわかってしまう。
「たとえば、ほかの人への思いのほうが強くなってしまうのも、忘れることだと思うんだ」
「そんなこと、ありません!」
きっぱり言いきる。
だけど、その言葉の底にはほんの少しだけ迷いがあったことに、私自身、気づいていた。
洋輔さんと連絡を取り合わなくなってから、2週間が過ぎた。
その日は本当なら洋輔さんの休日だったけれど、私はひとりで家で過ごした。
寂しい毎日。ときどき、泣いた。だけど、どうしていいのかよくわからなかった。
「僕のところに 来なよ」●西原ななみ
その数日後、私は高見さんに、ポスターを依頼した会社の社長との食事に誘われた。
麻布にあったその店は、質素ながらも品のいいところだった。高見さんと一緒にいるようになってわかったけれど、本当のお金持ちって派手なものに対してあからさまにお金を使ったりしない。そのかわり品や質の良さが内側からにじみ出てくるような一流品に、さりげなく、びっくりするほどの大金を払う。この店もそんな感じだった。ワインも料理もおいしかった。
社長は私のことを気に入ってくれて、社交辞令かもしれないけど、また機会があったらお願いしたいと言ってくれた。高見さんは私のことを「掘り出しもののモデルですよ」といって褒めてくれた。
食事が終わると、いつものように高見さんは私を送ってくれた。だんだんわかってきたのだけれど、高見さんは女性を送っていくことに対してべつに下心を持っているわけではなさそうだ。車を持っている自分がいて、持っていない相手がいて、その相手がそこそこ遠いところに住んでいるのであれば、ついでに送っていこう、そんな気持ちなのだろう。彼のほかの社員への接し方を見ていて、思った。だから私は、言葉に甘えて車に乗った。
夜景のきれいな道を走りながら、高見さんが切りだした。
「また、寂しいことがあった? 前よりももっと寂しそうだよ」
いつものことだけど、高見さんはちょっとした動作や表情の変化だけで、びっくりするぐらい私の心の中を読んでしまう。
そんなこと、ないですと否定しようとして、でも言ってもむだなんだろうなとすぐにあきらめた。だけど肯定するのも違う気がして、黙りこむ。
高見さんは何もいわずに車を走らせた。
赤信号で止まる。車通りのほとんどない、狭い道路だった。
高見さんがまた喋りだした。
「僕だったら西原さんに寂しい思いはさせない。西原さんの寂しい気持ちを埋めてあげたい」
そこまで聞いたとき、耳もとに熱いものがかかった。高見さんの息だ。
「僕のところに来なよ」
どくん! と心臓が高鳴る。顔が一瞬にして燃えたつように赤くなった。
「あ、あの……わっ、わた、わたし……」
動揺してしまい、うまく言葉が出てこない。もっとも、うまく出てきたとしても何を言っていいのかわからなかっただろう。
そんな状態なのに、頭の中では妙に冷静に動く一部分があった。洋輔さんではなく、高見さんを選べば楽になれるのかもしれない。
高見さんは魅力的な男性だし、きっと好きになれる……。
高見さんが私の肩に触れた。そのまま抱き寄せようとする。
「ごっ、ごめんなさい! 今は、まだ、その……うまく考えられなくて……」
私は高見さんを突き放した。ここがどこかわからないけれど、このままここにいてはいけないことだけはわかった。
急いでシートベルトをはずして、車を降りようとする。
高見さんはすかさず私の手首を握った。
「……ごめん、困らせてしまったね」
口先だけではないとわかる瞳の揺らぎに、私は動きを止める。
「こんな時間に女性をひとりで歩かせるわけにはいかない。もう少しだけ、我慢してくれる?」
「我慢なんて、そんな……」
信号が青になり、車が動き出す。
私たちは無言だった。
私は混乱していた。だから降りるときにスマートフォンを車の中に落としたことに気づかなかった。
「彼女は僕が幸せにする」●高見遥
車から降りるときに、西原さんのスマートフォンが落ちているのに気づいた。
このご時世にスマートフォンをなくしたりしたら、不便なことこの上ないだろう。といっても、肝心のコレがないのだから、連絡の取りようもない。
(仕方がない、明日会社に届けるか)
そう遠くもないから、さして面倒ではない。僕は西原さんのスマートフォンを持って車を降りた。
家に着いて時計を確認すると、11時を回る少し前だった。
キッチンの棚からブランデーを出して、アイスを入れたグラスに注ぐ。僕は車を運転するために、今日は酒を飲まなかった。アルコールの強い酒が体に染みこんでいく。
お気に入りのジャズを流して2杯目を飲んでいると、西原さんのスマートフォンに着信があった。少し気になったが、表示を確認したりするのは無粋だろう。裏返しにしたまま置いておくと、しばらくしてコールは止んだが、ほどなくして再び鳴った。
時計をもう一度見る。11時20分。その時間が少し気になった。こんな時間にかけてくるということは、ある程度は親しい関係の相手のはずだ。そんな人たちがもしかしたら何かどうしても伝えなければいけないことがあってかけているのだとしたら……。
とりあえず、西原さんがこのスマートフォンを忘れていったことだけは伝えておいたほうがいいかもしれない。
僕はスマートフォンを手に取った。表示を見て、首をひねる。国際電話の番号だ。海外に住む知り合いがいるのだろうか。 通話ボタンを押す。 電話の向こうからすぐに男の声がした。
「……ななみさん? ごめん、夜遅くに」
「ああ、すいません。彼女は今、ここにはいないんです」
僕が言うと、相手はぎょっとしたようだ。
「え、と……あなたは?」
「彼女の仕事の関係者です。西原さんはこのスマートフォンを今日、僕の車に忘れていってしまったんです。明日には返します」
「そうですか……ご丁寧にありがとうございます」
そのとき、僕はピンときた。彼女の失態への僕のフォローに対して、どうしてこの男が「ありがとう」なんて言うのだろう。それではまるで、西原さんが彼のものみたいじゃないか。
「失礼ですが……あなたは西原さんの恋人ですか?」
唐突な質問だったが、尋ねずにはいられなかった。チャンスだと思ったからだ。
「えっ、その……まぁ、そんなもの……かもしれません」
「かもしれない?」
僕には珍しいことだが、イラっとした。こんなふうに煮え切らない態度をとっているから、西原さんは苦しくなるのではないだろうか。
たぶんこの男は海外に住んでいるのだろう。そのために会う回数が限られてしまい、西原さんは寂しい思いをしているのだろう。だが、問題の本質はそこではない気がした。
「そんな中途半端な答えなら、僕が西原さんにアプローチをしても問題ないわけだ。これ以上西原さんを苦しめるぐらいなら、離れてくれ。彼女は僕が幸せにする」
電話の向こうで、相手は呆然としているようだった。
「違うんだ……僕と彼女は今、その……距離を置いていて……」
「距離を置く? そんな中途半端なことが彼女を苦しめているとわからないのか?それにまた元に戻れたとして、今のままならまた同じことを繰り返すだけだろうな」
相手は黙りこんだ。荒い息遣いだけが聞こえてくる。 言いたいことは言った。僕は電話を切った。 翌日、西原さんにスマートフォンを渡しながら、僕は自分なりに考えた結果、電話に出たことを話した。 そこで話した内容も。
(そう……ですか……)
西原さんは目を見開いて驚き、それから寂しそうに睫毛を伏せた。
「君を誰にも渡したくない」●高木洋輔
ななみさんと距離を置いてから、二度目の休日がやって来た。
前回と同じく、何も予定はない。ここしばらく、休日といえばななみさんと会ってばかりいたから、何をしていいのかよくわからず家にいて本を読んでいた。外出する気には、あまりなれなかった。
本を読んではいたけれど、中身はほとんど頭に入ってこなかった。考えていたことといえば、ななみさんのこと、そしてななみさんの電話に出た、誰とも知れない男との会話のこと……。
中途半端。その言葉が、胸に棘のように刺さり、なおかつ化膿してきたようにじんじんと痛む。 距離を置く前に、僕にはもっとできたことがあったんじゃないだろうか。
ななみさんの笑顔が脳裏に浮かぶ。僕は今まで、人の気持ちがわからないことがコンプレックスだった。だけどななみさんはそれをはっきり指摘しながらも、同時に笑って受け流してくれる。コンプレックスであることに変わりはないし、なおしていかなければいけない部分であることは間違いないけど、ななみさんと一緒にいるだけで、どれだけ楽に慣れたかわからない。
そのななみさんに、僕は本当に全力で向き合っていただろうか。
あの夜、ななみさんに電話をかけたのは、距離を置くと決定したことに対して、やはりそれは違うのではないかもう一度話したかったからだ。お互いの意見も聞かずにひとりで考え込んでいても、前には進めないような気がした。
でも、あの男性と話して、僕はもう一度電話をすることができなくなってしまった。今、何となくの気分で距離を置くのを撤回しても、確かに同じことを繰り返しそうだ。
夕方頃になってやっと、僕は外に出たいという気持ちになった。 車に乗って、ななみさんとかつて手をつないで歩いた公園に行った。
ひとりで黙々と歩きながら、考える。ななみさんとこのまま距離を置いたら、あの男性に取られてしまうことに焦りを覚えながらも、冷静に答えを出そうと努める。
辛いときにそばにいたのは山々だが、どうしたってできないときはある。
で、あるならば……
公園の中の小高い丘を前にして、僕は目を見張った。
丘の上に、こちらがわに背を向けて、ななみさんが立っていた。
ななみさんはまっすぐ、暮れゆく海を眺めていた。
僕は丘を登る。一歩、一歩。ななみさんから少し離れたところで止まった。
「ななみ……さん」
僕の声に、ななみさんが振り返る。その目が丸く見開かれた。
僕はもう、自分の動きを止めることができなかった。前に踏み出して、ななみさんを抱きしめた。
「ごめん……距離を置こうと言ったのは、間違いだった」
ななみさんの耳元で、まずそう呟いた。
「そう伝えようと思って電話したんだ。でも、あの……男性と話して、もう一度、もっとよく考えた。答え自体は変わらなかったけどね」
「答え?」
ななみさんが僕を見上げる。
「そう。僕ややっぱりななみさんのことが好きだ。君と連絡を取れなかったあいだ、心に穴が開いてしまったようだった。どんなに大事な人だったのか、よくわかったんだ。これからもそばにいたい。君を誰にも渡したくない」
「洋輔さん……」
ななみさんが、僕の服の胸の部分をぎゅっと掴んだ。
「ふたりで見つけていきたい」●西原ななみ
「辛い思いをさせてしまうかもしれないけど、僕には君が必要なんだ」
私を抱きしめたまま、洋輔さんは続けた。
「君のことが大好きで大事にしたいと思っている。僕もずっと一緒にいたいと思っているけど……僕の仕事は会えない日が多いから、君をまた不安にさせたり、悲しませてしまうかもしれない。その分、君の素直な気持ちをいつでも隠さないでいてほしい。我慢しないで、君の全部で僕に向かってきてほしいんだ。……会ったときには全部、受け止めるから」
心の底から絞り出すような、だけどはっきりとした自信に満ちた声。
私は小さくうなずいて、洋輔さんの胸を離れた。私も、きちんと伝えたいことがあった。
「私も……いろいろ考えて、答えを出しました」
洋輔さんをまっすぐ見つめる。もう逃げない。
「ここに来たのは、最後に自分の気持ちをちゃんと整理したかったから。そうして今、洋輔さんに会えて……心が決まりました」
何も言葉を差し挟まずに、洋輔さんはじっと私が次にいうことを待っていた。
「ぎくしゃくするからといって距離を置いてじっとしているのは違うと思ったんです。それでは不安が広がっていく一方だから、不安定なまま中途半端に揺らいで、まわりの人まで不幸にしてしまう。私、本当はもう一人男性にアプローチされていて、少しだけ、いいかなって思っていたんです。でも、それは洋輔さんがいない寂しさのせいだった。それがわかったから、もう迷いません」
私は高見さんを好きなわけじゃない。寂しさを埋めてくれるものに惹かれているだけだ。今までもうすうす感じていたけれど、はっきりそう思ったのは、高見さんに告白されたときだった。
高見さんをきっと好きになれる……そう思ったときに、すぐに自分の心に気づいた。私は寂しさを埋めてくれる何かと自分の心を引き換えにしようとしていた。
「寂しいという思いは絶対なくならないだろうし、これからも困らせてしまうこともたくさんあるかもしれない。でも、二人で生きていくなら、それでいいんじゃないかなって思ったんです。一人きりで考えるんじゃなくて、もがきながらでもそのときどきの、私たちなりの答えをふたりで見つけていきたい」
洋輔さんは私をもう一度強く抱いた。
あたりはすっかり暗くなっている。風もずいぶん冷たい。
「僕の車に行こう」
洋輔さんに誘われるままに、私たちは駐車場に向かった。
車の中で、私たちはキスをした。呼吸も絡めとられてしまうような、濃厚なキスだった。

「これからはいいたいことを絶対に飲み込まないで、何でも話して」
唇をときどき離しては、洋輔さんは私を覗きこむ。
「あと、そろそろ敬語も禁止」
少し、照れ臭そうだった。 帰り道、私は考えていることがあると話した。
「何か習い事を始めようと思っていて。寂しさを少しでも減らしたいから、洋輔さんと会えないあいだでも打ち込めるものを探したいの」
⇒【NEXT】直紀さんの手は、それ以上どこにもいかなかった。かわりに私の頬を包みこんだ。(パラレル・ラブ ストーリーA 〜直紀編〜 シーズン7)
あらすじ
会えないことを寂しく感じるななみにたいして、
洋輔は彼女と少し距離を置くことにした。
洋輔と会えない日々に元気がないななみだが…。