女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
官能小説 「妄カラ女子」…spotA〜未由編〜・シーズン7
好きなのかな ●小森未由
朝野悠人のところを飛び出したわたしは、どうしたらいいかわからなくて、とりあえず家に帰ってきた。
朝野悠人は困っているだろうか。でも、今は戻りたくない。仕事を請けてしまった以上、穴を空けるわけにはいかないから、戻らないといけないけれど、今は……いやだ。
少し気持ちを落ち着けて、それから……。
わたしは北村くんのことをもう一度思い出した。北村くんの言ったとおりになるかもしれないところだったね。胸の中に浮かんだ像に、ぼそりとそう話しかける。北村くんに叱ってほしい気がした。
でも、そうなったらなったでよかったんじゃないの? 少し、期待していなかった? どこか別のところから、自分自身の声も聞こえる。
(あぁっ! もう……っ!)
ベッドにうつ伏せになったわたしは、枕に顔をうずめた。
そうだ、いきなり朝野悠人の家に戻るのはハードルが高いから、まずは電話で連絡を取ろう……電話したら、こう言うんだ。突然飛び出してしまってごめんなさい。ネタ出しは大丈夫ですか?
(……違うっ!)
枕にうずめていた顔をぶんぶんと振る。
言いたいのは、聞きたいのは、そんなことじゃない。
――さっき、わたしのことが気になるって言ったの、本当ですか? キスしようとしたのは、本気で好きだから?
(……わたし、やっぱり朝野悠人のことが好きなのかな)
妄想の君じゃなくて。
だって、妄想の君だったら、相手がどんな本心を持っていようとも、わたしが自分の妄想の中だけで何とかしちゃえば済む話だもん。相手の気持ちなんて関係ない。それが妄想ってものだから。
でもわたしは、朝野悠人の本心が気になっている。
そんなことを考えているうちに、夜になってしまった。わたしは相変わらずベッドにうつ伏せになったままで、朝野悠人への連絡もできずにいた。
「未由、入るよ?」
ドアをノックして入ってきたのは、旭くんだった。わたしはベッドから動かない。
「ごはんも食べないで、どうしたの?」
お母さんと、旭くんを連れて帰ってきていたおねえちゃんに何度か晩ごはんの声を掛けられていたものの、わたしは「あとで一人で食べる」と答えていた。
「どこか具合悪いの?」
いつもは生意気な旭くんだが、今日はやけに優しい。
「そういうわけじゃないんだけど……ちょっといろいろ考えごと」
そう答えると、旭くんはこれ以上いるべきではないとわかってくれたようで、部屋を出ていこうとした。朝野悠人に「未由には恋人候補がいる」なんて話しかけたり、ファミレスでおかしな言動をとったりという悪戯をした理由を聞いてみたかったけど、気力がなかった。
ドアノブを回しながら、朝日くんは振り返る。
「未由、あのさ……僕、やりすぎていたんだったら、ごめん」
わたしはうつむいたまま答えなかった。ドアがパタンと音を立てて閉まった。
どのぐらい時間が経っただろうか。
スマホの着信音で、わたしは飛び起きた。名前の表示を見て、息を呑む。
朝野悠人。
慌てたし、迷った。取るべきか、無視するべきか。
でも、ちらりと時計を見て、取ることに決めた。夜11時。もしかしたらネタ出しが終わらなくて困っているのかも。
「も、もしもし……」
「あぁ、小森サン、俺だけど……」
「す、すみません!」
わたしはほとんど反射的に謝ってしまった。
「ネタ出し、困ったんじゃないですか。わたし、その、急に出てきてしまって……」
あぁ、自分の気の小ささが本当にいやになる。
「……俺のほうこそ」
一呼吸置いて、朝野悠人が言った。
「突然あんなこと言ったり、したりして、驚いただろう。ごめん。ネタ出しは何とかなったから、気にしないで」
「な、なら、よかったです……」
そのまま、わたしはしばらく無言でいた。
聞きたいことはある。だけど言葉が出てこない。
「あ、あのー……えー」
わたしがもごもごしていると、朝野悠人が喋りだした。
「……あのさ、一応言っておくけど、今日のことは俺、本気だから。ていうか、冗談とか遊びでああいうことできるほど器用な人間じゃないし」
「あ、はい」
聞きたかった答えをあっさり知ってしまうと、わたしはマヌケにもそうとしか言えなかった。
「明日、時間空いてないかな。今日のことはいくら何でも急すぎたって、反省しているんだ。よかったらちゃんと話したい」
「あ、はい」
わたしたちはいつも歩いていた並木道の入り口あたりで待ち合わせることにした。
確認しておきたい ●小森未由
翌日、待ち合わせた場所に行くと、そこにいたのは「妄想の君」だった。
つまり朝野悠人は、きちんとスーツを着、髪をセットして立っていた。
咲き始めた並木の桜の背に、一枚の絵のようで、まぶしかった。たぶん、彼なりに気を使ってくれたんだと思う。
わたしたちは桜の花を頭上に、並んで歩き始めた。会話は、ほとんどない。朝野悠人は何を考えてそうしていたのかわからないけど、わたしはどんなことを何から喋り始めていいのかまったく見当がつかなかったからだ。
憧れの相手と、美しい景色の中を歩いている。夢のようなシチュエーションなのに、そこに浸る余裕はない。
朝野悠人はわたしに遠慮しているのか、疑似恋人のときにしていたように、手を取ってきたりはしない。
なんだか、ちょっとだけ寂しかった。勝手な考えだって、わかってはいるけれど。
「次のアシスタントの日なんだけど……」
朝野悠人が話しかけてくる。無理して「フツーの声」を出しているのがわかった。
「すみません、確認してもいいですか?」
わたしはとっさに話をさえぎった。
これからアシスタントを続けるのであれば……うぅん、朝野悠人と顔を合わせ続けるのであれば、尋ねておきたいことだった。
「朝野さんがわたしのことが気になるって言ってくれたのは信じます。でもそれはわたし自身じゃなくて、疑似恋人としてのわたしなんじゃないですか。つまり、ネタ元として興味があるってことなんじゃないですか」
朝野悠人は目を大きく見開いてわたしをまじまじと見つめた。
「あんた……」
肩を震わせて笑い出す。
「な、何がおかしいんですか?」
「やっぱりあんた、妙なこと考えるなぁと思って」
「妙な、って……」
わたしはついむっとしてしまう。
「そんなこと、いちいち分けて考えていないよ。そりゃあ確かにあんたに興味を持ったのは発想が面白かったからだし、疑似恋人になってほしい理由にはそれもあった。でも疑似恋人でもネタ元でもあんたはあんただろ。そんなの分けて考えられないよ。俺はただ、あんたが好きだ」
朝野悠人はそこまで言い切ると、はっとしたように顔を赤らめる。言い終わってやっと、自分が何について啖呵を切ったのか気づいたようだ。
その反応に、今度はわたしは噴き出してしまう。
「笑うなって」
朝野悠人が照れたようにわたしの頭にぽんと手を置く。
あぁ、そうか。
それでいいんだ。
朝野悠人か、妄想の君、どちらが好きかなんて考えなくても。朝野悠人は、朝野悠人だ。
「どちらでもある」この人を、まるごと好きになればいいんだ。
わたしは何をひとりで、コトを難しくしていたんだろう。
「小森さんに気になる人がいるって聞いてからは、ずっと疑似恋人でもいいと思ってたんだ。でもその相手っていうのにあったら、なんかさ、たまらなくなって……」
朝野悠人は、言い訳じみた口調で話を続ける。
「え、ちょっと待って」
あのとき、わたしが考えていた「気になる人」はほかでもない朝野悠人だった。でもその後の旭くんの悪戯のせいで、朝野悠人は誤解したんだ。わたしが好きなのは北村くんだて。
わたしが気になっていたのは、朝野さんです……。
そう伝えようとも思ったけれど、恥ずかしくて、緊張して、声が出なかった。
たぶん待っていた ●小森未由
でも、言えなくてよかったと思う。
だってそんなことを言ってしまったら、たぶんわたしたちの関係はもっと進んでしまうから。
今のわたしには、まだそこまでの度胸はない。ずるいかもしれないけど、もう少し今のままの距離でいたい。
わたしはかろうじて、「あのときは質問の意図がわからなくて、適当なことをいいました」と変な言い訳をした。
「なら、ちょっと安心した」
歩きながら、朝野悠人がわたしの手をそっと取った。わたしが振り払わなかったのに安心したのか、握る力が少しだけ強くなる。
「あんたもびっくりしてると思うから、返事は急がない。アシスタントはこれまで通り来てほしいけど、どうしても無理ならしょうがないし、来たとしても返事を聞くまではこれまでと同じようにする」
「……わかりました」
これまでと同じようにといっても、わたしのほうがネタ出しタイムをいつも通りこなせるかわからない。まぁ、ネタ出しに関してはあと1ヶ月は猶予があるけど……。
それにしても、桜が咲いていてよかった。わたしは緊張と照れのあまり、びっくりするぐらい何も喋れなくなってしまったけど、桜の美しさが無言を埋めてくれた。
気がつくと、二つも先の駅まで歩いていた。
日が沈みかけて寒くなっていたのもあったし、わたしたちは電車で帰ることにした。
すでに帰宅ラッシュが始まりかけていて、電車は座れなかった。わたしたちは窓際に並んで立つ。
突然、電車が大きく揺れた。
「あっ」
よろけたわたしの腕を朝野悠人が掴んで、引き寄せてくれる。
そのままもとの位置に戻してくれるのかと思ったけど、それはなかった。
わたしと朝野悠人は密着したまま。
「これも壁ドンの一種なのかな」
朝野悠人が状況に似合わない、おかしなことを口にする。
「全然違います」
わたしは思わず素になってしまった。
「壁ドンはそもそも向き合っていないと……」
そのとき、電車が次の駅に停車した。
人々が続々と乗りこんでくる。そうだ、ここはターミナル駅だから、乗り換え客が多いんだった。
朝野悠人は無言で、人に押されながらも背後からわたしを守るように立ってくれた。片腕を壁に突いて、他の人に触れないようにしてくれる。
電車がゆっくりと動き出した。
「じゃあ、これは逆壁ドン?」
耳元でそっと囁かれる。わたしはといえば、その耳まで真っ赤になっていた。
そういえば以前、こんな妄想をしたことがあった……
モワンモワンモワワ〜ん♪…
* * * * * *
誰を相手にした妄想だったか、もう忘れてしまった。でも、こうやって後ろから壁に押に押しつけられて、腕で逃げ場をふさがれてしまうところまでは同じ。
妄想の中では、首筋や頬に何度も何度もキスをされた。ときにはついばむように。ときにはディープに。ディープなキスは跡が残ってしまいそうで怖いけど、そう考えるとよけいぞくぞくしてしまう。
だんだん、唇だけでは我慢できなくなってくる。もっと感じたい。もっとほしい。「おねがい」と振り向いて、おねだりをしてみたい……。
* * * * * *
次の駅名を告げるアナウンスでわたしは我に返る。朝野悠人はさっきの体勢のまま、わたしには指一本触れずに立っていた。
わたしはたぶん、朝野悠人を待っていた。身動きできないまま、朝野悠人が、わたしに触れてくれるのを。
(勝手だな、わたし)
関係を進めたくないと思ったり、触ってほしいと待っていたり。
こんな自分を笑い飛ばしていいのか、きらいになっていいのかもわからない。
最寄りの駅を降りてしばらく歩き、別れるときに、朝野悠人は尋ねた。
「アシスタント、次も来てもらえる?」
「……行きます」
わたしは勇気を振り絞って答えた。
自分の気持ちを… ●北村修
さんざん考えた末、俺は決心した。
やっぱり小森さんに連絡しよう。
それで、とにかく一度会うんだ。
旭くんのあのファミレスの一件以来、俺は小森さんに連絡を取っていなかった。小森さんからも連絡がなかった。
俺が小森さんの恋人候補――旭くんにそんなことをいわれて、連絡しづらくなった。たぶん小森さんもそうだろう。
あとで旭くんに、なんであんなことを言ったのか尋ねてみたけど、「北村くんがいちばんわかってると思うんだけどな」なんて返答をされてしまった。
……バレてる。
俺は確かに小森さんを好きになりかけている。というか、もうすでになっている。
小森さんに俺のことを好きになってもらえれば、俺の罪悪感が消えるから……なんて身勝手な理由ではもちろんない。ただ会う回数を重ねるうちに、口数は少ないけれど、こちらの話を誠実そうに聞いてくれるところや、ときどき意味深げに黙りこんで遠い目をする仕草に、少しずつ惹かれていった。
「会いたい」とか「食事をしたい」というだけではかえって返事をしづらくなりそうだから、ここはいっそ正直に、「ファミレスで旭くんが言っていたことについて話したい」とメールした。
答えは「イエス」だった。
小森さんも、旭くんの悪戯について謝らないといけないとずっと思っていたとのことだった。
……違うんだ。それは悪戯じゃなくて、旭くんなりの俺への優しさだったんだ。でも俺がヘタレで、それを活かせないだけだった。
俺が小森さんと何とかしてもう一度会おうと決心したのは、旭くんが何だかしょんぼりしていたのを見たせいもある。
「どうしたの?」と尋ねると「何でもないよ」とのことだったが、その後にすぐに「この間はよけいなことをしてごめんね」と無理してつくった笑いを浮かべられて、小森さんとの間に何かあったんだとわかった。
(俺がチャンスを活かせなかったからか……?)
旭くんの心遣いに応えるためにも、俺は小森さんと会いたかった。そしてできれば……自分の気持ちを伝えたかった。
これまでと同じ距離感を保ったままだったら、その距離は少しずつ離れて、フェイドアウトしてしまうような気がしたから。
あの漫画家と、もっと近づいてしまいそうな気がしたから。
会った場所は、この間と同じ系列のファミレスだった。ただ、場所は違うところにした。家の近所ではいやだろう。
ファミレスにしたのは、変にこじゃれたところではないほうが、小森さんも気負わないで済むだろうと考えたせいもある。
「ごめん、迷惑じゃなかったかな、呼び出したの」
「うぅん、迷惑じゃないよ。私も北村くんには旭くんのこと、言っておかないとって思っていたから」
……理由については複雑だが、とりあえず迷惑じゃないのなら、よかった。実際迷惑そうにも見えない。迷惑なのだったら、残念ではあるけれど、今日はすぐ解散にするつもりだった。
運ばれてきた食事に口をつけながら、俺たちは話し始めた。
「旭くんね、昔からよくああいう悪戯をするの。少し大きくなって、手が込んできたみたい。迷惑だったでしょう。ごめんね」
小森さんは深々と頭を下げる。
「いや、いいんだ……っ」
俺は慌てた。ここで小森さんに謝らせるわけにはいかない。旭くんだって悪くない。
焦った俺の声に、顔を上げた小森さんがきょとんとする。
「だって俺は……あれが本当でもいいと思っていて……その、小森さんさえよかったらだけど……」
俺たちの席のまわりに他の客はいない。店のBGMの音量も十分に大きい。それぐらいは、不器用な俺でも事前に確認していた。
「……え?」
小森さんの声が半トーン高くなる。
俺はナイフとフォークを置いて、改めて小森さんを見つめた。
「僕と真剣にお付き合いをしてほしい」
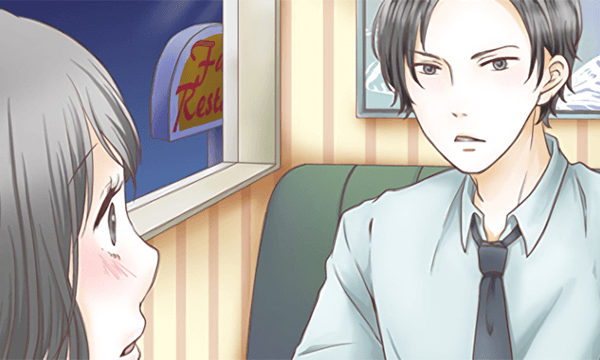
ファミレスで告白なんて、ムードもへったくれもないけれど。
でも、ここでまたいつものように友達のまま何となく別れては……同じ距離感のまま別れてはいけないと思った。
だから、今、伝えた。
モテ期が来た! ●小森未由
富士山の頂上から下界に向かって叫びたかった。
「モテ期が来た!」と。
まさか、こんな妄想女子のわたしにモテ期なんてものが来るなんて。
あの後、北村くんには「すぐには答えられないから、日を改めてちゃんと返事をする」と答えて、別れた。
家に着いてからは、ずっとぼーっとしていた。ただ北村くんの「僕と真剣にお付き合いをしてほしい」という声だけが、頭の中で繰り返し再生されていた。
こんな短期間に二度も、心ここにあらずな状態になるなんて……モテ期とはかくも波乱に満ちたものなのか。
本当だったら、北村くんに気持ちを告げてもらったときにすぐに、断るべきだったんだろう。わたしはもう、朝野悠人に思いを寄せていることを自覚してしまったのだから。
だけどすぐにそうできなかったのは、あのときの北村くんがあまりにも必死そうで、誠実そうで、正直を絵に描いたようで、一生懸命で……それらはわたしが心の底で男性に求めているものに他ならなかったからだった。
男性に、というか北村くんに傷つけられたわたしは、男性にまた傷つけられるのが怖くて、妄想女子になった。年をとるごとに妄想はひどくなっていったけど、そこには現実のいろんな男性を見て、「やっぱり現実の男はダメだ」と少しずつ見切りをつけていったせいもあったと思う。
現実の男性の多くは、嘘もつけば浮気もする。好きといいながらその女性をあんまり大事にしないし、見栄を張るのにも忙しい。男性がみんなそういうわけじゃないけど、そうじゃない男性はすぐに、きれいで性格もいい女性にとられてしまう。わたしみたいな地味な女子の出番はない。
朝野悠人と北村くん、2人はそれぞれ違う意味で、わたしの理想の人だといってよかった。
一度決めていたはずの心が、揺らいでしまう。
モテ期なんてなければ、こんなことにはならなかったのに、モテ期がうらめしい。
わたしは決めた。
(ここは第三者の意見を聞いてみよう)
第三者というのはわたしとっては彩子という意味だ。わたしには彩子しか友達がいない。おねえちゃんは絶対に北村くんを推すだろうし。
さっそく彩子をフェブラリー・キャットに誘う。だが、彩子は理由があってしばらくフェブラリー・キャットには行かないことにしたそうだった。
彩子は確か店員の中村くんのことが好きだったから、何かあったのかなと思ったけど、
<家庭の事情で少し忙しくなりそうで……>
メールにはそう書いてあった。
まぁ、何があったとしても、本人がいわない限りは詮索するべきじゃないだろう。彩子なら、聞いてほしければ自分からけたたましいぐらいに言ってくるはずだし。
とはいえ、フェブラリー・キャットに行きたい気持ちだけは変わらずあったので、わたしは一人で向かった。
夜のフェブラリー・キャットは珍しく暇だった。
一人で砂糖抜きのミルクティーを飲んでいると、暇を持て余しているらしい中村くんが話しかけてきた。
ライブのお誘いかなと思ったけど、違った。
「何かお悩みでもあるんですか?」
……鋭い。
とはいうものの、中村くんもわたしに負けず劣らず、何だかしょんぼりな空気を纏っている。わたしは彩子のメールの内容を思い出した。家庭の事情といっていたけれど、鵜呑みにはしていない。やっぱり中村くんと何かあったのかもしれない。
「まぁ、ちょっとね」
「僕も、まぁ、ちょっとです」
お互い苦笑し合う。その苦笑が、わたしたちを近づけた。
わたしたちは店が終わったら1杯だけ飲みに行こうということになった。
彩子が聞いたらうらやましがるかな。でも彩子、やましいことはしないからね。ていうか、そんな器用なことができたら妄想女子なんてやってないけどね。
飲みに行った小さなバーで、カミングアウト大会が始まった。中村くんとは普段それほど親しくない……どころかちゃんと話すのはこれが初めてだけど、彼にはなぜか何でも打ち明けたくなってしまう、謎の人徳オーラがある。自供しない犯罪者の隣に置いておいたりすれば、いい仕事をしてくれるに違いない。
ジャンケンをして、どちらが先に話すかを決める。負けたわたしが先になった。
わたしはそれぞれ違う「理想通り」の二人に思いを告げられ、自分もまた二人に惹かれ、どちらを選んだらいいかわからずに悩んでいると話した。
どちらを選んだらいいかわからずに悩んでいると話した。
「それは困りましたね……」
中村くんはウォッカトニックを一口飲んで、ふぅ、と息を吐く。
「でも、僕が選ぶとしたら……」
⇒【NEXT】「あの……朝野さん、この間のことの答えなんですが……」(「妄カラ女子」…spotA〜未由編〜・シーズン8)
あらすじ
悠人はアシスタントの仕事中に未由に「気になっている」と気持ちを伝え、キスしようとしてきた。
びっくりした未由はどうしたらいいかわからなくなり、家に帰りベッドの中で思い悩むのだった。


















