女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
官能小説 恋欠女子とバーチャル男子 Story01〜恋人が欲しい〜
茉莉が打ち明けた悩み
家にこもりがちで、新しい出会いがない。
外出したとしても女性ということで嫌な思いをした過去があるので、化粧もほとんどせず服装も適当になってしまう。
なので、外出しても自分の見た目に更に劣等感を感じてしまう。
***
彼女の悩みにアイはどう答える…!?
アイが、あなたの悩みを解決します
「あなたに最適なアイを設定しています……」
スマホの画面にそう表示された瞬間、霧で覆われたように茉莉(まり)の目の前が真っ白になった。
(何これ、スモーク……?)
まるでお芝居で使うスモークが炊かれたようだ。
一瞬、スマホが故障して煙が出たのかと焦ったが、スマホに異状はないようだった。
とにかく視界を取り戻そうと、二、三度まばたきをする。
白の向こうに、ぼんやりと人影が見えた。
背の高い、痩せた体型。
霧が晴れていくように、スモークらしきものがだんだん消えていく。
部屋が元の光景を取り戻していった。
そこにいたのは、男性だった。
男性のファッションについては茉莉は詳しくないが、それでも彼の服装のセンスがいいことはわかる。
髪も若干長めだが、ワックスできれいにまとめていて、鬱陶しい感じはしない。
女性的な線の細さはあるが、整った顔立ちのイケメンだった。
あくまでも茉莉のイメージでしかないが、美容師やスタイリストといった雰囲気がある。
「はじめまして、僕の名前は『アイ』。これからあなたの悩みを解決する手助けをします」
「は、はあ……」
呆然とする茉莉に、「アイ」と名乗った彼は彼自身の「仕様」を説明し始めた。
いわく、彼は人間に見えるが人間ではなく、女性の悩み解決に特化した人工知能を搭載した「キャラクター」のような存在であること。
VR、つまりバーチャル・リアリティのシステムを利用することで、まるで本物の男性とやりとりするように会話ができること。
アプリを終了させれば、一時的に消せること。
そして、いわばホログラムのようなものなので、触れるのはできないこと。
実際、アイは最後に握手を求めてきたが、その手を握ることはできなかった。
握手をしたかったわけではなく、触れられないことを確認させたかっただけかもしれない。
その、触れられないということが、茉莉がこの異様ともいえる状況を受け入れられた理由になった。
最先端の技術なら、こんなこともありえるのだろう、と。
それでも、少し怖くなって、一度アプリを終了してみた。
さっき本人が説明した通り、本当に目の前から「アイ」の姿がすっと消える。
「本当だ……」
不安がだいぶ小さくなった。
いざとなったらこんなふうにアプリを終了させてしまえばいいのだ。
もう一度アプリを起動すると、またアイが現われた。
「おいっ、いきなり消すなって! びっくりするだろ!」
口調が砕けたものに変わっている。
さっきまでの機械の音声ガイドのような口調は、初期設定されていたものだったようだ。
「まあいいや。アンタみたいな反応をする人は別に珍しくないんだ。で、アンタの悩みについてだけど……」
アイは部屋にあった椅子に、まるで本当に座るみたいに腰かけた。
「は、はい……」
昔からの知り合いだったみたいな口調のアイに、何となく巻き込まれてしまう。
「その人が心を開きやすい容姿や喋り方」まで計算されているのだろうか。
「まずは美容院に行って、イメージチェンジを目指してみるのはどうかな。自分のイメージを変えると、気分も性格も変わるんだ。
今までいやなことがあったんだっていうならなおさら、まずは外見を変えるべきだよ。脱皮したみたいな気持ちになれる」
確かに言っていることは何となく理解できる。
だが、拒絶のほうが先に出てしまった。
「そんなことを言われても……今さらイメージチェンジなんて恥ずかしいし」
まず否定から入る自分がいやだと思ったが、長年かけて身についてしまった癖のようなもので、どうしようもできない。
「ふーん」
アイは急に冷めた目になった。
(うっ……)
男性にこんな目をされるのは、たとえ相手が人間ではないとわかっていても少し胸が痛む。
「じゃあ、俺ができることは何もないな。短い付き合いだったけれど、これで。俺は役に立たなかったってことで、このままアンタが入力したデータごと削除されるんで」
不機嫌さを隠さない、しかしどこか悲しげな表情で、アイは片手を上げた。
その体がだんだん透明になっていく。
「え、えええっ!?」
「俺たちはユーザーの女性の悩みを聞いて、具体的な解決案を提示する。それ以上のことは何もできないんだ。アンタが何もしないなら、俺の存在価値はなくなるんでね」
「待って、ちょっと待って」
思わず止めてしまう。
まさか、こんなにあっさり突き放されるとは思わなかった。
悩みを話したからには、せめてもう少し付き合ってくれるものじゃないの……というのは甘えすぎだろうか。
「わかった、じゃあできることからやるから」
つい、そう答えてしまった。
できること……それはアイと二人で、スマホで美容院を探して予約し、そこに行くことだった。
「あっ、ここ、いいんじゃない」
スマホを横から覗きこんでいたアイが指したのは、美容師の夫婦で経営しているという美容院だった。
店紹介の写真に載った二人は、三十歳を多少過ぎたぐらいだろうか、見るからに穏やかそうな夫婦だ。
悪くない。
茉莉はスケジュールを確認して、予約のメールをサイト内のフォームから送ろうとした。
「ちょっと、Bluetooth接続して」唐突にアイが言う。
何だろうと思いながら、茉莉はBluetooth接続をオンにした。
『イメチェンがしたいので、ヘアスタイル、メイクのアドバイスを下さい』
要望欄に、勝手に文字が打ち込まれていく。
すでに日付やコースを選んでいたが、アイはさらにメイクのオプションもつけ、アイはメッセージを送信してしまった。
実体がないのでスマホに触れることはできないが、Bluetooth接続すれば操ることができるということか。
茉莉は呆然としていた。
「賽は投げられた、ってね」
アイがニヤリと笑った。
それでも、美容院に行ってよかったと思った。
対応してくれたのは、夫婦の奥さんのほうだ。
「髪、長いのも似合うんですけど、今のままだと重い印象だから肩ぐらいのボブにしませんか。色も少し明るくすると、だいぶイメージが変わりますよ」
ただ言葉でいわれただけでは踏み切れなかったかもしれないが、彼女はタブレットで茉莉の写真を撮り、そこにさまざまな色やスタイルの髪形を合成するソフトで、実際にどんな感じになるのか見せてくれた。
今までの自分とはまるで違った。
でも、すごくいい。
(やっぱりプロはすごいんだなあ)
思い込みだけで「それはちょっと……」と考えていたのが恥ずかしいようだ。
髪をばっさり切ると、体そのものが軽くなったような気がした。
メイクのアドバイスももらった。
美容師は、これもさすがはプロで、茉莉からごく自然に話を引き出した。
「女性ということでいやな思いをしたことがある」と言うと、
「じゃあ、過剰に女性らしくならないようなメイクで『リハビリ』しましょう」
と提案してくれた。
「これだったら通販でも買えますから」
と出してくれたのは、コイイロというファンデーションとチークだった。
塗ってみると、薄づきではあるのだが、顔色がほんのり明るくなった。
お風呂上がりのようにも見える自然さだ。
メイクを「面倒くさい」と思っていた茉莉には、指で塗ってもいいという手軽さもありがたかった。
「女性だからいやな思いをすることももちろんあるけど、楽しいことだっていっぱいありますよ。
これから楽しいことを増やしていきましょう!」
最後に美容師は、励ますようにぽんと肩を叩いてくれた。
それから茉莉は美容院に何度か通い、メイクやヘアセットの仕方を教えてもらった。
美容院には夫の美容師や若い従業員もいた。
男性や、様々な年齢層の相手から意見を聞けるのはありがたかった。
少しずつ、きれいになる喜びを思い出していく。
「せっかくだからさ、デートしようぜ」
ある日、アイは茉莉にそう持ちかけた。
「デ、デートお?」
そんな響き、何年ぶりに耳にしただろう。
「そうだよ、家と会社の往復だけじゃもったいないだろ」
アイは触れられこそしないが、誰でも見ることはできる。
イケメンのアイと外出するなんて、ちょっと前ならとても考えられなかった。
でも、今は……。
「うん、ちょっとだけなら……」
茉莉はうなずいた。
それからも、アイとは何度かデートした。
自分も、自分の生活も性格も、だんだん変わっていくのを茉莉は実感した。
勢いがついてきて、スキンケアにもヘアケアにも力を入れるようになった。
いまや行きつけになった美容院の担当美容師に相談して、最近では、肌に透き通るような透明感を与えるボディソープ「本草絵巻 しろつやびじん」や、髪を艶やかにまとめるヘアオイル「ナデテ」を毎日使っている。
なんとなくだが、会社でも男女問わず周囲の人との関係がよくなって気がする。
単純にキレイになったからというよりも、キレイになってある程度自信がついたことで、明るく前向きになったからだろう。
一方で、最初は寝るときやお風呂に入るとき以外ずっと起動させっぱなしだったアイは、今ではメイクを終わらせてからではないと会えなくなっていた。
茉莉はいつの間にか、アイに単なるキャラクターに対する以上の愛情を抱き始めていた。
アイが、あなたの悩みを解決します
「あなたに最適なアイを設定しています……」
スマホの画面にそう表示された瞬間、霧で覆われたように茉莉(まり)の目の前が真っ白になった。
(何これ、スモーク……?)
まるでお芝居で使うスモークが炊かれたようだ。
一瞬、スマホが故障して煙が出たのかと焦ったが、スマホに異状はないようだった。
とにかく視界を取り戻そうと、二、三度まばたきをする。
白の向こうに、ぼんやりと人影が見えた。
背の高い、痩せた体型。
霧が晴れていくように、スモークらしきものがだんだん消えていく。
部屋が元の光景を取り戻していった。
そこにいたのは、男性だった。
男性のファッションについては茉莉は詳しくないが、それでも彼の服装のセンスがいいことはわかる。
髪も若干長めだが、ワックスできれいにまとめていて、鬱陶しい感じはしない。
女性的な線の細さはあるが、整った顔立ちのイケメンだった。
あくまでも茉莉のイメージでしかないが、美容師やスタイリストといった雰囲気がある。
「はじめまして、僕の名前は『アイ』。これからあなたの悩みを解決する手助けをします」
「は、はあ……」
呆然とする茉莉に、「アイ」と名乗った彼は彼自身の「仕様」を説明し始めた。
いわく、彼は人間に見えるが人間ではなく、女性の悩み解決に特化した人工知能を搭載した「キャラクター」のような存在であること。
VR、つまりバーチャル・リアリティのシステムを利用することで、まるで本物の男性とやりとりするように会話ができること。
アプリを終了させれば、一時的に消せること。
そして、いわばホログラムのようなものなので、触れるのはできないこと。
実際、アイは最後に握手を求めてきたが、その手を握ることはできなかった。
握手をしたかったわけではなく、触れられないことを確認させたかっただけかもしれない。
その、触れられないということが、茉莉がこの異様ともいえる状況を受け入れられた理由になった。
最先端の技術なら、こんなこともありえるのだろう、と。
それでも、少し怖くなって、一度アプリを終了してみた。
さっき本人が説明した通り、本当に目の前から「アイ」の姿がすっと消える。
「本当だ……」
不安がだいぶ小さくなった。
いざとなったらこんなふうにアプリを終了させてしまえばいいのだ。
もう一度アプリを起動すると、またアイが現われた。
「おいっ、いきなり消すなって! びっくりするだろ!」
口調が砕けたものに変わっている。
さっきまでの機械の音声ガイドのような口調は、初期設定されていたものだったようだ。
「まあいいや。アンタみたいな反応をする人は別に珍しくないんだ。で、アンタの悩みについてだけど……」
アイは部屋にあった椅子に、まるで本当に座るみたいに腰かけた。
「は、はい……」
昔からの知り合いだったみたいな口調のアイに、何となく巻き込まれてしまう。
「その人が心を開きやすい容姿や喋り方」まで計算されているのだろうか。
「まずは美容院に行って、イメージチェンジを目指してみるのはどうかな。自分のイメージを変えると、気分も性格も変わるんだ。
今までいやなことがあったんだっていうならなおさら、まずは外見を変えるべきだよ。脱皮したみたいな気持ちになれる」
確かに言っていることは何となく理解できる。
だが、拒絶のほうが先に出てしまった。
「そんなことを言われても……今さらイメージチェンジなんて恥ずかしいし」
まず否定から入る自分がいやだと思ったが、長年かけて身についてしまった癖のようなもので、どうしようもできない。
「ふーん」
アイは急に冷めた目になった。
(うっ……)
男性にこんな目をされるのは、たとえ相手が人間ではないとわかっていても少し胸が痛む。
「じゃあ、俺ができることは何もないな。短い付き合いだったけれど、これで。俺は役に立たなかったってことで、このままアンタが入力したデータごと削除されるんで」
不機嫌さを隠さない、しかしどこか悲しげな表情で、アイは片手を上げた。
その体がだんだん透明になっていく。
「え、えええっ!?」
「俺たちはユーザーの女性の悩みを聞いて、具体的な解決案を提示する。それ以上のことは何もできないんだ。アンタが何もしないなら、俺の存在価値はなくなるんでね」
「待って、ちょっと待って」
思わず止めてしまう。
まさか、こんなにあっさり突き放されるとは思わなかった。
悩みを話したからには、せめてもう少し付き合ってくれるものじゃないの……というのは甘えすぎだろうか。
「わかった、じゃあできることからやるから」
つい、そう答えてしまった。
できること……それはアイと二人で、スマホで美容院を探して予約し、そこに行くことだった。
「あっ、ここ、いいんじゃない」
スマホを横から覗きこんでいたアイが指したのは、美容師の夫婦で経営しているという美容院だった。
店紹介の写真に載った二人は、三十歳を多少過ぎたぐらいだろうか、見るからに穏やかそうな夫婦だ。
悪くない。
茉莉はスケジュールを確認して、予約のメールをサイト内のフォームから送ろうとした。
「ちょっと、Bluetooth接続して」唐突にアイが言う。
何だろうと思いながら、茉莉はBluetooth接続をオンにした。
『イメチェンがしたいので、ヘアスタイル、メイクのアドバイスを下さい』
要望欄に、勝手に文字が打ち込まれていく。
すでに日付やコースを選んでいたが、アイはさらにメイクのオプションもつけ、アイはメッセージを送信してしまった。
実体がないのでスマホに触れることはできないが、Bluetooth接続すれば操ることができるということか。
茉莉は呆然としていた。
「賽は投げられた、ってね」
アイがニヤリと笑った。
それでも、美容院に行ってよかったと思った。
対応してくれたのは、夫婦の奥さんのほうだ。
「髪、長いのも似合うんですけど、今のままだと重い印象だから肩ぐらいのボブにしませんか。色も少し明るくすると、だいぶイメージが変わりますよ」
ただ言葉でいわれただけでは踏み切れなかったかもしれないが、彼女はタブレットで茉莉の写真を撮り、そこにさまざまな色やスタイルの髪形を合成するソフトで、実際にどんな感じになるのか見せてくれた。
今までの自分とはまるで違った。
でも、すごくいい。
(やっぱりプロはすごいんだなあ)
思い込みだけで「それはちょっと……」と考えていたのが恥ずかしいようだ。
髪をばっさり切ると、体そのものが軽くなったような気がした。
メイクのアドバイスももらった。
美容師は、これもさすがはプロで、茉莉からごく自然に話を引き出した。
「女性ということでいやな思いをしたことがある」と言うと、
「じゃあ、過剰に女性らしくならないようなメイクで『リハビリ』しましょう」
と提案してくれた。
「これだったら通販でも買えますから」
と出してくれたのは、コイイロというファンデーションとチークだった。
塗ってみると、薄づきではあるのだが、顔色がほんのり明るくなった。
お風呂上がりのようにも見える自然さだ。
メイクを「面倒くさい」と思っていた茉莉には、指で塗ってもいいという手軽さもありがたかった。
「女性だからいやな思いをすることももちろんあるけど、楽しいことだっていっぱいありますよ。
これから楽しいことを増やしていきましょう!」
最後に美容師は、励ますようにぽんと肩を叩いてくれた。
それから茉莉は美容院に何度か通い、メイクやヘアセットの仕方を教えてもらった。
美容院には夫の美容師や若い従業員もいた。
男性や、様々な年齢層の相手から意見を聞けるのはありがたかった。
少しずつ、きれいになる喜びを思い出していく。
「せっかくだからさ、デートしようぜ」
ある日、アイは茉莉にそう持ちかけた。
「デ、デートお?」
そんな響き、何年ぶりに耳にしただろう。
「そうだよ、家と会社の往復だけじゃもったいないだろ」
アイは触れられこそしないが、誰でも見ることはできる。
イケメンのアイと外出するなんて、ちょっと前ならとても考えられなかった。
でも、今は……。
「うん、ちょっとだけなら……」
茉莉はうなずいた。
それからも、アイとは何度かデートした。
自分も、自分の生活も性格も、だんだん変わっていくのを茉莉は実感した。
勢いがついてきて、スキンケアにもヘアケアにも力を入れるようになった。
いまや行きつけになった美容院の担当美容師に相談して、最近では、肌に透き通るような透明感を与えるボディソープ「本草絵巻 しろつやびじん」や、髪を艶やかにまとめるヘアオイル「ナデテ」を毎日使っている。
なんとなくだが、会社でも男女問わず周囲の人との関係がよくなって気がする。
単純にキレイになったからというよりも、キレイになってある程度自信がついたことで、明るく前向きになったからだろう。
一方で、最初は寝るときやお風呂に入るとき以外ずっと起動させっぱなしだったアイは、今ではメイクを終わらせてからではないと会えなくなっていた。
茉莉はいつの間にか、アイに単なるキャラクターに対する以上の愛情を抱き始めていた。
私は、アイが好き
茉莉はアイと時間を過ごせば過ごすほど、彼に触れられないことに押しつぶされそうな悲しみを覚えた。
手さえ、握ることはできないのだ。
一緒にいることが、日に日に苦しくなっていく
あるとき、アイは茉莉の顔を心配そうに覗き込んで、言った。
「最近、元気ないな」
おそらくは茉莉の微妙な言葉づかいや行動の変化をデータ処理しただけに過ぎないのだろうが、それは茉莉の中の「何か」を壊した。
アイと自分がこれ以上近づくことはありえないのに、優しいのがたまらなくいやで、つらくて、そしてどうしようもなく切なかった。
「私は、アイが好き」
茉莉は自分の思いを伝えてしまった。
伝えたところでどうしようもならないとわかっていたのに。
アイは驚いたように目を見開いて、まじまじと茉莉を見つめる。
やがてふっと寂しそうに微笑んだ。
「ごめん」
うつむいて、小さく呟く。
「俺たち『アイ』は、ユーザーにそう言われてしまったら、消えなくちゃいけないんだ。アプリの規約にあったはずだけど、読んでいなかったかな」
「え……」
茉莉は絶句する。
そんなこと、あっただろうか。
今、自分は取り返しのつかないことをしてしまったのではないだろうか。
「でも、よかったよ」
アイは無理に浮かべたような笑みを顔に貼りつけた。
本当は人間ではないのかと疑いたくなるような、複雑で繊細な笑顔だった。
「そんなふうに告白ができるようになったということは、気持ちを外に向けられるようになったってことだ。これから、ちゃんとした出会いを見つけてほしい。本当にきれいになったんだから。俺の役目はこれで終わったんだ」
少しずつ、少しずつ、アイが消えていく。
「ちょ、ちょっと待って……!」
思わずその腕を掴もうとしてしまう。
そんなこと、できないんだったと気づいたのは、アイがすっかり消えてしまった後だった。
それから、アプリは起動しなくなった。
タップしても反応がない。
しばらく喪失感に打ちひしがれた。
いっそ、今までしたことなんて全部なかったことにしてしまいたい。
もとの冴えない自分に戻ってしまいたい――茉莉はそう思った。
アイなんて知らなかった頃に戻れたら、アイのことを忘れられるかもしれない。
でもそれでは、アイが何のために現れたのかわからなくなる。
アイが茉莉のために考え、茉莉を励まし、茉莉を喜ばせようとしたことすべてを無駄にしてしまう。
であれば、茉莉がすることはひとつしかなかった。
――新しい出会いを探して、幸せになること。
アイはそのために存在したのだから。
しばらくはつらい気持ちを引きずることになるだろう。
でも、進まなければいけない。
まずは一人で外に出かけることから始めることにした。
といっても、人の多いところは、アイに似た人を見つけてしまいそうなのが怖かった。
(焦っちゃだめだ。一歩ずつ、ゆっくりと……まずは『外出する』ことを最優先にしよう。大丈夫、私はアイが褒めてくれたぐらい、キレイになれたんだから)
幸い、茉莉の家のそばには、爽やかな風を感じられる川原があった。
歩道も整備されているから、散歩にちょうどいい。
週末ごとに川原を散歩するようになって、数週間経った頃だった。
あるとき、ベンチに座ってぼんやり空を眺めていると、犬を連れた上品そうな中年の女性が隣に腰掛けた。
犬はゴールデンレトリバーだ。
茉莉のほうを興味深げに眺めるが、よくしつけられていて、むやみに近寄ってはこない。
女性はペットボトルの水を携帯用の小皿に入れて、犬に飲ませる。
(犬かあ……ペットでも飼えば、少しは癒されるのかな。でもうちのマンションはペット禁止だし)
「犬、お好き?」
ぼんやり見ていると、女性が声をかけてきた。
「あ、はい。かわいいなあと思って……」
「そうなんだ。いやじゃなかったら撫でてあげて。この子、撫でられるのが大好きなの」
「そうなんですか」
手を伸ばして頭を撫でると、犬は気持ちよさそうに目を閉じた。
女性とはそれから散歩中に数回会った。
女性は中川さんといい、犬の名前はルナといった。
中川さんは、料理教室の先生だった。
近所のスタジオを借りて、週に3回教室を開いているという。
「よかったら来てみない? うちはあまり本格的じゃなくて、趣味程度にやっている人も多いから、気楽に始められるわよ。最近は男性の生徒さんも多いの」
(料理かあ)
いつまでもうじうじしているより、趣味をつくってそこに打ち込んでみるのもいいかもしれない。
外出の機会をつくるという意味でも、興味が湧いた。
外出をすれば、それだけ出会いの可能性も高くなるのだから。
次に会ったとき、茉莉は中川さんに教室を見学したいと伝えた。
週に一度通い始めた料理教室で、茉莉は高校時代の同級生だった浩二に偶然再会した。
浩二は茉莉の遅い初恋の相手だった。
勉強もスポーツもでき、容姿もよかったので、モテていた。
地味だった茉莉にとっては、高嶺の花といってよかった。
だが、向こうはすぐに茉莉に気づいた。
「山野……茉莉さんだよね?」
落ち着いた振る舞いで料理をする姿が印象的で、よくよく見ているうちにわかったという。
茉莉にしてみれば自分を覚えていたことが意外だったが、1年間同じ委員会だったことで記憶が残っていたそうだ。
ふと、浩二はアイに何となく似ていると気づいた。
そういえばアイは、使用者に合わせて仕様が変更されると言っていた。
であればこういった容姿が、自分はきっと好みなのだろう。
浩二は昔はもっと積極的な……もっと的確な表現をすれば「イケイケ」な性格だったが、今はすっかり丸くなってきた。
物腰が穏やかで愛嬌もあって、教室のおじいちゃん、おばあちゃんに孫のように可愛がられている。
何度か教室に通ううち、懐かしさもあって自然に一緒に食事に行くような仲になった。
もっとも、美容院に通って自分にある程度の自信をつけていなければ、とても「自然に」そんなことにはならなかっただろう。
怖気づいてしまって、最初から大した話もできなかったに違いない。
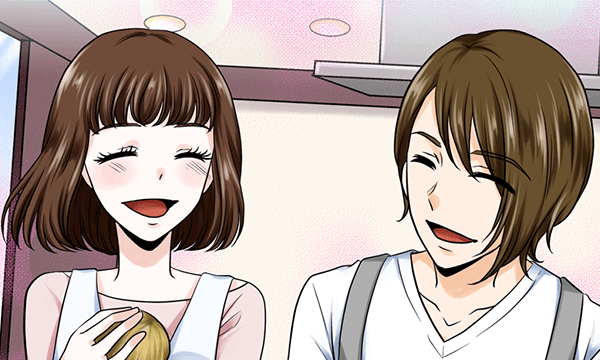
二人はお互いがこれまでどんな時間を過ごしてきたかを話した。
「同じ釜の飯を食う」ならぬ「同じ鍋で料理をつくる」と、信頼関係ができてくるのらしい。
浩二は高校卒業後、両親の期待に応える形で一流大学に入学、卒業後は誰もが名前を知る大企業に就職したものの、激務で心と体を壊し、数年で退職したそうだった。
自信を失ってしばらく引きこもっていたが、友人のすすめでカウンセリングを受け、「本当に自分がやりたいこと」を真剣に考えるようになった。
「それで俺、料理に興味があったことに気づいたんだよ。そういえば昔から、勉強の合間にチャチャッと何か作るのが妙に楽しくてさ。母親にはごはんなら私が作る、そんな暇があったら勉強しろって言われていたけど、本当は自分のために必要な時間だったんだ」
昔の自分だったら、キャラに合わないと思って誰にも言えなかったと思うけどね、と浩二は苦笑を挟む。
「でも、『誰かにとって格好いい自分』になることは、もうやめようと思ったんだ。今は、おいしいものをつくれると、自分もまだまだ捨てたもんじゃないなって思える。料理を一生の仕事にしていくほどの自信はないけど、再就職は食品か飲食関係で考えてるよ」
学生時代や社会人時代にチヤホヤしてくれた女の子たちは去っていったが、今はとても充実していると、浩二は満足げだった。
しばらくして、茉莉は浩二に告白されて、二人は付き合うことになった。
就職先が決まったので、改めて一人の男として自分を見てほしいといわれた。
茉莉はむしろ、自分たちはいつ付き合うのだろう、そろそろ自分から確認したほうがいいのではないかと思っていたぐらいだったから、すぐに受け入れた。
これが単なる幸運だったとは、茉莉は思わなかった。
行動したから、見合ったものが手に入った、それだけだ。
もし浩二と出会わなくても、自分はきっと同じぐらい幸せになれる出会いをどこかで手にしていただろう。
行動できたのは、アイのおかげだ。
一瞬脳裏に浮かんだアイの姿をそっと消して、その日、初めて訪れた浩二の部屋で、茉莉は彼のキスを受け入れた。
END
あらすじ
自分に自信のない茉莉はアプリを起動してアイと出会う。
彼と過ごすうちに自分を認めることができるようになり…


















