女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
官能小説 恋欠女子とバーチャル男子 Story13〜恋準備中〜
彼女が打ち明けた悩み
今まで家族のことでがんばってきた私
これからは自分のために恋がしたいと思っているのですが、どうすれば出会いがあるかが分からなくなっています。
自分磨きをすれば、何かがかわってくるのかな。
***
彼女の悩みにアイはどう答える…!?
一歩前に進めたんだから
(私の人生って、何なんだろう)
「アイ」というアプリを使ってみようという気になったのは、ふとそんな疑問が湧いたからだった。
今まで家族のためにがんばってきたことは、後悔していない。
でも、人生を振り返ったとき、自分ではない「誰か」のことだけで塗り潰されていたことにふと、気づいた。
「自分のために、恋がしてみたい。でも、恋の相手ってどうやれば出会えるんだろう」
今まで恋愛にまったくもって疎かった私には、まずそこがわからない。
(自分磨きをすれば、何かが変わってくるのかな)
とにかく、なんでもいいから意見を聞ければという思いだった。
生身の人間では恥ずかしかっただろうけど、相手がAIなら気兼ねを感じなくても済むだろうと思った。
最初は単なる対話型アプリなんだろうと思っていたから、アイが目の前に現れたときにはびっくりした。
びっくりしたなんてもんじゃない。悲鳴をあげそうになったぐらいだ。
ちょうど実家を出て一人暮らしを始めたばかりだったし、いきなり男の人が現れたらそりゃあ驚く。
彼は口の前に人差し指を立てて「しぃっ」と言ってみせた。
その姿に何とはなしに愛嬌を感じて、少し落ち着いた。
行きつけの美容院にいそうなタイプだった。線が細くて、どちらかといえば中性的。
それでもなよっとしているわけではなく、きちんと研がれた刃物のような印象もある。
鋭さと優しさが共存しているような、不思議な雰囲気の人だった。……人、ではないのだけれど。
細身のスーツに、肩あたりまで伸ばしてきちんと整えた髪が印象的だった。
アイは自分が何者なのか簡潔に説明してくれた。
その上で、悩みがあるなら聞きますけど、無理はしないでいいですよと言ってくれる。
ここまでリアルでも、不思議に照れや恥ずかしさはあまりなく、私は素直に悩みを打ち明けた。
AIが相手なら気兼ねなく話せるのではという目的自体は、達成できたことになる。
「自分磨きというのは、とてもいいと思います。きれいだと思える自分になること、つまり自信を持つことは、恋愛には不可欠ですからね。正しい自信は、いちばんのメイクでありアクセサリーです」
でも、とアイは付け足した。
「自分磨きと出会いは、正確にいえば別ものです。自分磨きは出会いのチャンスを増やしますし、そのチャンスを活かすことにもつながりますが、自分磨きさえすれば出会いが訪れるというものでもありません。出会いがほしいなら、そのための行動をしないと」
そのためには、まずは行動範囲を広げることが必要だという。今いる場所で出会いがないのなら、出会いのある場所に移動しようという理屈だ。
「それって、たとえば婚活とか、出会いのパーティとか?」
「それは少し敷居が高いでしょう?」アイはにっこり微笑む。
「うう、正直その通りで……」
「出会い」は確かに求めているけれど、いきなりそこにだけフォーカスした場は気が引けてしまう。
うまく立ち振る舞える自信がない。場数の問題なのかもしれないけれど……。
「趣味のサークルや教室に通ってみるのはどうですか。
大事なのは行動範囲を広げることだから、気負わすに済むことから始めましょう。
行動をすれば人間関係が広がって、そこから思わぬ出会いがもたらされることもありますから」
読書が好きな私は、ネットで会員を募集していた読書サークルに参加することにした。
***
読書サークルは、好きな本を皆に薦めるためにプレゼンしたり、指定の本を読んで感想を言い合ったりするところだった。
学生の頃からファンだった書評家の女性が立ち上げたサークルで、ずっと興味があってネットで活動を追っていたものの、引っ込み思案な性格な私は参加までは考えられずにいた。
今回、アイがアドバイスをくれたことは、いいきっかけになった。
活動は隔週一度、都内の公民館の一室を借りて行われる。
(う、うう……男の人も結構いるんだな)
男女比は大体半々ぐらいだったけれど、学生時代以来男性とまともに喋っていなかった私には、「結構」に見えてしまう。
会員は男女ともに、若い人で二十代前半ぐらい。上は六十代まで幅がある。
その書評家のファンだったり、すでに参加していた人に誘われて会員になったりした人が多いそうだ。
全員で三十人ぐらいだが、皆、毎回必ず参加するわけではなく、会に来るのはいつも二十人程度だという。
「今日は初めて参加される方がいるので、自己紹介をしていただきましょう。お願いします」
とリーダーである書評家の女性に促され、私は皆の前に立った。
(緊張する……!)
べつにぶっつけ本番ではなく、事前にきちんと知らせてもらっていて、何を言うべきかも一応は考えていた。
なのに、たくさんの人の前――とくに男性の前に立つと、頭がすっかり熱くなってしまった。
「よ、よ、よろしくお願いしますっ!」
自分の名前を告げ、好きな作家を挙げるだけなのに、私の声はみっともないことに終始上ずっていた。
挨拶を終わらせて席に戻ると、視線を感じた。
そちらを見ると、私と同じぐらいの二十代後半から三十代の始めぐらいに見える男性が微笑んでいた。
顔立ち自体がすごく格好いいというわけではないけれど、清潔感があり、年齢以上にいろんなことを経験して思慮を身につけたような、落ち着いた瞳が印象的な人だった。
(お疲れ様)
勝手な願望かもしれないけれど、そう言われているように思えた。
***
何度か参加するうちに、女性の会員たちと帰りにお茶をするようになった。
同じ趣味を持っていて相性も合うのか話しやすいと感じる人が多く、少しずつプライベートを教え合ううちに、恋愛の話にも発展した。
私は「今までは家族のことでがんばってきたけれど、これからは自分のために恋がしたい」ことを打ち明けた。
「サークルで気になる人はいないの?」
と、とくに深い意味はないのだろうが、聞かれた。
「気になる人……ですか」
真っ先に思いついたのは、初日に笑いかけてきてくれたあの人だった。
だが、
「いえ、とくには……」
相性が合うと感じた女性相手にも、照れてしまって言えなかった。
正直にいえば、力になってもらえるかもしれないのに……
私は自分で思っている以上に、恋愛に対して腰が引けているようだった。
「一歩前に進めたんだから、自信を持って」
そんな自分がいやだと相談すると、アイはそう励ましてくれた。
「せっかくの趣味のサークルなんだから、まずは趣味を思いきり楽しんでみたらいいですよ。そのうちに自分で自分を好きになれるところが見つかると思います。恋愛に対して積極的にはなれなかったとしても、ほかに好きになれるところがあればいいじゃないですか。そこから徐々に自信をつけていけばいいんです」自分を好きになれるところ。
私には、いったい何があるんだろう。どんな可能性を持っているのだろう。
なんだか少し元気が出てきた。
そろそろ気づいてほしいな
恋愛に対して引っ込み思案なことで、落ちこむことはない。
ほかのところで自分を好きになれればいい。
アイのアドバイスで、私は自分のことをもっとよく知ってみようと考えるようになった。
どんなことに喜びを感じるのか。何を楽しいと思うのか。
どんなことに対して、どんなふうに満足できるのか。
そうしてわかったのは、「私は人を観察するのが好き」だということだ。
相手に対して具体的なアクションは起こせなくても、どんな人なのか、今何を考えているのかなどを想像するのが楽しい。
そういえば、小さい頃から人間観察は好きだった。
大人になって、家族のことなどもあって、すっかり忘れていた。
ずっと気になっているあの男性――青島義明さんという名前だった――に、話しかけることは相変わらずできなかったけれど、行動や身に着けているものなどから、「どんな女性が好きなんだろう」と想像することが増えた。
一人で考えていたところで正解かどうかなんてわからないけれど、想像を広げるだけなら、べつに誰かに迷惑をかけるわけでもない。
「自分を好きになれるきっかけは、楽しいと思えることの中に往々にしてあるものですよ」
というアイの意見もあり、今は自由に没頭してみようと決めた。
メイク用品や服を買い足していくとき、美容院で髪形を決めるときなど、その想像を元にすることが増えた。
「こんな雰囲気が、青島さんは好きそうかな」
「この色、青島さんはどう思うだろう」
もちろん勝手な想像に過ぎないから、これで青島さんが振り向いてくれるなんて都合のいい結果にはそうそうならないだろう。
でも、いったんそれまでの自分の好みから離れて、新しい目線で自分磨きをしてみることは、過去から脱皮できるようでもあり、気分転換にもなった。
要するに、自分を変えるいいきっかけになったのだ。
そうしているうちに、サークルでもそれ以外でも、「雰囲気が変わって、きれいになったよね」と言ってもらえることが増えた。
素直にお礼を言うと、さらにアドバイスをもらえたりもした。
青島さんとは進展はなかったけれど、無理に自分を変えようとしないで、こんなふうに自分を見つめ直せる時間を持てて、本当によかったと思えた。
(お化粧もオシャレも、こんなに楽しいことだったんだ)
男性にも、ナンパとまではいかなくても眩しそうな目で見てもらえることがうれしかった。
***
青島さんのことを知ってから、数ヵ月。
(ひょっとして、どこかで会ったことがあるのではないだろうか)
ときどき、そんなふうに思うようになった。
それは、じっと見ていたからこそ気づけたことでもあった。
よくよく表情や仕草を観察していたからこそ、だ。
(いつ? どこで?)
少なくともここ数年ではなかった気がする。
頭をひねってみたが、いっこうによみがえってこない。
思い出せそうで思い出せなくて、気持ち悪くもあった。
あるとき、サークルで私より早く到着していた彼の隣に、私は思いきって座った。そして、話しかける。
「あのぅ、青島さん……」
会話からそれとなく、彼のことをもっと教えてもらえればと思っていた。
恥ずかしさもあったが、そろそろ前に進んでもいいんじゃないか、私、という気持ちからだった。
「はい、何ですか?」
爽やかな笑顔を向けられて、心臓がドキンと高鳴る。
(あ、私、思いきったことしちゃった)
最初からわかっていたはずのことを、改めて強く感じる。
でも、話しかけてしまったものはしょうがない。
同時に、これって自信がついてきたってことなのかな、とも思った。
少し前まで、目を合わせることですら躊躇していたのに。
「青島さんは、普段どんな本を読むんですか。なかなかお勧めのプレゼンの順番が回ってこないので……」
「そうですねえ……」
これまでの読書体験の話や、そこから子供の頃はどんな本が好きだったのかを言い合った。
こういうときに共通の趣味があると、私みたいな話下手でも自然にするすると言葉が出てくる。
そこから出身地の話になる。同じ県の出身だった。
「え、本当ですか。私もなんです。どこの市ですか」
そこでタイムアウトだった。
進行役の、書評家の女性が部屋に入ってくる。
「あとで、二人でゆっくり話しませんか」
青島さんがこっそり切り出してくれる。
もちろん、断らなかった。
***
「本当に、まだ気づいていませんか」
一緒に入ったダイニングバーで、彼は私を見つめて微笑した。
私が最初にサークルに来た日、自己紹介のときに声を上ずらせてしまったのを優しく見つめてくれたのと同じ表情だった。
「門野義明、といえば、思い出してもらえるでしょうか」
「え……」
私は絶句した。
目の前の相手、「青島さん」をまじまじと見つめる。
「あの、本当に……門野くん……?」
門野くんは、高校の同級生だった。
三年間のうち、同じクラスだったのは一年のときの半年間だけ。
確か、両親の離婚のために同じ県のほかの市に引っ越してしまったのだった。
成績がとても良くて、とくに数学はいつもトップクラスだった。
(それで苗字が変わっていたんだ)
「ごめんね。なかなか明かさなくて。でも、いつ気づいてもらえるかなって楽しみでもあって」 「私のほうこそ、気づけなくてごめんなさい」
言い訳をするつもりはないが、青島くんは高校のときとはだいぶ印象が変わっていた。
昔はもうちょっと、こう……もっさりしていた。もちろん本人には言わないけれど。
それが今ではこんなに爽やかな好青年になるなんて。
「そろそろ気づいてほしいなと思って、それで二人で話そうって誘ってみたんだ」
私たちはそのときをきっかけに、二人でよくサークル後に食事をするようになった。
やがて、サークルがなくても会うことが増えた。
何度目かわからないが、別れ際に、こう打ち明けられた。
「話そうと誘った理由はもうひとつあってね。どんどんきれいになっていたから、べつの人に取られてしまうんじゃないかって、焦ったんだ」
「え、それ……って……」
「……好きです。付き合って下さい」
***
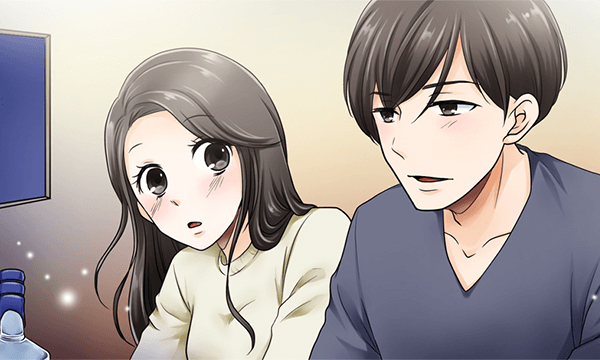
というか、本当は高校のときもちょっと気になっていたんだよね。
付き合ってしばらくしてから、そんなふうにも言われた。
それにしても、まさか私に彼氏ができるなんて。
望んでいたことではあったけれど、いざこうなってみると、不思議な気さえする。
「不思議でも何でもないですよ。行動を変えれば、世界も変わります。まあ、予想していたよりは早かったですけど」
アイは消える少し前に、そう言った。
最後のアドバイスは、「サークルで出会ったからには、付き合ったことを報告しておいたほうがいいですよ」というものだった。
青島さん――今はもう義明と呼んでいるけれど――に提案してみると賛成してくれたので、まずは書評家の女性に、それからサークルの会員に伝えた。
「そうじゃないかなと思っていた」
という人もいたので、やはり報告してよかったと思う。
言わなければ、きっと気を遣わせてしまっていただろうから。
「勇気を出して誘ってみてよかったなって思うよ」
義明は今でも、そう言うことがある。
私にキスをして、花束のラッピングを優しく剥がすように服を脱がせるときには、とくに。
「私も、勇気を出して新しいことを始めてよかった」
そのたびに、私も彼の耳元で囁き返す。
END
あらすじ
今まで家族の面倒を見るためずっと恋からは遠ざかっていた。
やっと一息つき見つけたサークルで出会った彼は…


















