女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
官能小説 恋欠女子とバーチャル男子 Story05〜愛情表現〜
理絵が打ち明けた悩み
彼のことが大好きすぎて、気持ちを抑えているつもりでも求めすぎてしまっていないか心配。
重いと思われたくないけれど1週間が限界…
彼が私のことを好きだという気持ちは信じていますが、あまりこちらから追いかけると冷められてしまうのではと考えてしまい怖いです。
***
彼女の悩みにアイはどう答える…!?
ちゃんと会って話したい
私、理絵の前に出てきたアイは、白い清潔感のあるワイシャツが印象的な青年だった。
なぜか黒いエプロンをしている。
腰から下の、一見スカートみたいに見える型だ。
「エプロンじゃなくて、これはサロンっていうんだ」
どうしてエプロンをしているのか尋ねると、彼はまずそう笑った。
「そうなんだ。じゃあ質問を変えるけど、どうしてサロンをしているの」
「パティシエだから」
どうやらこのアイは、パティシエという設定らしい。
とはいえ、コック帽に白いユニフォームという厨房にいるような格好では目立ちすぎるから、白いワイシャツにサロンだけと「抑えめ」にしているという。
「そもそも、なんでパティシエなの?」
アプリの説明によれば、アイは入力した悩みや自分の性格に応じた姿で出てくるという。
ということは、パティシエが私に「合っている」ということだ。
「だって、お菓子作りが好きだってあったから……」
「えっ、ああ……」
自分で入力しておきながらうっかりしていた。
確かに「趣味」の欄に、少し悩んだ末に「お菓子作り、料理作り」って打ち込んだっけ。
あまりはっきり記憶に残っていなかったのは、「とりあえず」打ち込んだものだったから。
そういえば最近は趣味といえる趣味なんてないな、あえていうなら昔こういうことが好きだったな……って、そんな感じで。
昔はお菓子や料理をつくるのに夢中になっていた時間を、今は彼のことを考えたり、SNSを追ってほかの女性とやりとりしているのを見つけ、その女性のプロフィールもチェックしたり、メールを出そうとして文面だけ考えてやめてしまったり、そんなことにばかり費やしている。
実りのない時間を過ごしている、バカバカしいことをしているとは自覚しているけれど、どうしても止められない。
会えない分だけ、ついそういうことをしてしまう。
「一緒にお菓子作りでもして、気分を紛らわせようよ。君にはもう少し広い視野でものごとを見ることが必要だと思う」
悩みをすべて入力したわけではないのに、アイは核心を突いたことを言ってくる。
最近の人工知能って、私が思っているよりもずっとスゴイみたいだ。
そのとき、メールの着信音が鳴った。
アイに「ごめん、ちょっと待って」と謝って、慌ててスマホを取り上げる。
彼からだった。
ずっとずっと待っていた、彼からのメール。
今日は休日。
まだ午前中。
これから会わない? というお誘いかもしれない。
メールを開く。
心臓がばくばくしている。
ひと通り読んで、私はがっくり肩を落とした。
私の「久しぶりに会わない?」と話題には触れていない。
ペットのことや家族の話ばかりで、さらに「会いたい」とか「寂しい」とかは伝えづらい文面だった。
「ふぅん……これはなかなかつらいね」
アイはBluetooth接続がオンになっているためか、スマホを見なくても書かれていたことがわかったらしい。
「私と会いたいと思ってくれないのかな」
大きな溜息と一緒に、少しだけ涙が出てきた。
「お菓子でも食べながら、少し話そうか。そのことについて」
「お菓子なんてないよ」
「今から一緒に作ろう。といっても僕は物理的には何もできないから、作り方を指示したり、応援したりするだけだけど」
最初はしぶしぶだったが、アイの提案に従ってよかったと思えたのは、手を動かしたことで多少なりとも気持ちが晴れたからだった。
結局私は家にあったかぼちゃを使って、一口サイズのかわいらしい蒸しパンを作った。
コーヒーを入れて、二人でつまめるようにする。
アイは食べられないけれど、席だけはきちんと作った。
「君は、彼にできればもっと会いたいという気持ちを普段からちゃんと伝えているの?」
「伝えてない……というか伝えられないよ。一週間に一度、さりげなく誘うのが精一杯。そういうことを口にしすぎて、重いと思われるのがいやなんだ」
「それじゃあだめだよ」
アイは静かな口調ながらもきっぱりと言った。
優しそうな外見の彼が言葉に力がこめると、耳を傾けざるを得なくなる。
「気持ちを伝えることは、命令することとは違う。願望は願望として伝えないと」 「でも、あんまりしつこくそういうことを言うと、重く思われて嫌らわれるって聞いたことがあるし……」
「それ、友達の話? それともネットか雑誌で見たの? どっちにしても理絵ちゃんたちとはまったく違うカップルの話だよね。一般論は一般論として受け止めるとして、カップルの数だけ関係の形は違うのだから、最終的には二人できちんと話し合うのが大事だよ」
アイはそこでいったん止めた。
覚悟を決めるようにわずかに目を細め、すぅと息を吸う。
本当に人間みたいだった。
「お互いの正直な気持ちを伝え合うことを怠るカップルは、いつか破綻する。僕の持っているデータ上では、の話だけど」
「破綻……」
言葉の強さに体がすくんだ。
いちばん恐れていて、でも見ないようにしていたことが、いきなりぱっと目の前に示された。
私はそれを避けようとしていたはずなのに、今とっている行動のせいで招き寄せているということ……?
「面と向かって切り出すのが難しいなら、まずはメールで触れてみるだけでもいい」
「……わかった」
蓄積されたデータは、私の思い込みや噂として聞いた情報よりずっと正しいだろう。
私はまず「一度きちんと話したいことがある」とだけメールで伝えた。
賽(さい)を投げてしまえば、あとは行動するしかない。
「何? 気になる」と返事が来たけれど、「ちゃんと会って話したい」と答えた。
***
翌週、ほぼ二週間ぶりに彼と会った。
彼は「家に来る?」と言ってくれたが、人の目があったほうが冷静に話せそうなので近くのカフェにした。
私は正直な気持ちを隠さずに伝えた。
重いと思われるのが怖くて、本当は毎日でも会いたいのに「ときどき会えればいい」とごまかしていた。
あなたのほうからはあまり会いたいと言ってくれなくて、最近はいつも私からなのも不安だった。
自分が誘わなければ言ってくれるかもと我慢しようとしても、一週間が限界だった。
だから、毎日会うのは無理だとしても、せめてもう少し会ってほしい。
それに、毎回自分から切り出すのは負担になりそうで怖いので、あなたのほうか
らも誘ってほしい。
彼の答えは簡潔だった。
「ごめん。理絵の気持ちはすごく嬉しいけど、今以上に会う時間を増やす気は、俺にはないんだ」
私も知っていたことではあったけれど、彼は音楽を作ってネットで配信するのが趣味だった。
その趣味に割く時間は、どうしても減らしたくないという。
私に会いたいと思う気持ちはもちろん強くあるけれど、自分にはどうしてもこの趣味が必要だ。
仕事との両立を考えると、今以上に時間を減らすわけにはいかない。
私は黙って彼の言うことを聞いていた。
次に会うのがとても楽しみ
顔には出さないようにしたが、ショックだった。
要するに、私のことは趣味の二の次でいいということだ。
何でも自分がいちばんじゃないとイヤなんていう気はなかったし、趣味ももちろん大事だと思う。
それでも、突きつけられるとつらい。
でも、私と彼は違う。
違うから、彼にとってどれぐらい趣味が大切で、どれぐらい彼のことを支えているかなんてわからない。
であれば受け入れるしかないのだろう。
こういうこともまた、気づかいや心づかいというのかもしれない。
「会いたいといってくれることを重いなんて別に思わないよ。でも、たくさん言ってくれるのなら、俺もたくさん断ることになる。それは……悪いなと思う」
彼はつらそうに目をそらした。
私たちはしばらく何も喋らなかった。
最初に口を開いたのは私のほうだ。
わかった、とうなずいた。
これからどうするのが正解なのか、あまりにも明確に答えが示されてしまった。
私はその答えを確認するように言った。
「あなたの考えていることが聞けてよかった。私はたぶんこれからも会いたいというのを我慢できないけれど、ダメなときは遠慮なくダメだっていってね」
「うん、ごめん。わかってくれてありがとう」
その日はもう別れることにした。
寂しい気もしたけれど、それ以上一緒にいたら彼にほとばしる感情のままぶつかってしまいそうな気がした。
別れ際、私は「また会いたい」ではなく、「次に会うのがとても楽しみ」と言い換えた。
***
しばらく落ち込んだ。
「おいしいものでも食べて元気出しなよ」
とアイは言ってくれたが、自分が作るわけではなく、レシピを教えてくれるだけだった。
それでもこの間と同じように、手を動かすことは私を元気にしてくれた。
おいしいお菓子や料理ができあがると、自信も持てた。
彼には二番目だといわれたけれど、私だって捨てたものじゃない。
こんなふうに思える瞬間がもっと必要なんだろう。
彼のことを考えるだけじゃなく、一人でも楽しめる時間を、私もこれからもっと作っていこう。
自分で自分を楽しませることができずにいたら、たとえ相手が彼ではなくても、誰かに心を依存させないといられない人間になってしまう。
そうだ、せっかくの会えない時間なのだから、肌も体型も髪も磨こう。
メイクの練習もしよう。
私は自分を奮い立たせるためにも「プエラリア・ハーバルジェル」や「ナデテ」を買って毎日のケアにいそしんだ。
それからもうひとつ、秘密のアイテムも。
外見だけじゃなくて、中身のアップデートも必要だ。
彼と一緒に語り合える話題を増やすために、彼が配信に使っているサイトを定期的にチェックするようにした。
オリジナルコンテンツの多いサイトで、私もすぐにファンになった。
そういえば最近、何かのファンになったり、何かを心から待ち遠しく思ったりすることがなかった。
ふとしたときに彼のことをまたメールを送りそうになったり、SNSをチェックしそうになったりするので、スマホは電源を切って見えないところに置いておくことにした。
スマホが視界にないというだけで、だいぶ気持ちが変わる。
アイに会えなくなるのは残念だったが、アイは集中する時間を作るならむしろそのほうがいいと言ってくれた。
作ったお菓子や料理は会社に持っていった。
一人では消費できない量だったし、すぐに分けられる友達も近くにはいなかったからだ。
もともと私の会社は女性が多くて、以前からみんなで家で作りすぎたものやお土産などを気楽に分け合っていた。
「うわあ、すごくおいしい」
「プロ顔負けだよ!」
「理絵ちゃん、最近きれいになったし何かあったの?」
みんなのそんな誉め言葉でさらに自信がついて、料理作りや自分磨きへのモチベーションはどんどん上がっていった。
***
二週間後に彼の家に遊びに行った。
(うわあ……)
家に入った瞬間、絶句した。
玄関にまとめられた透明なゴミ袋に、カップラーメンの空き容器が大量に詰まっている。
「ああ、最近カップラーメンばっかりなんだよ。自炊は苦手だし、寒くなると外に食べに行くのも面倒で」
私の視線に気づいた彼が言い訳のように言う。
それにしたってこれはあんまりだ。
「ごめん、ちょっと待ってて」
私は彼の家から数分のところにあるスーパーに走った。
ごく基本的な調味料と、安くなっている野菜を買ってくる。
その足でキッチンに立って、野菜たっぷりの中華丼を作った。
同時にすりおろしたニンジンでデザートのゼリーも仕上げてしまう。
「うわあ……」
彼は作業に戻ることもせず、私の手際に見とれていた。
「たまには健康のことも考えないとね。さ、食べよ」
いつも食事に使っている小さなテーブルの上を片づけ、中華丼を二つ並べた。
彼は目を白黒させている。
彼に家でこんなふうに積極的に行動したことはなかった。
私はいつも「お客様」で、端のほうにちょこんと座り、彼が何かしてくれるのをただ待っていた。
「……おいしい!」
とろみのある餡に包まれた野菜を口に運んだ彼は、ぱっと顔を輝かせた。
「久しぶりにまともなものを食べた気がする」
「大袈裟ね」
そう言いつつも、心の中でガッツポーズをとる。
食べながら、私は彼が作品をアップしているサイトの話をした。
そのサイトで最近見つけた番組やお気に入りの投稿者、彼の投稿についていた視聴者コメントのこと……。
今まではそんなことに興味があるように見えなかった私が突然話題にしたものだから、彼はびっくりしていた。
だが、素直に「あなたが好きなものをもっと知りたいと思って見るようになった」と言うと、嬉しそうにいろいろと教えてくれた。
彼が作る音楽のことも教えてもらった。
理論的なことはわからなかったけれど、「こういう風景をイメージしている」だとか、「誰々の音楽の影響が強い作品」などという話は私にもわかって、意見や感想を述べることができた。
***
数日後、切っていたスマホの電源を入れると、彼からメールが届いていた。
「いやじゃなかったら、また料理を作ってほしい。この間の中華丼、すごくおいしかった」という内容だった。すぐに「喜んで」と返す。
週末に会いに行くと、彼は、「自分から誘うのって照れくさいんだな。初めて知った」と照れくさそうに笑った。
「ごめん、気を悪くしなかったかな。料理を作ってほしいなんて、なんか図々しいよね」
でも、その……すごくおいしくて、忘れられなくて……それにあんなふうにちゃんと作ってもらったことが嬉しかったし、話も楽しかったし……。
彼はそんなことをもごもごと口の中で言っている。
「私が料理作りが趣味じゃなかったら、図々しかったと思う」
私ははっきり指摘した。
「でも、私は料理作りが好きだからやったのだし、自分が好きだと思えることであなたをこれからもサポートできるんだとしたら嬉しいな」
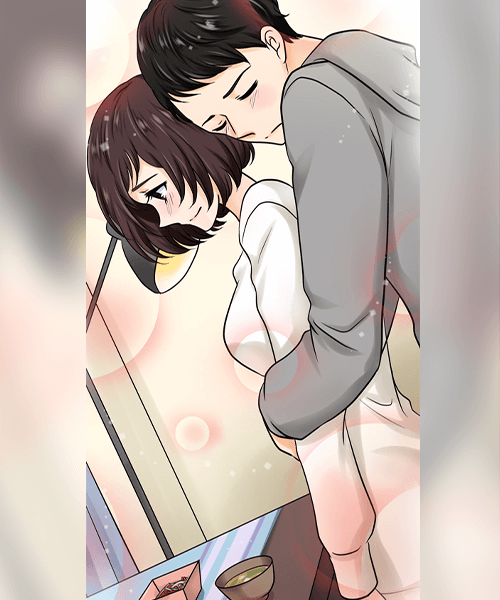
次の瞬間、彼はその場で私を抱きしめた。
これまでになかったぐらい、強い抱擁だった。
「……ありがとう。俺、理絵のいいところを全然わかっていなかったんだな」
その夜のエッチは濃厚だった。
いつもは一回で終わる彼が、果てた後ももう一度求めてきた。
私のアソコもいつもより濡れて、彼にぴったりと吸いついて締めつけた。
気分の問題もあるし、「秘密のアイテム」インナーボールで鍛えたおかげでもあるだろう。
「理絵、今日締めつけすぎ……マジで気持ちよくて、二回目なのにすぐにイキそう……」
余裕のなさそうな表情が愛おしい。
私たちは挿入の間に何度も何度もキスをした。
***
1年後、私たちは同棲に向けて準備を始めていた。
住みたいエリアも固まって、今は週末にそのあたりの不動産屋さんを回っている。
アイはずいぶん前から出てこなくなっていた。
きちんとお礼も言えていなかったのに、スマホの電源を切っている間にアプリ自体がスマホから消えていたのだ。
使用期限なんて確か明記されていなかったから、もう一度ダウンロードしようとしたけれど、不思議なことにアプリ自体見つからなかった。
(ありがとうね、アイ)
彼と幸せになることが、アイへの感謝を示すことになるのだと信じた。
END
あらすじ
理恵は彼のこと大好きで、毎日でも会いたいと思っている。
重い女とは思われたくなくて…
アイに相談を持ち掛ける。


















