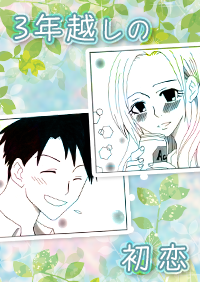女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
投稿官能小説「誕生日の別れ」
「誕生日の別れ」
西村みなみ、25歳。
たった今、誕生日に長く付き合った彼氏にフラれた。
サイアク…。
失恋のショックは大きいって聞いてたけど、今の私、何にもしなくてもぶっちゃけ死にそう。
左手の薬指を見る。今夜…もらえるかもって期待してたのに。
好きだった。
好きだった。
今でもこんなに好きなのに、思い出のすべてが過去形と化していく。
苦しい。つらい。
かなしい…。
フラフラと泳ぐように歩いた。気が付いたら家の前に立っていた。ただいまを言う元気もない…。
リビングに入ると、千里がキッチンでなにかを炒めていた。
千里「おお!おっかえりー!ちょうど今母さん買い物に行っとよ。すれ違わんかった?」
みなみ「…。」
私はわざとカバンをバンッ!と床にたたきつけると下を向いたまま2階に上がった。
千里は私の3つ年上で、となりの家に住んでいる。
というより家同士が接近しているため、行こうと思えば、私の部屋の窓から普通に千里の部屋に入れる。
生まれた時から家族ぐるみで仲が良くて、兄弟のいなかった私にとって、年の近かった千里はお兄さんというより、何でも話せる親友のような存在だった。
千里「みなみ…」
キイ…とドアが少し開き、真っ暗な部屋でベッドに倒れこんでいる私に千里が心配そうな声をかけた。
千里は明かりをつけて私のそばまで来て座り込んだ。
千里「どうしたっとよ…」
千里が私の頭をなでる。
マスカラが涙で流れたヒドイ顔を上げた。
みなみ「…別れちゃった…」
私の一言に千里が顔をしかめて、手を握ってくれた。
千里の胸でわんわん泣いた。
体の水分が全部抜けるくらい泣いた。
途中でお母さんが帰ってきてかなりビックリした顔してたけど、私を千里に任せて下に下りて行ってしまった。
寂しい…
気が済むまで泣いた私はすっきりしたバケモノ顔で夕飯を食べに千里といっしょに下へ降りた。
千里は夕飯も食べずに帰って行った。
お風呂に入ってベッドに入った。
明日は目が腫れるだろうな、と思うと悲しくなった。
心にポッカリ穴が空いたみたい。寝る前にメールする相手はもういない。
……さみしい。
コンコンコンッ!
ベッドの横の窓が音を立てた。
みなみ「千里…?」
カーテンを開けると、千里が向こうの部屋の窓からこっちに身を乗り出している。
こっちこっちとなにやら手を振っている。
ガラガラガラ…
みなみ「どうしたの?」
千里「渡したいものがあるからちょっとこっちに来んね」
なんだろ、と思ったが眠れなかったこともあり、窓から窓へ跳ぶ。
こうやって千里の部屋に来るのは久しぶりだった。
千里「ごめんな。けど眠れんかったじゃろ」
みなみ「うん…あれ?これって…」
ずっと前に撮った私と千里の写真だった。
みなみ「まだ飾ってたんだ!わ!…私若いな!あははは!」
千里「ばってん5年前の写真じゃけん、不思議じゃなかろ?」
みなみ「うん、でも千里はこのころからあんまり変わらないよね」
千里「そ…っそうとよ、変わっとらん…」
みなみ「今日のこと、すっごいショックだったけど、千里がいてくれて本当によかった…考えてみれば誕生日に別れ話切り出すなんて、別れて正解だったかも。なんだかスッキリしちゃった。ありがとね」
千里「…俺なら、そんなこと絶対せん…」
みなみ「え?」
千里「俺ならおまえを絶対傷つけたりせん!泣かせたりせん!さみしがらせたりせん!」
みなみ「…っ…!」
千里「俺はおまえが好きたい。こんまい頃からずっとずっと想っとった…好きたい」
そう言って千里はすごく切なそうな顔をした。
幸せな朝日
燃えるような恋じゃないけど、千里の気持ちが伝わってきた。純粋にうれしくて、気付いたら私の唇が千里の唇に触れていた。
千里はびっくりしたみたいだったが、すぐに反応し返した。
千里の舌が私を貫く。
熱い想いが私に伝わって、体が痺れた。
触れ合いは止まらず、さらに激しくなっていった。
みなみ「んっ…ん…んっ…は…」
こうなると千里も私も止まらない。
こんな関係になるとは思ってなかったけど、私の体は千里を求めた。
みなみ「ちょっと待って!この先は…」
千里「すっすまん…俺…」
私はスルリと窓から自分の部屋に戻って前の彼氏と使う予定だったLCハーバルローションを手に持って千里の部屋に戻った。
千里は私が逃げ帰ったと勘違いしてアタフタしていた。
可愛くて思わず笑ってしまった。
私は千里にローションを差し出して言った。
みなみ「塗って!」
千里は日焼け止めと間違えていたが、用途を説明するとすごく楽しそうに塗り始めた。
肩に、背中に、腰に、お腹に、そして胸にきた時にはもう相当感じていた。
みなみ「んっ…」
自然と漏れる声に促されるように千里は私をなでまわした。
こんな風に触れてくれる人を、どうして私は一番に愛さなかったんだろう…。
千里の指がわたしの脚の間に触れるともう力が入らなくなっていた。
激しい愛撫の波がひいて、いつのまにか私たちは眠っていた。
目が覚めると、千里は腫れあがったわたしの目を見て、大爆笑していた。
朝日が私たちを祝福しているようだった。