女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
官能小説 【小説版】タワーマンションの女たち 9話
擦れ違い
薄暗い部屋の中でベッドが軋む音が規則的に響く。綴昭さんが私の身体を貫く度、私は声を上げた。 マリンビーンズで開発をしているおかげか、いつもより気持ちいい。 中イキまではいかないものの、今までの綴昭さんとのセックスの中で一番気持ちが良かった。 快感に導かれるように高揚していくのがわかる。声だって、いつもより甘ったるくなってしまっていた。
「ここがいいの?」
綴昭さんは腰を振りながら、私のクリトリスをはじいた。
「……うん」
私が潤んだ瞳で綴昭さんを見上げると、満足そうな表情を浮かべた綴昭さんが私を見下ろしていた。
「朔、イキそう……」
「私も……」
綴昭さんの言葉に私も同調する。そして、また嘘をついてしまった。
罪悪感から胸の奥が微かに痛む。綴昭さんのピストン運動が限界まで速くなって、数秒後、綴昭さんは私の中で果てた。
けれど、私はイケない。まだ開発が足りないのかな……。
疑いの眼差し
セックスを終え、私たちは眠る為にベッドに横になった。
「朔、こっちにおいで」
綴昭さんはいつものように私の頭を抱き寄せる。
「あのさ、僕に隠していることはない?」
「え?」
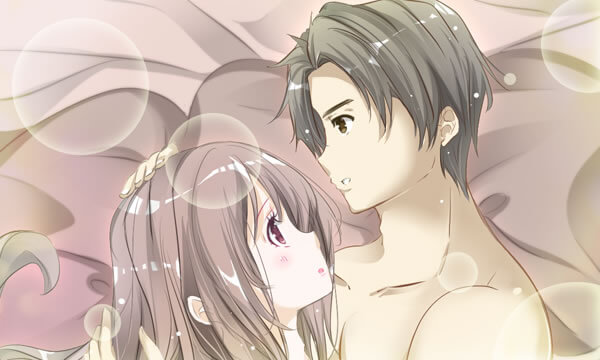
イク振りをしていることがバレたのかと思い、胸がきゅっと締め付けられるような緊張感に襲われる。
「隠し事? そんなのしてないよ」
「そうか」
少し声が上ずってしまったものの、綴昭さんはそれ以上何も言わなかった。 もしかしたら、綴昭さんは私がイク振りをしていることに気が付いているのかもしれない。 だとしたら、私のしていることは、彼を傷つけているのかな……。
質問の意味は?
身体の開発は順調そのものだった。
マリンビーンズを繰り返し使っているからか、感度も随分上がっているように思う。 これなら、中イキ出来るようになる日も近いかもしれない。 マリンビーンズを使い始めてから、 綴昭さんに任せっきりだったことが何だか申し訳なくさえ思えた。
嘘をついていることは後ろめたいけれど、綴昭さんとのセックスは今まで以上に気持ち良い。これも開発の賜物なのだろう。 今日も綴昭さんとのセックスを楽しみにしながら、私はベッドに潜り込んだ。しかし、綴昭さんは私に触れてこようとしない。 仕事で疲れているのかな……? 私は綴昭さんの腕に自分の腕を絡める。けれど、綴昭さんは微動だにしない。
「朔は僕とのセックスに不満はない?」
「ないよ」
予想外の質問に私は面食らいながらも平静を装って答えた。 実際、綴昭さんとのセックスに、なんの不満もなかった。綴昭さんはいつも私のことを思いやってセックスをしてくれる。 前戯だって丁寧だし、ピロートークだって欠かさない。 そんな彼とのセックスのどこに不満を持つというのだろう。
イケないことを隠していることにだって、罪悪感はあっても不満なんてなかった。
だから、綴昭さんがそんな質問をしてくることに私はただ驚いていた。
何かおかしなところがあったのだろうか?
私は彼が何を思って、そんな疑問を口にしたのか検討がつかないまま、気の利いたことを言えずに黙りこくる。
結局、この日の綴昭さんは私を抱きしめるだけで、それ以上のことは何もしてこなかった。
秘密を明かす時
綴昭さんの様子がおかしい。 あの日以来、セックスに誘ってこないし、食欲もないようだった。 仕事のことで何か悩んでいるのかとも思っていたけれど、仕事は順調そのもので特に問題はないらしい。 となれば、残る理由は私とのことだろう。
よくよく考えてみれば、セックスに不満がないかと訊かれる数日前、私は綴昭さんに隠し事の有無を問われた。 綴昭さんは私がイク振りをしていることに随分前から気が付いていて、それを気に病んでいたのかもしれない。 私だって、綴昭さんに何らかの嘘をつかれていたとしたらショックだ。
夫婦だからと言って、全てを共有する必要はないとは思うけれど、 二人に関することで嘘をつかれていたらと考えるだけで胸が押し潰されそうになる。 嘘をつくということは、たとえ相手を傷つけないようにする為や喜ばせる為だったとしても、 結果的に相手を裏切り、傷つける可能性があることには変わりはない。 私のしていることはそういうことだ。
でも、本当のことを言うことで綴昭さんを傷つけることになるかもしれない。 私の思考は行ったり来たりを繰り返す。 私はダイニングテーブルで一人コーヒーを飲みながら、綴昭さんが起きてくるのを待っていた。 しばらくすると、ドアが開き、少し眠たそうな綴昭さんがリビングへと入ってくる。
「おはよう。朔は今日も早いね」
「早起きが習慣になってるから。コーヒー飲む?」
「ああ、お願いするよ」
綴昭さんはパジャマのまま、席に着いた。 私はポットのお湯をドリッパーに注ぎながら、秘密を打ち明けるべきか考えていた。 コーヒーを注ぎ終えると、私は綴昭さんの前にマグカップを置く。
「どうぞ」
「ありがとう」
「ちょっと待ってて」
私はそう言って寝室に行くと、綴昭さんに見つからないようにしまっておいたマリンビーンズを引き出しから取り出し、再びリビングへと戻った。私は黙ったまま、綴昭さんの向かいに座る。
心を落ち着ける為に残っていたコーヒーに口をつけた。すでに冷めきったコーヒーは私の身体を冷やしながら胃の中に落ちていく。
「綴昭さん、話があるんだけど……」
「何かな」
綴昭さんはコーヒーを一口すすると、マグカップを置いた。
「私、綴昭さんに謝らないといけないことがあるの」
綴昭さんは私の視線を真っ直ぐに受け止めてくれる。しかし、その表情はどこか悲しげだった。
「私ね、セックスで一度もイッたことがないの。だけど、ずっとイク振りをしていて……」
綴昭さんは何も言わない。ただ黙って、私の告白を聞いてくれていた。
「ごめんなさい。悪気はなかったの」
「僕こそ、ごめん。そのことには気が付いていたよ」
「え……」
「女性がイク時は、女性の変化が男性にも伝わるんだ」
「そうなの……?」
「ああ、だから、君が僕の為に嘘をついてくれていることは随分前からわかっていたよ。それと同時に、朔が僕とのセックスに満足していないんじゃないかと思っていた」
「そんなことない」
嘘をついていた私が彼の言葉を否定しても説得力に欠けるかもしれない。それでも、私は首を横に振った。
「次第にね、僕とのセックスに対する不満から、他の人と関係を持っているんじゃないかっていう不安に駆られるようになったんだ」
「え……」
「君の感度が突然良くなったような気がしてね」
「……」
「朔に限って、そんなことするはずがないことはわかっているよ。でも、普段、仕事が忙しくて、朔と過ごす時間をあまり取れていなかったし、最近はデートもしていなかっただろう? そんな負い目もあってね」
綴昭さんがそんなことを考えているなんて夢にも思っていなかった。 いつだって、穏やかで私のことを気遣ってくれる彼に不満の抱きようなんてない。 仕事で忙しいと言ったって、私との生活を守る為に一生懸命働いてくれていることを私はわかっている。
「あのね、実はこれを使っていたの」
私は寝室から持って来たマリンビーンズを見せた。一瞬、綴昭さんは驚いたような表情を浮かべる。
「このマンションの最上階にバーがあるでしょう? そこに麗子さんっていうバーテンダーの方がいて、セクシャルな相談に乗ってくれるの。それでイク振りをしてしまっていることを伝えたら、自分で身体の開発が出来るからってこれをもらって……」
綴昭さんは合点がいったのか、ほっとしたように私を見た。
「一人で悩ませてごめん」
「怒ってないの……?」
「怒るわけないだろう? 二人の問題を朔一人だけに悩ませていたんだから、申し訳ない気持ちでいっぱいだよ」
その言葉に私は長い間、胸につかえていたものが取れた気がした。
「朔、寝室に行こう」
「うん……」
私たちは同時に立ち上がると、どちらからともなく手を繋ぎ、寝室へと向かう。 そして、この日、私はようやく初めて綴昭さんとのセックスでイクことが出来た。
あらすじ
綴昭から隠し事をしているか聞かれた朔。
ラブグッズで感度磨きをしていたということを打ち明けることに不安はありつつも、綴昭に正直な気持ちを伝えると…



















