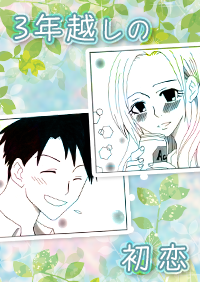女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
小説サイト投稿作品24 「この香りで惑わせて」(ペンネーム:大神ルナさん)
「この香りで惑わせて」(ペンネーム:大神ルナさん)
〜LC編集部のおすすめポイント〜
付き合ってからたった一度しかHしてないことに不安を覚える亜美。
女性としての魅力がないのかな…と落ち込む気持ちに、共感する女性も多いのではないでしょうか。
とあるきっかけでもらった香水に、彼は激しく惹かれ、大胆になっていく…。
大好きな彼に求められる喜びや初々しい亜美の反応が丁寧に描写されています。
セックスを覚えたての頃を思い出してしまうような、可愛らしい二人にドキドキできる作品です!
会議室から聞こえてきた声
社員十名の小さな会社。
お昼になると、一斉に昼食に向かう。
会社の回りには、いくつものレストランや食堂があり、価格も安いことからお弁当を持ってくる人はいない。
あたしも外食派の一人。
さあ、食べるぞって気分で同期の子と出たのはいいけど、会社にスマートフォンを忘れて一人戻ってきた。
今夜は彼との約束があるから、いつ連絡が来てもいいように持っていたい。
会社は二階建てで、二階に更衣室がある。
あたしは、急いで更衣室に向かおうと思ったけど、会議室から聞こえてきた声に思わず足が止まった。
「だめだ! もう……我慢できない」
「ああっ! んっ……あんっ」
明らかに、昼間の会社――
それも会議室から聞こえてきていいような声じゃない。
机の足が床を擦る音まで聞こえてきて、嫌でもどんな姿勢でしているのかを想像させる。
あたしは、顔を真っ赤にしながら足音を立てないように会議室から離れた。
「ねえ……そろそろ……行かなくちゃ」
「ああ」
離れても、静かな部屋に服を整える音が大きく聞こえる。
「また……今夜」
「ええ」
その会話が聞こえた直後、会議室の扉が開いて、あたしは出てきた人を見て驚いた。
出てきたのは、いつも真面目で性的な欲求なんてありませんってくらいの同期くん。
さらに驚いたのは、次に出てきた相手の子。
あまりの驚きに、隠れるのも忘れてばっちり目が合ってしまった。
女としての魅力
「あれ? お昼に行ったんじゃ」
「う、うん。スマホ忘れちゃってさ」
あたしは、そそくさと去ろうとしたけど、彼女に腕を掴まれてそれもできなくなった。
「もしかして……今の聞こえちゃいました?」
「えっと、あの……」
さっき聞こえてきた声を思い出して、顔が熱くなるのを感じた。
「やだ、顔が赤いですよ? あなただって、未経験じゃないでしょ」
そう言った彼女に、いつもの堅苦しいイメージはない。
一つに結んだ髪型が彼女のイメージだったのに、今は髪が下ろされて乱れている。
苦しそうなくらい留められていた首もとのボタンも、開けられて胸の谷間が見えていた。
それに、なんだか色っぽい。
二人で、黙って更衣室にはいると、きっちりと髪型をなおす彼女がちらりとこちらを見た。
「亜美さん。彼氏とちゃんとセックスしてます?」
「えっ! それは……」
「やっぱり。他人の喘ぎ声程度で真っ赤になるから、そうなんじゃないかなと思って。これ、試してみて下さいよ」
彼女は、鞄の中から小さな小瓶を取り出すと、あたしに差し出した。
「口止め料です」
「香水?」
ピンク色の瓶には半分くらい液体が入っていて、爽やかな匂いがする。
「はい。それを使えば、紳士な男も野獣に変わりますよ」
「ただの香水でしょ?」
「男の本能を刺激するような調合がされてるんですよ。
騙されたと思って使ってみて下さい。
つけるのは、首筋とか胸の谷間、腿の内側よ」
また堅苦しいイメージに戻った彼女は、先に行きますと言って出ていった。
更衣室には、戸惑うあたしと香水の小瓶。
香水にそんな力はない。
あたしは馬鹿馬鹿しいと思いながら、鞄に押し込んだ。
あたしと彼は付き合ってから、二年が経つ。
お互いに惹かれ、ゆっくりと恋愛をして愛を育んできた。
ただ、一つ気になるのが、二年の交際期間にセックスしたのがたったの一回ってこと。
会う機会も少なくて、あたしは会うたびに確かめ合いたいと思うのに、彼は紳士的にデートの終わりに家に送ってくれて帰っていく。
優しいのは嬉しいけど、時には理性なんて捨てて求めてほしい。
じゃないと、女として魅力がないんじゃないかって、自信がなくなる。
あたしに、彼を引き止めておけるだけのものがあるのかって――。
つけて、香って、惑わせて
夜、約束どおり彼とのデートに向かった。
待ち合わせは、昔から変わらず小さなイタリア料理店。
共通の友人がコックを勤める店で、雑誌やテレビの取材は断っているのに人気な店だ。
おすすめの白ワインと料理を頂き、
近況報告みたいな会話を楽しみ、
駐車場までの道をゆっくりと歩く。
今夜も、ホテルに行くような雰囲気ではない。
今まで自分から誘ったこともないし、
それをして嫌われたらなんて事を考えてしまう。
だんだん愛されている自信がなくなってくる。
本当は別れたいけど、言い出せないんじゃないか。
セックスをしたがらないのは、
別に発散させてくれる相手がいるんじゃないか。
だんだん思考がネガティブになってくる。
「どうした? いつもより、静かじゃないか?」
「そ、そう?」
あたしは、言葉を濁した。
じゃないと、さっきまで考えていたことを口に出してしまいそうで、怖かった。
「そうか? 気のせいならいいんだ。駐車料金を精算してくるから、車のところで待っててくれ」
あたしは小さく頷くと、助手席のところに行った。
サイドミラーに写った自分は、惨めなくらい魅力に欠ける。
少しでもましに見えるように、グロスを取り出そうと鞄を開けて、思わず手が止まった。
目に入ったのは、ピンク色の小瓶。
そして、思い出したあの言葉。
『紳士的な男も野獣に変わりますよ』
半信半疑で小瓶を手にして、彼がまだ戻って来てないのを確認して吹きかけた。
スカートをたくしあげるのは恥ずかしかったけど、腿の内側にも吹きかける。
こんな香水で、何かが変わるなんて思ってない。
でも、心のどこかでは変わったらいいなとも思ってる。
あまりにも矛盾してる。
「お待たせ」
その声に、あたしは小瓶を鞄に押し込んで、助手席に座った。
車はゆっくりと走りだし、車の少ない通りをあたしの家へと向かっていく。
「亜美……香水なんてつけてたっけ?」
「今まではつけてないよ。でも……今日、同期の子に試供品を貰ったからつけてみたの」
彼が気づいたことに驚いた。
そんなに目立つ匂いじゃないし、たいした量はつけてない。
その後、会話はぴたりと止んだ。
彼は真っ直ぐ前を見ていて、何を考えてるのかわからない。
やっぱり、効果なんてない。
そう思った瞬間、車は赤信号で止まり、彼の手が伸びてきた。
首の後ろを掴み、引き寄せられる。
唇が重なって、呆けたあたしの開いた口に舌が差し込まれ、はじめてキスされてることに気がついた。
ねっとりと熱く、口内をたっぷりと舐める。
離れる時に下唇を吸われて、軽く噛まれた。
「やばいな……」
彼が車を走らせ始めるときに呟いた言葉に、あたしの心臓はハチドリみたいに羽ばたいた。
今日は、我慢できない…
いつも以上に彼は車を飛ばし、あたしの家に辿り着くと、シートベルトを外した。
いつも、彼はシートベルトを外さないのに、さらにこう言う。
「今日、泊まってもいいかな?」
あたしは、思わぬ事態に口がきけなくなり、頷くことしかできなかった。
頭はぼんやりとして、彼に導かれるまま車を降りて部屋へと向かう。
彼は焦っているみたいに速足で、あたしは転ばないようにするだけで精一杯だった。
部屋に入れば緊張は高まり、とつぜん変わった彼に戸惑った。
真っ直ぐに寝室に向かい、ベットに軽く押される。
「悪い。今日は、我慢できない」
彼は謝罪を口にすると、乱暴にジャケットを脱ぎネクタイを外し、ボタンを外すと覆い被さってきた。
「今日の亜美……色っぽい匂いがする」
早急な仕草でブラウスのボタンが外され、あらわになった胸元に鼻を近づける。
「この匂いは、まずいよ」
手のひらがブラの上から胸を包み込み、前にあるホックを意図も簡単に外した。
「他からも……匂いがする」
彼は体をずらして下に向かい、スカートを脱がせると、膝から腿へとキスをしていく。
「ああ、ここだ」
香水を吹き付けた場所に鼻を擦り寄せ、恥ずかしいくらい秘められた場所に近いところにキスをする。
それだけであたしは、すすり泣きそうになった。
「やばいよ……興奮してきた」
熱い吐息を吐きながら、さらにショーツを剥ぎ取り、さらけ出された足の間に顔を埋める。
もう、息が止まりそうだった。
彼に、そこを舐められ、啜られたことはない。
まるで、猫がミルクを舐めるみたいにされて、はしたないくらい悶え蜜を溢れさせた。
ようやく舐める音が聞こえなくなる頃には、頭の中は霞がかかったみたいになっていた。
舐められただけで絶頂に達して、弛緩した体はうつ伏せにされるがままだった。
「わかるか、亜美」
何も身につけていない臀部に、彼の下半身が押し付けられる。
「もう、痛いくらいなんだ。君の体温が上がって、もっといい匂いがしてきた」
彼の下半身は、怖いくらい固くなり、布越しでも脈打つのがわかるくらいになっていた。
「今日は、優しくしてやれないかもしれない」
あたしの心と体は震えた。
別に怖い訳じゃない。
女としての期待が、そうさせた。
「好きにして」
それだけしか浮かばなかった。
すると、あたしの腰を掴み膝をつかせると、一度だけ何かを確かめるように彼自身を押しつけ、一気に貫いた。
あまりの気持ちよさに、あたしはベットシーツを握りしめ、快感に堪える。
彼は激しく抜き差しを繰り返し、何度も何度も絶頂へと導く。
こんな激しく抱き合ったことはない。
まるで理性のない獣みたいな混じりあいに、あたしは甲高い声を上げた。
それでも、彼の激しさは変わらず、ついには自分で腰を振りはじめてしまった。
彼が相手だから、色っぽくなれる
いつの間にか気を失っていたのか、目をさますと彼に髪を撫でられてた。
こんな風に、彼と朝を迎えるのはいつぶりだろう。
「ごめん。無理させた」
あたしが起きたことに気づいた彼は、まずそう言った。
「すごくいい匂いだと思ったら、もう亜美を抱くことしか考えられなかった」
なんだか恥ずかしそうに言われて、あたしまで恥ずかしくなってきた。
そもそも、仕組んだのはあたしだ。
まさか、効くとは思わなかったけど。
「いつもは、我慢できてたのに……昨日は無理だった」
「どうして、いつもは我慢するの?」
彼の言葉に驚いたあたしは、思わずそう聞いていた。
「亜美は、初めてを俺に捧げてくれただろ?あの時、痛みに堪えてたのも知ってる」
たしかに、初めての時は痛くて、二度とセックスなんてしたくないと思った。
でも、二度目に抱かれた時には、最初の時とは違って嘘みたいに気持ちが良かった。
「だから、無理強いはしたくなかったし、もしかしたら二度としたくないんじゃないかって考えた」
「そんなことっ」
ない。
そう言おうとしたのに、彼の人差し指があたしの唇に当てられて、言わせてもらえなかった。
「それに、亜美は誘ってくれなかったしね。一緒に部屋に来てほしいとかもなかった」
「それは……自分から言うのが恥ずかしくて」
「うん。わかってる」
彼は優しく微笑んだ。
「まさか、こんな罠を仕掛けてくるなんて思わなかったよ」
また覆い被さってきて、あたしの足の間に体をねじ込んできた。
「でも、悪くない。君に求められてるって分かったから」
首筋に顔を埋め、ゆっくりと息を吸うと顔を上げた。
その瞳には、もう一度を想像させる熱がこもってる。
「でもさ……」
「はい?」
「俺といる時だけにしてよ。こんな風に色っぽい匂いをさせるのは……心配になる」
心配する必要なんてないと、言いたかった。
香水があろうが、なかろうが、彼が相手だから色っぽくなれるんだと思う。
あたしは、小さく「はい」と答えた。
そして、満足そうに笑った彼のキスを受け入れた。