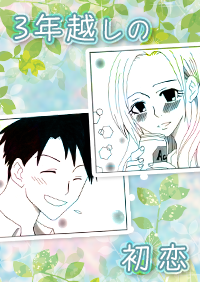女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
小説サイト投稿作品34 「chu to him」
「chu to him」
〜LC編集部のおすすめポイント〜
「入社試験のときから好きでした…」
キラキラと眩しい瞳の彼を見ていると、なんだか胸が痛む…
彼女の複雑な心境に、先の展開が気になりウズウズしてくるはず。
こんなふうにモテる女になりたいなと思わず憧れてしまう作品です♪
感じる視線
総務部で働く私は自社の新入社員の面接の手伝いで受付や面接の案内をしていた。
スーツを着慣れていない学生達が緊張しすぎて私を見ない。
もしくは、じっと見ている。
私も緊張してしまうけれど面接を受けにくる学生達にきちんと、対応する。社会人として恥じない行動を。
でも、顔と名前等一致しないまま1次面接、2次面接と流れていく。
最終面接になる頃には…
ほぼ内定する予定の学生ばかりで自然に顔と名前は覚えていくけどその一時だけで…
業務に追われると忘れていく。
入社書類の整理から始まって提出書類の確認をしていくのは大量で、ほぼ…流れ作業だった。
内定者に内定通知書を送付して、桜が咲き始める入社式の頃までに新入社員研修を1ヶ月行い、4月に入るとすぐに、各部署へ配属されることになる。
その新入社員研修も総務で仕切り私は特に誘導を行う。…まるで部活の顧問のように。
そんな私を観ている男性がいた。
ささやかな約束
彼の目はキラキラしていて…
私には眩しくて…見られなかった。
ずっとこのことは覚えていた。
そして少し…嫌な予感もあった。
確証ではなく、なんとなく。
そのなんとなく…が…的中した。
「今度、ランチ一緒に行きませんか?」
研修の休憩中に声をかけられた。
新入社員のなかでも、先輩に可愛がられるキャラクターで私の同期の営業部の男性も、彼を可愛がっているくらいだった。
ランチに誘ってくるのがなんとなく、頷いてしまいそうになる。
私はPCから目を離して静かに彼を見た。
やっぱりキラキラしていて眩しい目。
「俺ずっと観てたんです。貴女を。」
からかわれている気もした。
けれど…からかわれてもいいかと思ってしまって、つい、YESの返事をしていた。
「4月の…研修があけたらね」
私はまたPCへ目をやって新入社員研修での毎日の報告書を少しずつ作成していた。
「よかった。…約束ですよ?」
こんな約束、忘れると思っていた。
罪悪感
4月に桜が咲き始めた頃…
新入社員が社内を駆け巡って新しい風が優しく吹いていた。
新鮮な気持ちになって挨拶をして私自身の気持ちも改めて正す。
「…約束、覚えてくれてますか?」
相変わらずキラキラした目のまま私に話しかけてきてくれた彼はやっぱり眩しい。
4月に入ってからの業務は多忙でわざとPCを見つめて作業しながら答えることにした。
「ランチ、行きましょう…だっけ…?」
新入社員の彼が私に声をかけて笑っている姿は、少し自然だった。
私は、新入社員の相手をしていて彼には話しかける人がいないと、判断されているのだろう。
「よかった。今からどうですか?」
思わずキーボードを叩くのをやめて彼の、キラキラした目を見てしまった。
だめだ。この目を見ると胸が痛む。
既婚者の上司と毎日キスしていること同期の男性とも…キスをしていること
…悪いことしていることを全部…見透かされてしまいそうで、罪悪感に駆られてしまう…。
彼の目をじっと見つめられない。
嫌な予感
「…営業部だよね?」
既婚者の上司も、同期の男性も営業部だから…覚えてしまった。
「はい。俺…、新人賞狙って…同期の誰よりも早く役職者になる…って、自己紹介しました。」
こんな言葉が似合う彼には、私はどう映るんだろう…。
…私には眩しすぎる。
「だったら、営業部の先輩とランチ行った方がいい思うよ?」
「…わかりました。…じゃあ、今夜、コーヒー一緒に飲みませんか?」
私は思わず笑ってしまった。
眩しい彼がかわいく思えて、つい、YESの返事を言ってしまう。
「おいしいコーヒー屋さんならいいよ。」
私はまたPCに目をやって仕事を続けることにした。
彼の姿を見なくても、その後、ニコニコした笑顔で、営業部の先輩にランチ連れてってくださいよなどと言っているのが分かってしまう。
かわいいから、可愛がられるのが想像ついてしまって…
またクスッと笑ってしまった。
やっぱり、少し嫌な予感がする。
なんとなく…、なんとなく。
塞いだ唇
彼にとってのおいしいコーヒー屋さんは、コンビニエンスストアのホットコーヒーだった。
1杯ごとに挽かれたドリップコーヒーは私の手に優しく手渡されて…コンビニエンスストアの一番奥の駐車場で彼の車の中で…ゆっくり飲んだ。
「私、苦めのコーヒーが好きなの。
…ここのホットコーヒー、おいしいんだね。」
眩しい彼の目が少し見えた。
キラキラしていて…やっぱり眩しい。
「俺、大学の時から好きなんです。」
「うん…。」
「…貴女のことが。」
「…うん。」
少しの嫌な予感が、確証された。
私は…またホットコーヒーを一口飲んで右手で彼の左手をそっと握った。
「私ね。…好きな男性が、いるの。」
彼の左手はより…強く私の右手を握り返していた。
けれど私は…受け止められない。
「でも俺…、初めて逢った時からずっと憧れて、好きだったから…亜希さんのこと諦めません。」
私は…この言葉を聞きたくなくて彼の唇を私の唇で塞いだ。
小さくチュッと音が響いた。
「眞輔くんじゃ…ダメなの。ゴメンね。」