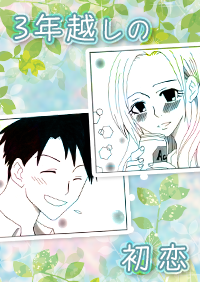女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
小説サイト投稿作品44 「BI・YA・KU」
「BI・YA・KU」
〜LC編集部のおすすめポイント〜
隣に住むひとつ年上の幼馴染・颯太は長身でかっこよくて優しくて女の子にモテる。
ある日、主人公・舞衣は偶然颯太の「好きな子」の話を耳にしてしまい…!?
甘酸っぱい二人の恋模様にキュンとすること間違いなし!
淡い初恋を思い出しながら読んでみて下さいね♪
年上のお兄ちゃんのような幼馴染との恋愛、女性ならば憧れのシチュエーションです。
主人公が自分の気持ちに気付いてからの戸惑いに共感すること間違いなしです。こんな恋がしたくなりました♪
彼の好きな人
『From:颯太 舞衣、助けて。今すぐ、ココに来て』
お風呂にゆっくり入って、髪をタオルで拭きながらバスルームから出てきて目に入った、メールの着信ランプ。
鼻歌交じりにスマホをみた瞬間、頭が真っ白になった。タイトルもなく、短い文章。久々に届いたメールは、私に衝撃を与えた。
颯太は一つ年上の幼馴染みで、去年やっとカレカノの関係になった。
学生時代は、お互い何とも思ってなくて家も隣同士だから、兄妹みたいな関係で喧嘩もしたし言いたいこと言い放題で恋の相談なんかもしていた。
そんな感情が変わり始めたのは、高校の2年の頃から。
中学校の頃から、颯太はバスケをしていて長身だし、そこそこ顔もよくて性格も優しいから、ファン、というか颯太目当ての女の子はたくさんいた。
けれど、颯太はバスケバカと言うべきかバスケ以外は目に入らないって感じて、相手にもしてなかった。
高校に入って、彼は益々カッコよくなっていってよく校舎裏とかで告白受けているのも、目にしていた。
その頃は、全然気にしなかったのに。それよりも、なんで彼女作らないのか不思議に思ったくらいだった。
だから、一緒に帰るときに茶化してたりしてた。そのとき颯太は、今はバスケが一番大事だからって言ってた。
でも、聞いちゃったんだ。本当の理由を――
それは移動教室で、颯太のクラスの近くに行ったときだった。
颯太は、自分の教室の前で友達3人と話をしていた。
「お前、なんで彼女作らないの?」
「そうだよ。お前なら、より取り見取りだろ?」
「隣のクラスの雪稀ちゃん、お前のこと好きだって言ってたぞ」
「マジで?雪稀ちゃんって、めっちゃキレーな子だろ?マジ、羨ましー」
「俺…好きな子いるから」
「マジ?だれだれ?教えろよー」
颯太、好きな子がいたんだ…そっか。そうなんだ…。
その後の言葉は、聞こえなかった。予鈴がなったのもそうだけど、それ以上聞きたくないって心のどこかで思っていたのかもしれない。
颯太たちに見つからないように壁に隠れながら、その場を足早に去った。
そしてその頃から、今まで以上に颯太の行動に敏感になっていった。
颯太の好きな子は誰なんだろう。視線の先に、その子がいるんじゃないかとか。
気になって気になって、仕方がなかった。自分の気持ちにも気づかないままに。
「ねぇ、舞衣。あんたと颯太先輩ってどうなってんの?」
「何が?」
「最近、余所余所しくない?前までは、颯太颯太ってめちゃくちゃ話にも出してたのに」
「そう、かな?気のせいだよ」
「あんた…今更、自分の気持ちに気付いたとか?」
「何のこと?」
「は?まだ気が付いてないの?あんた、颯太先輩が好きなんでしょ?」
好き?私が?颯太のことを…??そんなわけ…ない、よね?あれ、嘘。そんなはず…あれ、あれれ?
「なんで、そんなこと思うのよ」
「あんた見てれば分かるわよ。舞衣が颯太先輩を見てる目、恋してますって目してるよ?」
「う、そ…」
うそ、ウソ、嘘。そんな…そんなわけない。だって、私たちは幼馴染みで兄妹みたいで、それで、それで…
私が、颯太を――ス、キ?
思考回路がパンクしそうなくらいになっている私をみて、親友の友香は、はぁ〜と額に手を当てて勢いよく溜息を吐いた。
自分の気持ちにようやく気が付いた、2年の冬。でも、告白する勇気もなくてそれに今の関係を壊すことが怖くて颯太には、何も言えなかった。
気が付けば、颯太は卒業して地元の大学についていた。翌年には、私も大学に進学したけど別の大学だったからあまり会わなくなった。
気持ちは、変わらないままに。
ケジメ
月日は流れ、颯太が大学を卒業する年の夏。大学進学を機に、独り暮らしを始めた颯太が夏季休暇を使って実家に帰ってきたときだった。
「あ」
「よっ、久しぶりだな。元気してたか?」
「うん。颯太こそ、元気だった?」
「あぁ」
家の前で、彼が待っていた。夕方でもまだ暑いのに、いつからココで待っていたんだろう。
白のVネックのTシャツにジーンズといったラフな格好。でも、すらっとした腕と長い脚でモデルみたいに格好いい。
「暑いでしょ?中に入る?」
「あ、いや。舞衣とちょっと話がしたくて」
そういって二人で来たのは、近くの公園。なんかいつもと雰囲気が違う颯太。思い詰めてるっていうか、心ココにあらずって感じ。
「ねぇ、話って何?」
「あのさ。俺、今年大学卒業するんだ」
「うん。知ってる」
「でさ、卒業したらこの町離れようと思うんだ」
「え…」
陽も暮れかけた公園には、ほとんど人はいなくて木の傍にあるベンチに、座って隣に座る颯太を見上げる。
颯太は、公園の砂場辺りをボーっと見つめていた。
「でさ、俺。この辺りでケジメをつけようと思って」
「ケジメ?」
「そう、ケジメ。俺、舞衣に隠してたことがあるんだ」
もしかして、それって高校の時に聞いた“好きな子”のこと?嫌だ、聞きたくない。
「俺――」
「いや。聞きたくないっ」
「舞衣?」
「ヤダ。颯太の口から、私以外の女の人の名前聞きたくない」
「え?」
私は、両耳を塞いで目もギュッと閉じて頭を抱えた。すると、スッと隣にいた颯太が動いた気配がした。あ…私、颯太に呆られたかも。
でも、聞きたくないんだから仕方がない。ふっと、自分の耳を塞いでいた手に温かいものが重なって、ゆっくりと耳から外させた。
「舞衣。それって、どういうこと?」
「だから、だから…」
「うん」
「そ、その…私、颯太のことがス」
颯太のことが好きって言おうとしたら、その前に唇に人差し指が置かれて最後まで言えなかった。
「好き」
「そう、た?」
「俺、舞衣が好きだ」
「う、そ?」
「嘘じゃない。ずっと、ずっと好きだった。中学のころから、ずっと」
え…中学の頃から?だって、その頃はバスケが一番大事だからって言ってたのに。
後から聞いた話だけど、颯太は私よりずっと前に好きだって気が付いていて、だけど私とのこの関係が壊れるのが怖くて、ずっと言えなかったらしい。
私と一緒だ。
けど、私よりずっと長いあいだ苦しんでたんだ。それなのに、ずっと私の傍で優しくしてくれていたなんて。
「颯太、ごめんね」
「え…」
「気が付いてあげれなくて、ごめんね。私も、颯太のこと好きだよ」
「よかった。一瞬、断られるのかと思った」
そういうと、ギューッと抱きしめられた。だけど苦しくなくて、温かく包んでくれる感じ。その日、初めてキスをした。
ぎこちなくて触れるだけのkiss。だけど、颯太らしい優しいkiss。
それから、私たちは今まで一緒にいられなかった時間を埋めるように夜通し話をして、たくさん笑い合って、いっぱいキスをした。
媚薬のような香り
颯太が大学を卒業するまでは時間がちょっとでも空くと電話をしたりデートしたりしていた。
けれど卒業して隣町の会社に就職してからは1ヶ月に一度会えればいい方で。
ほとんど、会えない毎日。しかも、最近になってからは電話もろくに出てくれない。
仕事が忙しいのか、メールの返信も夜中だったり、翌日になっていたりで。正直なところ、寂しい。颯太、会いたいよ。
そんなときに、届いたメール。
『舞衣、助けて』
なに、どうしたの?何があったの?助けてって…え?事故?病気?不治の病にかかったとか?
颯太に何かあったら、私…
髪を乾かす時間も惜しくて、タオルドライのまま急いで服を着て颯太が指定した、あの公園に走った。
「颯太、颯太っ!!」
薄暗くなった公園を見渡しても、どこにも見当たらない。もしかして、もう…颯太、どうか無事でいて。
「颯太ぁ…ひゃっ」
「静かにしろ」
後ろから伸びてきた大きな手が私の口を塞ぎ聞き慣れない低い声が聞こえた。
嘘、こんなところに変質者?怖い。怖いよ、颯太、助けて。
「…震えてる。ごめん、やりすぎた」
「え…その声、颯太?」
抱きしめられていた腕の力が緩み私はゆっくりと後ろの人物へと顔を向けた。すると、ちょっと泣きそうな顔をした颯太がそこにいた。
「なんで、颯太が泣きそうな顔してんのよ」
「だって、もうどうにかなりそうだったんだ」
「どうにかって、やっぱり何かあったの?」
不安になって、身体の向きを変え向かい合うようにして彼の顔を見上げる。
「ん。舞衣に会いたくて、でも忙しくて会えなくて…本当にヤバかった」
「え…私に会えなくて?」
「うん。舞衣はそんなこと、なかったの?」
「そんなこと…私も会いたかった、けど…」
「けど?」
でも、助けてって――どれだけ心配したか。どれだけ不安だったか。
「わっ、舞衣?大丈夫?」
「もう、颯太のバカぁ。ばかばかばか。どれだけ、心配したと思ってるのよぉ〜」
颯太の腕を掴んだまま、いきなりしゃがみ込んで泣きじゃくる私に、オロオロしながらも背中を擦って、ゴメンを繰り返す颯太。
「あれ、舞衣。もしかして風呂上り?」
「え。うん…」
「髪、濡れてる」
「ごめん。乾かす時間も、惜しくって」
「俺の、せいだよね?ごめん」
「そうよ。颯太のせいだからね。風邪ひいたら責任、とってよね」
「うん。そのつもりだから」
ん?なんか噛みあってないような、合ってるような。ま、いっか。
「舞衣。いい匂い」
「やだ、颯太。くすぐったい」
「俺、舞衣の匂い大好き」
深呼吸するみたいに、鼻で思いっきり息を吸う彼。流れていた涙はすっかり乾いて、そのくすぐったさに肩を窄める。
「舞衣」
「ん?」
「このまま、舞衣を連れて帰ってもいい?最初は、抱きしめるだけって思ってたんだ。けど、舞衣の匂い嗅いたら、舞衣が欲しくなった」
「…うん、いいよ」
「帰ったら、髪も乾かしてあげるね」
学生のころと変わらない、爽やかで優しい笑顔。私の大好きな、笑顔。
その日は、公園の裏に停めてあった颯太の車に乗って、独り暮らしをしているマンションに行くことになった。
部屋に入るなり、颯太は待ちきれない感じで私を抱きしめ、優しいキスを繰り返す。
足に力が入らなくなった頃、私の両足の膝裏に腕を通してお姫様抱っこをして寝室へ。
何時にも増して、情熱的な彼。なんだか初めて見た気がする。違う、かも。
バスケの試合をしている時の颯太は、いつも情熱的で真っ直ぐで最後まで諦めない。そのときの颯太と、少し似ているかもしれない。
「舞衣、愛してる」
「私も。颯太を愛してる」
何度もお互いの名前を呼びながらそしてときには、彼の背中に爪を立てながら、幸せの波に身を任せて、濃厚で情熱的な一夜を過ごした。
そして、心地よい微睡の中で彼の腕に抱かれながら、少しだけ話をしていた。
「舞衣の匂いって、まるで媚薬みたい」
「びやく?」
「そう。ずっと、離したくなくなるし、ずっと触れていたい」
「っ…」
「なぁ、舞衣。一緒にここで暮らさないか?」
「ん」
「…舞衣、起きてる?」
「…」
すーすーと寝息を立てて幸せそうな顔をして寝ている。
そんな姿に、颯太はクスッと笑みを浮かべながら舞衣の頭を撫で、kissを1つ落とした。
「舞衣、好きだよ。これまでもこれからも、ずっと」