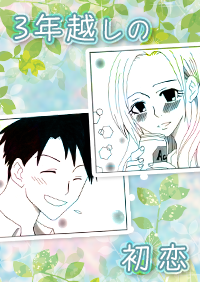女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
小説サイト投稿作品54 「キスしたくなる唇 後編」
「キスしたくなる唇 後編」
〜LC編集部のおすすめポイント〜
街頭アンケートの仕事中、千秋が再会したのはハトコで人気モデルの怜央。
彼に誘われて、ひとり暮らしをしているという彼のマンションに行くことになったけれど…?
10種類の唇の写真の中で、千秋が目に留まった写真。
それは、彼女のハトコであり、人気のモデル・怜央の唇で…?
ひとり暮らしの男性の部屋に誘われる…。そんなシチュエーションにドキドキです。
千秋の片思いの行方も気になります♪ハトコ同士の2人、今後の展開に注目です!
怜央Side:怜央の部屋
逢いたいと思っていた人が目の前にいる。しかもめちゃくちゃ疲れた顔をして。
駅近くの服屋で頼んでいた服を受け取った帰り、俺は千秋さんを見つけた。
さっき、千秋さんの唇に良く似たアンジュの唇を見てから無性に逢いたくなっていたから、テンションが上がる。
千秋さんは行き交う人を呼び止め、話をしている。俺は周りを確認してから、千秋さんの元へ足早に近づいた。
この出会いを無駄にしてはいけないと俺は行動に移し、うまく2人で食事をするところまでこぎつけた。
先に実家を出たのは千秋さんで、たまにしか会えなくなった。
俺も去年、一人暮らしを始めた矢先、ファンの子に自宅がバレて引っ越しをするはめになる。
今のマンションは原宿駅から少し歩くが、頻繁に仕事で使うスタジオは近いし、大学に通うのにも不便はない。
なによりもこの機会に恵まれたことを神様に感謝したいくらいだ。近々、千秋さんに電話をして食事に誘いたいと思っていた。
「着いたよ」
辺りをキョロキョロしながら歩く千秋さんは立ち止まり、マンションの外観を見上げる。
「いいところに住んでいるね。さすが売れっ子モデル」
「マネージャーに探してもらったんだ。以前のところはとてもじゃないけど女の子を呼んだらひかれそうなくらいのぼろ屋だったよ」
玄関に入り、オートロック式のパネルに鍵を差し込むと、ガラスのドアが開く。
エレベーターホールでエレベーターを待つあいだ、千秋さんが買ってきてくれたハンバーガーとポテトの匂いが漂ってくる。
キィ…
「どうぞ、入って」
「…お邪魔します」
千秋さんは玄関を入ると、あるものを見ている。視線はベッドだ。
「意外と狭いでしょ?2DKなんだけど、一部屋はアトリエに使っているからここにしかベッドが置けないんだ」
2DKの部屋で、玄関を開けると目に入るのはブルーで統一されたセミダブルのベッドだ。
普通のワンルームマンションよりは広いが、大きな家具のせいで狭く感じるだろう。
「わたしの部屋よりも広いよ」
「そうなんだ。そこへ座ってて。部屋すぐに暖かくなるから」
2月になったばかりで雪でも振りそうなくらいに外は寒かった。
千秋さんはローテーブルそばの2人掛けのソファに座ったが、すぐに立ち上がる。
「あ、怜央。手を洗いたいんだけど」
「そこのドアの向こうが洗面所。勝手にどうぞ」
千秋さんは示したドアの中へ入って行った。うがいをしている音が聞こえてくる。それから戻ってくると、ローテーブルの上に買ってきたものを出し始めた。
俺はお湯を沸かして、インスタントコーヒーを淹れている。飲み物は付いていたが、ずっと外にいた千秋さんには温かいものが必要だろう。
千秋さんのコーヒーの好みは熟知している。牛乳のたっぷり入ったカフェオレ。
冷蔵庫にあった賞味期限切れ近しの牛乳をマグカップに淹れてレンジで温める作業をしていると、千秋さんが本棚をじっと見ていることに気づく。変な本、置いてなかったよな?
そんなことを考えていると、千秋さんは本棚から1冊取り出した。
「これ、懐かしいね」
キッチンにいる俺に見せたのは芥川龍之介の「蜘蛛の糸」だ。中学の頃、夏休みの読書感想文を出した課題の本。
この話はたまに読み返したくなる本で、実家を出たときも持ってきた。
「意外と難しい本があるんだね。マンガばかりだと思ってた」
俺の青春時代を知っている千秋さん。
「千秋さん、俺はもうあの頃の俺じゃないから」
2つのマグカップを持ってローテーブルに置くとソファに腰をかける。
「そうだよね」
千秋さんは「蜘蛛の糸」を本棚に戻し、俺の横に座る。2人で並んだ状態。
しかも、女性2人だったらゆったりと座れるソファも、俺のせいで腕が触れ合うくらい密着している。
千秋さんの顔を見ると、戸惑っている表情だ。
「ごめん。俺、あっちに座ろうか?」
「えっ!?いいのっ!大丈夫。わたしの方こそ、ごめん」
なぜか千秋さんは顔を真っ赤にして謝った。
千秋Side:暴れる心臓
怜央の部屋に、とうとう来ちゃった!
玄関を入ってまず目に入ったベッドに視線が釘付けになってしまった。
25歳の大人の女だけど、一人暮らしの男性の部屋に入るのは初めて。
いくら小さい頃から一緒に過ごしていた怜央でも、今日は唇をずっと見ていたせいか意識してしまっている。
胸の鼓動を落ち着かせるために、洗面所へ行った。 洗面台に男物の化粧品に整髪料などが置かれている。
歯ブラシは1本。女の子を匂わすものがなくて、わたしは心から安堵した。
リビングに戻ると、怜央はキッチンでマグカップを用意していた。
コーヒーを淹れている怜央はカッコよくて…見ているだけで、心臓がドキドキしてくる。
心臓!静まれ!暴れる心臓は復活し、もう一度落ち着かせるために目についた本棚に近づいた。
懐かしい…。本棚から1冊抜いたのは芥川龍之介の「蜘蛛の糸」。実はこの本はわたしがあげたもの。
中学の夏休み、課題図書100選のプリントを読んでいた怜央に「この本ならあるよ」と言ってあげた。
ずっと持ってくれていたなんて…。ましてやここは実家ではない。
持っていてくれた嬉しさで顔がにやけてしまいそうだ。それを隠したくて
「意外と難しい本があるんだね。マンガばかりだと思ってた」
と言うと、怜央は写真に撮りたいくらいの憂いのある笑みを浮かべた。
「千秋さん、俺はもうあの頃の俺じゃないから」
怜央にしてみれば特に意味のない言葉だったのだろうけれど、わたしを困惑させるには十分な言葉だった。
わたしが好きなカフェオレを持って来てくれた怜央はソファに腰を掛ける。
無意識に隣に座ると、思ったよりソファは狭く怜央の腕に当たってしまった。
怜央も一瞬戸惑ったみたいで、別の場所に座ろうかと腰を上げる。
「えっ!?いいのっ!大丈夫。わたしの方こそ、ごめん」
すぐ近くの怜央はきれいな顔の造りの細部まで見える。
部屋に戻ってから、怜央は黒縁のメガネを外していた。
だから、弧を描く眉や涼しげな目元、少しアンバランスな唇をまじまじと見てしまって、はずかしくなり顔が熱くなった。
「食べよう?」
わたしは取り繕うようにテーブルのハンバーガーを1つ取って怜央に渡す。
「ありがとう。いただきます」
腰を落ち着けた怜央はハンバーガーの包みを開けて大きな口でパクリ。
美味しそうに食べる怜央から目を離し、わたしもハンバーガーの包みを開けた。
食べながら両親たちの話や、怜央の仕事の話を聞いていた。
「あの仕事、いつまでなの?」
「路上アンケートのこと? あと3日」
「で、サクサク進んだの?」
「それがまだ35、あ!怜央が答えてくれたから36人。ノルマはあと164人」
アンケートのことを考えると、気が重くなる。
「手伝おうか?クラブに行けばすぐに終わると思うけど?」
「だ、だめだよ」
嬉しかったけれど、怜央に迷惑をかけてしまいそうだ。
「どうして?」
断るわたしに首を傾げるようにして聞いてくる。
「そういうところでアンケートは取りたくないの」
「千秋さんは真面目なんだな」
怜央は大きなハンバーガーを3つ食べきった。わたしはひとつを食べ終わったところ。
お腹が空いているのに、怜央がすぐそばにいるせいで意識してしまい咀嚼するのにも時間がかかった。
まったくどうしちゃったのよ。怜央に変な風に思われないうちに帰った方がよさそう。
「怜央、も――」
もう帰ると言おうとしたとき、怜央の親指がわたしの唇に触れた。
怜央Side:キスしていい?
「ソースが付いてる」
それは千秋さんの唇に触れる口実。たしかにほんの少し付いていたが。今の千秋さんは化粧がすっかり落ちてしまっている。
それなのに、唇はきれいなベビーピンク色。
「えっ」
固まったように俺の指に拭かれているのが、可愛い。
「あ、ありがとう。寒さで荒れちゃったから恥ずかしい」
ふと、仕事で彼女にプレゼントしてくださいと、リップグロスをもらったことを思い出す。
俺は立ち上がると。チェストからグロスを持ってきた。
「仕事でもらったんだ。千秋さん、使ってよ」
手渡すと千秋さんはキョトンとした顔になる。
「ありがとう。でも、彼女にあげればいいのに」
「彼女がいないから千秋さんにあげるんだよ。保湿効果もあるみたいだからつけてみれば?」
「うん。つけてみるね」
千秋さんはバッグから化粧ポーチを出して、小さな鏡を出した。
「思ったより赤いね」
千秋さんの唇がいきいきとした表情を作る。艶やかな唇。鏡を見ながら、千秋さんはグロスをなじませるように唇を動かす。
「とてもきれいな色。できる女みたいでしょ?」
俺を見て、艶めく唇でにっこり笑う。
「それより、キスしたくなる唇だね」
「えっ…?」
驚く顔がまた可愛い。
「キスしたくなる唇って言ったんだよ」
「じょ、冗談言わないで」
「本当にそう思っているんだ。キスしていい?」
モデルで磨いた表情で、千秋さんを見つめた。
千秋Side:キスしたくなる唇
「ソースが付いている」って…怜央の親指が唇に触れてびっくりした。
そして、更にびっくりする。仕事でもらったグロスをくれた怜央は「キスしたくなる唇」だと言った。
からかっているの?
ハトコで5歳差。そんな垣根を越えて、わたしもキスして欲しいと思ってしまった。怜央の唇をついみてしまう。
今日のアンケート、女性20人中9人は怜央の唇が好みだった。そんな理想の唇がわたしにキスしたいって…。
頭がぼうっとして、思考能力が停止しそう。
「本当にそう思っているんだ。キスしていい?」
全てのパーツが整った顔で見つめられ…わたしは…。
「千秋さん?」
怜央は一時的な戯れをしたいのかもしれない。だけど、わたしはこのチャンスを逃したくなかった。
小さく深呼吸すると、ゆっくり目を閉じて誘うように顔を少し近づけた。怜央の唇がふんわりと下りてくる。
あ…こんなにやさしいキスを怜央はするんだ。
そう思ったのもつかの間、ふんわりと怜央の唇が触れたのち、啄むように何度も重ねてくる。
「んっ…」
気持ちよくてわたしの口から甘い声が。
「千秋さん、好きだよ」
ん?今、なんて言ったの?怜央の唇に翻弄されているわたしは物事をいいように聞き間違えたの?
「ん…怜央…今…」
わたしの口内を探っていた怜央は動きを止める。
「前から好きだったよ。俺の恋人になってくれる?」
「本気?ハトコだし、5歳も上だよ?」
「そんなのわかり過ぎるほどわかっているよ。いつも千秋さんを想っていた。
今までは年下だからと縛られて行動も出来なかったけれど、稼げるようになったし、もう我慢できなくなったんだ」
「わたしに彼氏がいたら?」
「いたら?でしょ?千秋さんのことはちゃんと情報入ってるから。恋人はいない」
「怜央…」
本当になにかのドッキリじゃないかと思った。怜央がずっと想っていてくれたなんて…。
「怜央、わたしも好きだったの」
わたしの告白に怜央は嬉しそうに笑う。
「俺たち、遠回りしていたね」
「そうみたい」
瞳を合わせ、クスリと笑みがこぼれる。
「じつはね?あのフリップに怜央の唇が載っているの。やっぱり一番人気だった」
「俺の唇が?」
「本音を話すと、その唇を見てからずっと意識しっぱなしだったの」
正直に話すと、恥ずかしくて目を伏せる。怜央の指がわたしの頬を撫でるように触れてから上を向かされて。
怜央の唇が重なり…
とろけるような甘いキスを落としてくれた。