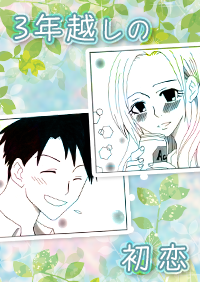女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
小説サイト投稿作品56 「大嫌いな唇 前編」
「大嫌いな唇 前編」
〜LC編集部のおすすめポイント〜
「エロイ唇」のせいで、女性には疎まれ、男性には好奇の目で見られてきた綾。
彼女にとってその唇はコンプレックスであり、大嫌いなものだった。
そんな中、男性の中では珍しく普通に、むしろ素っ気なく自分と接する村山課長と出会い…
他人には羨ましがられようと、自分にとってはコンプレックスなものだってありますよね。
今回は、そんな気持ちに焦点を当てたお話です。
こんな唇、いらない
「綾の唇って、無駄にエロイよね」
昼下がりのオフィスで、同期の浅野久美子がなんの前触れもなくそんなことを言い出した。
その言葉に、口に運ぼうとしていたサンドイッチを持つ私の手は、すっかりと止まってしまった。
「…そんな真面目に言わないでくれる?…知っているでしょ?こんな唇、大嫌いだって」
人には誰にだってひとつくらいコンプレックスはあるはず。
私、東條綾にとってのコンプレックスは、さっき久美子が言っていたように『無駄にエロイ唇』。
ぷっくりと厚みがあり、弾力があって、口紅がいらないほど赤みを多く含んでいる私の唇。
そして唇のすぐ右下には小さなほくろがひとつあって、それがまた“エロイ”を強調しちゃっている。
「なんでよ、私には綾のその唇が羨ましくて仕方ないんだけど」
「冗談じゃない!」
久美子の言葉に、ここはオフィスだということを忘れて、思わず大きな声を出してしまった。
「ちょっと綾!」
「…ごめん」
昼下がりのオフィスには、私たちと同じように業務から解放され、リラックスして食事をとる同僚がたくさんいて、一気に注目を浴びてしまった。
身を小さくして、どうにか視線から逃れられるようにしてみるものの、そんな視線なんて一瞬だけで、すぐにいつもの昼下がりのオフィスに戻る。
「もー!綾ってば本当にやめてよね?ただでなくても、新人の私たちには肩身の狭い場所なんだから!」
「…分かってるってば」
大学を卒業して今の会社に入社した。
有名な食品メーカーの製造・販売をしている我が社は、他人に勤めていることを話したら、羨ましがられるほどの大手。
内定を貰ったときは本当に嬉しくて嬉しくて堪らなかったけど、実際に勤務して半年。
これが意外に想像していたより辛かったりする。
学生時代にはなかった厳しい上下関係。そして久美子と一緒に配属された、販売促進部での手荒い歓迎…。
女はきっと年を重ねるごとにひねくれていくようで、若い私たちは先輩から目の敵にされている。
…特に私が。
「でもさ、本当にこんな唇なんていらないのよね」
溜息を漏らしつつ、ついいつもの愚痴をこぼしてしまう。
「その唇のせいで、男運がなかったから?」
「そう」
幼い頃は、他のみんなより少し厚い唇を見て、男子達に“たらこ唇”って言われてはバカにされた。中学から高校にかけては、この唇がやたら男子たちの気を引いてしまったようで、 “キスしたい女子ナンバーワン”に何度も選ばれていたことを、風の噂で聞いた。
極めつけは、高校二年のとき。
いきなり怖い三年の先輩に呼び出され『誘惑してんじゃねぇよ!』と、いきなり暴言を吐かれたことがあった。
全く身に覚えのない言葉に言われるがままだったけど、あとで事情を知る友達に聞いたら、
なんでも三年のアイドル的先輩が、私の唇にそそられる…なんて言っていたようで、
それを聞いたアイドル先輩のファンが、私に牽制してきたらしい。
そんな中でも高校三年のときには、初めての彼氏ができた。
初めて同じクラスになって、雰囲気がいいなって気になってて、つい何度も彼を見つめちゃってたんだよね。
そうしたら、彼から告白してくれて。嬉しくて幸せな日々だった。もちろん初めてのキスもエッチも、彼と体験した。
……なのに、聞いちゃったんだよね。彼が友達に私の唇の感触や身体のことも全部話しているのを。
そして片想い中、私が彼を見つめていたから、彼は絶対俺のこと好きだから、イケるって思って告白したって。
あの唇を味わえる男になって自慢したいがための告白だったって。…彼は最初から、私のことなんて好きじゃなかった。
すぐに彼には私から別れを切り出した。あの時は本当に悲しくて、辛かった。
…大学生になっても私を見る男の目は変わらなかった。
それでも本当の私を好きになってくれる人が必ずいるって信じては、コンパや合コンに参加したりした。
一人だけ付き合った人がいたけど、究極の唇フェチの人で、付き合い始めてそれに気づき、すぐに別れてしまった。
だって彼は、会うたびにすぐキスを求めてきては、話をすることもなく、ひたすらキスしている人だったから。
……それからは、誰とも付き合っていない。だって誰も本当の私を見てくれないんだもの。
こうやってまた昔のことを思い出すと、ほら。自然と大きな溜息が漏れてしまう。
「私に綾のそのエロイ唇があったなら、気になる男をかたっぱしから誘惑しちゃうけどね」
「本当にできるならぜひ久美子の唇と交換してあげたいくらいよ」
私はこんな唇なんていらない。
“エロイ唇”なんて、大嫌いよ……。
誘惑したい彼
「促進部の東條さんの唇ってさ、ヤバくね?」
「あっ、お前も?俺、許されるならずっとキスしていたいんだけど」
げっ!!
十階建てのオフィス。上司に頼まれ、二階下の営業部へ書類を届けに行った帰り。
聞こえてきたのは、喫煙所で一服していた男性社員の声。その話の内容に、思わず立ち止まり隠れてしまった。
「あのほくろがまた色気を増してるよな」
「分かる!男だったら、誰だってあの唇に一度はキスしたいって思うだろ」
「その先も、な」
そう言って笑う男性社員たち。耳を塞ぎたくなるような言葉の数々に、耳よりも唇を両手で隠してしまった。
本当にもう嫌!!だからこんな唇なんて大嫌いなのよ!!
「もー、本当にやだ!!」
「まーまー、落ち着いて」
入社して十ヶ月が過ぎた。
仕事にもすっかり慣れてきて、他の部署にはどんな人がいるのか、とか段々と分かってきたこの頃。
それは反対に新入社員の私の存在も、他の部署の人たちに知られてきたということでもある。
すると必然的にさっきのような話を耳にすることが、ここ最近増えてきてしまった。
「本当にやだ。あの人たち、私の唇で下ネタ話していたのよ?勤務中に!!」
あのあと彼等が話していた内容を思い出すと、食欲も失せてしまう。
「えー、どんな話!?」
それなのに久美子ってば私の気持ちも知らないで、興味津々で聞いてきた。
そんなに知りたいなら聞かせてやろうじゃないの!身体を前に屈め、小声でそっと言ってやった。
「私のこの唇で、イカせてほしいって」
「…は?」
案の定、呆気に取られる久美子。
「抜いてもらっても、キリがなさそうだよなって笑いながら話していたのよっ!」
吐き捨てるように言うと、久美子は急に大きな声を出して笑い出した。
「あっはははは!!さすがは綾の唇!そんなネタにもされるとか、ウケる!」
「なっ!全然面白くないわよ!!」
本当に失礼しちゃう!私の立場になってほしい。最悪よ。自分が下ネタに使われるなんて!
すっかり食べられなくなってしまったお弁当。そっと蓋を閉める。
「あー…久々に笑った」
「それはよかったわね」
なにがそんなに面白かったのか、涙を拭う久美子を冷めた目で見てやった。
「だけどさ、綾。世の中そんな男ばかりじゃないって最近気付いたんでしょ?」
久美子の言葉に思わずドキッとしてしまった。
「…そりゃ、まぁ…。そう、かな?」
そしてつい口ごもってしまう。そんな私を久美子は、何か言いたそうにニヤニヤしながら見つめる。
「他の男とは違うわよね?あの村山課長は」
そう。
久美子が言う“村山課長”。三ヶ月ほど前、我が販売促進部の新課長として販売部からきた人。
エリート中のエリートで、三十歳という若さで会社始まって以来のスピード出世を果たした人。
推定身長、百七十五センチ。黒髪の短髪はいつもワックスで無造作にセットされている。
少し太くて、だけど綺麗に整えられた眉。ブランドものの眼鏡の奥に見えるのは、切れ長の瞳。
そして私から見たら、羨ましくて仕方ないほどの、薄いけど形の良い唇。
赴任当時から女性社員のハートを鷲掴みにした村山課長。
もちろん私もその女性社員の中の一人だったりする。
だって村山課長は、他の男性と違うから。私をいやらしい目で一切見ない。むしろ、嫌われているのかもしれない。
話をするときだって、一切私を見ることはないし。
だけど逆にそれは私にとって新鮮で、つい気になってしまう原因のひとつだったりする。
「しかしまぁ、自分に冷たい男に惹かれるなんて…。綾、あんた究極のドMなんじゃないの?」
「冗談!そんなことない!…ただ、嬉しいの」
「えっ、嬉しい?」
不思議そうに私を見る久美子。だってそうでしょ?
「…私のこと、いやらしい目で見ないし。…村山課長なら、外見だけで人を好きになったりしなそうだから」
出会いたい、本当の私を好きになってくれる人に。
「そりゃそうかもしれないけど、多少は好きになってもらえるオプションがあった方が、有利じゃない?」
「それはそうかもしれないけど…」
この唇で誘惑できるなら、したい。
だけど彼には、私のこの唇では誘惑できそうにもない。だから気になる存在なんだけど。
「東條さん、ここ間違ってる」
「すっ、すみません!」
午後の勤務中。
村山課長に呼ばれドキッとしながらも向かうと、いつものように一切私を見ることなく、書類のミスを指摘してくる。
「新入社員だからって許される時期ではない。もうこういったミスは一切しないように」
「…はい」
ズキンと痛む胸を押さえながらも、「失礼します」と小さく一礼して、書類片手に自分の席に戻る。
「…綾ー、大丈夫?」
そんな私を心配そうに、久美子は声をかけてきてくれた。
「うん、大丈夫。…ありがとう」
久美子に心配かけたくなくて、笑顔で答える。そしてさっき注意された書類を作り直す。
自分が悪いんだから仕方ない。怒られても仕方ない…。
そうは分かっていても、上司と部下の関係になって数ヵ月も経つのに、一度も私のことを見てくれない。
この現実が、今の私にはちょっぴり切ない…。別にこんな唇なんていらない。
大嫌い。
…だけど、彼が私を見てくれるなら。この大嫌いな唇を使って、彼を誘惑したい――。
奪われた心
「東條、まじでムカつくんだけど!」
「あんな、たらこ唇のどこがそんなにいいわけ!?」
突然聞こえてきた自分の悪口に、お茶を淹れる手が止まってしまった。
それと同時に見つからないよう、今いる給湯室のさらに奥へと身を隠す。
聞こえてきたのは、給湯室の隣にあるコピー室から。解放感ありまくりな販売促進部のオフィスには、扉がついていなかった。
そして壁も薄い。きっと先輩たちは誰にも聞かれないよう、小声で話しているようだけど…。
残念ながら全て筒抜けです。隣の給湯室にいる私には。入社当時から、なんとなく気付いてはいた。先輩には好かれていないなって。久美子よりもずっと嫌われているって。
「男に媚びうっちゃって、見てて腹が立つ!」
「絶対あれ計算でやってるよね。『私、男には一切興味ないんですー』アピール!!」
…そんな計算ができるほど器用じゃないんだけど、な。
だけど先輩たちの目にはそう写ってしまうのなら、今後は気を付けよう。
それにしてもどうしたらいいものか。先輩たちが早くコピー室から出て行ってくれないと、お茶を運べない。
今私がここから出て行ったらさすがにまずいよね。『盗み聞きなんて最低!』とかまた言われてしまいそう。
そう思うと、つい大きな溜息が漏れてしまった。十時と三時のお茶汲みは、新入社員の仕事と決まっている。
販売促進部の新入社員は、私と久美子だけ。入社当時から十時に出すのは久美子で、三時に出すのは私と決めて行っている。
…だから気付いてほしいんだけどな。私がここにいることを。
いまだに隣のコピー室からは、日頃の鬱憤を晴らすように私の悪口のオンパレードが聞こえてくる。
この歳になると、こんなことに慣れてしまっていた。慣れた、なんてちょっぴり自分で言ってて悲しくなっちゃうけど。
とりあえずいつでも出て行けるように、と思い、残りのお茶をそっと淹れた。
隣の部屋にいる先輩達に、私の存在を気付かれないように。
そしてお茶を淹れ終わったとき、タイミングよく聞こえてきた声に、身体がオーバーにビクッと反応してしまった。
「東條、お茶汲みにどれだけ時間をかけているんだ?」
その声に直ぐ様振り返ると、コピー室と給湯室のちょうどあいだに立っていたのは、腕を組んで不機嫌そうな村山課長だった。
「村山課長っ!すっ、すみません!」
あれほど隣にいる先輩達に聞かれないように、って思っていたのに、突然現れた村山課長につい大きな声が出てしまった。
「俺は無駄に時間を使う奴が嫌いなんだ」
やっぱりいつもみたいに、私を一切見ることなくそう冷たく言い放つ村山課長に、ズキッと胸が痛くなる。
「すみません…」
『嫌い』って言葉だけが、頭に残ってしまっていて、辛くて。村山課長の顔が見れない。
すると聞こえてきたのは、小さく「お疲れ様です」と口々にしては走り去っていく足音。
そしてなぜか私の方へ向かって近づいてくる足音。
「いつも我慢していないで、辛いときは上司を頼るように」
え…?
突然聞こえてきた声。
すぐに顔を上げると、目の前には可愛い我が社のヒット商品のキャラクターのストラップ。
さっきの言葉も、この可愛いストラップを差し出してくれているのも、相変わらず私を見ない村山課長だった。
「…貰ったんだ。やる」
ぶっきらぼうな言葉。
「あっ、ありがとうございます…」
戸惑いながらも村山課長からストラップを受け取ると、何事もなかったかのように、村山課長は給湯室から出て行ってしまった。
そんな村山課長の後ろ姿を見つめながらも、呆然としてしまっていた。
突然すぎてさっきは全然理解できなかったけど、…ちょっと待って。
一気にボンッと音を立てて熱くなる私の身体。
さっきのって、絶対私を助けてくれたんだよね?それに頼れって言ってくれたよね…?
村山課長の言葉を思い出すと、キューっと締め付けられて苦しくなる胸。
もうダメ。一発でやられてしまった。私の心は完全に村山課長に奪われてしまった。
好き――。
一切私を見てくれない彼が。あんな優しい言葉をかけてくれた彼が。
誰もいない給湯室で、さっき村山課長に貰ったストラップを、ギュッと握り締めていた。
大嫌いな唇 後編へつづく…