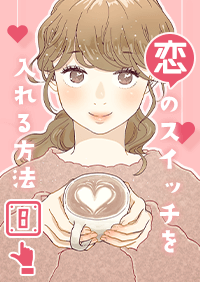女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
小説サイト投稿作品67 「濡れた唇の誘惑 前編」
「濡れた唇の誘惑 前編」
〜LC編集部のおすすめポイント〜
職場で憧れの藤野さんに片想いをする優奈のお話です。
バレンタインデーというイベントや尊敬している先輩の安永さんとの関わりで
ウェディングプランナーとして成長していく優奈を、つい応援したくなってしまいます!
ホワイトデーの夜、奇跡が起きる?!優奈の想いは実るのか?気になる藤野さんの心中は?
長編ですがどんどん読めてしまう作品です。感情移入できるポイントも多く、読みやすいですよ♪
明日はバレンタインデー
今日は忙しい日だ。午前中にひとつ挙式を済ませ、それからすぐにナイトウェディングの準備に入った。
本来なら、午後に出勤してナイトウェディングだけ担当すればよかったのだけど、午前の披露宴は会場の定員ギリギリの招待客の多さで、ひとりでもスタッフが多い方がいいに違いないと思った私は自主的に出勤していた。
私がここ「ローズパレス」でウェディングプランナーとして働き始めてから、もう6年が経つ。
後輩もたくさんできたけど、まだまだ足りないところだらけだ。
「新井さん、悪いけど、こっち手伝って」
「はい」
私を呼んだのはひとつ先輩の藤野さん。
藤野さんは、「ローズパレス」では数少ない男性プランナーのひとりだ。
背は160センチある私より15センチほど高く、割とがっちりした体つき。それなのに顔は小さくて、まとまっている。長いまつげが印象的だ。
そして、少しくせのある髪をムースで上手くまとめていて、清潔感がある。
以前にチーフプランナーをしていた桐生さんに憧れて、黙々と仕事をこなしていた彼は私達後輩プランナーの信頼も厚い。
桐生さんは1年ほど前に、避暑地にある系列の教会「フォレストガーデン」に支配人として行ってしまったけど、 藤野さんは今でも桐生さんが大切にしていたお客様へのきめ細かい心遣いを決して忘れていないようにみえる。
「優奈。ごめん、こっちも」
現在のチーフの北川さんは、サバサバした性格の女性だけど、常に全体に目が行き届いていて的確な指示のできる人だ。
「北川さん、間に合うでしようか?」
「間に合わせるの。大丈夫、ここのスタッフならできる」
北川さんは、常に私たちのことを褒めることを忘れなかった。
「テーブルセッティング終わりました」
「ありがと。藤野が大変そうなの。教会の方に行ってくれる?」
私は北川さんの指示で、藤野さんのもとに駆け付けた。
さっき引き出物の運び入れを一緒にした彼は、今度は教会のセッティングをしている。
「手伝います」
「サンキュ、助かった」
椅子に生花を飾っていた彼は、額に汗がにじんでいる。
「あの、これどうぞ」
「おぉ、ありがと」
私がハンカチをそっと渡すと、彼はにっこり笑ってくれた。
北川さんの言うとおり、準備は時間内に整った。
最後に北川さんがチェックを入れ「OK」と口にすると、スタッフ全員から安堵の溜息が漏れた。
「本番はこれから。皆、よろしく」
北川さんの一言で再び気持ちが引き締まる。
今日メインで担当するのは藤野さんだ。私たちは藤野さんの指示に従ってサポートする。
「新井さん、よろしく」
「はい。こちらこそ」
今回は藤野さんに言われて、新婦の介添えを任されていた。
新婦の介添えは何度も経験したことがあるけれど、未だに挙式の張りつめた緊張感でプレッシャーに押しつぶされそうになる。
新郎新婦にとっては、挙式は一生に一度のものだから、決して失敗は許されないのだ。
プレッシャーを背負いながら、それでも決して笑顔を絶やさず、新婦が困らないように精一杯の努力をした。
本命の彼
「お疲れさま」
すべてが滞りなく終わると、ホッと気が抜ける。
新郎新婦、そして招待客に満足してもらえたかどうか気になるところだけど、やるべきことはすべてできたと思う。
「藤野さん、お疲れ様でした。新婦様、お綺麗でしたね」
「そうだね。新井さんが常に新婦に気を配ってくれたおかげだよ」
「いえ、私はなにも」
新婦の介添えは、新婦が歩くたびにベールの向きを直したり、涙で化粧が崩れてしまったときにさっと直しに行ったり…常に気を張っていなくてはならない仕事だ。
だから終わったときの疲労感は、他のサポートの仕事の比ではない。
「本当にありがとう。新井さんの担当のときは、俺も頑張らないと」
「はい。お願いします」
藤野さんの笑顔に癒される。仕事中にお客様に見せる笑顔とはなんとなく違う柔らかい笑顔は、私の癒しだ。
「優奈、お疲れ様。今日も完璧」
「いえ、ありがとうございます」
北川さんに褒められて、うれしい。
私がこうして褒められるようになったのは、ローズパレスに来てからずっと指導してくれた安永さんというプランナーのおかげだ。
安永さんは半年前に電撃的にここを辞め、桐生さんを追いかけて行き、そのまま奥さんになってしまった。
ローズパレスにいたときは、ふたりともしばしば言い争いをしていて、結婚の話を聞いたときはとても驚いた。
だけど、仕事に対するストイックな姿勢とか、決して笑顔を絶やさないところとか…ふたりにはとても共通点が多く、すごくお似合いだと思った。
そして、あの言い争いもふたりの照れ隠しだったのだろうと想像している。
私は安永さんに憧れて、彼女から色々なものを盗んだ。
仕事のやり方はもちろん、メイクも髪形も、制服の着こなし方も。特に控えめでナチュラルだけど、上品さが漂うようなメイクは、私のお手本だった。
安永さんは「メイクさんに教えてもらいなよ」と笑ったけれど、彼女の使っている化粧品と同じものをいくつもそろえた。
一番気に入っているのは、リップグロスだ。
安永さんの使っているものは、グロスにしてはマットな付け心地で、唇に乗せると上品に仕上がる。
「優奈は明日は、遅番ね。疲れたからゆっくり休みなさい。あっ、そうもいかないか。作らないといけないわね」
作る?私が首をかしげると、北川さんは「もしかして忘れてる?」と笑う。
「明日……あっ!」
「そう。チョコ作るんでしょ? 本命は、藤野君辺りかしら」
「いえっ、本命なんて…いません」
今日は2月13日。明日はバレンタインデーだ。
突然本命だなんて言われた私は、胸がドクンと鳴るのを抑えられなかった。北川さんの観察力にはあっぱれだ。
確かに……私は藤野さんに恋している。
ひとつしか歳が違わないのに、私よりずっとしっかりしていて、常に向上心を持ち合わせている。そして、彼が仕事を終えたときに見せる笑顔は、本当に素敵だ。
だけど、彼女になりたいなんて、そんな大それたことを考えたことはない。
だってあれほど素敵な人に、私なんかじゃ釣り合わないと思うのだ。
それでも、北川さんの一言で少し心が動いた。
ガトーショコラの秘密
次の日、朝起きるとすぐに、キッチンに立った。
昨日は帰りが遅くなったけど、近くに24時間営業のスーパーがあるおかげで、チョコレートが手に入ったのだ。
なにを作ろうか迷いに迷って、ガトーショコラに決めた。生チョコやトリュフでは、帰りまでに溶けてしまうかもしれないと思ったからだ。
お菓子作りは、わりと得意な方だ。
それでも、好きな人に作るお菓子というのは特別で、いつもはいい加減な計量もしっかりした。ローズパレスの事務所には男性スタッフが総勢8名いる。圧倒的に女性の多い職場では、貴重な存在だ。
小さめのハート型ガトーショコラを8つ作った私は、その出来に満足した。
こんなに集中してお菓子を作ったのは初めてだ。
藤野さんが本命だとはばれないように、どれにも“いつもありがとうございます”とメッセージをつけ、同じように包装すると、ローズパレスに向かった。
「お疲れ様です」
遅番は13時から。12時くらいに事務所に入ると、ガトーショコラをそれぞれのデスクにそっと置いておいた。
早番の人のほとんどが接客中だったし、なんだか面と向かって手渡すのも恥ずかしかったからだ。
だけど、同じようにスタッフルームのデスクの上にはチョコが山になっていた。
藤野さんの分を置くときだけは、ドキドキして手が震えた。
「好きです」
スタッフルームに誰もいないのを確認した私は、小さな声でささやいた。
一組のお客様を接客し終えると、14時を超えていた。
資料を抱えてスタッフルームに戻ると、そこには早番のはずの藤野さんの姿があった。
「あっ、お疲れ様です」
「お疲れ。新井さん、これ」
彼は私が作ったガトーショコラを掲げてみせる。
「あっ、あの…よろしければ」
「ありがとう。これ、手作りだろ?すごくうれしいよ」
「本当ですか!?」
思わず顔がほころんだ。彼に喜んでもらえたらと思って作ったのだ。
たとえ気持ちを伝えられなかったとしても、うれしい。
「新井さん、お菓子作るの、得意?」
「得意というか…好きです。あっ…いえ、あの…」
お菓子作りが”好き”と言っただけだけど、藤野さんの顔を見ながら発した言葉に、自分で動揺する。
まるで、‘あなたのことが好きです'と言ってしまったような錯覚に陥ってしまったから。
「すごいなぁ。大切に食べせてもらうよ」
「はい。そんなものでよければいつでも」
「ホントに?」
藤野さんは私が大好きな笑顔を、向けてくれた。
「それじゃ、今日はお先」
「はい。お疲れ様でした」
彼は私にお礼を言うと、すぐに帰っていった。
もしかして、私にお礼を言うために待っていてくれたんじゃないかって、淡い期待を抱いてしまう。
きっと偶然なのに、そんな気持ちになるのは、やっぱり恋の力なのかもしれない。
私は、私
この時期は挙式が特別多いというわけではないけれど、挙式が増える6月に向けての準備が忙しくなる。
相談に訪れるお客様も増えるし、衣装の試着も多い。
「新井さん」
「はい」
「ちょっと休みなよ」
朝から走り回っていた私に声をかけてくれたのは、藤野さんだった。
バレンタインのことがあってからなんだか恥ずかしくて、あれからふたりで話したのは初めてだ。
「いえ、でもまだ…」
「落ち着いて。まずはなにをすべきか整理しよう」
藤野さんに言われて冷静になった私は、とりあえずデスクに座って、今している仕事に順位をつけた。
「あっ…」
「どうかした?」
「いえ、冷静に考えると、まとめてできる仕事がたくさんありました」
こうして紙に書きだすだけで、頭まですっきりする。
「そうそう。新井さんは、一生懸命すぎてときどき周りが見えなくなっちゃってる。 プランナーは常に冷静に全体を見渡す力が必要なんだ。 それは式の時だけじゃなくて、準備の段階も。って、全部桐生さんの受け売りだけど」
クスクス笑う藤野さんは、私を優しく見つめる。
「ありがとうございます。私、ほんといつまで経っても安永さんみたいにはなれないな」
これでも頑張っているつもりなんだけど…現実はなかなか厳しい。
「ならなくていいんじゃない?」
「えっ?」
「安永さんのことは俺も尊敬してるけど、新井さんは、新井さんだよ。さぁ、もうひと踏ん張りしてくる」
藤野さんは意味深な言葉を残して、スタッフルームを出て行った。
私は、私…か。なんだか彼の言葉が胸に深く刻まれた。
藤野さんにアドバイスをもらってから、私は焦りすぎる自分のくせに気がついて、
時々頭を整理する時間を持つようになった。
そうすると、驚くほど仕事の効率が上がって、気持ちにも余裕ができた。
「あなたの成長を梓が見たら、喜ぶでしょうね」
「ありがとうございます」
北川さんから出たのは、最高の褒め言葉だ。安永さんは私の永遠の憧れだ。
どうしたって追いつけっこないけど、褒めてもらえるのはうれしい。
「梓、来週来るわよ」
「ホントですか!?」
「うん。ローズパレスと、フォレストガーデンが提携して新しい企画を始めるの。その打ち合わせに梓が来るって」
心躍った。フォレストガーデンは、桐生さんと安永さん夫婦が今働いている避暑地の教会だ。
桐生さんはフォレストガーデンに行ってしまってからも、何度かここにも顔を出したけど安永さんは初めてだ。
「楽しみです」
「そうね、私も」
それから、ますます安永さんを意識して働くようになった。こういうときは、彼女ならどうするだろう?なんていちいち考えたりもした。
そして…使い方は個人に任されている制服のスカーフも、安永さんがしていたように首元で結んでみたり、彼女と同じように長い髪をバナナクリップを使ってまとめていた。
安永さんの真似をすることで、自分も彼女に近づける気がしたのだ。
それから1週間後、安永さんがやって来た。
憧れの存在
「皆さん、お久しぶりです」
「安永さん!」
ローズパレスにいた頃からかわいらしい人だったけど、それに大人っぽさが加わって、女の私が見ても魅力的になっていたから驚いた。
髪はここにいたときと同じように緩いパーマがかかっているけれど、今日はお客様の前に出ないせいか、ハーフアップにしている。
メイクは……少し変わったかもしれない。
透き通るような白い肌は相変わらずだけど、チークの入れ方とか、アイラインのひき方とか…ちょっと違う気がする。
それと、一番違うと思ったのは唇だ。以前よりヌーディな感じに仕上がっている口元は、なんとなく色気を感じる。
「新人君たちは初めてね。以前ここで働いていた安永さんです。あっ、今は桐生さんね」
「いやだ北川さん。安永でいいですから」
優しい笑顔は、ここにいたときのままだ。
「彼女は、今、系列のフォレストガーデンでチーフプランナーをしてるわ」
「よろしくお願いします」
北川さんの紹介に合わせて、安永さんはぺこりと頭を下げた。
「優奈ちゃん、久しぶり。北川さんに聞いたわよ。もうすっかり一人前だって」
安永さんは私を見つけると、すぐに声をかけてくれた。
「いえ。安永さんみたいになりたいと思っても、なかなか」
「バカね。私はあなたに見えないところで、失敗ばかりしてたんだから」
そんなことはない。安永さんに助けられたプランナーは多いと思う。
「ほら、いつも怒られてたでしょ、あの人に」
それはきっと桐生さんのことをさしているのだろう。
桐生さんは安永さんにはとても厳しかったけど、それは彼女に期待していたからだと思う。
実際安永さんは、桐生さんの要求に応えるだけの行動力も決断力もあった。
「そういえば、ご結婚おめでとうございます。びっくりしましたよ」
「あはは、ありがとう。どうしてだか、そういうことになったわ」
照れながらも幸せそうな安永さんがうらやましい。
「安永さんの挙式、見てみたかったです」
ウェディングプランナーは何度も何度も挙式を経験する。
だけど、どれひとつとして同じものはなく、経験するたびに勉強になる。
「ダメよ。プロフェッショナルに観察されたら、ほころびがバレちゃうでしょ?」
安永さんに『プロフェッショナル』なんて言われるとは思っていなかった。だけど、純粋にうれしい。
そうはいっても、出席した北川さんが「今までで一番素敵だった」なんて溜息を洩らしていたから、おそらく想像以上の素晴らしさだったのだろう。
「安永さん、幸せそう」
「うん。まぁ、ね」
もしかしたら謙遜するかもしれないと思ったけど、彼女は清々しいほど幸せオーラを振りまいていた。
「優奈ちゃん、そろそろ結婚?」
「いえ、結婚どころか彼氏だっていません」
突然降りかかった話に驚きながら、大きく首を振る。
「えっ、まだ進展なしなの?」
「進展?」
「あっ…ううん。なんでもない」
安永さんは言葉を濁しながら、私の顔を覗き込む。
「あー、これ。あのグロスでしょ?」
「はい」
安永さんに教えてもらったグロスをずっと愛用している。もちろん、色も同じだ。
「これ、ちゃんと唇が潤うしいい匂いだし、言うことないけど、優奈ちゃんには地味じゃない?」
「そうですか?」
「そうそう。もうちょっと赤味が強いの使ってみたらどう?男が放っておかないわよ」
「まさか」
安永さんと同じグロスを使っているはずなのに、確かに私の方がぼやけた感じがする。
教えてもらった通り、リップライナーも使ってるのに。
「安永さん、グロス変えたんですか?」
「うんうん。私は常に進化してるの。メイクもそれに合わせて変えなくちゃ…なーんて」
クスクス笑う安永さんは、「冗談」と言いながら、再び私の顔を覗き込む。
「優奈ちゃん、もっと冒険してみなよ。私には私の似合う色があるし、優奈ちゃんは優奈ちゃんの色がある。あとは褒めてくれるオトコが欲しいわね」
「桐生さん、褒めてくれるんですか?」
「まさか。彼は絶対にそういうことは言わない。でもね…」
ふふふと笑った安永さんは、「またあとで」とスタッフルームを出ていった。
『優奈ちゃんは優奈ちゃんの色がある』か。似たようなことを藤野さんにも言われたな。
オトコ、か…。バレンタインにチョコを渡せただけでドキドキしている私には、告白なんてとても無理そうだ。
「梓、幸せ全開でしょ?」
「えっ?あはは。そうですね」
北川さんがクスクス笑いながら近づいてきた。
「桐生君も梓も、感情の表現が苦手だから、どうせ意地の張り合いをしてケンカしてるんだろうけど…お互いの言葉の裏にある感情には、ちゃんと気がついてるんだよね。まったく、面倒な夫婦よね」
『面倒な夫婦』って…。思わず笑ってしまう。
「さてと、梓に負けないようにチーフ業頑張りますか」
北川さんは大きく伸びをした後、スタッフルームを出て行った。
私の
「あのー」
休憩時間にメイク室を覗くと、メイクさんも手が空いていた。
「どうしたの?」
「私、安永さんにもっと赤味の強いリップ使ったら?って言われたんですけど…」
「そうね」
即答されて驚いていると、にっこり笑ったメイクさんは、私の手をとって鏡の前に座らせた。
「安永さんと同じグロス使ってるんですけど、なんか違うんです」
「それは当たり前よ」
メイクさんは大きな化粧ポーチを開いた。
「安永さんと新井さんの唇は、元々の色が違うの。安永さんはピンク色が強くて、新井さんは薄い。だから同じ色を乗せても、違って見えちゃう」
「そう、なんですか」
大きく頷いたメイクさんは「ちょっとごめんね」と言いながら、私のグロスをそっとふき取ると、私がいつも使っているリップライナーよりずっと赤味の濃いものでラインを取り始めた。
こんなに赤いと派手になってしまう。
接客業だし、あまり濃いメイクは困る…と思っていると、今度はショッキングピンクのグロスを取りだしたから慌てた。
「あの、休憩中なだけで、まだお仕事が…」
「いいから、任せて」
メイクさんは私の心配をよそに、グロスを唇の中央から手でポンポンと乗せていく。
しかもこのグロスは、いつも使っているものよりツヤツヤだ。
「あれ?」
出来上がった自分の唇を見て、不思議に思った。
いつもよりは唇の印象がはっきりしているけど、決して派手ではない。
「グロスのカラーは、見た目よりずっと薄付きなの。どう、これ?」
「素敵です!」
「新井さんはこの方が顔色もよく見えると思うよ。それに、このくらいの艶があった方が魅力的。チークももう少しオレンジ寄りの色の方が似合うかも」
安永さんが言っていた『私は私の似合う色がある』というのはこういうことを言うのだ。
それにしても、さすがプロだ。
こうやってお客様の”色”に合わせて、いつもメイクをしているに違いない。
それから、少しメイクの手直しをしてもらうと、なんだか明るいイメージに変身した。
そして、他のメイク方法についても教えてもらう。
口紅をつけたあと、真ん中だけグロスを乗せるというのも、唇がぷっくり見えることを知った。
シャドウの入れ方も、「安永さんとは目の形が全然違うんだから」と、私に合った方法を教えてもらった。
「はぁ、メイクって奥深いですね」
「そうね。だから楽しいの。新井さん、素材がいいんだから、それを殺さないメイクをしたらいいのよ。あなたが安永さんを素敵だと思うのは、多分彼女が自分に似合うメイクを知っているからなのよ」
なるほど…。
安永さんに似合うものが、誰にも似合うとは限らないんだ。
「だけど安永さん、桐生さんと結婚して、ますますきれいになったわよね」
「やっぱり、そう思いました?」
「うん。メイクの仕方も、前より腕を上げてる」
プロのメイクさんが言うのだから間違いない。安永さんは何事にも妥協を許さない人だ。
それは身だしなみについても同じで、だからこそ私は彼女のすべてに憧れているのだ。
「このグロス、もうこれだけしかないからあげる」
「いいんですか?」
「うんうん。これ、実は私の私物だったの。でも似合わなくて結局仕事に使ってた。似合う人がいてよかったわ」
メイクさんにつけてもらったグロスは、私の気持ちを前向きにした。