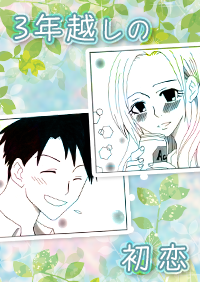女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
小説サイト投稿作品40 「最高のご褒美」
「最高のご褒美」
〜LC編集部のおすすめポイント〜
会社で理不尽な叱責を受けて落ち込む理香に上司である裕介が優しく声をかける。
そんな2人の恋の始まりは、仕事上でのトラブルがきっかけで…
社内恋愛の2人の甘い空気、憧れてしまいます…♪彼の男気ある告白のセリフにも感激です!ドキドキしたい大人向けの作品です。
理不尽な叱責
会社とは往々にして理不尽なことが起きる場所である。ましてや、上司が仕事のできない男であればなおのこと―。
「まったく、後輩の指導も大切な仕事なんだよ。君の指導が行き届いていないから、だからこういったミスが起こるんだろ?わかってるのか?」
「申し訳、ありません…」
皆のまえで叱責され、頭を下げて謝罪する。実際は叱責も何も明らかな言いがかり。
悔し涙をぐっとこらえて、唇をぎゅっと強く噛みしめる。
ここは企画営業部で、私が所属する第1グループのリーダーは典型的な仕事のできない困った上司。
部下の手柄は自分の手柄にするくせに、部下のミスは部下のミス。上司としての責任なんて決して取らない。いつも誰かに責任転嫁。
そして、今日の犠牲者はこの私…。後輩のミスは先輩である私の指導力不足である、と。
そもそも私はまったくその案件にかかわってもいないのに、たまたま席が隣で同じ女性社員という理由で。もう、わけがわからない…。
「何年目になる?いつまでも新人気分じゃ困るんだよ」
自分のデスクに呼びつけて声高に罵るのが上司のいつものやり方だ。わざと皆に聞こえるように、まるで見せしめみたいに。
上司としての威厳を見せているつもりか。あるいは、責任は自分にないと誇示しているのか。
毎日のようにグループ内の誰かしらが被害にあっている。
もはや状況も心情も暗黙のうちの了解だ。昨日の俺や、明日の私。わかっていないのは上司だけ。
おそらく、誰も私を責めてはいないし、誤解だってしていない。それはわかる、わかってる。
でもやっぱり、憐みの目でこちらを見る皆の視線が痛かった。
「以後は十分に気をつけるように」
「はい」
「この件については君が責任をもって処理すること。早急にだ。わかったならもう下がりなさい」
「はい。失礼いたします」
不本意ながら、もう一度だけ頭を下げる。この場から一刻も早く立ち去りたくて、私は俯き加減のまま化粧室へ足早に向かった。
すると…ちょうど部屋を出たところですれ違いざまに誰かにぶつかった。完全にこちらの前方不注意だ。
「あっ…す、すみません」
「いや、こちらは大丈夫。藤倉さんは?平気?」
その声にはっとして顔を上げると、第2グループのリーダー戸波さんだった。
タイミングが悪すぎる…。こんなひどい顔、見せたくなかったのに。
こんな、悔しさでみじめに歪んだ醜い顔。特に戸波さん…彼には見られたくはなかった。
「私、ちょっと急いでいて…不注意ですみません!」
恥ずかしくて、情けなくて、申し訳なくて、ぺこぺこ平謝り。そんな私の耳元で彼は囁いた。
「(本当に、大丈夫か?)」
ちらりと周りの様子をうかがいつつ、他の誰にも聞こえない小さな声で。
「(今夜、ゆっくり話聞くから)」
心配そうに優しく微笑むその顔は、上司ではなく恋人の戸波裕介の顔だった。
直属ではないけれど、彼は上司で私は部下で。
2人の関係がそれだけでなくなったのは、3か月ほど前のこと。彼が所属する第2グループで起きたトラブルがきっかけだった。
頼りにしていた中堅メンバーの急病…その穴を皆でカバーするべくグループの違う私も助っ人として駆り出された。
私に与えられた仕事はリーダーである戸波さんをサポートすること。
そうして、思いもよらない転機が訪れた。
会議室といってもそう広くはない部屋に、2人きり。プリンタが資料を印刷する音が地味に響く。
戸波さんと私はこの小会議室を作業場所にして、プレゼン資料の作成を進めていた。
「助かるよ。藤倉さんは仕事が早いうえに正確で」
「そんなことないです。戸波さんの指示がわかりやすいからですよ」
「そう言ってもらえると気が楽になるな。まったくこっちは無理ばかり言っているのにさ」
少しほっとしたようなその笑顔が素直に嬉しかった。
二人の始まり
「戸波さんの下だと仕事しやすいです。なんか、すごく…安心感があって」
お世辞でもなんでもない、紛れもない本心。
戸波さんは、その業績が認められて異例の若さでグループリーダーに抜擢された実力派。厳しいけれど頼れる上司として人望も厚い。
私もそんな彼を尊敬し、ひそかに憧れを抱いていた。
「戸波さんって、責任は俺が取るからやってみろって言ってくださるじゃないですか。あれってすごく勇気が出るし、頑張れるって思うんですよね」
私の直属の上司は絶対に言わない言葉だもの。隣のグループで戸波さんの部下としていきいきと仕事する同期が羨ましかった。
「藤倉さんは、周りのことをよく見てるよな」
「えっ」
意外な指摘に思わず戸惑う。だけど、少しでも気にかけて見ていてくれたなんて。すごく嬉しくて、すっごく…感激。
「いつも状況を冷静に見ていて、さりげなく周りをフォローしてくれてさ。うちのグループの新人も藤倉さんのこと頼りにしてるみたいだし」
「そんな、褒めすぎですよっ」
職場で褒められるなんて、まして直属ではないにしろ上司に認めてもらえるなんて。
そんなこと慣れていないからどうしていいかわからない。それなのに、戸波さんはさらに私を混乱させる。
「俺、前から藤倉さんと仕事したいって思ってた」
「ええっ。本当、ですか…?」
「本当。藤倉さんが同じグループだったらなぁとか思いながら、ずっと―」
ずっと…?!まるで夢のようなシチュエーション。これってホントに私の現実?なんだか、信じられない…。
でもやっぱり目の前にはちゃんと憧れの人がいて。2つ並べた長机の向こうから私のことを見つめている。
「ずっと、気になってた。いつもその、つい気になって。 出先から戻りの電話するときなんか、藤倉さんが出てくれたらいいなぁとか期待したりして。 で、そう思って電話して本当に藤倉さんがでたときなんて、すっごい嬉しかったりしてさ」
これって、これって、これって…!?私の勘違いじゃないよね?私の思い上がりじゃないよね?心臓はもう破裂寸前。
私は何も言えなくて、ただ黙って戸波さんの言葉を待った。
「藤倉さん」
「は、はいっ」
「俺、藤倉さんと真剣に付き合いたいと思ってる」
「はいっ」
「もし付き合ってる人とかいないなら…俺とのこと、考えてみてくれないか」
「はいっ」
「もちろん返事は今すぐでなくていいから。本当に、ゆっくりでいいから」
「はいっ」
「あのさ…」
「はいっ」
「さっきから、はいばっかりなんだけど…」
「ああっ。えーと…はい」
私、恥ずかしすぎる…。性懲りもなくまた「はい」なんて。
戸波さんはそんな私を見て愉快そうに笑った。楽しそうに、どこか嬉しそうに、仕事中には見せたことのない表情で。
「藤倉さんのそういうところも好きだよ」
「えっ」
今、好きって…。戸波さんが好きって、私のこと。好きだよって言ってくれた。
「真面目でまっすぐで…可愛くて」
「そんな…」
「藤倉さんが好きだよ、本当に」
戸波さん…。誠実で率直で男らしい、戸波さんらしい告白だと思った。
戸波さんこそ、真面目でまっすぐで。誰にでも公平で思いやりがあって、誰よりも努力家で。
ちょっと硬派な見た目のわりに、実はけっこうな甘党で。そんなところがまた愛らしい、とっても愛おしい人。
「唐突だよな、俺。それに仕事中なのに」
「いえっ…」
「いきなり困らせて…すまない。ごめんな」
決まり悪そうに伏し目がちになる戸波さん。私、ちっとも困ってなんかいないのに。
すっごく驚いたけど、嬉しい気持ちっていっぱいなんだから。だから…勇気を出して全力で言った。
「あやまらないで下さいっ。あの、私…とても、とっても嬉しいです。戸波さんが私のこと、見ていてくださって。だから、ですからその…私で、よければ―」
頑張って、頑張って、頑張って、やっとの思いで伝えた。
「藤倉さん」
「はいっ」
机越しでちょっぴり遠いけど、戸波さんと見つめあえた。と、思った瞬間―。
「あっ」
「紙切れ、だな…」
あろうことか…なんとも言えないタイミングで、プリンタがピーピーピーッと用紙の補充を催促してきた。
「私、やりますね」
「あぁ、頼むよ」
なんだか水を差されてしまったみたいな。でも、おかけでちょっと気持ちを緩めることができたような。
あたふたと用紙の補充をする私の背中に向かって、戸波さんは朗らかに言った。
「早速だけど、今晩一緒に飯でもどう?」
「はいっ。ぜひ一緒に」
私が振り返って2つ返事でOKしたのと同時に、プリンタは快調に印刷を再開した。
「よっしゃあ!俄然やる気でてきたぞぉ!絶対に早く終わらせる」
「はいっ」
「食べたいもの、考えておいてな」
「はいっ」
「ほんと、はいばっかりだな」
「あっ…。うぅ、もう指摘しないでくださいよぉ」
無邪気に笑う戸波さんに、私もつられて一緒に笑う。2人は、こんなふうに始まった。
魔法の手
結局、昼間の1件のせいで作業が全部ずれこんでしまった。こうなることは予想していたけれど、やっぱり残業…。私は会議室の一つを占拠して、お客様向けの資料サンプルの発送準備をしていた。
あと、もう少し。今日のうちに準備が整えられれば、明日の土曜出勤の当番の人へ集荷と発送を託せるもの。
だから、頑張ろう。疲れた自分にそう言い聞かせ、背筋を伸ばしてイスに掛け直した。すると、ちょうどそこへ―。
「あ…」
「やっぱり、ここで作業してると思った」
申し訳程度にノックをしつつ、こちらの応答も待たずに入ってきたのは戸波さん。
彼の顔を見たとたん、急に――張りつめていた心が解けていく。組織の中で身を守るための心の鎧が、がらがらと音をたてて崩れて消えた。泣きだしそうな気持ちで見つめる私のところへ、彼がゆっくりと歩み寄る。
「話はだいたい聞いてる」
「うん…」
机にちょっと腰掛けるようにして私の傍らに立つ彼と、彼をじっと見上げる私。
「災難だったな。よく我慢した」
彼の手のひらが私の髪にふわりと触れ、ぽんぽんと軽やかに頭を撫でる。大きくて、あったかくて、頼りがいのある優しい手。
「裕介」
「うん?」
「私…」
「どうした?」
「私、頑張れてる?」
こんなときに、こんな聞き方…ずるい私。でも今は、優しい言葉が欲しくて、思い切り甘やかして欲しかった。
「理香は頑張ってるよ。いつだって頑張ってる」
「うん…」
「みんな知ってるから。おまえが真面目にきちんとやってるってこと」
「うん…」
「まああれだ、約1名わかってないのがいるのが問題なんだけどな」
「うん……」
「でも、そのぶん俺がちゃんと見てるし、わかってるから」
「うん……」
「後輩の面倒、よく見てくれて助かってるよ。うちのグループの木下さんが心配してたぞ、おまえのこと」
「えっ、木下さんが?」
「藤倉さんはぜんぜん悪くないのにあんまりだ、って」
「木下さん…」
「‘私は藤倉派ですから’とか力強く言ってたぞ」
「もう、木下さん。藤倉派って…」
元気で可愛い後輩の様子が目に浮かんで、思わずふふふと小さく笑う。こんな私を慕ってくれる気持ちが嬉しくて有難かった。
「派閥の領袖じゃないか。俺の彼女ってすごいのな」
「裕介は、そうやってすぐからかう」
私はちょっと拗ねて、いたずらに彼の上着を引っ張った。
「私、頑張れてるんだよね?」
「ああ」
「本当に、ちゃんと…」
「俺が保証する」
彼の手が私の肩を優しく撫でる。触れるだけで、触れるほどに私を癒す。私だけの魔法の手。
「裕介」
「うん?」
「ご褒美」
「あ?」
「ご褒美、ください…」
こうして独り占めするだけではあきたらない、欲張りな私。その愛おしい手で、もっと触れて、もっと愛して癒して欲しい。なのに…。
最高のご褒美
「おまえ、目ざといな」
「へ?」
彼は左右のポケットからコーヒーのショート缶を1本ずつ取り出した。
「はい、ご褒美。うっかり出し忘れるとこだった」
「…ありがと」
もう、私が欲しいのはこういうご褒美じゃなのに…。
1本はブラック微糖で、もう1本はミルク増量マイルド仕上げ。私にくれたのは前者のほう。
まあね…私の好みをちゃんと把握しているあたりが彼らしいけど。そして、そんな彼は無類の甘党なのだから。
「裕介のそれ、すっごい甘々のやつでしょ。缶コーヒーって、けっこうな量のお砂糖が入ってるの知ってる?」
「この甘さがいいんだよ。理香こそ、甘いもんとか欲しくならないの?」
「なるなる。欲しくなるよ、甘いもの。特に今みたいに疲れているときとか」
甘い言葉、甘い時間…疲れなんてあっという間に忘れされる刺激的な甘さ。
あなたのその手で―とびきりの甘さで心もからだも満たして欲しい。
「理香。おいで」
「えっ」
ひょいと彼に手を引かれ、あっという間に腕の中。
「ご褒美」
「うん」
ちゃんと、わかっていてくれた…。私の気持ち、望むこと。
彼の手が私の髪を優しく撫でる。愛しむように、幾度もそっと。すごく気持ちがよくて、安らいで、身も心もとろけてしまいそう。
私、ずっとずっとこうして欲しかったんだ。彼の優しさに包まれて満たされて…。ありのままの自分を取り戻して、認めて欲しかったんだ。
「理香ってさ、いつも甘い香りがするのな」
「え?」
「柑橘系、なのかな。理香に似合ってて、すっごいいい香りでさ―」
髪に感じる彼の吐息に、どきどきして胸がきゅんと熱くなる。
「癒される。理香とこうしてると、ホント…すごく癒される」
「裕介?」
「ご褒美もらってるの、俺のほうみたいだな」
ちょっぴりばつが悪そうに微笑む彼が、とても大切で愛おしい。彼もまた仕事で何かあったのかもしれない。たとえ多くを語らなくても察しはつくもの。
「私のほうがいっぱいもらってると思うよ、ご褒美」
「そうか?」
「うん、そうだよ。絶対そう」
手のひらから、あふれるほどに伝わる愛情と信頼。
そっと髪を梳く指先の繊細な優しさ。私をこんなにも想ってくれるあなた。そんなあなたの癒しになれる。これほど幸せで誇らしいことってない。
癒しと自信を与えてくれる、最高のご褒美。
「裕介、ありがとう。すっごく元気でた」
「俺も」
「うん」
見つめ合って、笑い合う。なんだか気恥ずかしいけど、とっても幸せ。
「あと30分くらいでなんとかなりそうか?」
「大丈夫」
「俺も残った仕事ちゃちゃっと片付けちまうからさ。早く旨いもん食いに行こ」
「うん」
「よしっ」
そうして彼はご褒美ついでに(?)私の髪に優しいキスをひとつくれた。会議室をあとにする彼の背中を見送って、また1人きり。
机の上には、あともう少しのやりかけの仕事と、差し入れの缶コーヒーが1本。
甘さこそ控えめだけれど愛情たっぷりのコーヒーをごくりと飲んで、私は再び気合いを入れた。
「さーて、と。一気にやっつけますか」
1秒でも早く彼のもとへ―。一緒に美味しいご飯を食べに行くために。約束どおり、私の話をじっくり聞いてもらお。あ、彼の愚痴もたくさん聞いてあげよう。だから、頑張れる。
今日1日のご褒美、2人の甘い夜のために。