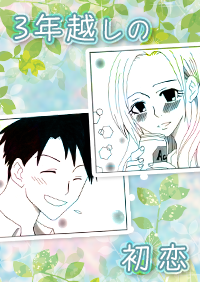女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
官能小説 ときめき☆サプライズ 前編
サプライズが好きな彼
「今日は特別オシャレね。デート?」
会社の更衣室で着替えていると、同僚にそう声をかけられた。
谷戸あいりは頬を染め、会社の制服から私服のワンピースへと袖を通す。薄桃色のそれは今日のために特別に買ったものだ。
「クリスマスだから…」
「相手は取引先との飲み会で知り合った人だっけ?確か―高石…」
「高石明彦さん」
「そうそう。もうだいぶ長くない?」
「うん」
あいりは照れながら、ロッカーに入れていたプレゼントの包みを大事そうに抱えた。
二十七歳になるあいりと二歳年上の明彦は、付き合って二年目になる。あいりに一目惚れしたという彼からの告白で恋人同士になり、今日で二回目のクリスマスを迎えることになった。
「それ、プレゼントでしょう?どこに行くの?」
ひやかすように言う同僚を前に、あいりは困ったように眉根を寄せた。
「そうなんだけど…どこかはわからないの」
サプライズ好きの明彦は、いつもデートプランを事前に教えてくれないのだ。
「へえ、でもうらやましいわ。結婚も近いんじゃない?」
「えっ…」
最近心のうちでほのかに考えていたことを言い当てられ、あいりは戸惑った。
「もしかして今度のサプライズは、プロポーズだったりして…!」
「そ、そんな…まさか―」
表ではそう否定してみたけれど、あいりの中でその可能性は捨てきれないでいる。明彦が婚約指輪を渡してくれる図が頭をよぎった。だけど期待して違っていたら落胆も大きいから、なるべく考えないようにしていたのだ。
そんなあいりの葛藤など知るはずもなく、先に着替え終わった同僚がぱたんとロッカーを閉めた。
「どっちにしろ、いいなあ。私はこれから寂しく合コンよ」
苦笑する同僚を尻目に、あいりは白いコートを着てから鏡で身繕いを済ませた。
「そっか。楽しんでね」
「そっちもね」
同僚と別れの挨拶を交わしたのち、あいりもまた会社をあとにしたのであった。
クリスマスデート
明彦が待ち合わせに指定してきたのは、彼のマンションの最寄り駅だった。
去年は突然、テーマパークに連れて行かれ、パレードや夜景を堪能したのだが…そう考えていたところで、明彦が改札を抜けてやってきた。背が高く体格のいい彼はよく目立ち、あいりはすぐに彼を見つけることができた。
「あいり!」
「明彦さん」
笑顔で迎えたら、明彦は人目もはばからずあいりを抱き締めてきた。

スーツ姿にトレンチコートを羽織った彼の甘い香水の匂いに思わずぼうっとなりそうになり、あいりは慌てて彼から離れる。
「もうっ、こんなところで恥ずかしいわ」
「クリスマスだから誰も気にしないよ」
明彦はそう言ってあいりの手を取ると、当然のように握って歩き始めた。
「今日はどこに行くの?」
今日まで明かしてくれなかった質問に、明彦はようやく答えてくれる。
「俺のマンション」
「明彦さんの?」
てっきりどこか外でクリスマスデートをすると思っていたあいりは拍子抜けた。互いの家に行き来するデートは、会社帰りであればいつもと同じだったからだ。いつもよりずっとオシャレしてきたのに…と、少し残念に思ってしまう。
そんなあいりの様子を察したのか、明彦が言葉を続ける。
「まあ、楽しみにしていてよ」
「う、うん…」
気分のよさそうな明彦に手を引かれ、あいりは彼のあとに従うほかなかった。
プレゼント交換
「わぁ…」
明彦の部屋に入ったあいりは、思わず感嘆の声を上げていた。
暗がりの中、部屋中にある電飾が光を発していたからだ。色とりどりの電球がちかちかと輝き、メリークリスマスという文字を彩ったり、サンタやトナカイなどの人形が楽しげに瞬いたりしている。そこは小さなイルミネーションハウスと化していた。
「驚いた?」
うれしそうに言う明彦に、あいりはこくこくとうなずいた。
まさか平日で多忙の中、部屋を飾っているなどとは思いもしなかったから、相変わらずサプライズ好きの彼に今度もあいりは驚かされることになった。
「今夜はふたりだけで過ごしたかったから、ふたりだけのイルミネーションを演出したかったんだ」
明彦はそう言うと、あいりの手を引いてさらに部屋の奥へと促す。
「ごちそうも完璧さ」
テーブルの上にはローストチキンやホールケーキを始め、牛肉の赤ワイン煮、芽キャベツとにんじんのサラダ、ほうれん草のニョッキ、かきのチーズ焼きなど、凝った料理がところ狭しと並べられていた。
「こんなことまで…大変だったでしょう?」
感動に言葉が詰まるあいりの頬に優しく口づけ、明彦は彼女のコートを脱がせた。
「君を驚かせるためなら楽しいことしかなかったよ。さあ、食事にしよう」
「ええ」
あいりは嬉々としてテーブルについた。
豪華な食事を心ゆくまでたいらげ、ソファでくつろいでいたあいりは、肝心なプレゼントをまだ渡していないことに気づいた。鞄の中からプレゼントの包みを取り出し、隣に座る明彦に差し出す。
「たいしたものじゃないんだけど…」
中身はブランド物の時計だった。あいりにサプライズを仕かけるためによく時間を気にする明彦だったから、きっと気に入ってもらえると思ったからだ。
「これ、俺が欲しかったブランドだよ!よくわかったね」
思っていた通り明彦は喜び、さっそく古い腕時計を外すと、あいりがあげた時計をはめてくれる。
「どう?似合っている?」
「よく似合っているわ」
自慢げに見せてくる明彦に、くすりとあいりは笑みをこぼした。年上なのに、明彦にはこんなふうに子供っぽいところがあるのだ。そこも好きなのだけれど。
「じゃあ、俺からもプレゼントを渡さなきゃね」
明彦は立ち上がり、サイドボードの前にしゃがみ込んだ。
「いいのよ、明彦さん。私はこんなにたくさんプレゼントしてもらったんだもの」
部屋中のイルミネーションにおいしいごちそうの山…これ以上のプレゼントはない。逆にもらってしまったら、あいりのあげた時計がかすみ、申し訳なくなってくる。
けれど…明彦が婚約指輪を渡してくれるところが、どうしても頭をちらついてしまう。
「俺があいりにプレゼントを用意していないと思うの?」
明彦はプレゼントの包みを持ち、再びソファに腰を下ろした。
「開けてみて?」
急かすように言われ、あいりは申し訳ないと思いながらも(それでもわずかに期待をにじませながら)リボンのかけられた包みをほどいた。しかし現れたふたつのものを見て、あいりは硬直してしまう。
刺激的な夜の始まり
「あ、あの…明彦さん…これ―」
中身はふたつあった。ひとつは突起のついた細長い物体で、ひとつは化粧品のように小さなボトルだった。
「マリンビーンズとリュイールって言うらしい」
明彦はあいりの膝の上からそれらを取ると、マリンビーンズのほうに電池を入れた。スイッチが入ると、ブブブっと振動し始める。その卑猥な動きに、あいりはすぐに用途を察した。
「もしかして、それ…」
「そう。バイブレーター」
明彦がいたずらっぽく片目をつぶってみせる。
「たまには刺激的な夜もいいかと思ってさ」
「で、でも私…そんなもの使ったことないわ」
困惑するあいりの肩に腕を回し、明彦は自分のほうに引き寄せた。
「俺だってないさ。でもあいりとなら使ってみたいって思ったんだ」
「明彦さん…」
それはそれでうれしかったけれど、やはりプロポーズではなかったという落胆は大きかった。だけどいまは形だけでも明彦のプレゼントを喜ばなければならない。
「それで、あの、こっちは…?」
もうひとつのボトルに目を向ければ、明彦は「美容液だ」と答えた。
ほっとしたのも束の間のこと、「ベッド専用のラブコスメだ」と続けられる。
「これらを…使うの?」
「もちろん」
明彦はうなずき、あいりをソファに押し倒してきた。
零れる吐息
「う…ん…」
ソファで全裸にされたあと、あいりはベッドに運ばれていた。仰向けに寝かされ、同じく全裸の明彦が上から覆い被さってきている。
明彦はあいりの両手を頭の横に縫い止めながら、執拗に彼女の唇を吸ってきた。
やがて弾力のある舌があいりの歯列を割り、口腔内を犯していく。歯茎から頬の裏、口蓋まで丁寧に舐め上げられ、あいりはぞくぞくと身体を震わせた。
「ふ…ぁ…は…」

息継ぎするたびに、あいりの口からは甘い吐息がこぼれてしまう。
明彦はあいりの唇から頬、顎から耳へとキスを散らし、やがて首筋に顔をうずめた。ちゅっと音を立てて柔肌を吸われ、甘い疼きがあいりの身体を駆け抜けていく。
「んんっ…」
明彦はあいりの両手を解放すると、鎖骨部分を撫で、胸元に手を滑らせてきた。
「あぅ…ん…!」
乳房を優しくつかまれ、あいりの身体がびくりと跳ねる。
明彦は片方の乳房を揉みながら、もう片方の乳首を乳輪ごと口に含んだ。生温かい感覚に、思わず背筋を弓なりにしならせてしまう。
「ああっ…はん…っ」
唾液を溜めた口腔内で乳頭を転がされているうちに、いつしか先端は熟れた果実のように硬く尖っていった。乳房を刺激されているのに、どんどん下肢が熱くなっていく。
あいりは下腹部に溜まる熱がもどかしく、自然と足を擦り合わせていた。それに気づいた明彦が、身体を下にずらしていく。
「あいり、足を開いてごらん」
「で、でも…」
明彦と交わることは初めてではないけれど(もう付き合って二年なんだから、それこそ数えきれないほどある)、今夜はあの大人のおもちゃを使うと宣言されている。 そう思うと恥ずかしさが込み上げ、反対に太ももを閉じようとしてしまう。けれど明彦はそれを許さず、自身の身体をあいりの足の間に割り込ませてきた。
「あ、明彦さんっ」
あいりが泣きそうに叫ぶが、明彦はもうリュイールのフタを開けたところだった。
「大丈夫、きっといままでより気持ちよくなるから」
「そ、んな―あ…はんっ」
先ほどの愛撫で既に濡れそぼっていた秘部にリュイールを塗り込められ、あいりはわなないた。ぬるりと花びらを撫でられ、思わず腰が浮いてしまう。
「あいり…もうこんなになって―」
言いながら、明彦が円を描くように秘列に指を滑らせていく。
「んぁっ、あっ」
これまでとは違う感覚に驚き、押し寄せる快感にあいりは目がくらみそうだった。局所がじんわりとほてり、どうにかなってしまいそうだ。たかが大人のオモチャと思っていたのに、ラブコスメはこんなにも気持ちがいいものなのだろうか。
「あっ、ダメ…それ以上は…っ」
あいりはいやいやするように懇願するが、明彦は指の動きをやめようとはしない。それどころか、ぷっくりと膨れ上がった雌芯を目ざとく見つけると、そこを重点的に攻め立ててきた。
「あ、ああっ…ん…やぁっ」
あいりの中に眠っていた官能が呼び覚まされ、気づけば彼女はベッドの上でひどく乱れていた。シーツをつかみ、必死で快楽の波をこらえる。いつもよりずっと感じる明彦の手淫に、いまにも達してしまいそうだった。 けれど明彦は、陰部に這わせていた指を唐突に離した。
「あ…」
喪失感に思わず眉を下げたあいりを見て、明彦が苦笑する。
「まさかこんなに反応があるとは思わなかったよ。こんなにもあいりが興奮するなんて」
「明彦さん…意地悪しないで…」
涙目で見上げれば、明彦の手にはいつの間にかマリンビーンズが握られていた。
あいりが驚きに目をみはり、ひくりと喉を鳴らす。あれが自分の中に入るなんて…最初こそ大人のオモチャと揶揄してラブグッズに抵抗があったあいりだったが、いまは好奇心でいっぱいだった。早く中を満たして欲しいと、蜜口からはねだるように愛液がしたたってきていた。
恋人とイベントを過ごす小説を読みたいあなたにオススメ!
今、人気・注目のタグ<よく検索されるワード集>(別サイト)
あらすじ
「今日は特別オシャレね。デート?」
会社の更衣室で着替えていると、同僚にそう声をかけられた。
「クリスマスだから…」
あいりと二歳年上の明彦は、付き合って二年目になるのだが、 サプライズ好きの明彦は、いつもデートプランを事前に教えてくれない。
「クリスマスだし…」と、素敵な場所へ連れてってくれるだろうと期待を抱いていたあいりだったが…?