女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
官能小説 あなたと感じ合いたい
何が楽しいの
★作品について
この作品は、小説サイト「ムーンライトノベルズ」と合同で開催した、「ラブグッズで熱く感じる小説コンテスト」のLC賞作品です。ドキドキの小説をお楽しみください。
何度も何度も、彼の熱くて脈打つぺニスが狭い器官を行き来する。
初めても彼ーー尚志ひさしだったが、その時から変わらないことが一つーー。
「あ……あんっ、ま、まって……はぁんっ」
「どうした、夏希なつき。気持ちいいのか?」
「ん……やっ、あ、あ、イク!イッちゃう!」
夏希の言葉に合わせるように、尚志は細かく腰を打ち付けて身体を震わせた。最後の一滴まで避妊具の中に吐き出すために、何度か強く突き上げると、荒い息を吐き出しながら倒れこんでくる。
別にこの瞬間が嫌いな訳じゃないが、尚志と同じ気持ちにはなれない。
覆いかぶさり、少し体重をかけてくる彼の背中を撫でる優しい行為だが、夏希の心は冷え込んでいた。
「ごめん。重いよな」
息を整えた彼が身体を起こし、腰を引いて硬さを失ったぺニスを抜くと、ようやく夏希はほっとした。
避妊具を始末して軽くティッシュで拭う尚志の様子を横になりながら眺めていると「気持ち良かったよ」と言って、満足げに頬にキスしてからシャワーを浴びに行った。
数分待って、シャワーの音が聞こえてきた頃、夏希は大きなため息を吐いて俯せになると枕に顔を埋めた。
「うー、セックスの何が楽しいのよ」
そう唸るように言った言葉は、枕でくぐもって聞こえづらい。
尚志と付き合って二年。
付き合った三ヶ月後にキスをして、半年後にセックスをした。
自分の年齢が二十九歳ということもあって焦っていたのかもしれない。
本気で好きな相手だから幻滅されたくなくて、痛みを我慢した。
色々な話は聞いていたから、最初が痛いのは仕方がないと思っていたし、尚志とセックスした喜びで気にするほどのものでもなかった。
夏希が違和感を感じたのは、三度目のセックスの頃だ。
彼は早急なタイプではないし、時間をかけて愛撫をしてくれる。
なのに、夏希の中は少ししか濡れないのだ。
お互い最高に気分が高まり、あとは尚志が避妊具をつけて入れるだけってなった頃には、夏希の秘処が乾いてしまう。
その結果、彼のぺニスが押し付けられて入ってくるのに、愛液が足りなくて痛みしか感じない。
月に二回くらいなら我慢もできるだろうが、疲れた時こそ尚志はセックスをしたがり、会うのは週末や休日だけではないし、一度会えば最低でも二回はする。
こんなこと、誰にも相談出来なかった。
夏希は、そこまでセックスに対して開けっ広げにはなれない。友達がそんな話題をしはじめても、始終聞き役である。
今では、ローション付きのコンドームを使うか、尚志に気付かれないようにローションを使うこともあるけれど、根本的な解決にはなっていない。
セックスとは、苦痛なもの。
今の夏希には、セックスの必要性が分からなかった。
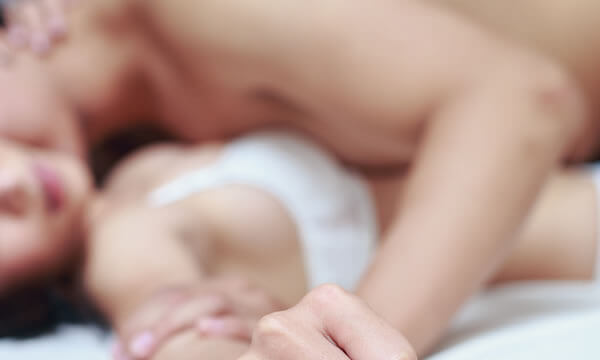
ギャップが必要
「……さん!夏希さんってば!」
若干の疲れを感じつつ、ぼんやりとしていた夏希は、向かい側に座るぱっちりとした二重が印象的な可愛らしい後輩の声に、はっとした。
「なに?千鶴ちゃん」
「なに?じゃないですよ。今日は朝から変ですよ?昨日って、彼氏さんと会ってたってことは……そんなに激しいんですか?」
赤面もせずに言われた言葉に、喉を潤そうと口にしたビールを夏希は思わず吹き出しそうになった。
「な、なんのこと」
「夜のほうってことですよ。とぼけるなら素直に言いますよ?彼氏さん、セックスが激しいんですか?それとも絶倫とかですか?」
「千鶴ちゃん……あなた、よくはっきりと言えるわね」
「いやですね、夏希さん。中学生か高校生じゃないんですから、何も恥ずかしいことないじゃないですか。処女じゃあるまいし」
「そういうものなの?」
「そうですよ。女子会といえば、彼氏とセックスの話で盛り上がるのが普通ですよ」
女子会というものに参加したことのない夏希にとって、そうなのかと頷くしかない。
「わたしの彼氏って一日に何回も求めてくるんですよ。でも、何回もなんて付き合いきれないんで、最初の数回は口と手でイかせるようにしてるんです」
可愛らしい笑顔を浮かべながら言う卑猥な言葉に、何も言えない。赤裸々すぎじゃないだろうかと夏希は思うのだが、千鶴は天気の話でもしているかのようにナチュラルに話している。
「夏希さんの彼氏はどうですか?しつこいとか、下手くそだとか、小さいだとか。それとも、テクニシャンで立派なものをお持ちですか?」
どう返せばいいのか分からない。
そんな風に困っていると、千鶴は持っていたグラスを置いて真面目な顔で正座した。
「なにかお困りですか?これでも、それなりに場数はふんでるんで相談にのりますよ」
夏希は唾を飲み込んだ。
千鶴とは長い付き合いである。夏希が入社三年目にできた初めての女の後輩だった。
女性の少ない職場というのもあったが、波長が合うというのだろうか、自然と仲良くなっていた。
他人が見れば首を傾げたくなるほど真逆の二人だろう。
モテモテな勝ち組女子と、色気もないぱっとしない女。
「どうぞ。言ってみて下さい。ここは個室ですから、安心してください。あっ……それとも、カラオケに移動しますか?」
ずずいっと、前のめりになった彼女の迫力に少々ひきつつ、夏希はジョッキに注がれたビールを一気に飲み干すと、口を開いた。
「千鶴ちゃんが言ったのには、当てはまらないの」
「どういうことですか?」
「あのね」
夏希は素直に自分の気持ちを口にした。恥ずかしくて、穴があったら入りたい気分の彼女とは裏腹に、千鶴は真剣に先を急かすような事はせず聞いてくれる。
全てを話し終えて、俯くと沈黙がやけに長く感じた。
自分はどこか変なのだろうか。そんな不安に苛まれ始めた時、千鶴が口を開いた。
「夏希さん。そんな顔しないで下さい。別に、夏希さんが変な訳じゃないですよ。世の女性たちには、同じような悩みを抱えている人はいますから」
「そうなの?」
「そうですよ。わたしだって、そういう相手はいましたよ。下手とは違うんです。ようは刺激が足りないってことです!」
「し、刺激!?」
驚きと動揺で机を揺らす夏希とは違い、千鶴は冷静だ。現に、スティック状の野菜を掴むと、ディップソースを絡ませてポリポリと食べている。
「はい。そうですよ?だって、夏希さんと彼氏さんって長い付き合いですよね?おまけに夏希さんの経験って彼氏さんだけ」
「う、うん」
「となれば、答えは一つ!相手にキュンッとか、萌えとか感じなくなってません?見慣れたものって、いまいちときめかないんですよね。こうギャップがないと」
「ギャップ?どんな?」
尚志の顔を思い描いて見るが、昔から変わらず優しい。
他の姿は見たこともないと言ってもいいほど、苛立ちや怒りを見たことがなかった。
「たとえば、クールに見えてふとした時に笑顔が可愛いとか、普段は優しいけどセックスの時にはドSだったりとか?」
「彼にはないかな」
「やっぱり。そんな夏希さんに、オススメの物を思いつきました。ちょっと待ってくださいね」
そう言った千鶴は、鞄からスマートフォンを取り出すと画面をタッチしたりスクロールしはじめた。
何かを探しているような様子に、夏希は手付かずだった焼き鳥を手に取ると口に運んだ。
しばらく黙々と口を動かしていると、ようやく千鶴が顔を上げた。
「ありましたよ、夏希さん!これです、これ!」
目の前に差し出されたスマートフォンの画面には、可愛らしいピンク色の猫の置物のような物が映っていた。
「【さくらの恋猫】?」
「はい!こんな可愛らしい見た目ですけど、バイブとかインナーボールとかローターなんですよ」
「ば、バイブ!?」
「そうですけど。どうかしましたか?」
あっさりと、まるで今日の夕飯の話しでもしているかのように言われて、夏希は頬に熱が集まるのを感じた。
「あれ?もしかして、夏希さんはこういうの使ったことがないですか?」
「……使ったことないよ。だって、なんていうか」
「恥ずかしいですか?もー、夏希さんってば純情さんですね。自分で気持ちのいい場所を探したり、気持ち良くなることは悪いことじゃないんですから。それに、膣トレは美容にもいいと思いますよ」
「そ、そうなの?」
「そうですよ。騙されたと思って、試して見てくださいよ。これ、スマホと連動してて、色々なシュチュエーションボイスを聞きながらで、すっごく気持ちがいいんですから」
そう背中を押されて、夏希はサイトを教えてもらいその場でインナーボールの注文を済ませた。
注文してから、自分の人生の中で一番すごいものを買った気がして落ち着かない気分になってくる。
千鶴には、楽しみに待っていて下さいなんてエールを贈られたが、恥ずかしさしかない。
その後は、夏希が気まずい思いをしないようにか話題を変えてくれた。
おかげで、楽しく飲んで食べて、いい夜を過ごすことが出来た。
俺も勉強しないとな
数日後ーーーー
ようやく訪れた有給休暇に、溜まっていた外での用事を済ませ、夕食後にまったりとした時間を過ごしていると。
玄関のチャイムが鳴った。「こんな時間に?」なんて思いながら応対に出れば、それは宅配便の配達員だった。
何か頼んだだろうかと思いながらサインをして、はっとした。
普通の段ボール過ぎて、忘れてしまいそうだが、それは間違いなく例の物を注文した店からの物だ。
箱の普通さにほっとしつつ、ベッドに箱を置いて思わず正座してしまう。
人生で初めて買う物に対して、こんなにドギマギする物があるだろうか。
今日ほど、一人暮らしをしていてよかった思う日はないだろう。
一つ、小さく深呼吸をして開封するべくガムテープを剥がし始めた夏希は、思いきって箱を開けた。
卑猥なイメージの強い物だけに、衝撃に備えていたのだが、箱の中を見て小さな声で「えっ?」という言葉が出ていた。
それもそのはず、中にはまるでプレゼントのように可愛らしいピンク色の袋が入っていた。
恥ずかしさとは無縁の見た目に、夏希の心はほっとしている。
少なからず、ワクワクするような気持ちまで沸き上がってきた。
袋を開けて、中身を取り出した夏希は、卑猥とは程遠い可愛らしいインナーボールにまじまじと見つめていた。
一緒に入っていた説明書を見ながらスマートフォンを手に、アプリをダウンロードしその他の接続を終わらせ、とりあえずほっと息をついた。
落ち着かない気分に、なりながらも好奇心を抑え切れず、スマートフォンとインナーボールを掴んでベッドに潜り込んだ。
横になりながら、イヤホンをつけて選んで購入したストーリーを始めると、セクシーな声が耳元で囁いた。
選んだのは、優しいけれど少しSっ気のある男性。
最初の囁きは優しかったのに、徐々に意地悪な事を言いはじめる。
言葉に合わせて、そのシュチュエーションの想像を通り越して、リアルに感じさせる振動に鼻から息が漏れた。
言われた通りの場所に当てる度、強弱の変わる振動に、足の間がじんっと痺れて、置くから愛液が滲み出てくるのがわかる。
これまでの夏希なら、恥ずかしくてしょうがなかっただろうが、そんな気持ちも消し飛ぶくらい翻弄されて夢中になってしまう。
最終的には、パンティーの上からクリトリスに押し当て、思わず声が漏れた。
「やぁ……ん、あっ……いっ、イクッ!」
腹部の奥がキュンとしたと思った次の瞬間、つま先が丸まる程の快感が夏希の体を襲った。
しばらく体が震え、胸で荒い息を繰り返す。
感じたこともないエクスタシーに、頭の奥まで痺れているような気がする。
「へー、どこでそんな遊びを覚えたわけ?」
耳はイヤホンで塞がっていたし、意識はぼんやりとしていたから気づけなかった。
イクと同時に耳からこぼれ落ちたイヤホン。
その耳に聞こえてきたのは、間違うはずもない愛しい彼の声。
夏希は体を起こして、上掛けで体を覆った。
さっきまでの高揚感は引いていき、代わりに頬に熱が集まる。
気を抜いていた。
お互いの家の合い鍵を持っているのだから、いつ尚志が来てもおかしくないというのに、チェーンをかけ忘れていたのだ。
恥ずかし過ぎて、彼の顔を見ることが出来ない。
ぎしっと、ベッドの片隅が軋み体が強張る。消えてしまいたいーーそんな事を思っていると、呆れたようなため息が聞こえてきた。
心臓がぎゅっと締め付けられるように痛んだ。
嫌われたのかもしれない。
そんな考えが、頭の片隅を過ぎったが。
「いつも無理してた?」
少し気落ちしたような声に、はっと顔をあげれば表情を曇らせた尚志の姿があった。
「ちっ、違うよ!そうじゃなくて、私が」
一瞬、言うのがこわくなったが、彼に勘違いされたままなのも嫌だった。
「尚志が悪いんじゃなくて、私が変だから……嫌われたくなくて」
「変って、どういうこと?」
「心は満たされてるし、尚志に求められるのも嬉しいのに、エッチの最中に……痛くて。心と体がちぐはぐなのを知られたくなかった」
一息に言い切り、俯くと上掛けを握りしめていた手に、彼の手が重ねられた。
ぎゅっと掴まれ、親指は慰めるように手の甲をくるくると撫でさする。
思いやりに満ちた行為に、目の奥がツンッとして涙が出そうだったが、彼のからかうような声に引っ込んだ。
「それで?この男に助けを求めた理由を聞いてもいいかな?」
尚志は、夏希の目の前でスマートフォンを振って見せた。
そこには、さっき彼女を絶頂へと連れていった優しいけれど少しSっ気のあるキャラクターが映っていた。
「自慰しているくらいなら驚かないし、気にしないけど……これはちょっと気になるな」
「そっ、それは後輩の千鶴ちゃんが紹介してくれたもので」
「へえー、こういう男が好きなんだね。ってことは、俺の前戯が優し過ぎたから物足りなかったのかもしれないな。つまり、夏希に痛い思いをさせていたのは、俺のせいかもしれない」
「ちょっと、違うってば」
そう言ってスマートフォンを取り返そうと手を伸ばすが、簡単には返してくれづ、代わりに肩を優しく押されてベッドに倒された。
訳も分からずぽかんと倒れたままでいると、ベッドに上がった尚志はコートを脱ぎ捨てスマートフォンからイヤホンを抜くと、いつの間に見つけたのか可愛い猫型のインナーボールを振って見せた。
「俺も勉強しないとな」
「なにを」
何を言っているのかと問い掛け終わる前に、枕元にスマートフォンを置くとまたストーリーを再生させていた。
ついさっき聞いたばかりの音声が流れはじめ、意地悪な言葉が囁かれる。
「へー、夏希はイジメられたいんだ?」
覆いかぶさってきた尚志は、振動するインナーボールを服越しに乳首へと軽く触れさせた。
目の前にいる尚志がやっているからなのか、さっきまではそこまで感じる事のなかった乳首への愛撫が、まるで電流でも出ているのかというほど疼いた。
たまらず鼻にかかったような声が零れてしまう。
「そんなに気持ちがいい?それは、この声優の声だから?それとも……俺が目の前にいて押し付けてるから?」
これまでにないほど意地悪に囁かれ、寧ろ声優の声なんて耳に入ってこない。
我慢できなくなった
「夏希は優しく抱かれたいのかと思っていたから、今まで優しい愛撫でやってきたのに……今度からは、俺のやりたいように抱こうかな」
「へえっ?」
「男はみんなそうだろうけど、好きな子ほど優しくしたい反面ーー意地悪したいって気持ちもあるんだよ?焦らして、焦らして、俺が欲しいって懇願させたいってね」
そう微笑みながら、胸の間を通って腹部に押し付けたかと思うと、さらに下を目指す。
パンティーの中に滑り込み、自分では出来なかった直接の振動がクリトリスをなぶる。
「やああっん、んぁっ!」
怖いほどの快感が腹部の奥を熱くさせ、手を退けようと尚志の手首を掴むが優しいキスが額に押し付けられる。
「大丈夫だよ、夏希。イッてごらん」
そう微笑みながら、胸の間を通って腹部に押し付けたかと思うと、さらに下を目指す。
パンティーの中に滑り込み、自分では出来なかった直接の振動がクリトリスをなぶる。
「やああっん、んぁっ!」
怖いほどの快感が腹部の奥を熱くさせ、手を退けようと尚志の手首を掴むが優しいキスが額に押し付けられる。
「大丈夫だよ、夏希。イッてごらん」
振動がおさまった途端、インナーボールはどろどろに溶けて蕩けている入口へと移動して、何の抵抗もなく飲み込んでいく。
蕩けきっていて、圧迫感は感じない。
少しの異物感はあるが、尚志のぺニスと比べたらなんて事のない大きさに、自分の中が物欲しそうにうごめくのが分かる。
締め付けようとするその動きに、頬が熱くなると同時に、振動が再開した。
ぺニスではありえない刺激の仕方に、背中が反って足の指先はシーツを乱す。
一番強い振動になった瞬間、目の前がチカチカして、頭の中が真っ白になって、全身を快感が走り抜けた。
「すごく綺麗だよ、夏希。でも、一人だけ満足するなんて狡くない?」
何を言っているのか分からないくらい、頭の芯が痺れた夏希の耳に不穏な音が聞こえてきた。
金属の音が二度続き、どうにか軽く頭だけを上げて尚志を見れば、ジーンズの前を寛げているところだった。
「なあに?」
ベッド脇の引き出しに手を伸ばした動作に、何が意味しているのかが分かった。
「夏希の本気でイッてるところ見たら、我慢できなくなった。責任……取らないとね?」
少しどころか、かなり意地悪な笑みを浮かべた彼は、パンティーを剥ぎ取ると歯でコンドームを噛み切って、素早くボクサーパンツを引き下ろしてぺニスに被せると、夏希の足を割開き腰を入れると、中に入ったままだったインナーボールをゆっくりと引き抜いた。
抜かれるときの刺激に声を漏らすと、シーツまで愛液が零れ落ちるのが分かった。
今まで、こんなに濡れたことも、中で感じたこともない。

「やばいな。俺は今まで、何を見てたんだろうな」
「んっ……何が?」
指で入口を撫でられ腰を揺らすと、彼は息を吐いた。
「こんなに濡れたことないだろ?そりゃ、痛いよな。ごめんな」
指が離れていき、代わりにぺニスの丸い先端が押し付けられた。
ぷちゅっという水音と、ゆるゆると押し付けられる熱いぺニスの感触に、物欲しげに中がヒクつき飲み込んでいく。
いつもは入るときに痛みがあって、体が強張るのだが愛液の滑りを借りて驚くほどすんなりと奥まで入った。
「えっ?嘘!全部入ったの?」
「ああ、そうだよ。これで分かるだろ?」
尚志が腰を前に押し出すと、腹部の奥をノックするような感覚があった。さらに揺すり上げられると、お互いの肌が当たりぬるぬるとした感触がする。
中を一杯に広げられて、奥まで入り込んでいるのに苦しくも痛くもない。
それどころか、中をぺニスで擦られ一杯にされているのが気持ちが良い。
「どうだ?動かして欲しい?」
「なっ!」
彼はぴたりと腰をつけたまま、動こうとはしない。
訳も分からず見上げていると、にやりと口角を上げた。
「腰を打ち付けて欲しいって言わないと、俺は動かないよ。それどころか、抜いて終わりだ」
「で、でも」
中にあるぺニスは熱く脈打ち、今までで一番固くなっている。
彼だって我慢はきついはずだと言いたかったのに、首を横に振った。
「俺は平気だよ。夏希の中から出て、ちょっとトイレで処理すればいいだけだからね」
そういう尚志の額には汗が滲んでいる。
言いようのない愛しさに、中がキュンとしまりぺニスを締め付けると、彼が唸った。
その声と表情は、とてつもなく破壊力があって、夏希の理性は蕩けていった。
「お願い!動いてっ」
尚志は、はっと息をのむと夏希の腰掴んだ。膝で腰を挟むと、それを合図に激しい抽挿が始まった。
これまでだったら、こんな動きをさせたら痛くて泣き叫んでいただろう。
なのに、今回はーー。
中を括れで擦られる度に、甘く鳴き叫んだ。
ベッドは激しい動きに軋み、お互いまだ洋服を身につけたままだというのに、あられもない声を上げ、恥ずかしげもなく夏希も腰を揺らした。
これがセックスなのか。
頭の片隅ではそんなことを考えていた。
片方だけが我慢するのは優しさではない。
お互い追い求め、与え合うからこそエクスタシーが高まり、最高の瞬間を迎えるのだ。
最後の瞬間、二人はどちらの震えか分からないほどスパークした。
薄暗い室内に、二人の荒い呼吸だけがある。
全身汗だくで、どちらの体液かもわからない。
こんなセックスはしたことがなかった。
「悪い、重いよな」
だらりと覆いかぶさっていた尚志が離れ、自然と中からぺニスが滑り出ていくと、喪失感で腰が震えた。
とてつもなく怠い。
今まで使っていなかったのかというほど、心地好い怠さに夏希の口元は綻んだ。
ようやく重なった心
「夏希、一緒に汗を流そう」
いままでにない提案に動揺していると、そのまま抱き上げられた。
べたついていてシャワーは浴びたいが、これまで彼とベッド以外で裸で向き合ったことがなのに、今日は恥ずかしいところばかり見られる気がする。
当の本人は、すたすたと脱衣所まで行くと、夏希を降ろしてから戻っていった。
取り合えずちぐはぐなTシャツしか身につけていないというのが嫌で脱ぎすてる。
先に入っているべきかと悩んでいると、戻ってきた尚志は一つの物を掲げて見せた。
「これって防水性?」
それは、あの猫型のインナーボールだ。
さっきまで中に入っていた物を見せつけられて、一気に羞恥心が戻って来る。
「ちょっと、返して!」
「うーん、中に入れられるってことは、防水性ってことなんだろうけど、スマホと連動してるんじゃなぁ」
少し残念そうに言いながら、素直に夏希の手に渡してきた彼だったが、耳元でとんでもないことを囁いた。
「次は、スマホと連動無しのを一緒に選ぼう?」
ゆっくりと腰を撫でられて、ぞくぞくとした感覚がダイレクトに子宮を疼かせた。
尚志の新たな一面と、二人が本当の意味で一つになったような気がする。
彼がご機嫌な様子に、そっと息を吐いたが、一緒に感じ合えた幸せにこっそりと微笑みを浮かべた。
この日、始めて本当の意味で二人の心が一つになったような気がする夏希だった。
END
あらすじ
彼とのセックスでも少ししか濡れない…
セックスの良さが全く分からない夏希がそのことで悩んでいると、会社の後輩から『さくらの恋猫』という新感覚のラブグッズをおススメされて…

















