女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト
エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】
ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます
官能小説 彼の秘密
彼の秘密
「ねえ、あなた。今日のプレゼン、最高だったわ!さすが私の旦那様!」
会社の廊下で、私は夫の腕に抱きつき、満面の笑みで言った。周囲の視線なんて気にならない。
だって私たちは、社内でも公認のおしどり夫婦なのだから。周囲の同僚たちが微笑ましげに私たちを見るのがわかる。
中には、少し羨ましそうな視線を送る女性社員もいるけれど、それもまた誇らしかった。
「はは、ありがとう。でも、君が的確なアドバイスをくれたおかげだよ」
彼は少し照れたように笑う。その口元には、いつも通りの優しい弧が描かれているけれど、その奥に潜む瞳は、どこか自信に満ちている。
私の夫、亮は、社内でも一目置かれる優秀なビジネスマンだ。彼の企画は常に革新的で、人を惹きつけるカリスマ性がある。
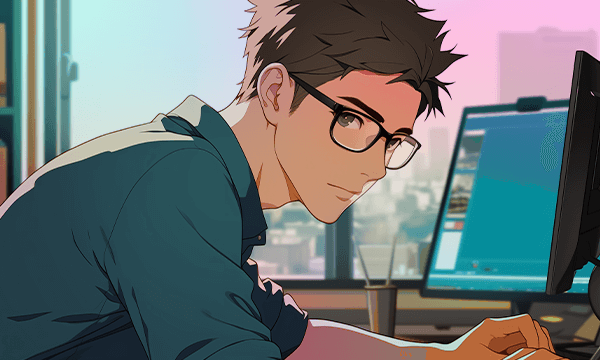
そのうえ、外では常に私を立ててくれる、絵に描いたような優しい夫。
普段の私たちは、どちらかというと私がリードしているように見えるだろう。
デートの計画も、休日の過ごし方も、ほとんど私が決める。
亮はいつも「君のしたいように」と言って、私のワガママを優しく受け入れてくれる。その姿は、まるで大きな包容力を持つ兄のようで、私はそんな彼に甘えるのが好きだった。
「今日は美味しいものでもお祝いしなくちゃね!予約、私がしちゃおうか?」
「いや、今夜は…家でゆっくりしないか?」
彼からのその言葉に、私の胸は早くも期待で高鳴った。
彼が「家でゆっくり」なんて言うときは、それが私たち二人にしかわからない特別な合図だと、私はよく知っている。
昼間の穏やかな表情の裏に、別の彼の顔が潜んでいることを、私は知っているから。
今日、私が彼をどれだけ煽り、彼がどれほどその本性を抑え込んできたか、お互いに分かっているのだ。
「…分かったわ」
私はにっこり笑って、彼の腕をぎゅっと握った。その瞬間、彼の指が、私の腕の内側をそっと撫でた。
会社では決して見せない、ほんの小さな仕草。それでも、私には十分すぎるほどの合図だった。
家路の予感
電車に揺られ、家路を辿る間も、私の胸の高鳴りは収まらなかった。今日の亮は、いつも以上に私のそばに寄ってくる。
吊革を掴む彼の腕が、私の肩に触れるか触れないかの距離にある。
まるで、周囲には気づかれないように、私たちだけの秘密の空間を作り出しているようだった。
彼のシャツから漂う、どこか落ち着く彼の香りが、私を包み込む。昼間はキリッとしたスーツ姿だったけれど、今はネクタイも緩め、シャツの襟元が少し開いている。
その隙間から覗く鎖骨に、妙に目が吸い寄せられた。
マンションのエントランスを抜け、エレベーターに乗り込む。密閉された空間。
二人きりになった途端、昼間の明るい笑顔が薄れ、亮の表情がわずかに引き締まったのがわかった。彼の視線が、私の顔にゆっくりと向けられる。
「疲れてないか?」
優しい声。けれど、その響きは、オフィスで聞く彼の声よりもずっと低い。そして、私の目を覗き込むような、深くて熱い視線。
彼はそう言いながら、私の肩に掛かっていた大きめのバッグを、ごく自然に引き寄せた。
その手が、背中に回され、うなじの少し下のあたりから、ゆっくりと背骨に沿って下へと滑っていく。
服の上からでも、その指先の熱がじんわりと伝わり、ゾクゾクと全身に粟立つような快感が駆け巡った。
思わず、喉の奥から「あ……」と小さな声が漏れそうになる。
その瞬間、チーンと軽やかな音を立てて、エレベーターのドアが静かに開いた。
私の声は、まるでそれに吸い込まれるように、かき消されただろう。
彼は何もなかったかのように、私のバッグを軽く持ち直し、先にエレベーターを出ていく。
「大丈夫よ。あなたも疲れているでしょう?」
そう答えるのが精一杯だった。エレベーターの箱が上昇する独特の浮遊感と、彼の視線、そして背中に残る彼の指先の感触が、私の頭の中を支配する。秘密の解放
家に帰り、夕食を済ませてリビングでくつろいでいると、亮が私の隣に座った。
間接照明の柔らかな光が、部屋全体を包み込む。
いつもなら、ここで今日あった出来事を話したり、テレビを見たりするけれど、今夜は違う。
彼の視線が、私から離れない。
そして、何も言わずにそっと私の指先に触れた。彼の大きな指が、私の小さな指を優しく包み込み、ゆっくりと、まるで愛おしむように撫でる。
普段は社内で見せないその仕草に、私の胸はキュンと締め付けられた。
指の腹が、私の手のひらをそっと押し、爪先まで優しく辿る。その丁寧すぎる愛撫に、私の体はゾクゾクと熱を帯び始めた。
「疲れただろ?……もう、力抜いていいんだぞ、俺の前では」
彼の声は、昼間の穏やかなトーンとは違い、低く、甘く響く。
まるで、深い海の底から聞こえてくるような、抗えない響きがあった。
「別に…ッ!」
私の言葉を遮るように、彼は私の腰に手を回し、そのまま抱き寄せた。彼の腕の力が、どんどん強くなる。
いつもの優しい亮は、もうそこにはいない。私の体をソファに押し倒すように、彼の体が覆いかぶさってくる。
彼の視線が、私を絡め取る。
彼の指が、腰から背中を撫で上げ、服の裾から、わずかにその温かい肌に触れる。
ぴくりと反応した私の体に、彼は満足げに口角を上げた。
「ふふ、どうしたの?今日は積極的ね」
私が挑発するように言うと、彼の瞳がさらに深く、獲物を捕らえる獣のように光った。
その眼差しは、私を逃がさないと告げている。
「君が俺を煽るからだろ?」
普段は私に甘い彼が、こんなにも支配的な言葉を口にする。その言葉が、たまらなく私をゾクッとさせた。
彼の呼吸が、私の顔にかかる。それが、熱い。
「観念したか、俺の可愛い奥さん?」
そのまま、首筋に顔を埋め、深く息を吸い込む。
彼の熱い吐息が、うなじの敏感な部分に触れるたび、全身が甘く痺れていく。
「いい匂いだ……もっと、感じさせてくれ」
普段は嗅ぎ慣れたはずの彼の香りが、今夜はまるで媚薬のように、私の意識を朦朧とさせる。
彼の指が、私のブラウスのボタンに触れ、一つ、また一つと、ゆっくりと外していく。その動きは滑らかで、まるで訓練されているかのようだ。
「焦らなくていい。その代わり、隠さずに、すべて俺に見せろ。な?」
開かれた襟元から、彼の指が滑り込み、鎖骨をなぞる。
そのまま胸元へと降りていくたびに、私の呼吸はどんどん乱れていく。
「ああ、そんなに震えて……たまらないよ。もっと、感じさせてやる」
「見せて、俺の可愛い奥さんが、どう俺に蕩けていくのか」
彼の熱い唇が、私の鎖骨に吸い付く。ゾクゾクと全身に熱が広がり、私の呼吸はどんどん乱れていく。
「おっと、可愛い奥さん。もう、そんなに敏感になったのか?」
彼の視線が、私の体の隅々までを舐めるように這う。それは挑発的で、私を深く誘い込む。
私の抵抗もむなしく、彼は私の両手首を片手で軽々と掴み、私の頭上へと固定した。もう片方の手は、私の頬を優しく撫でる。その指先が、首筋を滑り、鎖骨へと降りていく。
「もっと、もっとだ……お前が俺に夢中になるまで、止めないからな」
「ん…」
「可愛いね、俺の奥さん」
彼の唇が、私の耳元で甘く囁く。
その声は、私を完全に支配するかのようで、抗うことなんてできなくなった。
私の中から、理性が溶けていくような感覚に陥る。羞恥心と、それ以上の快感が、私の全身を駆け巡り始めた。
昼間の優しい夫とはまるで別人の、Sな魅力全開の彼。このギャップが、私を何度でも彼に溺れさせる。
今夜も私は、彼の甘い罠に、喜んで落ちていくのだろう。
END
あらすじ
社内でも公認のおしどり夫婦の私たち。優しい夫は二人の時間になると…
私だけにしか見せない顔がある。
















